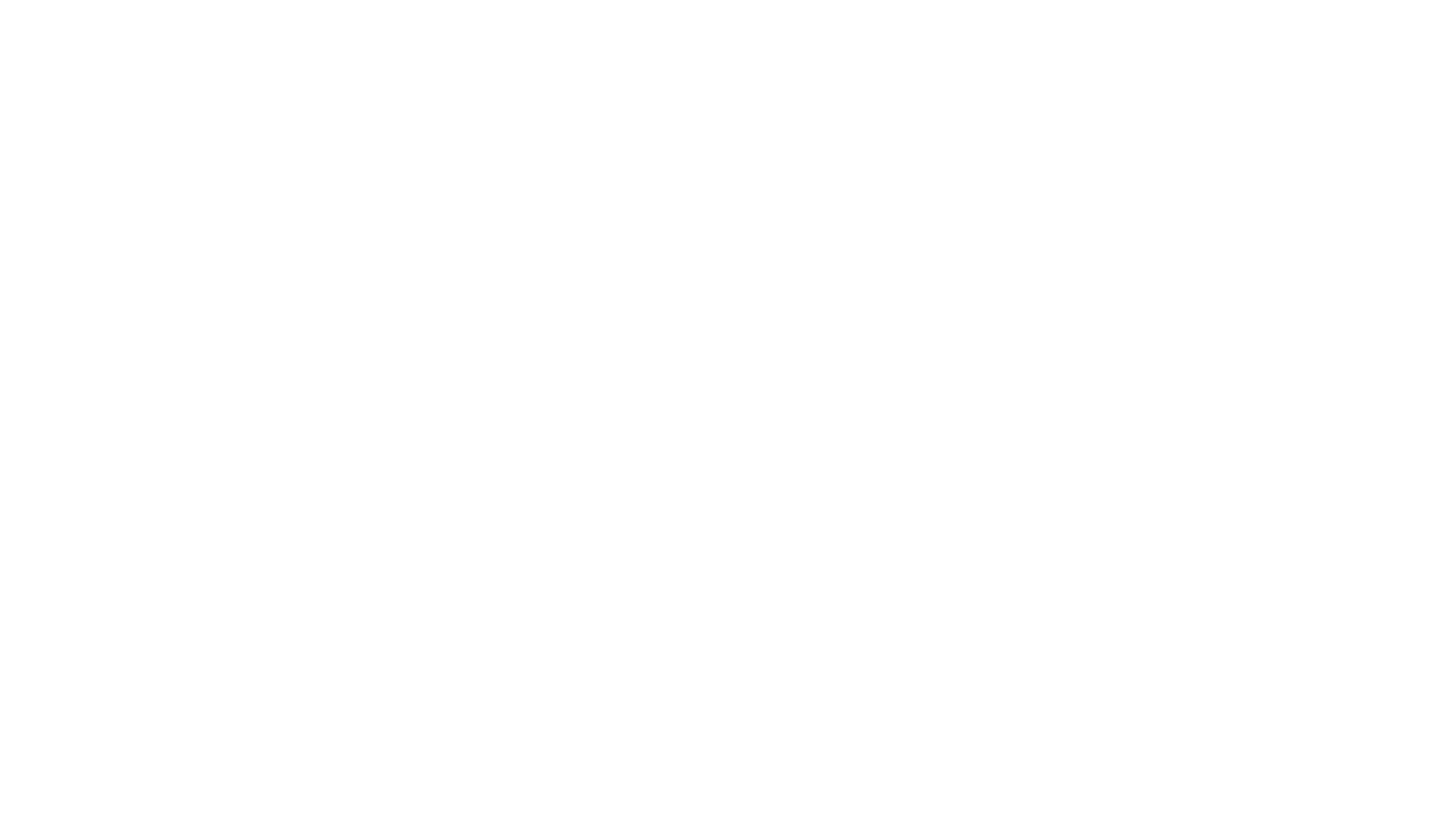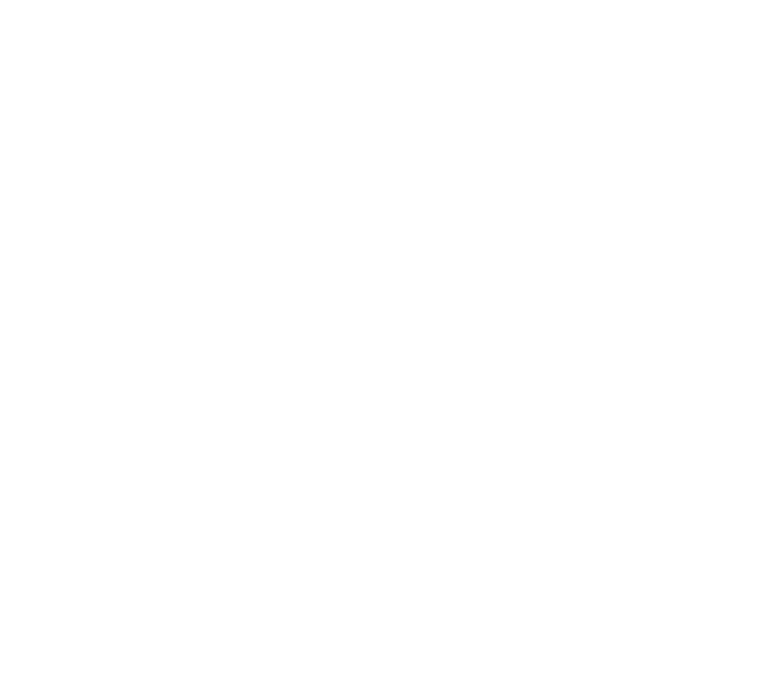スモールビジネスから抜け出す新戦略は早期収益化で勝負するソリッドベンチャーか?
公開日:2025.01.22
更新日:2025.4.17
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠

近年、スタートアップとスモールビジネスの中間に位置する「ソリッドベンチャー」が注目を集めています。大規模調達に頼らず、受託・コンサルなどで早期に安定的な売上を確保したうえで、新規事業へと段階的に進むこのモデルは、着実なキャッシュフローを背景に柔軟に挑戦を続けられる点が大きな特徴です。本記事では、スモールビジネスに留まらず長期成長を目指すソリッドベンチャーの基本構造やメリット、具体的な事例を通じて、その可能性を掘り下げます。
ハイライト
- 受託・コンサルで早期収益化し、そこから新プロダクトやSaaSを“ジワ新規”で展開
- 大規模資金調達に頼らず、自己資本の範囲で投資をコントロールでき、リスクを最小化できる
- スモールビジネスの域を脱し、多角化や隙間市場の攻略で長期的な成長と企業価値向上を狙える
なぜ「早期収益化」を重視するソリッドベンチャーが注目されるのか
スタートアップというと、赤字を恐れず莫大な資金を調達し、爆発的な成長を目指すイメージが強いかもしれません。華々しくメディアに取り上げられる事例も多く、上手くはまれば超短期間で時価総額が跳ね上がる夢のある世界です。
しかし、その一方で急成長モデルに参入できるのはごく一部の企業であり、多くの起業家や中小企業にとってハードルが高いのも事実。資金ショートの危機や投資家リターンに追われるプレッシャー、希望のEXIT(売却・IPO)タイミングを逃すリスクなど、華やかな面だけではありません。
こうした流れの中で、「ソリッドベンチャー」と呼ばれる形態が近年注目を集め始めました。ソリッドベンチャーの特徴は、スタートアップのように赤字覚悟で大金を投下するのではなく、「創業初期から安定収益を上げる」ことを重視する点です。
地道に受託やコンサルで稼ぎ、その利益を徐々に新事業やサービスに転換することで、早期収益化と長期的な成長の両立を図ります。こうしたモデルは「短期的に爆発する」スタートアップとは対照的ですが、じわじわと確実に売上と組織を積み上げるため、経営リスクを抑えながら拡大できるのが最大の利点と言えます。
本記事では、早期収益化を目指すソリッドベンチャーについて、以下の内容を順番に見ていきます。
- ソリッドベンチャーのビジネスモデルの概要
- スモールビジネスとの比較:どう違うのか
- 初期キャッシュを得るための代表的アプローチ
- 実際の企業事例
- 今後の展望や、どんな人・企業にマッチするのか
「起業はしたい、でもいきなり大きく資金を集めて赤字を掘るのは怖い……」そんな悩みを持つ方にとって、ソリッドベンチャー型の経営は大きな示唆を与えてくれるでしょう。
ソリッドベンチャーの特徴:早期収益化の仕組み
「大きく始めて爆発させる」より「地道に受託・コンサルで稼ぐ」戦略
多くのスタートアップは、アイデア段階で大きな資金を調達し、そのお金をユーザー獲得やプロダクト開発に投入して、一気に市場シェアを取りに行きます。いわゆるJカーブ型の成長を志向するため、短期間で売上よりも先行投資が膨らむケースが一般的。結果的に創業から数年は赤字を出すのが当たり前です。
ソリッドベンチャーは、こうした「赤字を掘ってでも早期に巨大化する」モデルとは異なり、「創業期から黒字またはプラスのキャッシュフロー」を重視します。
具体的には以下のような仕組みが見られます。
- 受託開発・コンサル・BPOなどでまずキャッシュを得る
- 自社プロダクトを作りたい場合も、初期は他社案件を請け負って売上を確保
- そこから蓄積した利益やノウハウを使い、自社サービスや新事業へ段階的に投資
- 外部から調達するとしても「必要最小限」に留め、急激な株式希薄化や投資家のリターン要求を回避。
スモールビジネスとどう違うのか?
「それって単なる小規模のビジネス(=スモールビジネス)と何が違うの?」と思われるかもしれません。たしかに共通点はありますが、ソリッドベンチャーは“スモールビジネスで終わらない”のが大きな違いです。
- スモールビジネス:
- 個人事業や数人で完結
- 事業規模を大きくする必要がなく、オーナー自身の生活を支えられれば十分という考え方が多い
- ソリッドベンチャー:
- 早期収益にこだわる点はスモールビジネスと似ているが、同時に組織の拡大や事業の多角化を前提としている
- 受託やコンサルを入り口に、SaaS・プラットフォームなど新事業へ“ジワ新規”し、長期で成長し続ける狙いがある
- 必要があれば外部資本も注入する
言い換えれば、ソリッドベンチャーは「第1段階はスモールビジネス風だが、そのまま終わらずに段階的に大きくしていく」のが特徴。
ここが一般的なフリーランスや小規模専門店とは異なる点です。
早期収益化で得られるメリット
資金繰りの安定
スタートアップにありがちな「次の調達を半年以内に決めないと事業が回らない」という焦燥感が低い。
外部投資家への依存を減らせる
大きな資本を入れられれば成長は早いかもしれないが、投資家のリターン要求やEXIT期限の縛りが厳しくなる。
自社キャッシュフローを再投資に回せる
“稼ぐ → 次の開発投資へ投入 → さらに稼ぐ”という好循環。
希薄化を最小限にし、創業者の経営権を守りやすい
調達ラウンドを重ねるほど株式の持分が小さくなるが、必要最小限ならコントロールも維持しやすい。
スモールビジネス的な“受託・コンサル”×段階的な“ジワ新規”の流れ
初期段階:地味な領域でも「確実な受注」を狙う
プログリット社は英語コーチングというニッチ領域で、短期集中プログラムを運営して安定的に収益をスモールビジネスがまさに得意とするのが、「確実に現金を生み出す仕事をまず取る」動きです。ウェブサイト制作、システム受託、コンサルティング、広告運用代行、翻訳・通訳……とにかく地味でも確実な案件があれば、それが安定収入につながります。
ソリッドベンチャーの場合もこの点は同じ。しかし、そこから先に「会社を大きくする/SaaSへ転換する/グループ化する」ビジョンがあるため、単なる個人依存にはしないで仕組み化を進めるのがセオリーと言えます。
次ステップ:既存顧客や市場に“ジワ新規”を仕掛ける
1つの受託案件で安定収益が出始めると、次は「顧客が抱えている別の課題を別サービスで解決する」という形で横展開を図ります。いわゆるアンゾフの成長マトリックスで「既存顧客×新商品」か、「新顧客×既存商品」を少しずつ試すのです。
- 例えば、SEOコンサルしている会社が、その技術を用いて自社メディア運営を始める
- デザイン受託をやっていた会社が、顧客の悩みに合わせてSNS運用代行もセットにする
- BPOで事務作業を代行していた会社が、オンラインで人材をマッチングするプラットフォームを開発
こうすることで、いきなりゼロから新市場へ飛び込むリスクを下げながら、収益基盤を拡大できるのがソリッドベンチャーのうまみです。
最終的には自社サービスやM&Aで“企業価値”を高める
初期の受託・コンサルを続けるだけでは、どうしても利益率に限界があったり、人的リソースの制約があったりします。そこでソリッドベンチャーは、中期・長期の視点で「自社サービス化(SaaS展開やプラットフォーム構築)」を目指し、安定的なストック型ビジネスを育てていく動きに出るわけです。
もし大きく成長した際には、スタートアップのようにIPOを狙ってもいいし、スモールM&Aで10〜20億円程度で事業売却して、創業者や社員が大きなリターンを得る選択肢もあります。
また、最近は海外投資家も小規模ながら着実に売り上げを伸ばす日本企業を評価するケースが出てきているため、グローバルなM&Aも十分に考えられます。
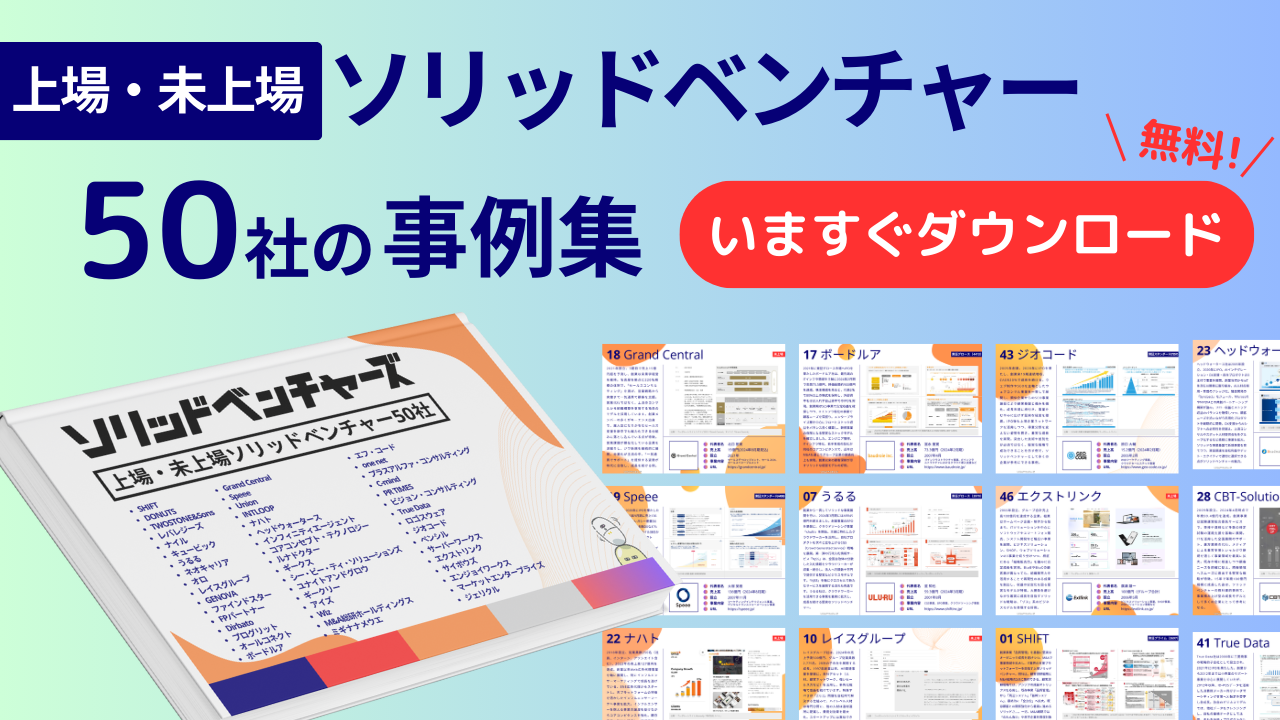
プログリット社の実例(英語コーチングを堅実に組織化)
コーチングの隙間市場にフォーカス
英語学習市場は大手英会話スクールがひしめくレッドオーシャンに見えますが、“コーチング”というニッチ領域はまだ十分カバーされていなかった時期がありました。
プログリット社はここに注目し、マンツーマンの短期集中プログラムを提供する形で、安定収益を確保したのです。
スモールビジネスとの違い:マニュアル化・仕組み化
もし個人の英語講師が同じようなコーチングをすると、講師個人のスキルに依存するケースが大半。ところがプログリット社は、指導マニュアルを整備し、複数のコーチを雇用する「仕組み」を作り上げました。
これにより創業者本人が現場に入らなくても、一定のクオリティで大量の受講生をサポートできるようになります。ここが単なるスモールビジネスで終わらないポイントです。
- サービスの即金性
受講生は3〜4か月など短期間のプログラムを一括前払いするため、キャッシュがすぐ回る - オンライン化による顧客拡張
元々対面でもオンラインでもコーチングが可能で、地方や海外からの受講にも対応 - 安定収益があるから新事業にも注力可能
自社アプリ開発や別分野のコーチング(語学以外)への展開も検討しやすい
結局、英語学習という“地味だけどニーズが途切れない領域”で確実に売り上げを立てられたことが、プログリット社の長所になっています。
ナイル社の実例(SEOコンサルから自動車サブスクへ)
創業はSEOコンサルでキャッシュを稼ぐ
ナイル社は、もともとSEO(検索エンジン最適化)のコンサルティングや運用支援で安定した売上を築きました。SEOコンサルは、クライアント企業からのプロジェクト受注により、比較的短期間で売上を回収できるビジネス。
しかもノウハウがある程度固まってくれば、同じ手法を別のクライアントにも横展開でき、キャッシュの拡大がしやすい分野です。
そこからアプリ比較メディア、ついには“定額カルモくん”を生む
初期のSEOコンサルで利益を積み上げつつ、自社メディアやスマホアプリ比較サイトを立ち上げ、さらには自動車サブスク「定額カルモくん」へと発展させています。なぜこんなにも違う領域に踏み込めたのでしょうか?
- SEOコンサルで身につけた集客ノウハウ
どんなテーマでも「ネット集客」を得意とし、メディア運営に乗り出しやすかった - 安定したキャッシュフロー
コンサル収益で日々の運営コストを賄い、新規事業は「新市場×既存スキル」で段階的に試せる - 地味だが継続ニーズのある分野を選ぶ
自動車リースは大手も手掛けていたが、細分化されたニーズに応じた月額プランをネット完結で展開する隙間があった
結果として、ナイル社は「ただのSEOコンサル会社」から「複数の自社サービスを持つソリッドベンチャー」へ進化し、安定的な収益源をさらに増やしています。
オロ社の実例(受託制作からERPを自社開発し、中堅企業を狙う)
受託Web開発の経験をERP化に活かす
オロ社は、創業初期は受託Web制作やシステム開発を行い、堅実にキャッシュを獲得していました。その過程で「案件管理が煩雑だ」「受注金額と実際の原価が見合わない」といった課題に直面し、自社用に業務管理ツールを開発。
そこから「このツール、他社でも使えるのでは?」と考えERP(ZACシリーズ)として外販を始めたわけです。
ニッチな中堅・中小企業ERPの大きな需要
大企業向けの高機能ERPは既に市場が飽和気味ですが、中小〜中堅規模が導入しやすい価格帯や機能セットはまだまだ空白がありました。オロ社はここを攻めることで、受託だけに頼らないサブスクモデル(クラウドERP)を確立。
受託での売上があるからこそ、ERPの開発コストや営業コストを自己資金でまかなえたといえます。
- 受託×ERPの相乗効果
ERP導入に付随するカスタマイズやコンサルで追加売上を得られ、顧客は一貫して同社に依頼できる - 早期収益化しつつ新規プロダクトを実装
自社アセット(ノウハウや開発チーム)を活かし、効果検証を行いながらローンチ - M&Aやグループ経営にも展開可能
後々は関連ツール会社を買収し、エコシステムを拡大
M&A総研ホールディングス社——「完全成功報酬制」で中堅市場を席巻
もう一つ、早期収益化の事例として挙げたいのが、M&A総研ホールディングス社。
後発ながら「完全成功報酬制」で突き進み、2024年9月期は売上165億円を見込む上場ユニコーン企業です。
- 完全成功報酬制の導入
高額な仲介手数料がネックになりがちなM&A市場で、成功報酬以外の着手金をカットして差別化 - 労働集約型ビジネスでもITやDXを駆使
組織力を強化し、人材の数×生産性向上で売上を積み上げる - 着実な受注→追加サービス開発へ
仲介契約から始まり、企業のDX支援や資産運用コンサルをクロスセルして安定収益を拡大
このように、地道な仕組みづくりとニッチな差別化でキャッシュを確保しながら、着実に規模を伸ばすのはソリッドベンチャーの典型パターンと言えます。
ソリッドベンチャーが拓く「地に足のついた」成長シナリオ
ここまで、早期収益化にこだわるソリッドベンチャーのビジネスモデルを見てきました。プログリット社が英語コーチングを仕組み化することで地味でも確実な売上を獲得し、ナイル社がSEOコンサルから自動車サブスクにまで領域拡大、オロ社が受託制作からERPのSaaS化に成功など、いずれも「最初に受託やコンサルで安定収益を取り、そこで得たアセットを横展開する」という共通項が伺えます。
また、補足例のM&A総研ホールディングス社のように、労働集約型ビジネスの形で確実に売り上げるケースも存在し、そこから周辺サービスを展開することで着実に業績を伸ばす企業も増えてきました。いずれの企業も、当初は大きな投資をせずに地固めをしている点が共通しています。
スタートアップのような急成長を志向する場合は、大量の資金とリスクを取る覚悟が要る一方、ソリッドベンチャーは地道に安定売上を築きながら、周辺領域に徐々に拡張するモデルです。
ここに競合優位性や経営権の安定など多くの利点がある一方で、「爆発的なユーザー獲得が難しい」「競合が先に資金を投下して市場を取りに来た場合のスピード負けもあり得る」といった欠点も存在します。
それでも、日本市場やニッチ領域における需要構造を踏まえると、ソリッドベンチャーのアプローチは「合理的かつ持続的なビジネス拡大」を可能にする大きな選択肢になってきています。
“スモールビジネスの殻”を破るために:最初の一歩を踏み出そう
ソリッドベンチャーは、スモールビジネスの延長にあるようでいて、その先に明確な「拡大戦略」を持つ点が最大の特徴です。早期収益化できるモデルにより創業期のリスクを抑えつつ、徐々に自社プロダクトや新規顧客領域へと踏み出していけるわけです。
もし、「自分のビジネスが受託やコンサルで収益を上げているが、そこから先が見えない……」と感じているなら、以下のステップをヒントに動き出してみてください。
- 既存顧客の課題を徹底的に調査
受託・コンサルの現場で拾える情報を集める。顧客が抱える問題を一覧化する - スモールスタートで“ジワ新規”
プロトタイプやテストサービスを小規模にローンチ。初期投資は抑えながら実験し、顧客からの反応を得る - 組織づくりを意識
個人依存ではなく、誰が運営しても品質が維持できるようなマニュアル化・プロセス整備を行う - 外部資本は必要最小限
赤字覚悟の大規模投資ではなく、自己資本や銀行融資でコントロール可能な範囲で投資し、過剰な株式希薄化を防ぐ
このような小さな一歩を重ねてこそ、“スモールビジネスの殻”を破り、大きな成長を掴むソリッドベンチャーへの道が開けていくでしょう。急激な拡大はないかもしれませんが、だからこそ土台がしっかりし、リスクと成長が両立した健全な企業文化を築きやすいのも利点です。
ソリッドベンチャーで生み出す着実な未来
ソリッドベンチャーという選択肢は、いわば“地に足のついた”ベンチャーのあり方と言えます。華々しいハイリスクのスタートアップと違い、一歩ずつ着実に稼ぎながら新領域に拡張できるため、失敗リスクを抑えつつも長期的な大化けのチャンスを狙える点が魅力です。
- 短期的に爆発しなくても良いからこそ、社員の育成や新規事業の試行錯誤ができる
- 外部投資家に振り回されにくいので、自社のペースで将来像を描ける
- スモールビジネスを抜け出して大企業へ成長した実例も多数(プログリット社やオロ社など)
日本のビジネス環境は成熟化や人口減少が進み、むやみにハイリスクを取ることが難しい情勢になりつつあります。そんな時代だからこそ、早期収益化を核にしたソリッドベンチャーは、多くの起業家や中小企業が選べる“もう一つの王道”になるかもしれません。
「受託やコンサルしかやっていない」と思われがちでも、その中にこそ、次のサービスや事業のヒントが潜んでいます。じわじわと売上を安定させながら、あらゆる新規領域に挑む柔軟性を兼ね備えたソリッドベンチャーは、これからの時代の主役になり得る存在と言えるでしょう。