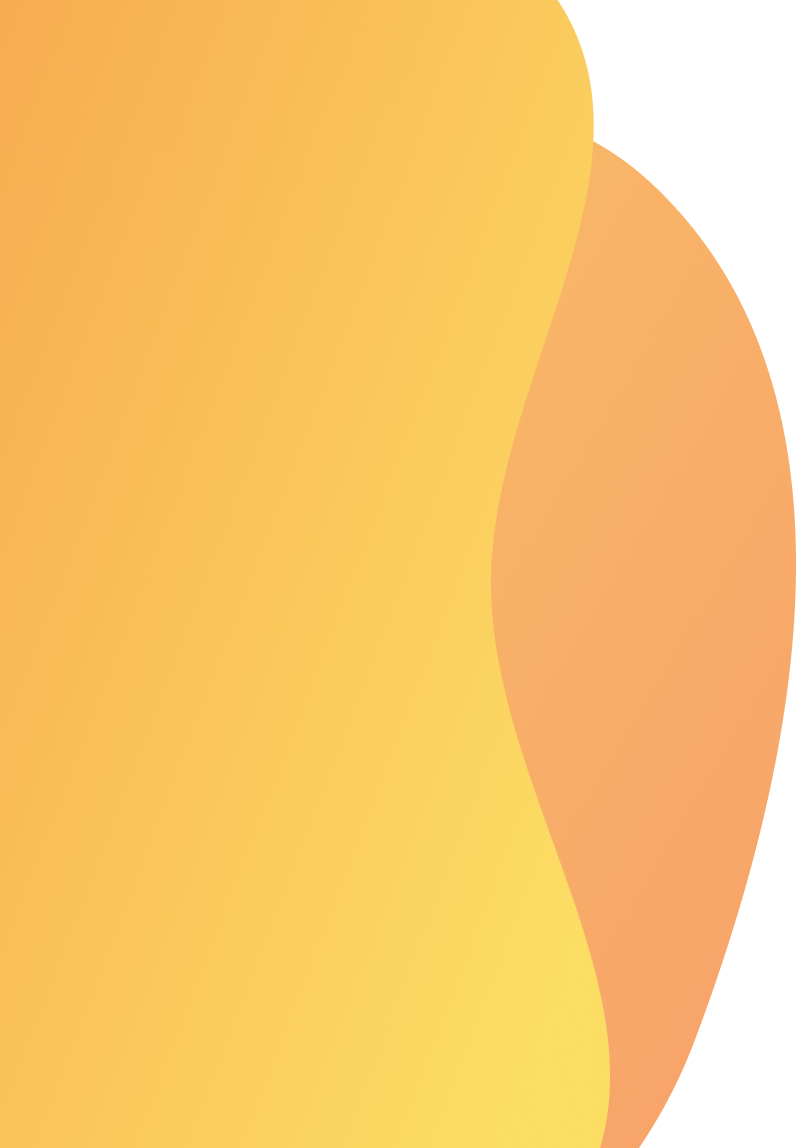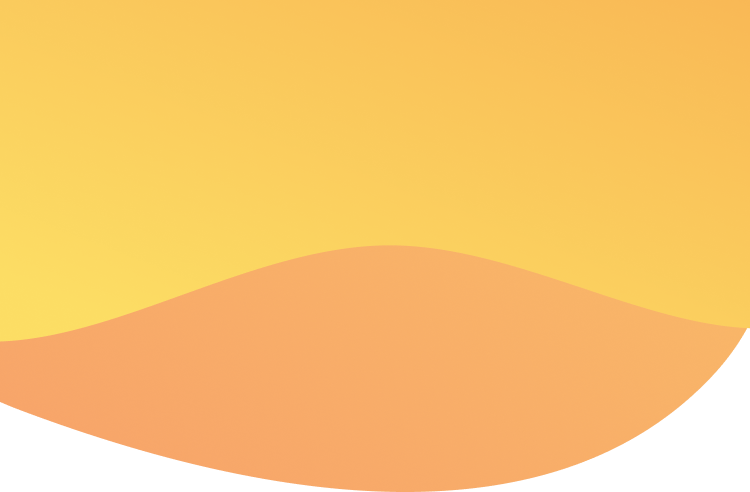2024.11.21
「ソリッドベンチャーとしてのうるる」著者の視点
スタートアップの世界では、大量の資金を調達して赤字を掘りながら一気に成長するモデルが注目されがちです。
しかし近年、「ソリッドベンチャー」と呼ばれる、既存事業での安定収益を拠点に、無理なく新規事業を積み重ねるかたちで着実に事業拡大を図る企業も注目を集めています。
そこには大規模な投資や急激なJカーブではなく、堅実なビジネスモデルとキャッシュフローの積み上げを基盤にしつつ、「段階的な外部資金調達」や「上場」などを組み合わせる柔軟性が見られます。
本記事で取り上げる「株式会社うるる」(以下、うるる)は、2001年の創業以来、OCR(光学文字認識)を活用したデータ入力事業(BPO事業)から始まり、いまではクラウドソーシングを活用した独自の“CGS(Crowd Generated Service)事業”で大きく成長を遂げてきました。
2014年に東証マザーズ上場を果たすなど、堅実なビジネス基盤と着実な多角化戦略によって躍進している「ソリッドベンチャー的な例」と言えます。
ここでは、うるるの創業背景や成長の軌跡、多角化のポイント、そしてその裏にある課題や失敗事例を紐解きながら、ソリッドベンチャーとしての強みを探ります。
■会社概要と創業期
会社情報
- 会社名:株式会社うるる
- URL:https://www.uluru.biz/
- 代表者名:星 知也(代表取締役社長)
- 設立:2001年
創業当初:OCR×データ入力サービス
うるるの創業は2001年。創業者である星知也氏は、大学時代にOCRの研究に取り組み、その技術を活かしてOCRベースのデータ入力をメインとするBPO事業をスタートしました。
OCRは紙の書類などをスキャンして文字をデジタル化する技術ですが、当時のOCRは精度が低く、誤認識した文字の修正作業が不可欠でした。そこで、
- OCRで一次変換
- 人力で検証・修正
というプロセスを外注(BPO)サービス化することで顧客企業の手間を削減し、安定的な収益を上げることに成功。創業期から“OCR+人力”というハイブリッドモデルを確立し、データ入力市場で徐々に顧客基盤を築いていきました。
創業者のビジョン:「人のチカラで世界を便利に」
星氏は「人のチカラで世界を便利に」というビジョンを掲げ、IT技術だけでなく人間の力を組み合わせた事業モデルにこだわりを持ちました。これは後に「クラウドワーカー」という概念に進化し、独自の大きな競争優位を生むことになります。
ソリッドベンチャーとしての成長戦略
1. BPO事業からのキャッシュ創出
うるるがソリッドベンチャーと呼べる特徴の一つは、創業当初から黒字のBPO事業を軸にし、無理のない形で新規事業に投資してきた点です。
OCR×人力データ入力という堅実なサービスは在庫リスクや設備投資が比較的少なく、営業さえうまくいけば一定の収益を安定確保できます。ここで生み出されたキャッシュフローを使い、徐々に新しい取り組みを始めていったのです。
2. クラウドソーシングサービス「シュフティ」の開始
次の飛躍点となったのが、2007年にローンチしたクラウドソーシングサービス「シュフティ」です。当時としてはまだ早期だった「在宅ワーカー」「フリーランス」を組み合わせ、オンライン上で事務作業やデータ入力、簡単なライティングなどの仕事を委託できるプラットフォームを作ったのです。
- 「子育て中の主婦を中心とした在宅ワーカー」に着目
- BPOの下請け構造をさらにオンライン化・マッチング化
によって、コストを低減すると同時に、全国に散在する“働きたい主婦”たちの力を活かすことを狙いました。ここから、うるるのクラウドワーカー活用ノウハウが蓄積され、CGS事業という独自のビジネスモデルに発展していきます。
3. CGS(Crowd Generated Service)事業への進化
クラウドソーシングで集まる大量のワーカーを使って、自社サービスを内製化することで、これまでになかったサービスを生み出す――これがCGS(Crowd Generated Service)の本質です。うるるはここで生まれたアイデアを具現化し、複数の新規事業を成功に導きました。
- fondesk(ファンデスク):電話応対の受託や請求書処理などをクラウドワーカーで行うBPOサービス(テキストは請求書周りの自動化など、資料によっては少し違う説明があるが、ここでは概念的に捉える)。
- NJSS(入札情報速報サービス):全国1,700以上の自治体・公共機関の入札情報を、クラウドワーカーが収集・整備し、一括検索・配信サービスとして提供。
特にNJSSは、日本中の自治体Webサイトに散在する入札公告情報をクラウドワーカーが毎日チェックし、データベース化する発想が大ヒットしました。
既存の大手企業すらやりたがらない膨大かつ地道な作業をクラウドワーカーの力でカバーし、結果として月額課金モデルを構築できたのです。こういったニッチな領域で独自のシェアを確保する「堅いビジネスモデル」は、まさにソリッドベンチャー的発想といえます。
4. 上場による資金調達と加速
うるるは2014年に東証マザーズに上場。元々はOCRやクラウドソーシングといった地味だが着実な収益を生む領域で堅実経営をしながら、上場で得た資金や信用力を活かし、更なる新規事業投資やM&Aを加速できます。ソリッドベンチャーが上場する典型的パターンとして、
- 黒字事業をベースに手堅い財務内容
- ソリッドなビジネスモデルが評価されIPO
- 調達資金で新規事業・既存事業強化
というフェーズを踏んでいます。大きく赤字を掘ることなく、この道筋を実現できたのは、BPOとクラウドソーシングの融合がもたらすキャッシュフローが大きかったからにほかなりません。
事業多角化の成功要因
(1) 既存の強みを延長した新事業
うるるは単に「新規事業はリスクが高いからやらない」のではなく、既存事業とシナジーが高い分野を着実に攻めるという方針を取りました。
BPO事業で得たノウハウと、クラウドソーシング事業「シュフティ」で培ったクラウドワーカー活用技術を掛け合わせた結果、fondeskやNJSSといった独自性の高いサービスが続々と生み出されています。ここがスタートアップ的な「全く新しい領域に飛び込む」のとは異なる、ソリッドベンチャーの王道パターンです。
(2) 地道な業務をクラウドワーカーとITで仕組み化
NJSSを例にとると、全国の自治体サイトからの日々更新される入札情報を“人力”+“自社システム”で収集しているのが大きな要素です。
Webスクレイピングだけでは扱えない形式のファイルやバラバラな公開方法も多く、これを大量のワーカーが“目視チェック”して整備することで、競合他社が参入しづらいデータベースを築けるわけです。このように
- テクノロジーが補いきれない部分をクラウドワーカーが担う
- データベース化した情報をSaaSのように提供し、ストック型ビジネスを確立
するスキームは、いかにもソリッドベンチャーらしい安定収益モデルといえます。
(3) 組織力と“失敗を許容する”文化
創業から約20年の歴史を持つうるるは、各フェーズで試行錯誤や失敗も経験してきました。M&Aで期待通りのシナジーが出なかったり、新規事業の撤退を迫られたりといった事態もあったようです。しかし、その度に学びを得て、組織面・事業面の改善につなげてきた。
「失敗を恐れず挑戦を続ける」という創業者のマインドと、堅実な既存事業に支えられた財務基盤が、うるるをより強固にしてきた要因です。
市場・地域と今後の展望
市場展開:BPO/クラウドソーシング/CGS
うるるの展開する市場は、大きく3つの領域が重なり合っています。
- BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)
- データ入力や請求書処理、電話応対など、企業のバックオフィス業務を代行する市場。市場規模は大きく、人件費低減ニーズは高止まり。
- データ入力や請求書処理、電話応対など、企業のバックオフィス業務を代行する市場。市場規模は大きく、人件費低減ニーズは高止まり。
- クラウドソーシング
- 在宅ワーカーやフリーランスと企業をオンライン上で結ぶモデル。コロナ禍以降、在宅で働きたい層の増加により需要がさらに拡大傾向。
- 在宅ワーカーやフリーランスと企業をオンライン上で結ぶモデル。コロナ禍以降、在宅で働きたい層の増加により需要がさらに拡大傾向。
- CGS(Crowd Generated Service)
- クラウドワーカーがデータを生成・整備することで新しいSaaS型サービスを作る独自のモデル。国内外含め、類似サービスは少なく、まだ競合が薄い市場とも言える。
- クラウドワーカーがデータを生成・整備することで新しいSaaS型サービスを作る独自のモデル。国内外含め、類似サービスは少なく、まだ競合が薄い市場とも言える。
地域:国内中心だが全国を対象
うるるの本社は東京都中央区にあり、BPO拠点を複数地方にも展開している。クラウドワーカーは基本的にインターネットさえあれば全国どこからでも業務可能であり、サービスのリーチも全国をカバー。
今後、海外のデータを扱う可能性や、海外人材の活用などの拡張も視野に入れると、更なるマーケットが開けるかもしれません。
今後の課題と展望
- 課題1:システム・人員のスケール
CGSモデルではシステム面の開発・保守と、クラウドワーカーのマネジメントを拡大する必要がある。ワーカー数が増えすぎると管理コストが急増するため、自動化やAIをどこまで取り入れるかが重要。 - 課題2:競合の参入
同様のプラットフォーム型サービスが増えれば競争は激化し、差別化が必要となる。うるるはOCRやクラウドワーカー活用ノウハウで先行しているが、新規参入企業が台頭してくる可能性もある。 - 展望:CGSのさらなる応用
fondeskやNJSS以外にも、「膨大かつ散在するデータをクラウドワーカーが集約し、SaaS提供する」スタイルは他分野でも通用するかもしれない。医療データ、地方公共団体の各種調査、市場調査分野など、アイデア次第で新規事業を生み出しやすい点が大きな強み。
ソリッドベンチャーとしてのうるる
うるるは創業期からデータ入力BPOで地道に利益を積み上げ、そのキャッシュをもとにクラウドソーシング「シュフティ」をローンチ。さらにCGSモデルへと発展させることで、自社で“労働力を調達する仕組み”を構築し、他社が簡単に真似できないSaaS型ビジネスを立ち上げることに成功しました。
そして、一定の黒字経営と成長トラックが評価され、2014年マザーズ上場という形で資金調達と信用力を手に入れ、事業拡大を加速するという、ソリッドベンチャー的成功ロードマップを具現化しています。
そのポイントを整理すると、
- 安定キャッシュを生むBPO事業を創業期から保有
- 赤字を大量に掘るモデルではなく、地道に利益を得られる基盤を確立
- 赤字を大量に掘るモデルではなく、地道に利益を得られる基盤を確立
- クラウドソーシング事業とのシナジー創出
- 「OCR+人力」から「クラウドワーカー+SaaS」への進化
- 「OCR+人力」から「クラウドワーカー+SaaS」への進化
- CGS(Crowd Generated Service)という独自モデル
- 膨大な作業をクラウドワーカーでこなし、SaaSとして提供するビジネスを連続的に生み出す
- 膨大な作業をクラウドワーカーでこなし、SaaSとして提供するビジネスを連続的に生み出す
- 上場で資金と信用を確保し、さらなる拡大へ
- ソリッドな基盤があるからこそ投資家からの評価も高く、上場後の成長投資がスムーズに
- ソリッドな基盤があるからこそ投資家からの評価も高く、上場後の成長投資がスムーズに
- 失敗を恐れず新規事業に挑み、そのなかで学習を重ねる
- うまくいかなかった撤退案件やM&A失敗も糧とし、組織を強化
- うまくいかなかった撤退案件やM&A失敗も糧とし、組織を強化
このようなプロセスは、典型的な「ソリッドベンチャー」の姿を体現しています。派手なメガファイナンスや高速スケールはないが、確固たる収益源を作り、その強みを軸に段階的に新しい事業領域へ踏み込む。さらに上場で資金を得て、着実に多角化と拡大を果たす――大きく失敗しにくい優れた経営手法です。
「人のチカラで世界を便利にする」という理念は、BPOやクラウドソーシングを通じて多数のワーカーに仕事機会を生み出し、CGSというプラットフォームサービスへと昇華。
日本全国の自治体情報を取りまとめるNJSSをはじめ、膨大な人海戦術をITで効率化するモデルは、まさに「アナログ×デジタル」の融合。ソリッドベンチャーの新たな地平を切り拓いた事例と言えるでしょう。
うるるの事例は、これから起業する方々にとっても示唆に富みます。巨大なイノベーションを狙うのではなくても、確実な需要がある領域でスモールスタート→安定収益を築き→段階的に新規事業→上場も視野に入れるという、リスクが低いがリターンも十分狙える道筋が存在するのです。
こうした企業が増えれば、日本のスタートアップ/ベンチャーシーンも多様化・厚みを増し、より健全なエコシステムが形成されることが期待されます。