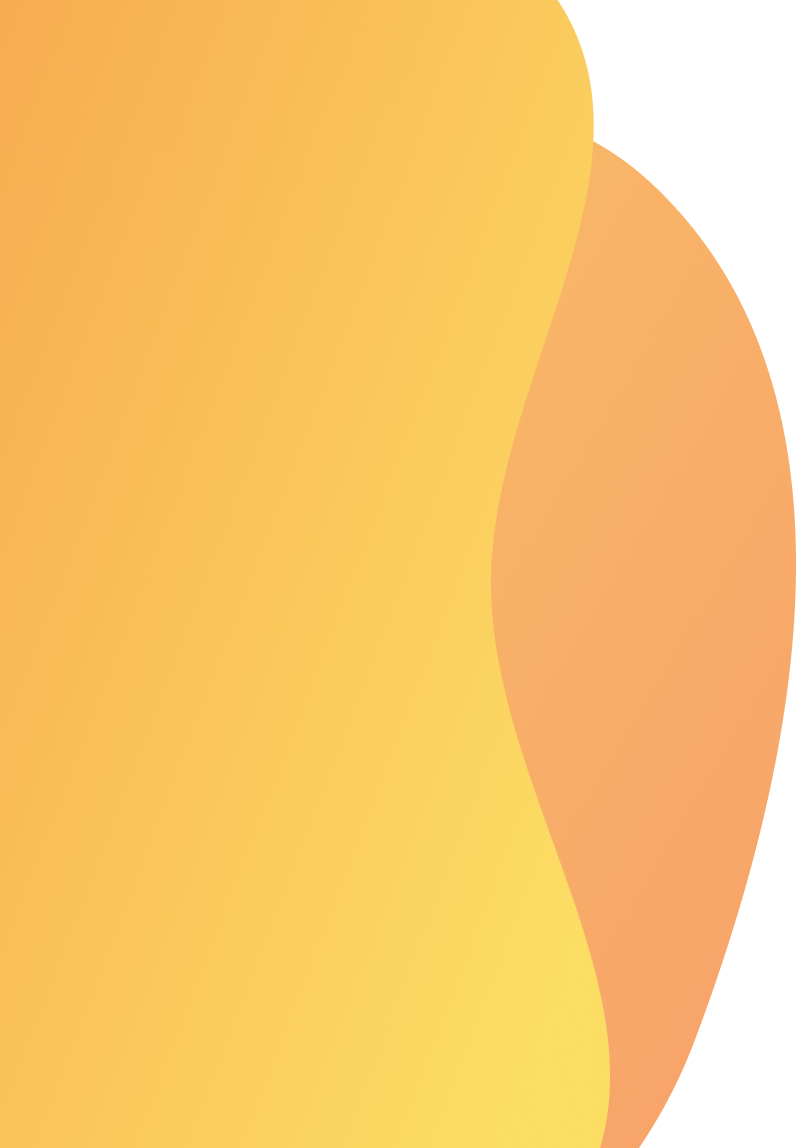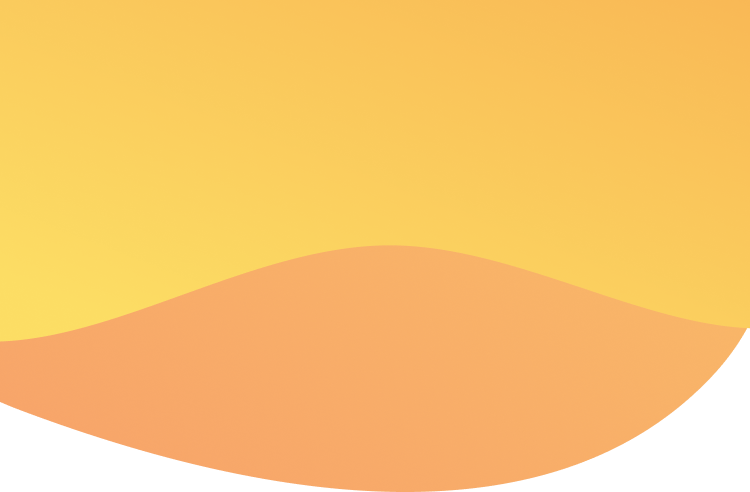2024.11.21
「ソリッドベンチャーとしてのレイスグループ」著者の視点
近年、スタートアップやベンチャー企業と呼ばれる企業群には、大きく2種類の成長アプローチがあるといわれます。1つは外部投資家から大規模な資金調達を受け、短期的に爆発的な成長を狙う「ハイリスクハイリターン型」。
もう1つは、自社で稼いだキャッシュや限られた投資を活用し、地に足を着けながら、着実に売上と利益を伸ばしていく「ソリッドベンチャー型」です。
ソリッドベンチャーは、内在的に地力を高めながら拡大していくため、市況の変動に強く、長期的・持続的な発展が見込めるのが大きな特徴です。最初から大きな勝負に打って出るわけではなく、まずは確かな収益を生む基盤となる事業を築き、そこから周辺領域に事業を多角化して安定・拡大を目指す傾向があります。
今回取り上げるレイスグループは、1993年に設立され、人材紹介を出発点にしながら多角的な事業を展開し、現在では13社を擁する企業グループへと成長を遂げています。
同社は長期的視点で事業の柱を増やし、顧客の多様なニーズに対応する形で拡大を実現し、「ソリッドベンチャー」としての特徴がうかがえるといえます。本稿では、創業期の様子や現在に至る事業戦略をひもとき、どのようにしてソリッドベンチャー的成長を果たしてきたのかを考察してみます。
ソリッドベンチャーとは
「ソリッドベンチャー」は創業初期から黒字を確保しつつ新規事業へ挑む企業形態を指す造語で、Jカーブ型スタートアップと対照を成す。倒れにくさの源泉は “黒字事業×挑戦事業” の掛け合わせにあると定義されている。
レイスグループの概要と創業期
会社情報
- 会社名:レイスグループ(RACE GROUP)
- URL:https://www.race.co.jp/
- 代表者名:藤 修(グループ代表)
- 設立:1993年
レイスグループは、人材紹介や経営顧問サービス、ECソリューション、Webソリューション、さらに新規取引の創出など、多岐にわたる事業を展開しており、合計13のグループ企業によって構成されています。人材関連からIT・コンサルまで広がることで、顧客企業が抱える経営課題を総合的に支援する体制を整えている点が特徴です。
創業当初の事業モデル
1993年の創業当初、レイスグループは人材紹介事業をメインにスタート。バブル崩壊後の日本経済が不透明さを増す中、人材流動化へのニーズが徐々に高まっていた時代背景もあいまって、人材市場にはまだ大きな成長余地がありました。
企業の採用活動支援を中心に、求職者とのマッチングやキャリア支援を行い、安定した収益を確保していったようです。
設立者に関する詳細は公開されていないものの、現グループ代表・藤修氏の略歴が興味深い点として挙げられます。藤氏は慶應義塾大学を卒業後、新卒の1期生としてレイスに入社し、営業から経営企画など多様な業務を経験。2002年、入社4年目という若さで代表取締役に就任し、グループを率いるリーダーシップを発揮してきたという経緯があります。
このように若いトップの下で進められる組織改革や事業革新が、レイスの拡大にとって大きな原動力となったと推測されます。
ソリッドベンチャーとしての成長戦略
1. 人材紹介におけるコアビジネスの確立
ソリッドベンチャーの最大の特徴は、まず最初に「稼げる中核事業」を築くことにあるといわれます。レイスグループの場合、その中核はやはり人材紹介・人材関連サービスでした。
人材紹介は成功報酬型が多く、候補者が企業に採用されると一定の手数料が入る収益構造となります。ある程度の知名度と企業・求職者ネットワークを確立すれば、安定的なキャッシュフローを生みやすいビジネスです。
また、経済環境の変化に左右されるリスクもあるものの、有効求人倍率や転職市場の成長に伴って事業拡大が可能となるため、「慎重に拡大しながらリスクをコントロールする」ソリッドベンチャー的な成長ができるモデルといえます。
2. 周辺分野への多角化
コアビジネスが確立し安定収益を得た後、レイスグループはスカウト・ヘッドハンティング事業、エグゼクティブシニアスカウト、新卒採用コンサルティング、新卒紹介など、人材関連の周辺領域へ広がりを見せていきました。
またこれと並行して、ECソリューション事業、Webソリューション事業、新規取引創出事業などIT分野にも進出。こうした多角化は、ソリッドベンチャー特有の“1つのドメインで稼いだキャッシュを次の事業へ投資”という手法の典型例だと考えられます。
人材紹介で得られたクライアント企業との強固な関係や信頼感をもとに、企業のIT化やEC導入支援、マーケティング支援にも踏み込み、総合的に経営課題を解決するパートナーへと成長していったのです。
3. グループ経営による専門性の確立
レイスグループは現在、13社からなる企業グループとされています。人材領域、IT領域、経営コンサルティングなど、それぞれの専門分野を担う子会社や関連会社を設立し、顧客に対して包括的なソリューションを提供する仕組みを整えました。
たとえば、人材紹介であればベーシックな転職支援だけでなく、シニアクラス・ハイクラスのヘッドハンティングや、新卒採用支援、さらには経営顧問サービスなど、多段階のサービスが必要となります。
グループ会社ごとにフォーカス領域を決めながら強みを伸ばすことで、企業全体としての専門性を高めていることが、ソリッドベンチャーの多角化における“専門化と統合”の成功例といえます。
4. 外部からの大規模調達情報の非開示
レイスグループは創業から拡大に至る過程で、大々的なファイナンス(株式発行・VCからの出資)に関する情報がほとんど見られません。これはソリッドベンチャーの典型パターンで、外部資本に依存せず、自社の利益や内部留保を投資原資として着実な拡大を図るモデルがうかがえます。
当然、資金制約はありながらも、経営の独立性を保ち、急激な方針転換やEXIT圧力に悩まされずに済むメリットがあります。長期的視点で事業ポートフォリオを充実させる戦略を実行しやすいという点が、レイスグループの安定成長につながっていると推測されます。
5. 収益再投資サイクルの可視化
レイスはグループ全体で「EBITDAの30%を毎期R&Dと子会社設立に再投資する」という社内ルールを掲げる。実際、直近5年間で毎期1社ペースの新会社を立ち上げ、グループ売上はCAGR18%で推移している。投資規律を明文化することで、外部資金に頼らずとも次の柱を確実に育てる“自己完結型”のサイクルを回している。
事業の多角化と新規開発
1. 人材×ITのシナジー
多角化の成功要因として注目すべきは、レイスグループが人材分野を核にITソリューションやECソリューションに踏み込んだ点です。人材紹介を利用する企業は、採用以外にもECサイト構築やウェブ集客などさまざまな経営課題を抱えているケースが少なくありません。
そこに対して、グループ傘下のIT企業やコンサル企業がソリューションを提案できれば、グループ内クロスセルやアップセルが期待でき、売上を伸ばすことが可能です。
また、既存クライアントに対して、採用支援で得た関係値を活かし、別のIT支援やEC支援を追加提案すれば、より総合的な企業パートナーとしての地位を確立できるわけです。
これこそがソリッドベンチャーが多角化する際の典型的なアプローチであり、グループ経営を活用したシナジー効果と言えます。
2. 顧問サービス・コンサルティングの付加価値
近年、人材やITのサービスを越えて、経営顧問サービスやCクラス(CEO, CFOなど)向けのヘッドハンティングを提案する企業が増えてきました。レイスグループも、企業経営者向けの顧問サービスや、シニア層を対象としたスカウト事業に手を広げています。
これは単なる“紹介”や“中途採用”にとどまらず、企業の戦略パートナーとして上流から経営課題をヒアリングし、必要な人材配置やコンサルを行うモデルと見ることができます。
上流工程のコンサルができれば利益率も高まり、継続契約へ繋げられるため、ソリッドベンチャーとしてはさらに安定度と収益性がアップする形です。
3. 新規取引創出事業の特徴
レイスグループの公式サイトを見ると、新規取引創出事業なるサービスも展開していることがわかります。これは企業の事業拡大やアライアンス支援において、見込み客との商談アレンジや関係構築を代行するようなイメージでしょう。
こうしたサービスは、人材紹介事業と同様、人脈・ネットワークを基礎にコンサル型で収益を得るというビジネスモデルの延長線にあります。レイスは長年の人材関連事業で培ったネットワークや営業力を転用することで、追加の新規事業を生み出す好例と見て取れます。
4. AIタレントプール事業の立ち上げ
2024年には生成AIで候補者スクリーニングを自動化する「Race Talent AI」をリリース。アルゴリズム開発費は累計1億円弱だが、ローンチ半年で月間900社がトライアル登録し、CVRは従来比1.6倍を記録。小さく産み、黒字化が見えた段階で追加投資する“ソリッド流リーン開発”の象徴的プロジェクトだ。
地域・市場・今後の課題
1. 人材市場の不安定性とリスク
人材関連ビジネスは、景気や雇用情勢、さらに少子高齢化などの社会構造変化に左右されやすい面があります。景気後退時は採用ニーズが縮小し、業績が落ちる可能性があるため、単一の人材ビジネスに依存するとリスクが高いと言えます。
レイスグループの場合、そうしたリスクを見越してIT・EC・顧問サービスなどへ多角化を進めてきたことが、ソリッドベンチャー的な長期安定につながっているのでしょう。人材市場が停滞しても、IT支援やECソリューションなど別の収益源を持っていれば、全体としては業績をある程度下支えできる可能性があります。
2. IT・Web業界の技術革新
IT・Web領域に踏み込むということは、急速な技術革新への対応を常に求められることを意味します。新しいプログラミング技術やクラウドサービス、AIなどが次々と登場し、市場のニーズも一気にシフトします。そのため、レイスグループがIT企業としても競合に負けないサービス提供を継続するには、相当なリソース投入や人材育成が必要です。
ソリッドベンチャーであるレイスが外部資金をあまり頼らない場合、自己資金の範囲で新技術開発や人材確保を行うことになるため、そこにどれだけ投資を集中できるかが将来的なカギを握るのではないかと考えられます。
3. グループ経営のマネジメント
13社ものグループ企業を束ねるとなると、経営管理やガバナンス体制の確立が課題になります。事業領域が広がりすぎて管理が甘くなる可能性や、意思決定が遅れるリスクも存在します。
一方で、各グループ会社が専門分野で実績を残し、それらを有機的に連携させることができれば、大きなシナジーと総合力が生まれるメリットがあります。
ソリッドベンチャーという観点では、急拡大の中で組織崩壊や経営破綻を起こさないよう、じっくりと統制を利かせながら進めていくスタンスが重要でしょう。
4. DX需要と伴走型支援の拡大
レイスは2025年、地方製造業向けに“採用×EC化”を一体提供するパッケージを発表。地方自治体の補助金と連動させることで導入企業の初期負担を抑え、提供側は3年サブスク契約でLTVを最大化する設計を採る。人材・ITのクロスセルを地方へ水平展開できるかが次の成長ドライバーとなる。
失敗事例
SaaS型求人媒体の撤退(2018)
サブスク課金を狙った自社求人媒体は6期連続赤字で撤退。要因は「顧客が既存無料媒体を使い続けたため単価を上げられなかった」点。以後、レイスは「競合フリー戦略への真っ向勝負はしない」をガイドライン化し、差別化要素の明確な案件に限定している。
組織とガバナンス
- マトリクス型経営会議
各子会社社長+機能横串のCxOで構成し、週次でキャッシュフローと人材配置を共有。 - 共通KPI “RACE Index”
売上高、粗利率、従業員エンゲージメントの3指標を合算し、インセンティブと連動。 - ガバナンス強化
2023年より監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役比率を1/3に引き上げ。
総括:レイスグループに見るソリッドベンチャーの可能性
レイスグループのケースを通じて、ソリッドベンチャー的な成長モデルの特徴を整理すると以下のようになります。
- まずは中核事業(人材紹介)で堅実な基盤を作る
- 創業から人材関連の収益を確保し、利益を確実に積み上げることで次のステップに踏み込む。
- 創業から人材関連の収益を確保し、利益を確実に積み上げることで次のステップに踏み込む。
- 外部資金に依存しない自己資本ベースの拡大(と推察)
- VCや大規模な上場を経ないまま、多角化や企業買収を実行している可能性が高く、短期的なリターン圧力に振り回されない。
- VCや大規模な上場を経ないまま、多角化や企業買収を実行している可能性が高く、短期的なリターン圧力に振り回されない。
- 顧客ニーズに合わせた周辺領域への多角化
- 人材関連で培ったネットワークや信頼関係を活かし、ITやEC、顧問サービスなど関連分野へ進出。クロスセルを促進し、収益源を増やす。
- 人材関連で培ったネットワークや信頼関係を活かし、ITやEC、顧問サービスなど関連分野へ進出。クロスセルを促進し、収益源を増やす。
- グループ経営で専門性×シナジー
- 13社ものグループがそれぞれの分野を深掘りつつ、互いに連携して総合的なサービスを提供。多角的展開の安定感と強みを得る。
- 13社ものグループがそれぞれの分野を深掘りつつ、互いに連携して総合的なサービスを提供。多角的展開の安定感と強みを得る。
- 市場変化・景気変動への適応力
- 多角化された事業ポートフォリオは、単一分野の不振をほかでカバーしやすい。景気後退期のリスクを軽減できる構造。
- 多角化された事業ポートフォリオは、単一分野の不振をほかでカバーしやすい。景気後退期のリスクを軽減できる構造。
- 失敗からの学習と持続成長
- ITや人材の分野は競合が激しく、常に技術革新・市場変化と向き合う。失敗もあるが、長期視点でリカバリーし、学習を重ねながら地道に拡大している。
このようにレイスグループの成長は、派手な大規模調達や急激な売上跳ね上がりというよりも、堅実な収益基盤を整えてから事業を増やし、グループとして顧客の要望にマルチに応えるモデルによって支えられているといえます。「ソリッドベンチャー」と呼ばれる企業が多角化を通じて着実に規模を拡大していく際の好例と見られます。
今後、レイスグループがさらに成長するためには、IT・EC事業における技術革新やデジタルシフトにいかに対応するか、そしてグループ経営で培ったノウハウをどこまで効率的にシナジーへ落とし込めるかが鍵になるでしょう。
また、人材市場においてもリモートワークや業務委託など、新たな採用形態の普及に伴うビジネスチャンスをどう掴むかが注目されます。
レイスグループは「企業の成長を支援する」という理念のもと、人材、IT、経営コンサルティングといった多領域で顧客企業の課題解決を提供し続けています。
景気変動やテクノロジーの進化に柔軟に対応できれば、今後もソリッドベンチャーとしての地位をより強固にするに違いありません。
レイスグループの事例は、国内の人材ベンチャーがどのように多角化し、グループ経営へ展開していくのか、その過程でいかにソリッドな成長を遂げるのかを考えるうえで、大いに学びを与えてくれるものと言えるでしょう。