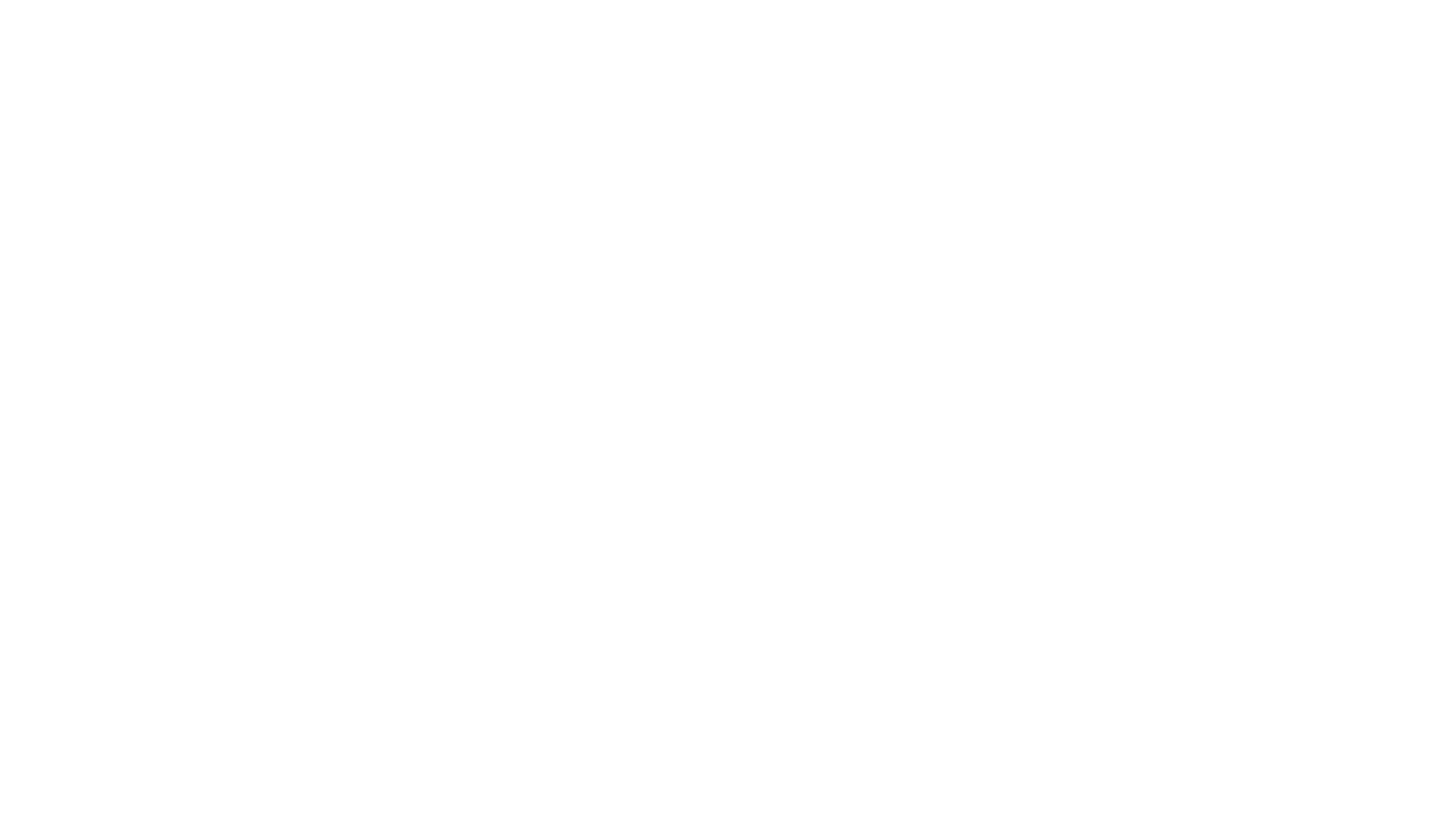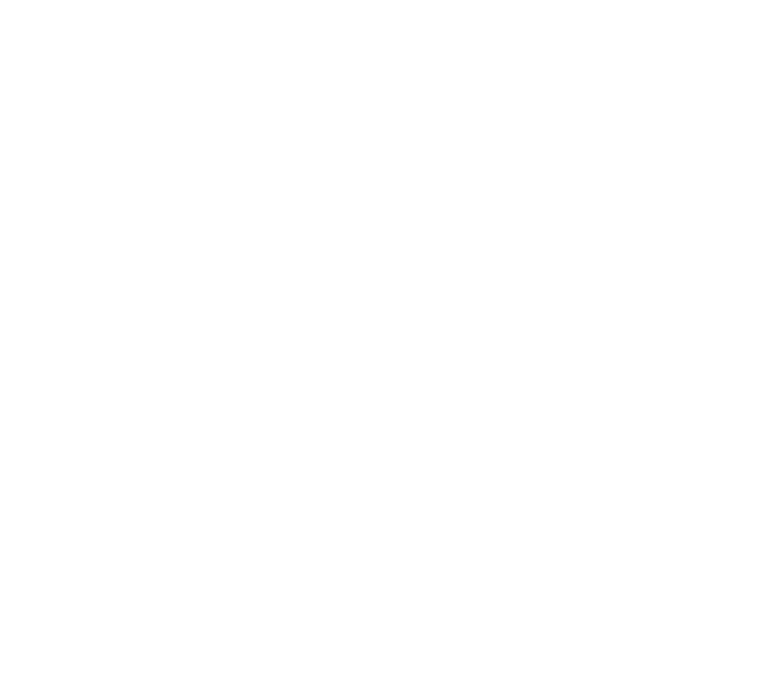- #IPO
- #M&A
- #ソリッドベンチャー
- #出口戦略
「IPOをあえて目指さない」ソリッドベンチャーの非上場成長モデルを考える
公開日:2024.12.24
更新日:2025.6.30
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠
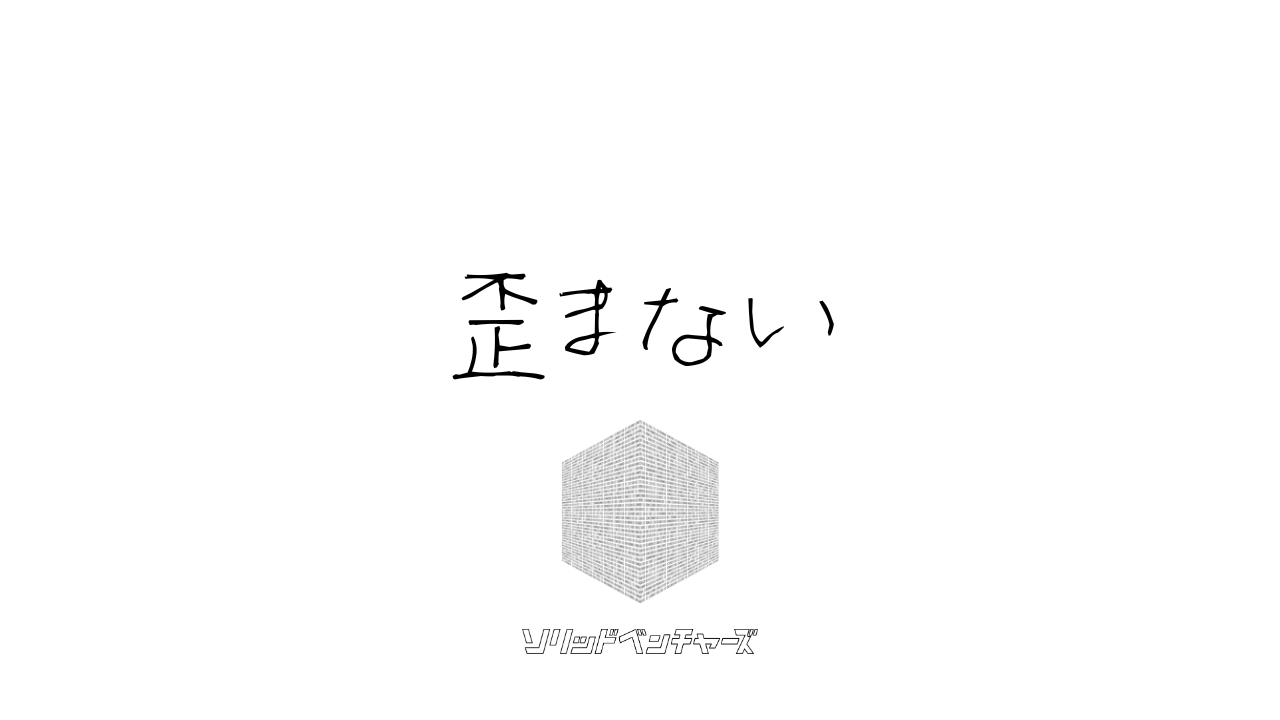
近年、スタートアップの“上場一択”という空気に一石を投じる形で、あえて非上場のまま堅実に成長を遂げるソリッドベンチャーが注目を集めつつあります。投資家や株価への短期迎合を避けながら、長期的な視点で事業を深め、多様な出口戦略を確保する――そんな姿勢が、今のビジネスシーンに新たな選択肢を示しているのです。本記事では、非上場でも大きく伸びているソリッドベンチャーの実例や、そこに潜むメリット・課題、さらには多様なエグジットの方法について詳しく探ります。
ハイライト
- 短期的な株価や投資家要求に左右されず、長期的視野で事業価値を育める
- M&Aや社内持株会など、IPO以外にも多様な出口戦略が存在
- 独自の企業文化と顧客関係性を守りながら、堅実に売上を伸ばす強みがある
IPOを避ける狙いと非上場ソリッドベンチャーの姿勢
スタートアップの典型的な成長ルートには「短期間で上場して投資家リターンを最大化する」という方向性があります。しかし、ソリッドベンチャーと呼ばれる企業の中には、“IPOしない” という明確な意思を持ったところが増えてきました。そこには以下のような背景が見え隠れします。
- 長期的なビジョン重視
四半期決算や株価を気にする必要が薄い分、自社のサービス・プロダクトを腰を据えて磨ける。 - 大きなリスクを回避
上場準備にかかる大幅なコストや複雑な手続き、上場後のIR対応などから解放される。 - 経営者の自由度
外部株主が少ないため意志決定が速く、株主に口出しされない柔軟な経営ができる。
「上場して当然」という風潮への疑問
スタートアップ周辺では「一定の規模になれば上場すべき」という論調も根強くあります。確かにIPOによる大量の資金調達は企業を一気に大きくできますが、その分、短期志向の投資家から成長を急かされるプレッシャーも生まれがちです。これが企業カルチャーを変質させる要因になることもあるでしょう。
反対に、非上場であれば会社の資源をどこに振り向けるかは創業者や経営陣の意志で決められます。事業モデルや従業員の働き方、顧客との関係づくりなども、より長い目で最適化できるのです。
“脱 IPO” ムーブメントの3つの背景
- 資本市場のボラティリティ拡大
新興市場では公募価格割れが常態化し、「上場=資金調達メリット」が縮小。 - 人材の価値観変化
ストックオプションより“やりがい”と“働きやすさ”を重視する若手が増え、上場メリットが相対的に低下。 - M&A エコシステムの成熟
大手・PE ファンドの買収意欲が高まり、“上場前に数百億円規模で売却”という選択肢が現実的になった。
非上場成長モデルの強みと懸念点
経営の柔軟性と長期視点がもたらす恩恵
ソリッドベンチャーが非上場を選ぶ最大の利点は「自由度の高さ」。上場企業ほどフォーマルな株主対応やIR活動を求められず、意思決定は早くなる傾向にあります。社内で「3年先を見据えた投資をしよう」という声が上がっても、四半期決算を気にして舵を急に切らなければならないケースが少ないのです。
- 地道なプロダクト改良
毎期の利益目標を急激に追い求めるのではなく、3年5年先を見据えた開発投資が実現しやすい。 - 独自カルチャー醸成
社員とのエンゲージメントを高める施策に時間を割ける。人材定着や組織力強化につながる。
大きな資金調達が難しいという課題
IPOほど多額の資金が一気に集まる仕組みがないため、“利益を出して再投資” を基本とする経営が求められます。急拡大を狙うスタートアップのように、赤字上等で広告費や開発費を突っ込むスタイルは取りづらいのが現実です。
- 金融機関からの借り入れ
ある程度キャッシュフローが安定していれば銀行融資は受けやすいが、リスクを大きくとるのは難しい。 - 外部監査や透明性の確保
非上場だからこそガバナンスが甘くなるリスクもある。内部統制をどこまで厳密にするかも経営者の判断に委ねられる。
自由度が高い反面、自律的なガバナンス体制の整備は不可欠となり、企業としての「責任ある経営」が問われるのです。
バリュエーションの不透明さ
上場株価のように“誰もが納得する市場価格”がないため、ストックオプションやエクイティ報酬を設計しにくい。↔ 解決策として第三者割当増資で定期的に株価を算定し、社員と投資家に共有している企業が増えている。
非上場でも大きく伸びたソリッドベンチャー
DONUTS社:連続チャレンジで多角化
創業時はSI(受託開発)で安定収益を得つつ、その後は自社メディア「ハウコレ」、ゲームアプリ、そしてSaaS型の勤怠管理「ジョブカン」などを連発。いずれも自社キャッシュフローを元手に“連続的な新規事業”を試し続ける手法で多角化を達成しています。
上場による株主の目を気にせず、同時並行で複数のサービスを回しながらヒットを探せるのは非上場ならでは。結果的に売上や従業員数を大きく伸ばし、有名企業とも肩を並べる存在になっています。
レバレジーズ社:人材サービスを裾野へ拡張
ITエンジニア領域から始まり、医療・介護など人手不足が深刻な領域へと横に広げているレバレジーズ社。長期視点で人材採用やプラットフォーム作りに投資し、非上場ながら年間売上1,000億円を超える規模に。
短期の投資家リターンよりも事業基盤拡大を優先できた結果、IT以外の多様な人材分野でも大きくシェアを獲得。これも、四半期決算に合わせて無理な成長をしなくても良い非上場の強みが生きた例といえます。
非上場でも用意できる多様な出口戦略
「非上場=創業者や社員が株式を現金化しにくいのでは?」と考える人も多いですが、実はIPO以外にもいくつもの出口(Exit)の方法があります。
- M&Aや事業譲渡
- 大手企業やシナジーある同業へ売却し、創業者や株主が株式を譲渡してキャッシュを得る。
- 買収先グループの一員として事業継続するケースもあり。
- 社内持株会・バイバック
- 社内持株会を設立し、社員に株式を渡すことでエクイティインセンティブを付与。
- 創業者が株式を会社に買い戻してもらう「バイバック」制度を活用すれば部分的Exitができる。
- 長期経営でEXITしないモデル
- “永続オーナー企業”として配当や役員報酬でリターンを得る。
- 後継者を社内から育て、長期視点でビジネスを回し続ける。
いずれの選択も、短期的な株価の上下に振り回されず、自社のタイミングと方向性に合わせて進められるのが魅力です。
非上場成長モデルがもたらす長期的メリット
企業文化や顧客関係をじっくり育む
上場企業ではないため、財務的なプレッシャーよりも自社が目指す事業価値に注力しやすいのが強み。例えば、以下のような取り組みがより自然に行えます。
- 顧客とのコミュニケーション重視
売上を急激に伸ばすよりも、顧客満足度を高めるためのサポート体制やサービス改良に腰を据えられる。 - 従業員の育成や福利厚生に投資
“将来を見据えた人材戦略”を優先しやすく、結果的に社員のモチベーションや定着率が向上。
上場準備や短期株価対策からの解放
IPO前後には監査法人対応や証券会社との折衝、決算書類の作成に多くのリソースを割かねばなりません。さらに上場後はマーケットの眼が常に向けられるため、守りに入った経営へシフトしやすいのも実情です。
一方、非上場であれば“数字”より“サービスの質”に焦点を合わせ、よりクリエイティブな経営判断ができる可能性があります。実際、多事業同時並行や“じわじわ成長”ができるのは、投資家向けの急成長プロットを描かなくていいからこその恩恵でしょう。
長期的メリットを享受する運営キーポイント
- キャッシュマシンを複数持つ
例:DONUTS は SI/ゲーム/ジョブカンの三本柱で景気変動をヘッジ。 - 社内 CFO/監査室の早期設置
上場並みの内部統制を自前で実装し、資金調達機会と M&A 交渉力を高める。 - “いつでも上場できる”状態を保つ
月次決算3営業日締め、J‑SOX 相当のプロセスを整備し、外部評価の信頼度を担保。
今後も増え続ける可能性――非上場ソリッドベンチャーの選択
従来、スタートアップ界隈では「大きく調達して一気に上場を狙う」という図式が正攻法とされてきました。しかし、最近の市況変化や投資家の多様化もあり、非上場での持続的成長に光が当たっています。ガートナー調査では、2023年にシリーズC以降の国内スタートアップ78社のうち32%が「上場予定なし」 と回答。2019年比で約2倍に増加しています。
- 投資環境の変動
金融市場の不確実性が増し、上場直後の株価が大きく下落するリスクが強まっている。 - 企業の志向変化
短期的な成長至上主義よりも、組織の安定・文化形成・長期収益を重視する企業が増加。
ソリッドベンチャーが示すモデル
「上場しなくても企業規模を大きくできる」 という事例が積み重なってきたことで、後発の起業家にとっても非上場の選択肢が現実味を帯びてきました。また、M&Aや社内持株会などを巧みに使えば、オーナーと従業員の双方がメリットを享受しながら会社を発展させることが可能です。
“本当にやりたい事業”を徹底できる
IPOを目指さないことで、外部株主の短期的な要望を優先せず、自分たちの理想とするプロダクト・サービスに集中できるのはソリッドベンチャーの真骨頂。地味かもしれませんが、長い目で見れば確固たる顧客基盤や企業文化を形成しやすく、それこそが差別化の源泉となるでしょう。
非上場こそ選択肢の一つ
非上場のまま確かな売上と利益を伸ばし、企業文化を守り続けるソリッドベンチャーの姿は、上場をゴールとした“定型スタートアップ”とは一線を画しています。もちろん、投資家からの大規模資金調達が難しい、ガバナンス整備が自律に委ねられるなどの課題もありますが、それを上回る柔軟性と長期視点が大きなアドバンテージになっているのです。
多様化する市場環境のなか、「IPOだけが答えじゃない」 と気づき始める起業家や企業も増えています。これからも、非上場のまま独自色を発揮して成長を遂げるソリッドベンチャーが増えていくことは十分に考えられます。短期の株価に囚われず、自社が本当にやりたい事業を貫きたい――そんな思いを持つなら、非上場という道も十分に検討に値するのではないでしょうか。
“IPO だけが正解ではない”という現実 - まとめに代えて
- 非上場ソリッドベンチャーは、キャッシュエンジンを持ち自律ガバナンスを整えれば、上場企業に匹敵する成長と社会的インパクトを実現できる。
- 出口戦略は多岐化しており、創業者・社員・ステークホルダー全員がメリットを得られる形を“オーダーメイド”で設計できる。
- 重要なのは「なぜ資金が必要か」「誰のための上場か」を問い直し、自社のミッションに最適な資本構成を選ぶことだ。
短期株価より長期価値を――。それが、IPOをあえて目指さないソリッドベンチャーが示す、もう一つのサクセスストーリーなのかもしれません。