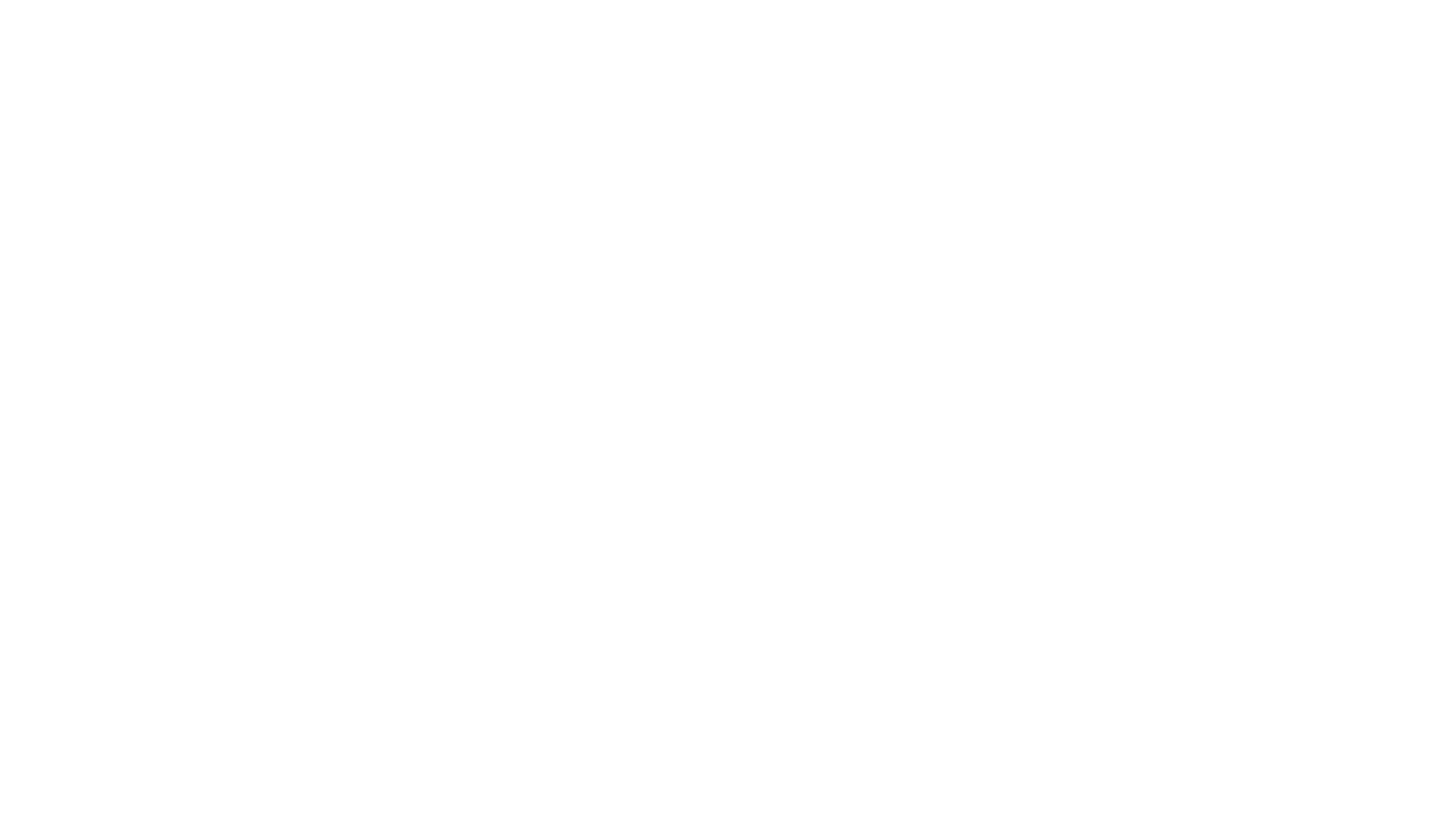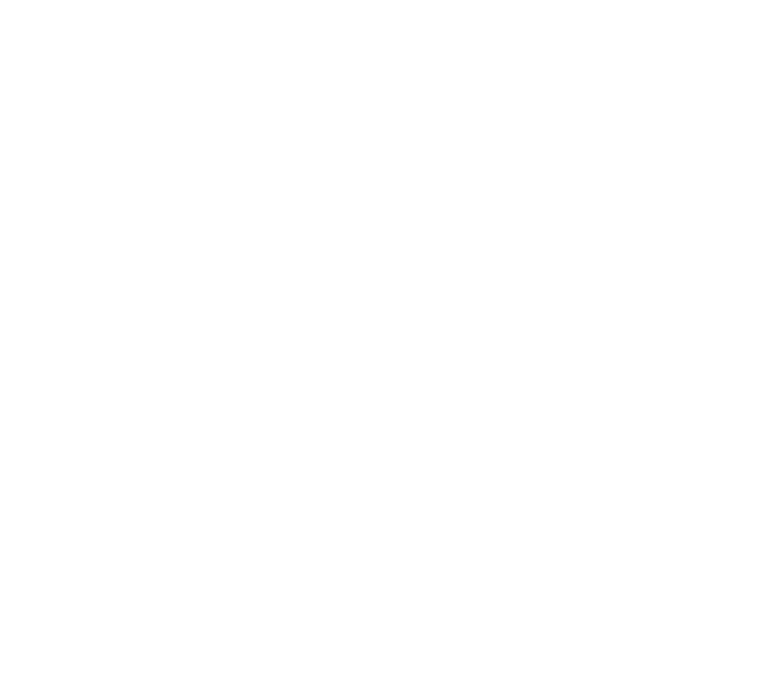- #ソリッドベンチャー
- #ビジネスモデル
- #事例
ソリッドベンチャーのビジネスモデルは現代ビジネスの新たな成長モデル?
公開日:2024.09.12
更新日:2025.4.25
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠
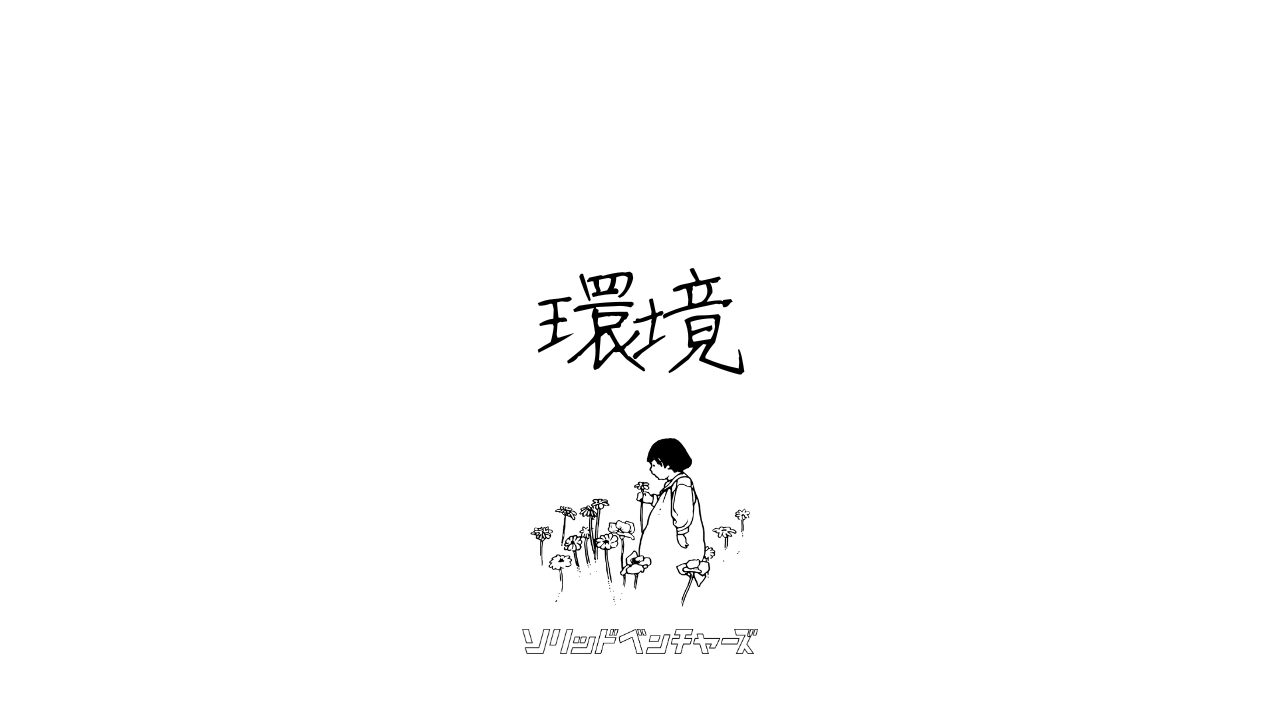
ソリッドベンチャーは、スタートアップのように赤字覚悟で急拡大を目指すのではなく、創業初期から安定した黒字を確保しつつ段階的に新規事業を開拓するビジネスモデルです。地道に稼ぐ受託開発やコンサルを基盤とし、得られたキャッシュフローを自己資金として新たなプロダクトやサービスに投資し続ける姿は、“スピードより着実さ”を重視する現代の起業家や中小企業にとって、大きな示唆をもたらしています。本記事では、なぜソリッドベンチャーが注目され、どのようにリスクと挑戦を両立し、社会に新たな波を生み出すのかを具体的に解説します。
ハイライト
- 安定と挑戦の両立:創業期から黒字を確保することで倒産リスクを抑え、徐々に新規事業を育てる“ジワ新規”が可能。
- 投資家依存を低減:VC資本への過度な依存を避け、創業者が自社のペースや戦略を自由にコントロールできる。
- 社会的インパクトの拡大:地方創生や後継者問題の解決にも資するモデルとして、中小企業を中心に存在感を増している。
ソリッドベンチャーとは何か
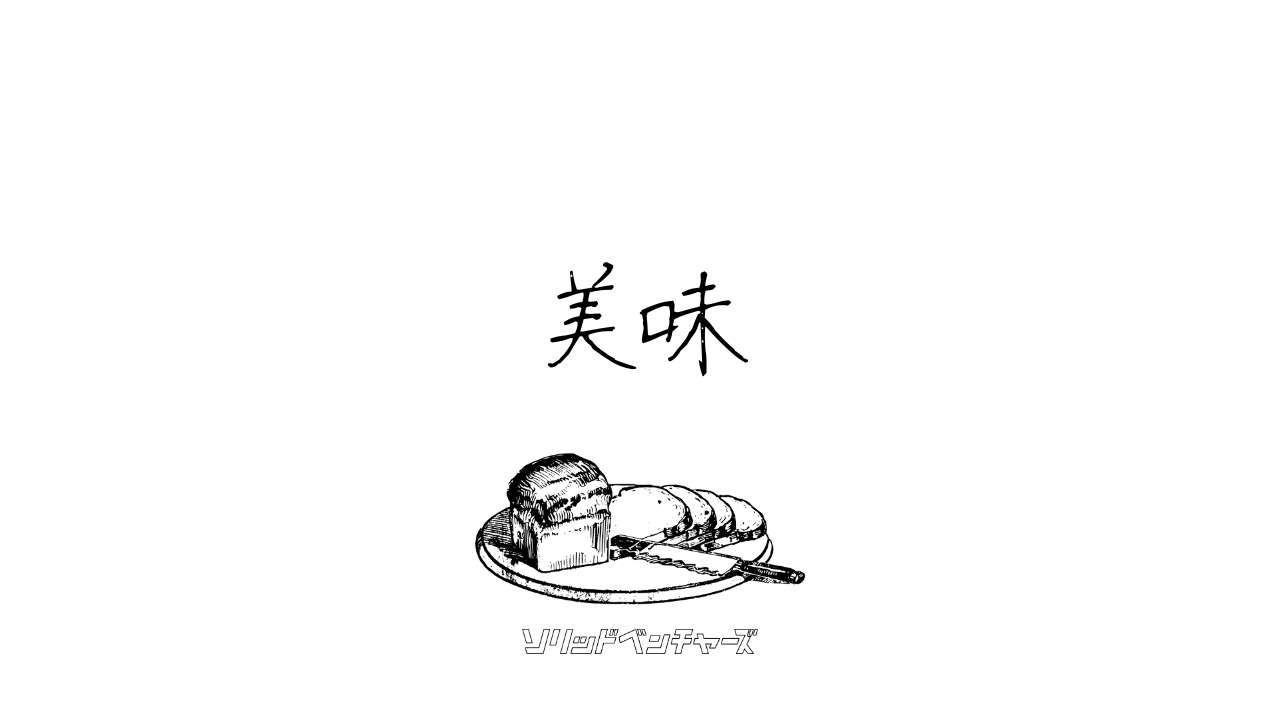
概念と背景
「ソリッドベンチャー」とは、初期段階から収益を安定的に確保しながら、長期的視点で新規事業を開拓していく企業のことです。スタートアップが短期勝負のハイリスク投資に依存しやすいのに対し、ソリッドベンチャーは“自己資本”や“デットファイナンス”を活用し、リスクを抑えて確実に黒字を生み出すモデルを構築します。
- スタートアップ:VC資金 → 急成長狙い → IPOやM&Aで短期EXIT
- ソリッドベンチャー:受託開発・コンサルで黒字 → 新規事業に段階的投資 → 長期的視野で多角化
近年、ユニコーン一辺倒の投資家マインドやIPO至上主義に疲弊した企業も多く、「華々しくなくとも倒れにくい」「しぶとく成長できる」ソリッドベンチャーに注目が集まっています。
現代ビジネスの文脈
VC投資が活況を呈した一方で、短期間で大きな資金調達を繰り返すスタートアップが増加した結果、経営者が投資家の要求に縛られたり、調達タイミングに振り回されるケースも後を絶ちません。
ソリッドベンチャーは、そういった外部要因よりも自己資金での黒字運営を優先し、安定収益が軌道に乗った後に新規事業やM&Aに挑むため、経営者主導の計画が立てやすいのが特徴です。
ソリッドベンチャーのメリット
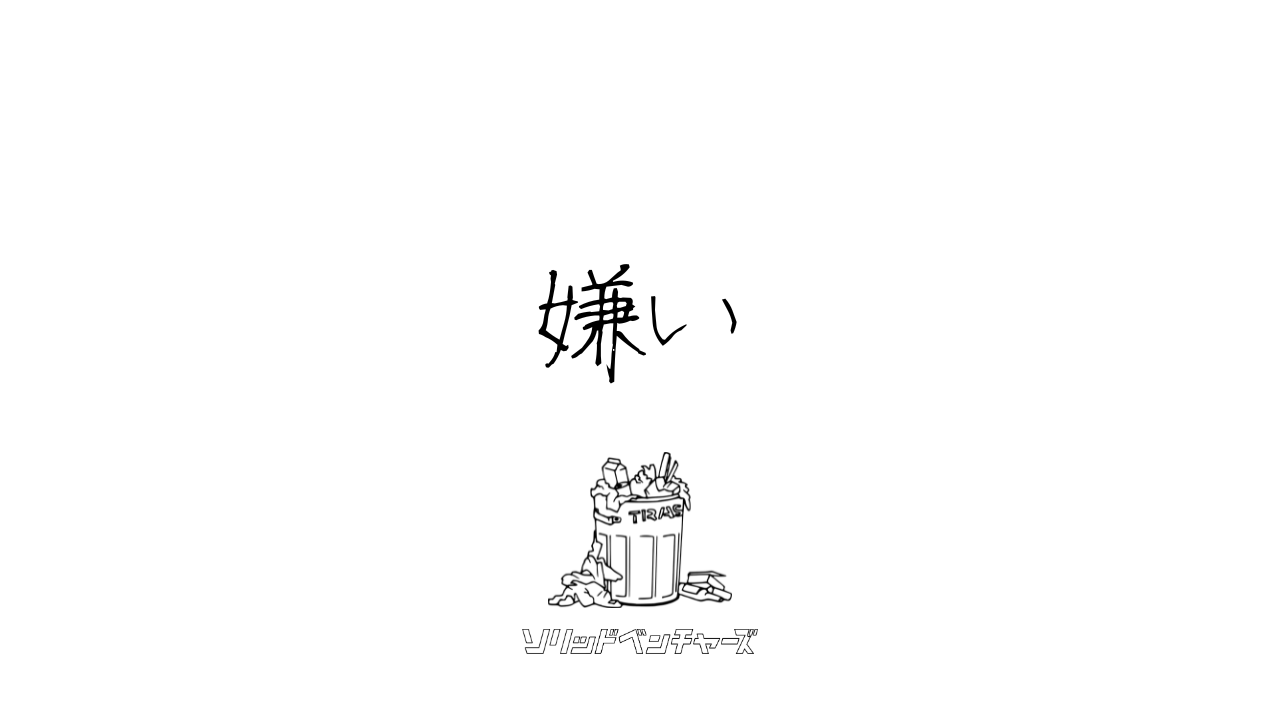
安定した収益基盤
初期からのキャッシュフロー確保
スタートアップでは赤字を掘りながらユーザー獲得を急ぐのが一般的ですが、ソリッドベンチャーは受託・コンサル・BPOなど「すぐに売上になる」事業を創業期から手がけ、短期間で黒字化します。VC頼みにならないので、調達ラウンドが途切れて資金ショートするリスクが低減します。
外部資金に振り回されずに済む
スタートアップが資本政策や投資家対応に多大な労力を割くのとは対照的に、ソリッドベンチャーはVC出資が少なく、銀行借入と自己資金が中心なため、経営者自身で経営方針をコントロールしやすいのです。
失敗に強いビジネスモデル
新規事業での失敗を吸収できる
既存事業が黒字を生む“キャッシュエンジン”の役割を果たすため、新たに始めるSaaSやプロダクト開発がうまくいかなくても、会社全体が即倒産に追い込まれるリスクが少なく、再挑戦のハードルが低いです
M&AやEXITの柔軟性が高い
“安定黒字”であれば、銀行借入などで小ぶりのM&Aを仕掛けて機能強化することも可能。反対に、既存事業を譲渡して得たキャッシュを新規事業に集中するなど、経営の柔軟性が高まります。
市場変化への柔軟対応
既存顧客ニーズから“ジワ新規”へ
ソリッドベンチャーは、既存顧客の課題や要望に合わせて少しずつ事業領域を拡張するやり方を好みます。アンゾフの成長マトリックスでいう、「既存顧客×新商品」や「新顧客×既存商品」の路線で堅実に売上を積み上げ、リスクを最小限に抑えるのです。
技術トレンドや経済変動に耐性
どこか1つのハイリスク領域だけに集中投資するスタートアップと違い、複数の堅実事業を軸に成長するため、市場の浮き沈みに強いのもメリット。地味だが需要が絶えないテスト工程や人材ビジネスを“コアキャッシュ”として持つ企業が多いのはこのためです。
ソリッドベンチャーのデメリット
一方で、このモデルにはスピード感の欠如や投資家とのギャップなどの弱点も存在します。ここでは、その主要なデメリットを詳しく見ていきましょう。
スピード感の欠如
短期的な大規模投資を避ける結果、市場シェアを素早く獲得したスタートアップに先を越されるリスクがあります。特に技術革新が激しい領域だと“先行者メリット”を失いやすく、後塵を拝する恐れがあるのです。
投資家とのギャップ
ハイリスク・ハイリターンを求めるVCとは相性が悪く、**“ミドルリスク・ミドルリターン”**を嫌う投資家からの追加資金を得にくい。大きくリソースを拡張したいときに、まとまった投資が集まりづらい可能性が残ります。
競争激化への備え
安定して稼ぐ仕組みが確立されると「ここは儲かる」とみなされ、後発競合が参入してくる可能性も。そこで差別化するためには、サービス品質の向上やブランド力の強化が必須となります。
ソリッドベンチャーの成功事例
M&Aセンター:着実な組織強化で拡大
既存事業=M&A仲介で安定収益
株式会社M&Aセンターは、中小企業やオーナー企業向けのM&A仲介を専門に手がける事業で着実に収益を確保しています。この領域では、1件あたりの成功報酬が高いため、少数精鋭でも大きな売上を生み出せるのが強み。
多角的サービス展開
M&A仲介から始まりつつも、後継者不在問題に対するコンサルティングや業種特化型M&Aサービスなど、徐々にサービスを拡張。これにより“M&A=M&Aセンター”というブランドイメージを確立し、多角化にも成功しています。
ソリッドベンチャーらしさ
M&Aセンターは短期間での爆発的成長を狙うというよりも、「中小企業のオーナーが安心してM&Aに臨める」仕組みを堅実に作り上げ、それをもとに徐々にサービス領域を広げてきました。
外部投資に左右されず、安定的に高い利益率を確保し続けている点が、まさにソリッドベンチャーの王道といえます。
ベイカレント・コンサルティング:組織力重視のソリッド型
技術革新より組織力・ブランディングを最重視
ベイカレント・コンサルティングは、ITコンサルやDX支援など、コンサルティング事業を中心としたビジネスモデルで着実に成長してきました。
大手コンサルとは異なる“国内企業に合った支援”を強みとして打ち出し、“地に足の着いたコンサル”というポジショニングを獲得。
安定収益の中でリスクを取る余裕
コンサルティングはプロジェクト型でありつつも、リピートや保守運用フェーズの契約などで一定のキャッシュフローを確保可能。この収益を背景に、新規サービスや研修プログラム開発への投資を行い、さらに人材採用・育成にも力を注いでいます。
大手企業のDX需要をキャッチ
国内大企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める波に乗り、多くのプロジェクトを手がけることで一気に知名度を上げたのも事実。
ただしベイカレントの場合、最初から豪快に広告投下をするスタートアップの手法ではなく、地道に成果を積み上げてリピーターを増やす形で、コンサル企業としての地位を固めたのです。
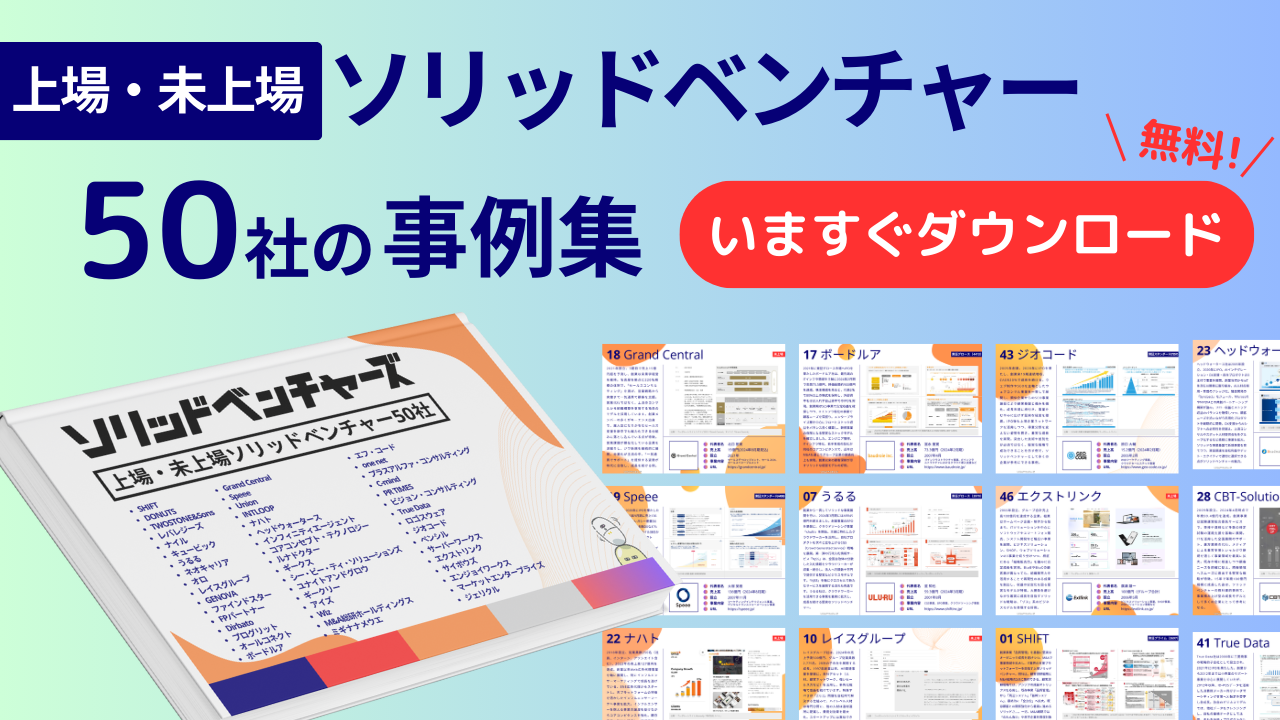
ソリッドベンチャーを目指すための基本ポイント
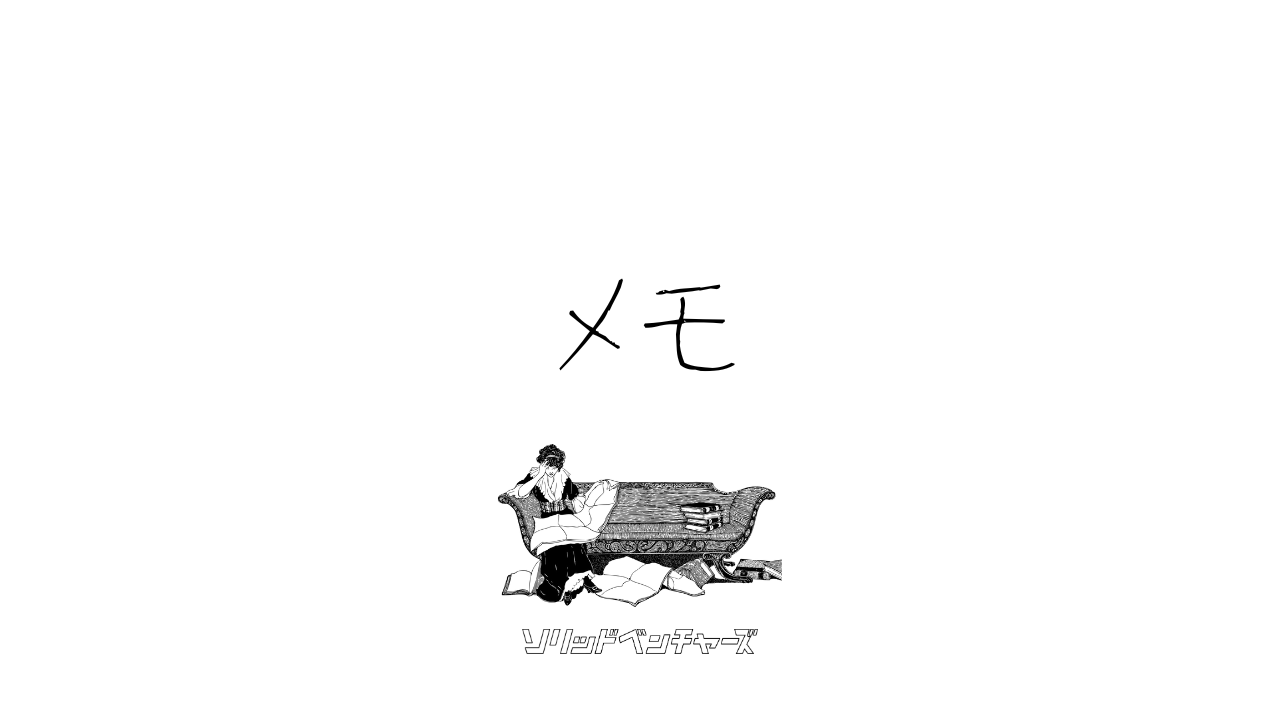
既存事業の強化
まず肝心なのは、“稼げる”既存事業があること。ここがキャッシュフローを生む土台となり、新規事業やM&Aへのリスクテイクを可能にします。既存事業が強固であればあるほど、ソリッドベンチャーとしての安定感が増すわけです。
段階的な“ジワ新規”展開
ソリッドベンチャーでは、いきなり未知の分野に大投資するより、既存顧客や近隣市場の課題を捉えた拡張が主体。「アンゾフの成長マトリクス」でいう“既存市場×新商品”“新市場×既存商品”を少しずつ埋めていく戦略は、リスクを最小限にしながら売上拡大を図る巧妙な手法です。
リスク管理と長期ビジョン
スタートアップが短期勝負でIPOを目指すのに対し、ソリッドベンチャーは長期目線で経営します。そのため「今期で大きなリターンを得なくてもいい」と割り切れる反面、投資家からのプレッシャーに屈しない強い意志が必要です。
受託ビジネスからソリッドベンチャーへ
(1) M&Aで事業を一気に拡大
23株式会社は、もともと中規模のWeb制作・運用会社でした。受託案件で安定した売上があったため、そのキャッシュを活用して関連サービスを提供する小さな会社を次々に買収。デザイン・マーケティング・システム開発など、多彩な機能を社内に取り込むことで、総合的なWebソリューション企業へと進化を遂げました。
(2) 既存顧客を軸にシナジーを発揮
買収先企業が提供するサービスを、既存顧客へのアップセルとして展開。これにより買収先企業も短期間で売上を増やせるという好循環が生まれました。さらに、23株式会社は既存事業(Web運用)からの安定収益があるため、M&A後の統合コストや追加投資をカバーしやすく、失敗リスクを低減できたのです。
(3) ソリッドベンチャーの要諦
23株式会社のケースからわかるのは、**「既存事業で稼ぎつつ、必要な機能をM&Aで補完」**という戦略がソリッドベンチャーらしい手法だということ。外部資金を頼らず、自己資金および銀行借入でM&Aを進めたことで、経営の主導権を維持しつつ、段階的に事業をスケールさせることに成功しました。。
組織づくりとマネジメント戦略
ソリッドベンチャーとして成功を収めるには、組織体制とマネジメントが非常に重要です。ここでは、特に人材採用・組織カルチャー・権限移譲の3点に注目します。
人材採用:少数精鋭と専門性の確保
受託ビジネスやコンサルにはプロフェッショナル人材が必要
初期収益を得る手法として多いのは、コンサルや受託開発ですが、ここでは専門性の高い人材が欠かせません。ベイカレント・コンサルティングがそうであるように、人材の質が直接サービスのクオリティに直結するため、採用にはコストと手間をしっかり割く必要があります。
大量採用よりも厳選採用
ソリッドベンチャーはスタートアップのように短期間で100人、200人と増やすやり方より、組織の成長フェーズに合わせて厳選採用する傾向があります。給与水準や働き方、キャリアパスなどを丁寧に設計し、長期的にコミットしてくれる人材を囲い込むのがセオリーです。
組織カルチャー:失敗を許容する風土
(1) 新規事業への挑戦を奨励
既存事業の利益を背景に、新規プロダクトやサービスを試せる余裕がある反面、社員が「どうせ本業があるから」と新規挑戦を先延ばしにするリスクも。そこで重要なのが、“試行錯誤を推奨し、失敗しても責めない”文化を育むことです。ベイカレントやM&Aセンター、さらにはタンソーマンGXも、「社内提案制度」や「新規プロジェクトの小規模テスト運用」を積極的に行っています。
(2) 事業横断のコミュニケーション強化
既存の収益事業部と、新規事業部・開発チームとの情報交換が円滑に行われることも重要です。顧客ニーズやフィードバックをリアルタイムで共有し、新規プロダクト開発に活かす仕組みづくりが欠かせません。これは“連鎖的イノベーション”を起こす土台となります。
権限移譲と経営者の役割
経営者の視点
ソリッドベンチャー経営者は、スタートアップのように「調達・投資家対応」に奔走するより、自社の事業戦略と組織マネジメントに時間をかけやすいメリットがあります。自己資金ベースで進めるため、経営判断に対する自由度が高く、CEO自身が新規プロダクトの可能性を直接チェックできるのも強み。
事業責任者への権限委譲
既存事業が拡大してくると、経営者がそこに張り付いていると新規事業に割くリソースがなくなるため、事業部長やCOOなどを信頼して任せる仕組みを作る必要があります。
この権限移譲がうまくいかないと、現場が社長依存になり、新規領域への挑戦が遅れてしまうのです。
スモールビジネスからソリッドベンチャーへ移行するステップ
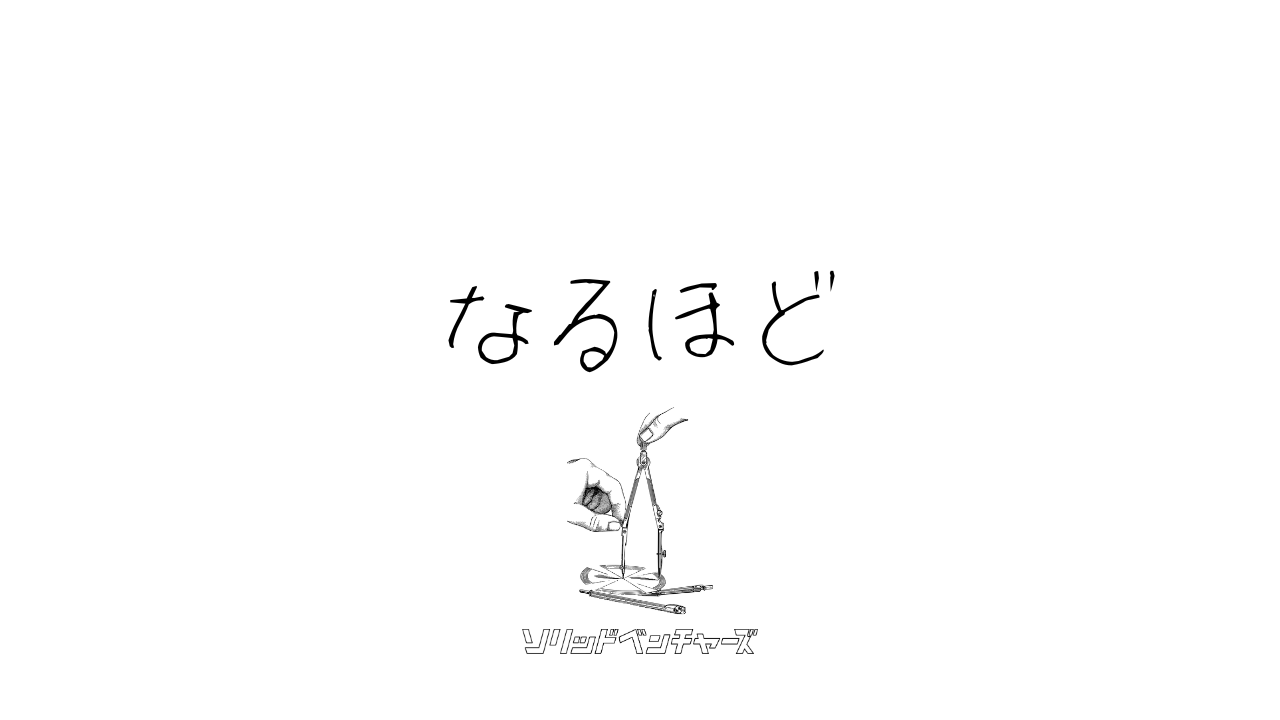
ここでは、小規模ビジネスやスモールビジネスとして安定している企業が、どのようにしてソリッドベンチャー的な成長路線を目指すのか、その具体的ステップを提示します。
ステップ1:キャッシュフローの安定
まずは既存サービスの強化
スモールビジネスの多くは、小回りの利くサービスや限定的な顧客層を持っています。最初に取り組むべきは、その顧客層でのシェア拡大や単価向上です。たとえば、助成金コンサルをやっているなら、その成功率を上げたり、追加のアドバイザリー契約を提案したりして、売上をより安定させます。
営業基盤の確立
キャッシュフローを安定させるため、定期契約やサブスクモデルへの移行を試みるのも有効。特にBtoBの企業向けには、毎月のコンサルフィーや運用代行費などを“継続課金”にすることで、事業計画を立てやすくなります。
ステップ2:新規事業の可能性を探る
既存顧客との接点から課題を収集
クライアントとのコミュニケーションを通じて、「こんなサービスが欲しい」「手間がかかる作業をもっと効率化したい」という具体的課題を聞き出します。その課題が共通しているなら、新規プロダクトや事業化を検討できます。
例:助成金コンサルが「手続きの煩雑さ」を感じる顧客を多数抱えている → クラウドサービス化 → 新規事業へ。
“ジワ新規”の実験導入
いきなりフルスケール開発せず、PoC(概念実証)や最小限のプロトタイプで顧客に試してもらい、フィードバックを得る。ソリッドベンチャーは短期回収を求められない分、こうした小さな実験をじっくり進められるのが利点です。
ステップ3:段階的な投資とスケール拡大
得られた利益を再投資
既存事業の利益を、開発費や人材採用に回す。銀行借入を併用してもよいですが、株式で外部調達する場合はコントロール権を失わない範囲にとどめておくのが理想です。CEOが大半の株を保有する状態なら、長期経営方針を崩さずに済みます。
M&Aの検討
新規サービスの拡張や、足りない機能・ノウハウを迅速に手に入れるためには、スモールM&Aが有効です。23株式会社のように、自社とシナジーのある小規模企業を買収し、顧客基盤を一気に拡大する事例も。
ソリッドベンチャーは黒字経営を続けているため、買収後の資金繰り不安が小さく、銀行からも融資を得やすいのがメリット。
ソリッドベンチャーの未来:持続的成長と社会的意義
さて、ソリッドベンチャーが今後どのような影響をビジネス界に与え、どんな社会的役割を果たしていくのかを考えてみましょう。
リスク管理と安定経営の価値再評価
ユニコーン偏重からのシフト
スタートアップブームにおいては、ユニコーン(評価額10億ドル超)のような企業が脚光を浴びました。しかし、近年の経済情勢や株式市場の変動などを受け、VC投資が慎重になる局面も増えています。ハイリスク路線に疲弊した投資家が、ソリッドベンチャーの安定経営を再評価する流れは今後加速するかもしれません。
中長期で人材を育成しやすい
ソリッドベンチャーにはキャッシュアウトリスクが小さいため、人材育成に投資できるという利点も。組織風土が安定していれば、社員の定着率が上がり、結果的に企業力が高まる好循環が生まれやすいです。
短期利益に追われず、腰を据えて組織を作り上げる点で、社会的に見ても持続可能な企業が増えるのは望ましい傾向といえます。
地方創生や中小企業の後継問題への貢献
地方のスモールビジネスとマッチ
地域に根ざした小規模ビジネスが、ソリッドベンチャー的発想を取り入れれば、地道に安定収益を確保しながら新商品・新サービスを開発できます。大きくはないが確実な市場で黒字を出しつつ、地方特有のニーズに対応した新規事業を生み出すことが可能です。
後継者問題を解決する選択肢
日本の中小企業が抱える後継者不足問題に対し、黒字を維持するソリッドベンチャーが買収することで事業承継をスムーズにするケースも期待されます。M&Aセンターなどが仲介役となり、こうしたスモールM&Aが活発化すれば、地方経済の活性化にもつながるでしょう。
スモールビジネスから大企業へ:長期的進化の可能性
“地味”だが長期で大きくなれる
ソリッドベンチャーは短期的なバリュエーションの爆発こそ狙いませんが、長い年月をかけて多角化し、結果的に大企業並みの規模を達成する可能性があります。M&Aセンターやベイカレントなども、地道な拡大を続けて結果的に大きく成長しています。これは日本の伝統的な“中堅企業が徐々に拡大する”モデルとも通じるところがあるでしょう。
ソリッドベンチャーのIPO・海外展開
黒字基盤がある企業ほど、IPO後の株価も安定しやすいとされます。また海外展開においても、スタートアップのように「一発当てる」路線ではなく、特定の国や地域に腰を据えて進出し、現地パートナーと提携しながら少しずつ売上を伸ばす手法を取る傾向があります。
“次のアクション”へ
組織づくりやスモールビジネスからの移行手順、さらに今後の社会的インパクトまで展望しました。以下に改めて、重要なポイントを簡潔に整理します。
- 既存事業を安定させ、黒字基盤を作る
- “ジワ新規”と段階的M&Aでリスクを抑えた成長を目指す
- 人材・組織カルチャーが鍵。失敗を許容し、新たなチャレンジを続ける風土を育む
- 長期的視点が不可欠。投資家の短期リターン要求に流されず、未来を見据えた経営
ソリッドベンチャーは、スタートアップの輝かしい“爆速”ではなく、あくまで“堅実な進行”のモデル。しかし、だからといってイノベーションを生まないわけではありません。
むしろ、失敗を許容できる安定収益があるからこそ、新しいアイデアをじっくり育成し、段階的に市場投入することが可能になります。
大きな波こそ起こしにくいかもしれませんが、着実に積み上げた成果が、やがて大企業にも匹敵する規模へと成長する可能性を秘めているのです。
ソリッドベンチャーという安定と成長の新潮流
ここまで見てきたように、ソリッドベンチャーは「創業初期からの黒字化」「既存事業でのキャッシュフロー」「段階的リスクテイク」などによって、安定と挑戦を両立するビジネスモデルです。
スタートアップのような華やかな急成長こそありませんが、長期的な視点で見ると“堅実に利益を積み上げ、その余力を活用して新たな芽を育てる”ことで、大企業へと進化する可能性も十分にあります。
ソリッドベンチャーは企業と社会に何をもたらすのか
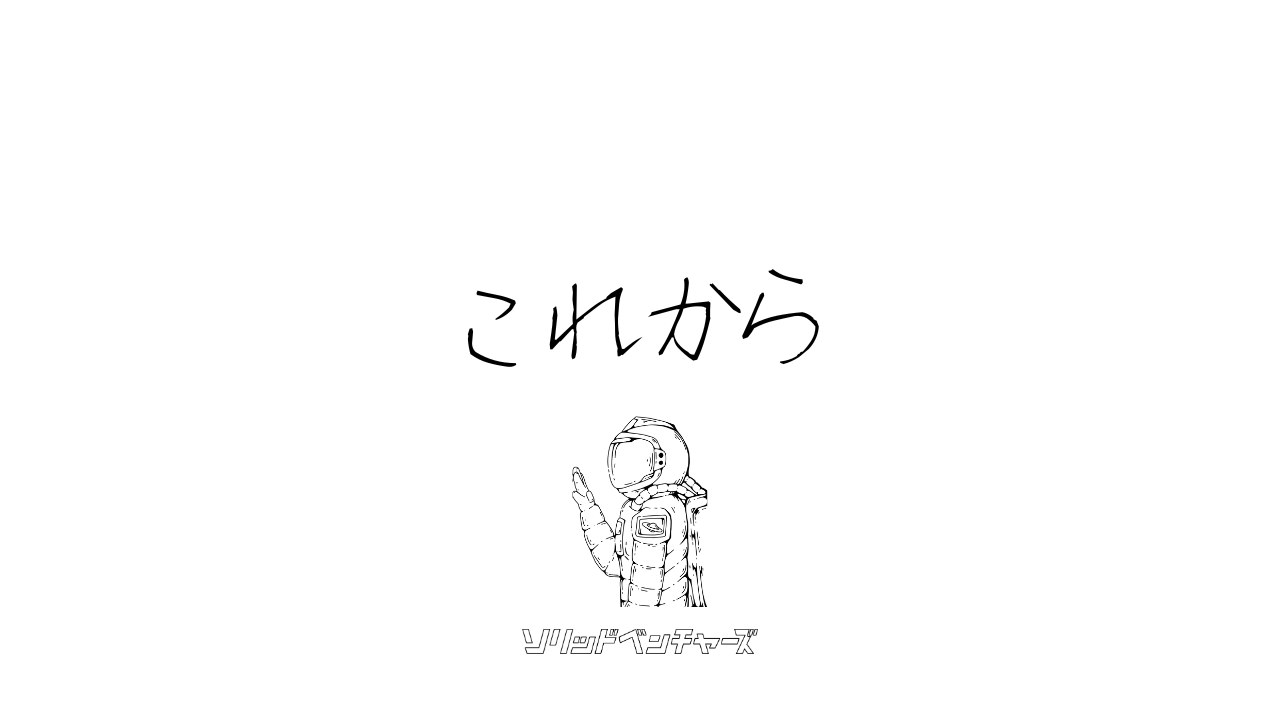
- リスクと安定のバランス
急成長に伴うリスクを抑えつつ、新規事業やM&Aで段階的に攻めていける柔軟性を備える。 - 長期ビジョンでの組織づくり
社員の挑戦を後押しするカルチャーや権限移譲などにより、持続的に成長できる体制作りが可能。 - 地方創生や後継問題の解決策にも
スモールM&Aや安定収益モデルを活かし、地域企業の活性化や中小企業の承継問題に寄与する可能性が高い。
現代のビジネス環境は常に変化し、先行きの見通しが立ちにくい時代だと言われます。そうした時代だからこそ、ソリッドベンチャーのように「短期的な爆発力」ではなく、「堅実な継続力」を武器にする企業が増え、社会や市場に多様な成長モデルをもたらすことが期待されます。
スタートアップとソリッドベンチャー、さらには大企業やNPOなど、多様な企業形態が共存してこそ、経済全体のレジリエンス(強靭性)は高まるでしょう。
もしあなたが起業や事業拡大に興味を持ち、「華やかに資金を集めるのではなく、まずは着実に収益基盤を築きたい」と考えているなら、ソリッドベンチャーの概念は大きなヒントになるはずです。
地に足を着けた経営でリスクを小さくしながら、未来に向けて新たな挑戦を続ける──そんな企業が増えることで、日本のビジネスシーンにも新たな活気と安定がもたらされるかもしれません。