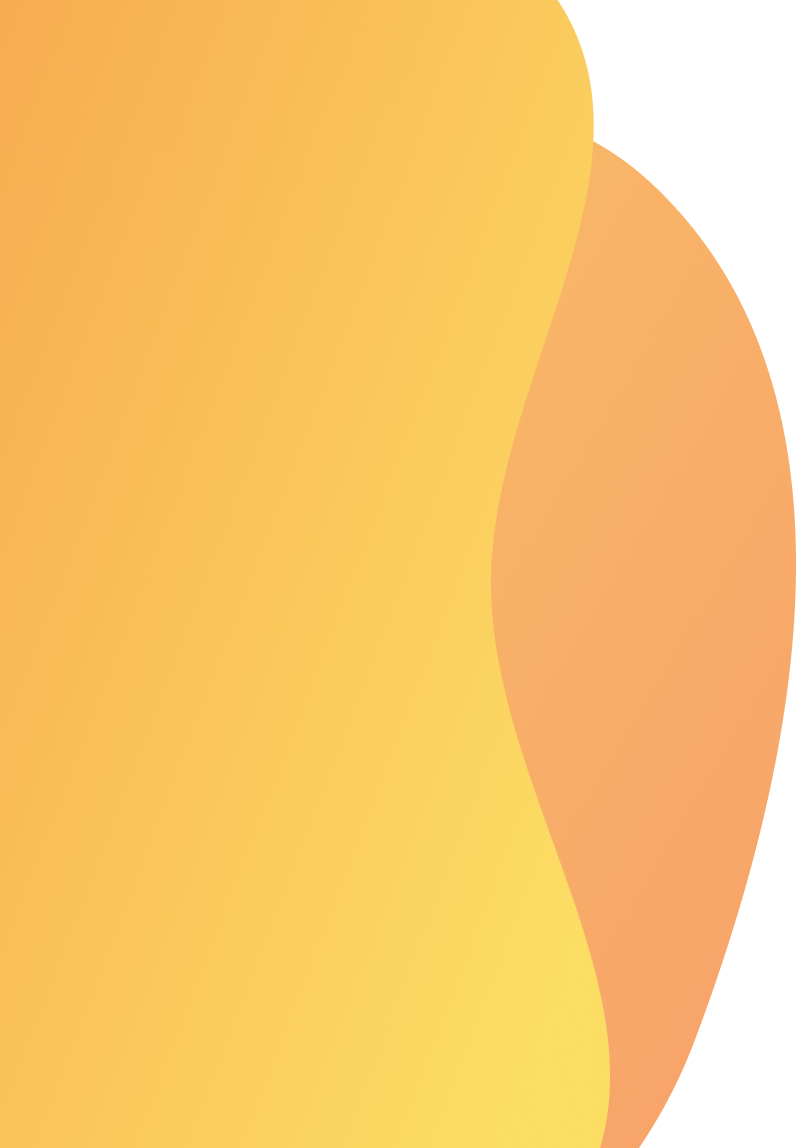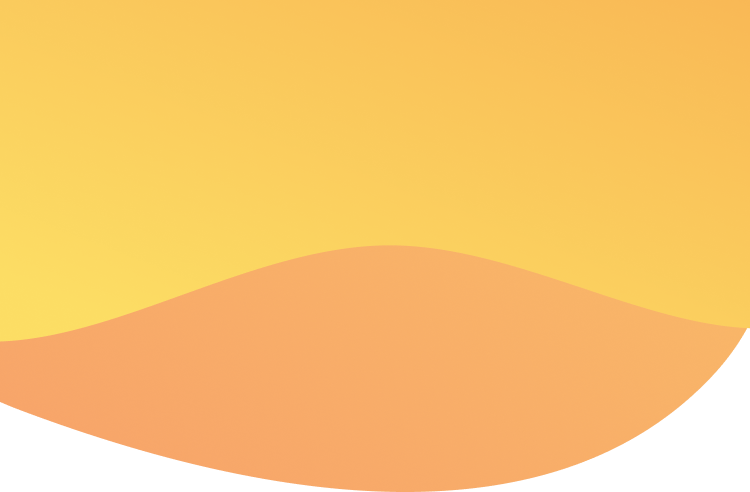2024.11.21
「ソリッドベンチャーとしてのレバレジーズ (Leverages)」著者の視点
レバレジーズ株式会社は、2005年に創業して以来、ITエンジニアのフリーランス支援事業を起点に、人材紹介・派遣、システム開発、DX事業、メディカル事業、教育事業など、多彩な領域へと事業を拡大してきました。
同社の成長の背景には、「顧客の創造を通じて関係者全員の幸福を追求し、各個人の成長を促す」という経営理念が存在し、それを実践するための具体的なアクションが行われています。
ソリッドベンチャーとしての特徴は、
- 創業から大型資金調達を行わず、自己資本や営業利益を再投資することで事業を拡大する
- 最初の事業領域を軸に周辺市場へ多角化し、堅牢なビジネス基盤を作る
- 社会課題の解決に寄与する姿勢を貫きつつ、堅実かつ柔軟に組織を成長させる
といった点が挙げられます。レバレジーズがIT領域からスタートし、なぜここまで幅広い事業を立ち上げられたのか――そこにソリッドベンチャーとしてのエッセンスが詰まっていると言えるでしょう。
レバレジーズ株式会社の基本情報
- 会社名:レバレジーズ株式会社 (Leverages)
- URL:https://leverages.jp/
- 代表者名:岩槻 知秀(代表取締役)
- 設立:2005年
- 本社所在地:東京都渋谷区
創業者の岩槻知秀氏は1980年生まれで、大阪府出身。早稲田大学在学中からエンジニアとしてアルバイトをし、大学卒業と同時に2005年にレバレジーズを設立したという経歴を持ちます。学生時代からIT業界に携わっていたことで培ったネットワークやノウハウを活かし、企業のIT人材ニーズを的確に捉えたビジネスを展開したことが最初の成功要因の1つと推察されます。
創業当初の事業モデル
フリーランスITエンジニア支援の軸
レバレジーズの原点は「ITエンジニアのフリーランス支援事業」でした。2000年代前半から日本においてもエンジニアの働き方が多様化し始め、フリーランスとして活躍する人が増え始めていましたが、まだ企業とエンジニアのマッチングを支援するサービスは十分整っていなかった時代です。岩槻氏はそこに商機を見出し、特化型のエージェントサービスとして事業をスタートしました。
初期のフリーランス向けエージェントビジネスは、大規模な資本投下を必ずしも必要としない一方で、優秀なエンジニアの登録や企業の信用を得るための営業力が求められます。
この点、岩槻氏のエンジニア兼経営者としての経験や、同世代IT人材とのネットワーク活用が功を奏し、比較的早期から顧客企業・エンジニア双方を獲得できたことが大きいと推察されます。
資本政策の特徴:自己資金主導
初期段階での大規模な外部資金調達の情報はなく、レバレジーズは自己資本による創業を経て、事業拡大に伴う外部資金調達の有無も大きくは公表していません。
これはソリッドベンチャー的な特徴の一つであり、利害関係者が少ない分、自社の利益を元手に事業を伸ばし、オーナーシップを保ちやすいという利点があると言えます。
外部投資家からの短期的なリターン要求に縛られないため、やや時間をかけながらも、持続的な拡大路線を選択できるメリットがあるのです。
事業拡大と多角化
1. 人材関連事業の強化
フリーランス支援が軌道に乗ると、レバレジーズはそのノウハウを活用し、人材紹介や派遣、アウトソーシングといった多様な人材サービスにも進出していきました。
ITエンジニアに限らず、看護師など医療従事者や営業職、事務職など、職種ごとに専門特化した人材サービスを提供することで、企業の採用課題に幅広く対応できる体制を構築したわけです。
また、人材ビジネスは、顧客企業との長期的な契約関係や、登録者への信頼構築によって成長する面が大きいため、安定した収益とキャッシュフローをもたらす可能性があります。ソリッドベンチャーの道を選ぶ企業としては、人材業界の比較的安定した収益モデルは好相性と言えるでしょう。
2. システムエンジニアリング事業・DX事業
フリーランス支援で培ったエンジニアリソースと企業ニーズのマッチング知見を生かし、レバレジーズはシステムエンジニアリング事業やDX事業にも進出しています。
クライアント企業からすると、優秀なIT人材を派遣・紹介するだけでなく、具体的にプロジェクトの上流工程(企画・要件定義)から開発・運用までを包括支援してほしいという要望があるため、同社はより上流寄りのサービスを広げたと考えられます。
これにより、単なる人材仲介に留まらず、受託開発やコンサルティングも含めてプロジェクト全体の価値向上に貢献できるようになり、結果的に1案件当たりの売上規模が拡大するのみならず、顧客との関係性がさらに強固になるメリットがあります。
3. M&Aアドバイザリーや教育関連事業
さらにレバレジーズは、M&Aアドバイザリー事業や教育関連事業、さらにはメディカル関連事業に至るまで、IT以外の領域にも果敢に進出しています。これは一見、IT企業のイメージからは遠いように思えますが、以下のような論理で多角化を進めていると推測されます。
- M&Aアドバイザリー:
IT人材の採用やDX課題を抱える企業にとって、買収・統合という手段が課題解決になるケースもある。あるいは、人材ビジネスを通じて得た企業とのネットワークを背景に、M&A案件の相談が自然と集まる可能性が高い。また、既存顧客がM&Aで事業拡大を図る際に、追加のコンサルやIT支援が必要になるなど、連携要素が多い。 - 教育関連事業:
ITスキルのトレーニングや社員研修などの領域で、企業からの需要は大きい。フリーランスやIT人材を抱える同社が教育ビジネスを持つことは、内外の人材育成にシナジーをもたらす。 - メディカル関連事業:
日本では医療・介護の人材不足や施設運営におけるDXなど、多くの課題が存在する。人材サービスで蓄えたノウハウを持つレバレジーズにとっては、新たな社会課題への挑戦として合理的な一手となり、既存基盤を活かして多角化を図っているといえます。
要するに、「IT人材」「社会課題の解決」「企業成長支援」というキーワードが同社の事業多角化の下地になっているわけです。
ソリッドベンチャー視点で見る成長のポイント
1. 外部投資に大きく依存しない経営
創業当初のエピソードから察するに、大規模なベンチャーキャピタルからの資金注入や株式上場による資金調達を経ずに、フリーランス支援の成功による利益を再投資しながら領域を広げてきた形がうかがえます。
ソリッドベンチャーでは、ここが重要な分岐点で、短期的に急成長させるためのVCマネーではなく、堅実な事業収益を事業拡張の原資とすることで、オーナーシップや経営の自由度を保っています。
このアプローチにより、株主の短期リターン圧力に苦しむことなく、長期的な視点で新事業の開発や既存事業の強化に注力できるという利点があるでしょう。
特に、人材関連ビジネスの場合、クライアントとの信頼構築や社会的信用を得るまでに時間がかかる反面、一度軌道に乗ればストック的な利益が期待できるビジネス構造を持つため、ソリッドベンチャー型のモデルと親和性が高いのです。
2. 既存基盤を活かした段階的な拡張
フリーランス支援のノウハウを起点に、IT領域→人材関連全般→システム開発→DX→M&Aアドバイザリー→メディカル・教育と、射程を少しずつ広げていく方法は、ソリッドベンチャーの典型といえます。
いきなり全く異なる業界へ大規模投資を行うのではなく、周辺市場へ段階的に進出することで、失敗リスクを抑えながら新規収益源を確保しているのが特長です。
また、レバレジーズは各事業の独立性を保ちつつ、相互に協力し合える体制を築いていると思われます。例えば、IT人材を欲するクライアントが、M&AやDXの課題を抱えていれば、そのまま別事業部門へと紹介しシナジーを生むという構造です。これこそ、多角化のメリットを最大限に活かすやり方と言えます。
3. 社会課題を意識した事業選択
同社が掲げる「顧客の創造を通じて関係者全員の幸福を追求し、各個人の成長を促す」という理念は、事業を進める上で社会的意義や課題解決を重視しているメッセージが強く込められています。
人材不足、デジタル化の遅れ、医療介護の逼迫など、社会に存在する問題に対してビジネスモデルで取り組むことで、安定した顧客ニーズも得られやすいという側面があります。
ソリッドベンチャーにおいては、企業の存在意義が「単なる利益追求」ではなく「社会的課題への取り組み」や「持続可能性」に根ざしている方が、社内外のステークホルダーの支持を得やすく、長期的成長に向けた基礎になると考えられます。
市場・地域と競合
1. 人材サービス×ITマーケットでの優位性
人材ビジネスは非常に競合が激しい市場ですが、ITエンジニア領域は需要が供給を上回る構造が続いており、優位性を確立しやすい分野でもあります。レバレジーズはここにフリーランス支援や派遣などの実績を積み重ねることで、企業やエンジニア双方からの信頼を得て成長してきたと推測されます。
他社との違いを打ち出すには、特定の職種・スキル領域に強みを持つことや、サポート体制の充実、エンジニアコミュニティへの貢献などが挙げられます。ソリッドベンチャーとして、地道に口コミや評判を高めることでシェアを拡大してきたのではないでしょうか。
2. 全国・海外展開への道
レバレジーズは東京都渋谷区に本社を構えながら、国内外に複数拠点を持ち、そのネットワークを活かして事業を展開しています。IT人材の市場は都市部が中心ですが、地方企業がDX推進を図るケースも増えていることから、地方拠点を活用する意義は十分にあるでしょう。
また、海外でもITエンジニアの需要は高く、日本企業の海外進出支援やグローバル人材の送り出しなど、ビジネスチャンスはいくらでもあります。ただし、ソリッドベンチャーとしては、拠点の拡大に伴うリスクを慎重に判断しながら、着実に進めていく方針が考えられます。
レバレジーズに見るソリッドベンチャーの本質
レバレジーズ株式会社は、「ITエンジニアのフリーランス支援」から始まり、IT×人材ビジネスを軸とした多角化で大きく躍進を遂げてきた企業です。
創業社長の岩槻知秀氏が大学生時代からITエンジニアとしてビジネス経験を積んだ背景は、事業への深い理解とネットワーク構築に役立ったと考えられます。
事業拡大の過程を見ると、外部資金を大々的に調達するよりも、事業利益を投資源にしながらステップを踏んで多角化し、失敗リスクを分散しつつ着実に規模を拡大する「ソリッドベンチャー」的アプローチが色濃く表れています。
- 人材ビジネス×ITの掛け合わせにより、安定的な収益源を確保
- 社会課題の解決(IT人材不足、医療人材不足、DXの遅れなど)を軸に新事業を創出
- 大量の外部投資に頼らず、自社の強みと利益を活かして徐々に事業範囲を広げる
これらは、ソリッドベンチャーらしい成長のパターンを体現しているといえます。一方で、さらなる事業多角化が進めば進むほど、組織内での管理・人材教育、ノウハウ共有、ブランド統一性など新たなハードルが出てくるはずです。
今後、レバレジーズがそれらをどう乗り越えるかによって、真の意味での持続的成長が実現するかが左右されるでしょう。
ITや人材という需要の絶えない市場を背景に、同社は日本国内の人材紹介市場にとどまらず、DX支援やメディカル領域、教育領域にもビジネスチャンスを拡大しています。こうした柔軟な事業展開と、社会課題に向き合う姿勢は、ソリッドベンチャーとしての本質的な強みを示すものです。
今後も、日本全体で深刻化する人材不足やデジタル化課題をどのように解決するかという点で、レバレジーズの役割はさらに大きくなる可能性があります。企業のみならず個人のキャリアアップやエンジニア育成といったテーマにおいても、彼らの挑戦は注目に値するでしょう。
総括すると、レバレジーズの歩みは、
- エンジニア人材サービスでニッチを攻略
- 得意分野から派生する形で多角化
- 外部投資家に左右されずマイペースに拡大
- 社会貢献・社会課題の解決に根ざした事業選択
というソリッドベンチャーの成功要件を満たす良い事例です。これから創業する企業家や、既に事業を運営している中小企業にとっても大いに参考になるはずです。
大きな投資なくとも、コアコンピタンスを軸に社会ニーズを捉え続けることで、着実に成長していく道があり得ることを実証している――それがレバレジーズという企業の姿と言えるのではないでしょうか。