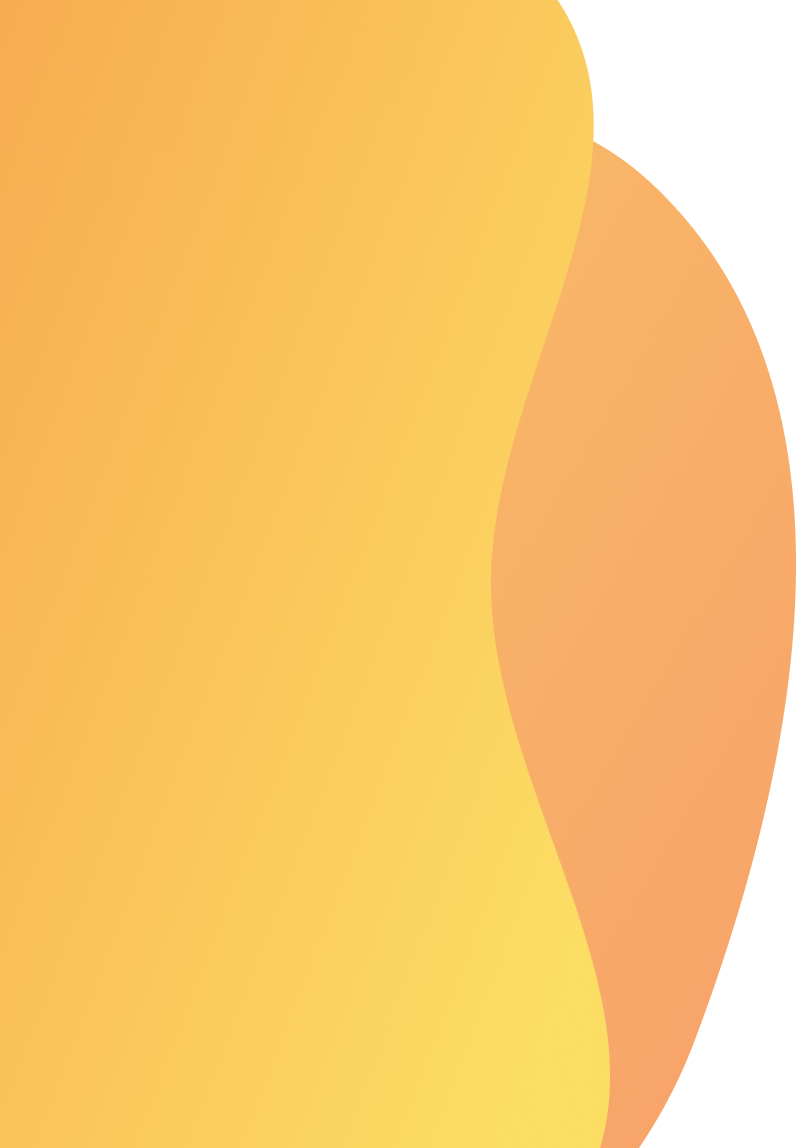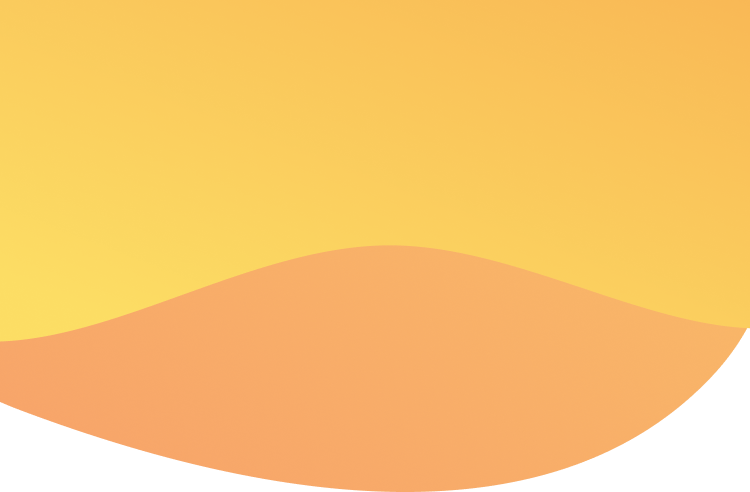2024.11.21
「ソリッドベンチャーとしてのオロ」著者の視点
ソリッドベンチャーとは、急拡大や派手な資金調達に依存せず、まずは堅実な収益基盤を築き、その利益と必要最小限の外部資本を活用しながら、徐々に事業領域を拡大していく企業を指す概念です。
いわゆるスタートアップの一部が描く短期的なJカーブ成長やユニコーン化とは異なり、地に足を着けた成長が最大の特色です。
株式会社オロ(以下、オロ)は、ITを中核にしたシステム開発やクラウドソリューション、デジタルマーケティングを展開しながら着実な収益をあげ、上場を果たすに至った実績のある企業です。
同社は創業当初から、安定したシステム開発の受託を行い、クライアント企業との信頼を深めつつ、ERP(Enterprise Resource Planning)などの自社プロダクトを育ててきました。
ここからは、オロの創業背景と拡大戦略、多角化を成功させた要因やソリッドベンチャーとしての特性を読み解いていきます。
会社概要と創業期の事業モデル
会社情報
- 会社名:株式会社オロ
- URL:https://www.oro.com/ja/
- 代表者名:川田 篤(代表取締役社長執行役員)
- 設立:1999年
本社は東京都目黒区に所在し、システムソリューション事業を基盤に、クラウドサービス「ZAC」や「Reforma PSA」などの自社プロダクトを提供する一方、マーケティングコミュニケーション事業も手がけています。1999年の創業以来、IT市場の潮流を捉え、顧客の業務効率化や経営課題の解決にフォーカスして成長してきました。
創業当初の事業モデル
オロは、1999年 に川田篤氏と日野靖久氏らによって設立されました。代表の川田氏は北海道札幌北高等学校を卒業後、東京工業大学工学部を経て起業を志し、大企業へ就職する道を選ばずにシステム開発請負を始めました。その資金を元手に創業されたのがオロです。
当初は企業向けのWebシステム開発や業務システム開発を中心としたソリューション提供を行い、顧客の業務効率化やコスト削減をサポートするモデルを構築していました。
創業期において、システム開発という受託ビジネスは安定した売上を狙いやすいものの、労働集約型で高い利益率を出すには限界がある側面もあります。
しかしソリッドベンチャーとしては、最初に安定的なキャッシュフローを得る事業を持つことで、社内体制の強化や次なるプロダクト開発への投資を進めやすくなるというメリットがあります。
オロも例外ではなく、創業当初は安定した受託案件を獲得しつつノウハウと顧客基盤を築き、新しいサービスや製品の開発へと段階的に移行していったのです。
ソリッドベンチャーとしての成長戦略
1. 自己資金を中心に始まり、拡大段階で外部資金を導入
創業当時は、大学で学んだIT知識とシステム開発の実務経験を武器に、自己資金や少人数のメンバーだけで事業を始めたとされています。大手資本をいきなり受け入れたり、多額の調達を行うのではなく、まずは受託開発を着実に回して売上を確保する姿勢を貫いたのです。
その後、事業が軌道に乗り、顧客数が増加するタイミングでベンチャーキャピタルからの資金調達を実施。ここで得た資金を、自社プロダクトの研究開発(R&D)や社員の採用・育成に振り向けることで、サービスラインナップを一気に拡大していきました。
これはソリッドベンチャーの特徴的なアプローチであり、無闇に大型調達して赤字拡大を狙うのではなく、成長余地を見極めつつ必要最小限の外部資金を手に入れるやり方と言えます。
2. コア事業の安定確保:システムソリューション
オロの第一の柱は、システムソリューション事業です。顧客企業の業務システムやWebサイトを開発・導入することで、安定的な受託収益を確保してきました。IT業界では、受託開発というのはプロジェクトごとの売上が大きく、また継続的な保守契約が取れればキャッシュフローの見通しが立ちやすい側面があります。
ただし競合が多い領域でもあるため、オロは高付加価値の提案を可能にする技術力やコンサルティング能力を身につけることで、単なる下請けではなくパートナーとしてのポジションを確立してきました。
このコア事業が堅調に推移していることが、同社が新たなプロダクトや事業領域へ投資できる土台となっています。
3. クラウドソリューション事業「ZAC」「Reforma PSA」への展開
2000年代後半からクラウドコンピューティングの普及が加速すると、オロは自社開発のクラウドERP「ZAC」をローンチ。さらにプロジェクト管理や工数管理を行うためのクラウドPSA(Professional Services Automation)「Reforma PSA」も提供し、サブスクリプション型ビジネスへと歩を進めました。
この動きは、受託事業だけではなくプロダクト型ビジネスを持つことで、ストック収益を積み上げる狙いがあります。特にERPやPSAは企業の基幹業務を担うソリューションであり、導入後は長期にわたって保守・アップデート需要が期待できるため、売上安定化に寄与します。
これもソリッドベンチャーがよくとる戦略の一つで、「堅いコア事業+自社プロダクト」という収益構造を作り上げたのです。
4. マーケティングコミュニケーション事業への多角化
オロは、ITとクラウドだけでなく、マーケティングコミュニケーション事業にも進出しました。ここではデジタルマーケティングや広告運用、PRなどをサポートし、顧客企業のブランド価値向上や販促活動を支援します。
この多角化の背景には、顧客企業との深い関係性があります。元々システム開発や導入支援で関わっていた企業から、「サイト制作や広告運用もやってほしい」という要望が増えたことで、新しい事業領域を開拓したと推察されます。
ソリッドベンチャーでよく見られるように、コア事業で得た顧客ネットワークや信頼関係をテコに周辺領域へ展開するパターンです。
上場とその後の展開
◇1. マザーズから東証一部へ上場
オロは2013年に東証マザーズ、2014年には東証一部(現プライム市場に統合)に上場しました。上場によって多くの資金を調達できるようになり、さらなる研究開発や人材採用、マーケティング活動を活発化させます。
このように、企業規模を拡大する適切なタイミングで上場を果たした点は、ソリッドベンチャーとしての戦略をうまく遂行した結果と言えるでしょう。
多くのベンチャーが上場を急ぎすぎると、売上や利益が安定する前に株主へのリターンを求められるリスクがあります。しかしオロの場合、既存のコア事業と自社プロダクトがある程度成熟してから上場を実施しているため、上場後の経営がより安定しやすくなります。
2. 研究開発と海外戦略
上場後は得た資金を、研究開発(R&D)や海外拠点の設置に振り向けることも検討されています。日本国内だけでなくグローバルでも通用するERPやPSAを視野に入れれば、市場規模は格段に大きくなります。ただし海外市場への挑戦はローカライズやサポート体制構築が不可欠であるため、リスクも伴うのが事実です。
ソリッドベンチャーにとっては、海外展開も慎重に行われるのが一般的です。既存顧客やパートナーシップを活かしながら特定の地域に試験的に進出し、成果を得たらさらなる拡大を狙うという、段階的なアプローチが望ましいと考えられます。オロが今後グローバル展開をどう進めるかにも注目が集まります。
失敗事例や課題から見るソリッドベンチャーの強み
1. 変化の激しいIT業界
IT業界は技術変革が著しいため、常に新しい言語やフレームワーク、クラウドサービスが登場し、トレンドが移り変わります。オロも過去にはクラウドサービスへの移行に乗り遅れれば大きな機会損失となり得たでしょうし、新規事業開発で競合に先行された時期もあったかもしれません。
しかしソリッドベンチャーのアプローチでは、コア事業で安定したキャッシュフローを得ているため、思い切った技術投資やスピンオフ的な新規事業を取り込みやすいメリットがあります。たとえ一部の新サービスが失敗しても、会社全体が立ち行かなくなるほどのリスクは負いにくいのです。
オロのERP開発なども、受託システム開発の収益が後ろ盾となって進められてきた構造がうかがえます。
2. 人材確保と組織マネジメント
IT企業にとって、人材の確保と育成は永遠の課題です。特に急成長フェーズでは、人の増加とともに組織体制の不整合やノウハウの属人化などが問題となる可能性があります。オロはシステムソリューション事業で多くの人材を抱える一方、自社プロダクト開発やマーケティングコミュニケーション事業でも専門スキルを必要とします。
ソリッドベンチャー的な経営であれば、利益を焦って再投資を狙うのではなく、段階的に人材を増やし、じっくりと教育や組織文化の醸成を行うことができるのも強みです。上場後のガバナンス強化も含め、適切な組織マネジメントができれば、競合他社との人材競争を乗り越えていくことが可能です。
オロに見るソリッドベンチャーの姿
最後に、株式会社オロが歩んできた軌跡をソリッドベンチャーという文脈で整理します。
- 着実なコア事業の確立
- 創業当初はシステム開発受託を通じて安定的な売上を確保。
- 顧客企業との信頼関係を築き、コンサルティング的な付加価値を追求。
- 自社プロダクト(クラウドERP・PSA)への投資
- 受託事業で培った知見と売上を活用し、サブスク型ビジネス「ZAC」「Reforma PSA」を立ち上げ。
- ストック収益を拡充することで収益基盤をより安定化させる。
- マーケティングコミュニケーション事業の多角化
- コア事業の顧客ネットワークを活かし、デジタルマーケティングや広告運用など新領域を開拓。
- 顧客の経営課題をワンストップで支援する総合的なIT企業へと進化。
- 慎重な外部資金導入と上場タイミング
- 創業時は自己資金で始動し、必要なフェーズでVC資金を調達。
- 2013年東証マザーズ、2014年東証一部上場と、ある程度事業が成熟してから資本市場へ。
- 上場で得た資金をR&Dや海外展開、人材採用に再投資する好循環を実現。
- 失敗事例のカバー力と組織強化
- IT業界の変動や人材不足などの課題に直面しつつも、コア収益を持続させることで大きなダメージを回避。
- 段階的に組織体制を拡張し、技術トレンドや顧客ニーズの変化に柔軟に対応。
このようにオロは、ソリッドベンチャーのエッセンスとも言える「地盤固め→周辺拡張→ストック収益強化→必要時の外部資金活用」というプロセスを丁寧に踏んでいます。大規模な赤字を出しながら一気に成長を目指すのではなく、利益を出しつつ次なる投資を行うという健全なスパイラルを回しているのが同社の特色です。
ITベンチャーの中には派手な資金調達や爆発的なユーザー獲得を狙う企業も多いですが、オロのように堅実な道を選び、着実に企業価値を高めていくスタイルこそソリッドベンチャーの理想的な形と言えるでしょう。
先行き不透明な時代にあっても、安定した収益モデルと段階的な多角化、労務管理やガバナンスの強化を適切に行うことで、企業としての持続的な成長を可能にしている点が大きな魅力です。
こうしたオロの事例は、IT企業のスタートアップが「どのようにリスクを抑えつつ新規事業を生み出し、スケールを目指していくか」を学ぶ上で極めて参考になるでしょう。これからも同社は海外展開や新技術活用などを通じて成長を続け、ソリッドベンチャーとしての存在感をさらに高めていくと期待されます。