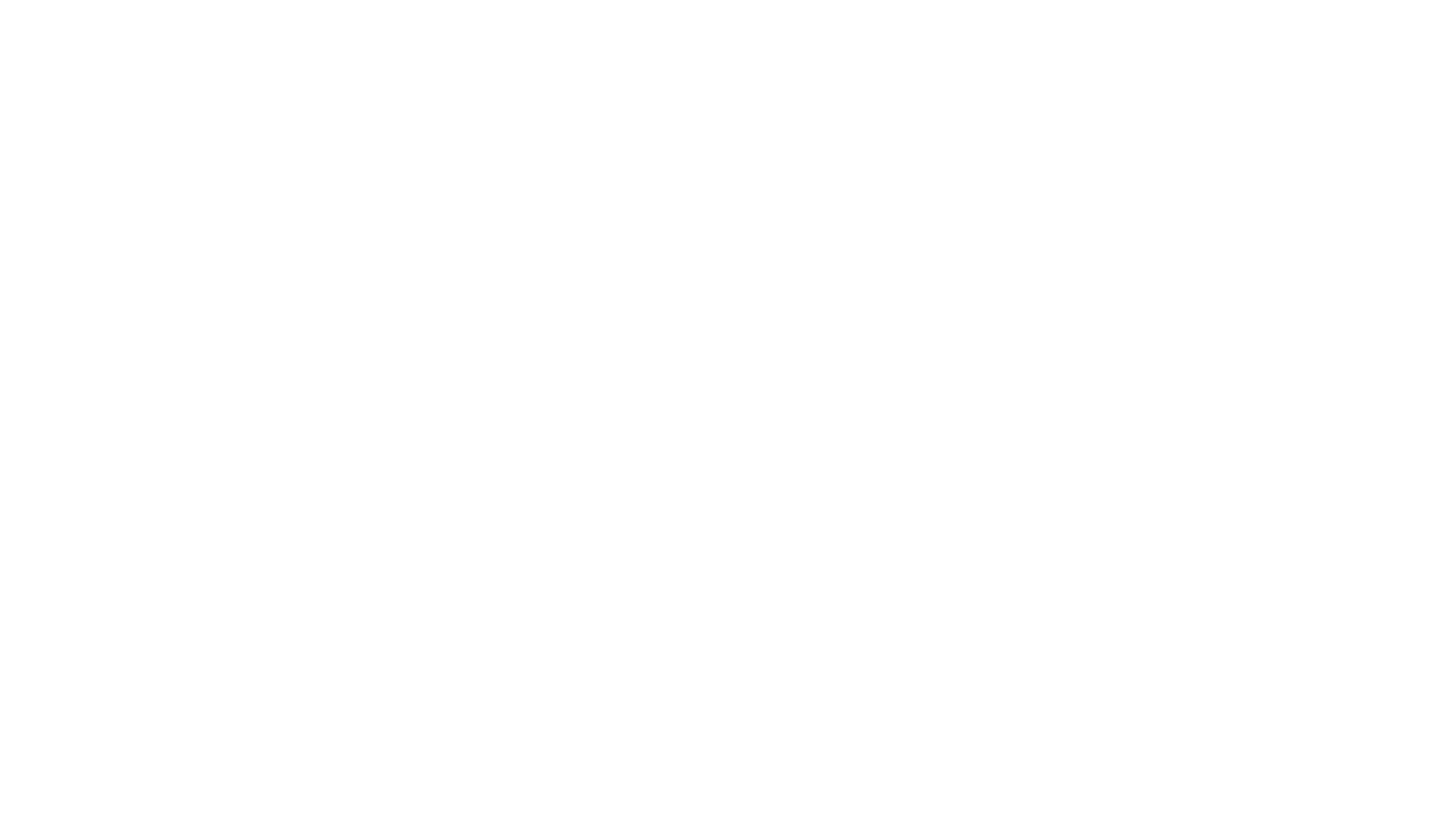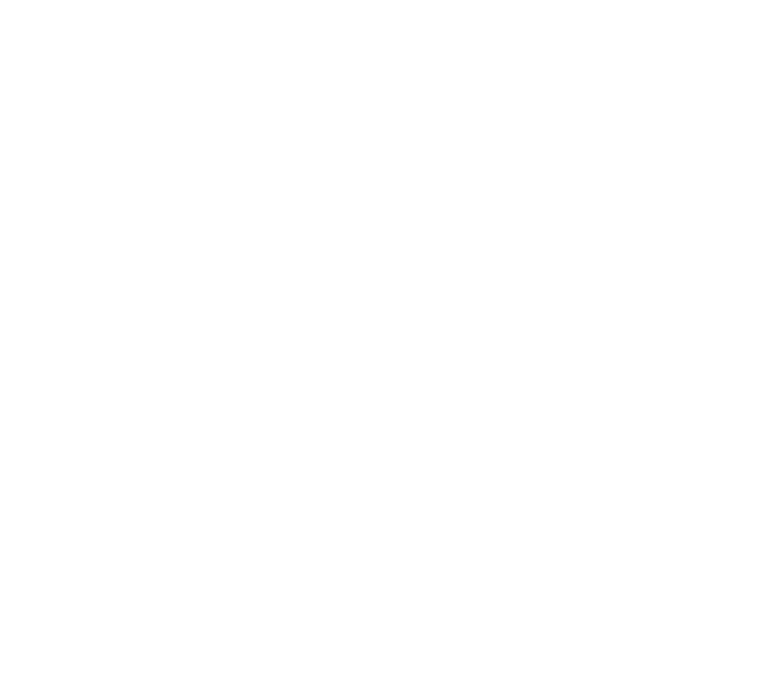- #スタートアップ
- #スモールビジネス
- #事例
- #収益モデル
- #成長戦略
結局、スタートアップとソリッドベンチャーってどちらが有利?
公開日:2025.02.25
更新日:2025.11.12
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠

「ソリッドベンチャーは“型”ではなく“状態”。」早期黒字の土台で倒れず学び、機会にだけ強く張る——そんな“負けにくい成長”と、VC主導で速度を買うスタートアップ。両者のちがいを、物語と事例でほどきます。
結論(TL;DR):倒れにくい黒字の土台で学び続け、勝機にだけ強く張る。“状態”を保てば速度は後からいくらでも自在に足せる。
- “状態”=黒字の土台があり、挑戦を継続できる余力と文化がある
- 既存の稼ぎ(キャッシュ源)→小さく新規→横展開で負けにくく伸びる
- 外部資本は速度の燃料。希薄化と主導権の設計が要点
スタートアップとソリッドベンチャーの違い
スタートアップの一般的なイメージ
スタートアップと言えば、まず思い浮かぶのが「短期間で大きな株式価値を狙う」というイメージです。多くの場合、VC(ベンチャーキャピタル)による出資を受けて赤字拡大路線に踏み切り、ハイリスク・ハイリターンを前提とした急拡大を図ります。
具体的には、ラウンドごとに数億円から数十億円を調達し、広告・マーケティング・大規模な採用などに一気に投資するのが通例です。
- 大量調達による急拡大が可能
スタートアップはシェア争いにおいて「スピード重視」で勝負をかけやすく、Jカーブ(最初は赤字が膨れ上がり、後から大きく黒字化する成長曲線)を狙う。 - 高い失敗リスク
市場にそぐわなかった場合、一気に資金ショートで撤退せざるを得ないケースも多いです。VC側も数年以内のEXIT(IPOまたはM&A)を重視するため、創業者が経営判断を急がされるプレッシャーが強くかかる可能性もある。
一言でまとめるなら、スタートアップは「短期間で爆発的成長を狙うが、失敗時はハイリスク」。特に海外市場まで一気に拡大したい企業にとっては、VCラウンドを重ねながら成長を加速する戦略が当たり前とされることが多いでしょう。
ソリッドベンチャーの定義
一方、ソリッドベンチャーとは、創業初期から堅実な黒字経営を重視し、自社のキャッシュフロー(自己資本)や銀行からの借入などを活用して、無理のないペースで事業を拡大していく企業形態を指します。
近年、国内外で「VC非依存ながら上場後に時価総額数千億円~1兆円を達成する」企業が増えており、これらがソリッドベンチャーとして脚光を浴びています。
- 地味なBtoB受託やニッチ市場から始める
例:システムの受託開発、コンサルティング、保守サービスなど、すぐにキャッシュが得られるビジネスを基盤とするケースが多い。 - 段階的な拡大と新規事業への挑戦
既存事業で利益を積み上げながら、M&Aや新規プロダクト開発に投資し、数年〜十数年かけてユニコーン級へと成長するパターンも少なくない。
端的に言えば、「地に足をつけた堅実経営から始め、最終的に大化けを遂げる」ことがソリッドベンチャーの魅力です。とはいえ、地味だからこそ成功までの時間はかかりがちで、急激な飛躍は期待しづらいという面も持ち合わせています。
資本戦略の違いは、外部資本に頼るか自社キャッシュを回すか
スタートアップの資本構造
スタートアップは、何よりVCなど外部投資家からのエクイティ調達が中心です。創業初期から大型のラウンドを組んで数億~数十億円を獲得する場合も多く、「数年以内のIPOや大型M&AによるEXIT」をゴールに据えます。
- メリット:
調達直後のキャッシュが豊富になり、大規模開発・広告投資を一気にできる。 - デメリット:
株式希薄化や投資家からのリターン要求が激しく、短期視点の経営を余儀なくされやすい。
また、市場や技術トレンドに大きなポテンシャルがある際はスタートアップ型が優位に立つことも事実ですが、失敗リスクも相応に高まります。
ソリッドベンチャーの資本構造
ソリッドベンチャーは、黒字経営を継続しながら自己資本と借入を活用し、必要に応じてM&Aにも踏み切る戦略を取ります。典型的な例として、SHIFT社が挙げられます。SHIFT社はソフトウェア品質管理を軸とするコンサル・テストサービス会社ですが、
- のれん負けするほど高額なM&Aは行わない
- 買収後すぐに連結黒字に貢献できない案件は検討から外す
という基準を打ち出し、財務面で無理をしないまま多数の小規模M&Aを重ねています。結果、希薄化リスクを抑えながら自己資本+借入で買収を実行し、上場後も経営主導権を維持しつつ事業領域を拡大。時価総額数千億円を達成しました。
- メリット:
- 追加増資が少ないため既存株主の価値(EPS)が上がりやすい
- 創業者が大株主として長期的ビジョンを貫ける
- デメリット:
- 大型プロジェクトや急な海外展開など、瞬発力に限界がある
- 自己資金を作るために、創業初期から一定の収益モデルを求められる
このように、黒字経営×借入を軸にした資本構造のおかげで、ソリッドベンチャーはゆるやかだが安定した拡大を可能にします。ただし、一気に勝負をかけたい場合は資金面での爆発力に欠けるのが難点です。
成長戦略の違いは “じわ新規”と“圧倒的速度”
スタートアップの成長モデル
スタートアップは、赤字を厭わず「スピードを最優先」して市場を取りに行きます。大規模なマーケティング投資や急激な採用で製品やサービスを一気に展開し、競合が追いつく前にシェアを確保する作戦です。
- 優位点:
波に乗れば短期間で巨大化し、IPO時には時価総額数千億~1兆円も狙える。 - 弱点:
需要予測や製品開発が外れた場合、資金ショートで撤退。膨らんだ赤字負担が経営を圧迫しやすい。
実際、国内でもスマホゲームやSaaS領域で一気に資金を集めて成長した企業が少なくありません。しかし、その半面、「撤退」の判断もまた早く下される傾向があります。
ソリッドベンチャーの成長モデル
ソリッドベンチャーは、よく“ジワ新規”と称される段階的アプローチで事業を育てます。特に、うるる社のケースが分かりやすい例。うるる社は創業当初、主婦を活用したBPO(クラウドワーク)事業から着実に黒字を積み上げました。その後、
- 入札情報サービス「NJSS」を自社開発し
- BPOで確保したクラウドワーカーを活用して行政入札情報を一括収集
- 月額で法人に提供するSaaSビジネスへ拡張
このように、既存事業の収益(BPO)をベースに新規事業(NJSS)をローンチし、結果としてARR45億円超の規模にまで成長。さらに他のサービスへもクロスセルが可能になるなど、地道な拡張が功を奏しています。
- メリット:
- 赤字リスクを最小限に抑え、長期視点で新事業を育てられる
- 5~10年スパンで見たとき、時価総額1,000億円超え(いわゆるユニコーン級)に至る例が多い
- デメリット:
- 短期的な爆発力は限定的で、競合に一気に抜かれる場合もある
他にもナイル社(SEOコンサル→メディア事業→定額カルモくん)などが典型的な“キャッシュ・カウ”(既存事業)ד新サービス”の組み合わせで大きくなった企業です。こうしたモデルがソリッドベンチャーの真骨頂と言えるでしょう。
リスクマネジメントと事業多角化。失敗に強いのはどちら?
スタートアップが抱えるリスク
スタートアップは、大型調達が叶えば大きく飛躍できますが、その反面投資家の意向に左右されやすく、しかも赤字拡大による資金消耗が進みます。ラウンド間で経営指標が伸び悩むと、次の調達が厳しくなる「ダウンラウンド」リスクにも直面しやすいです。
- 事業が軌道に乗れば急激な企業価値向上が期待できるが、
- 失敗した場合、資金ショートから一気に撤退というシナリオも十分に起こり得る。
つまり、スタートアップのリスクマネジメントは「大きく賭けて短期的に成果を出す」ことが前提になり、外部環境(景気や市場潮流)によって打撃を受けやすい構造です。
ソリッドベンチャーのリスク回避策
一方、ソリッドベンチャーは「受託ビジネス」や「既存市場」を基盤としながら、そこから派生する形で新事業に投資します。たとえば、
- オロ社:
創業当初はウェブやシステムの受託開発
社内用の業務管理ツールをERP「ZAC」として外販 → クラウド版で大ヒットし2017年にIPO - GENOVA社:
医療機関向けWeb制作で安定収益 → 自社メディア → スマート受付機のように徐々にソリューションを拡張
こうした流れなら、既存事業でキャッシュフローを確保しているため、万が一新規事業が失敗しても会社全体が傾くリスクが低いのです。“地味”な事業モデルをバカにせずに固めているからこそ、多角化もしやすくなります。
- 倒産リスクが低く、複数ポートフォリオで経営安定
- 大爆発的成長(短期間で海外市場へゴリゴリ参入など)は苦手
このような堅実さと引き換えに、急拡大のタイミングを逃す場合もあり得ますが、総じて長期的には失敗しにくい安定経営を築きやすいと言えるでしょう。
結論、両者の向き不向きと成功のポイントは?
元も子もないですが‥‥どちらが有利かは“ビジネスモデル・起業家のスタイル”次第
最終的に、スタートアップかソリッドベンチャーか、どちらのアプローチが“優位”と一概には言えません。市場規模や創業者のビジョンによって、有利不利が大きく変わります。
- 早期IPOやグローバル展開を目指すなら
スタートアップの高速スケール戦略がマッチしやすい - 安定収益を軸に数年~10年スパンで段階的成長を狙うなら
ソリッドベンチャー型が向いている
事例から学ぶ成功の鍵
- SHIFT社
創業事業の「品質管理」→顧客深耕→M&Aで「周辺領域」「基幹システム」「全方位」へ進出
“のれん負けしない買収”方針で財務的リスクを最小化しつつ、急拡大を達成 - ナイル社
SEOコンサルの利益→メディア事業→定額カルモくんで見事にJカーブを描き、IPOへ - プログリット社
英語コーチングで黒字化→派生サービス(「シャドテン」や「AI会話ツール」)を追加
大幅な調達に依存せず、地道にプロダクト群を増やした
これらはいずれもソリッドベンチャー型の企業であり、創業時から黒字を重視してきた結果、堅実な基盤を築きつつ後に大きく跳ねています。
一方で、もし「海外市場を制覇して3年で100倍成長を狙いたい!」となれば、VCラウンド前提のスタートアップ型が王道と言えるかもしれません。かつてのメルカリのように短期間でマーケットを掌握し、グローバル展開に踏み込む上でVCマネーは非常に有効な手段となります。
「大きくなる道」は1つだけではない。
- スタートアップ: ハイリスク・ハイリターン、投資家と短期目線で競争力を高める
- ソリッドベンチャー: 安定経営&徐々に新規事業を追加し、最終的にユニコーン級へ
この両極の特徴を理解した上で、自分の事業や市場特性にあった選択が必要です。企業の目的・市場規模・創業者のビジョンによってベストアプローチは変わります。改めてまとめると、
- スタートアップはVC主導の調達に支えられた短期の急成長モデル。
資本面での自由度は高いが、リスクと外部圧力も大きい。 - ソリッドベンチャーは早期黒字を重視し、自己資本・借入を中心に経営。
大爆発的成長は遅いかもしれないが、長期的に時価総額1,000億円超を狙う例が多数ある。 - SHIFT社・ナイル社・うるる社・オロ社などの事例 を見ても、堅実経営をベースにした“じわ新規”戦略は国内で確実に成果を上げている。
- どちらが有利かは起業家の目指すゴールと市場状況次第。
早期大量調達を狙いたいならスタートアップ路線、長期視点の着実な成長を重視するならソリッドベンチャー路線を選ぶと良い。
いずれにしても、「自分のビジネスにはどの方法が最適なのか?」という点を見誤らず、資金調達・事業開発・リスクマネジメントをトータルで考える必要があります。
ソリッドかスタートアップか、次のアクションを見据えて
スタートアップとソリッドベンチャーは対照的な戦略をとりながらも、最終的に目指すゴールは「事業を大きくし、価値を生み出す」ことに変わりありません。
外部資金を活用して短期集中で規模を狙うか、じっくりと黒字を積み上げてリスクを低く抑えるか――この選択は、単にファイナンス面だけでなく、自社のカルチャー形成や採用戦略、さらにはプロダクト開発の優先度にも大きく影響します。
- もし、起業家として「早期に大きな勝負をかけたい」 ならば、スタートアップ型のメリットを最大限に活かすべきかもしれません。
- 逆に「自分のペースで経営を進めたい、株式のコントロールを手放したくない」 のであれば、ソリッドベンチャー型で段階的な成長を重視するのが得策です。
M&A総研ホールディングス社やユナイトアンドグロウ社のように、受託・コンサルやシェアリングサービスで安定的にキャッシュを得つつ、その蓄えを新規事業やシステム開発へ回すことで、最終的に上場やユニコーン級の時価総額へたどり着いた例も少なくありません。
派手さは少ないかもしれませんが、堅実経営の強みは外部環境の変動に対する耐性の高さと言えるでしょう。
一方で、スタートアップ路線では「当たればデカい」分、失敗時の撤退速度が速く、投資家との利害調整が必要になるケースも多々あります。事業と資本が一体化し、組織としての短期的成果圧力が高まりやすいことも覚悟が必要です。
いずれの道を選ぶとしても、重要なのは「自社のサービスがどのように社会で機能するか」を見極めつつ、適切なリスクテイクと拡大ペースを設計すること。今後の起業環境では「ハイリスク・ハイリターン以外の選択肢」として、ソリッドベンチャーの存在感がさらに増すと考えられます。
事業の性質や創業者のビジョン、そして市場の規模やタイミングを総合的に考慮し、自分に合ったモデルを検討してみてください。
ソリッドベンチャーは“状態”である
ソリッドベンチャーは、特定の業態や資本構成の“型”ではなく、会社が持続的に挑戦し続けられる“状態”を指します。たとえば、キャッシュが定常的に回る柱があり、そこから新しい打席に立ち続ける余地と、撤退を恐れない文化がある。この“状態”さえ保てれば、受託でもSaaSでも仲介でも、選ぶ手段は変わり得ます。
最後に──“状態”で選び、速度で設計する
結論として、どちらが“有利”かは固定ではありません。外部環境、プロダクトの熟成度、創業チームの強み、そして何よりも「倒れず学び続けられるか」という“状態”が鍵になります。速度は戦略で足せますが、耐久力は一朝一夕では作れません。自社が今どの段にいるのかを確かめ、足場を固めつつ機会にだけ強く張る——その反復の先に、急拡大も静かな大化けも、どちらも開けています。
Q1. ソリッドベンチャーは“状態”といいますが、何を指しますか?
A. 倒れない黒字の土台があり、挑戦と撤退を繰り返せる余力と文化を備えた会社の状態です。業種や手段ではなく、続けられる体制そのものを指します。
Q2. 外部資本はソリッドベンチャーに不要ですか?
A. “常に不要”ではありません。勝機が見えた局面で速度を足す燃料として使う選択肢はあります。前提は、会社の状態(主導権や再現可能な稼ぎ)を損なわないこと。
Q3. どちらを選ぶべきか、最初に決め打ちする必要は?
A. 決め打ちは不要です。今の市場・顧客・チームに合う作法から始め、状態を保ちながら必要に応じて速度を足す。移行は可能です。