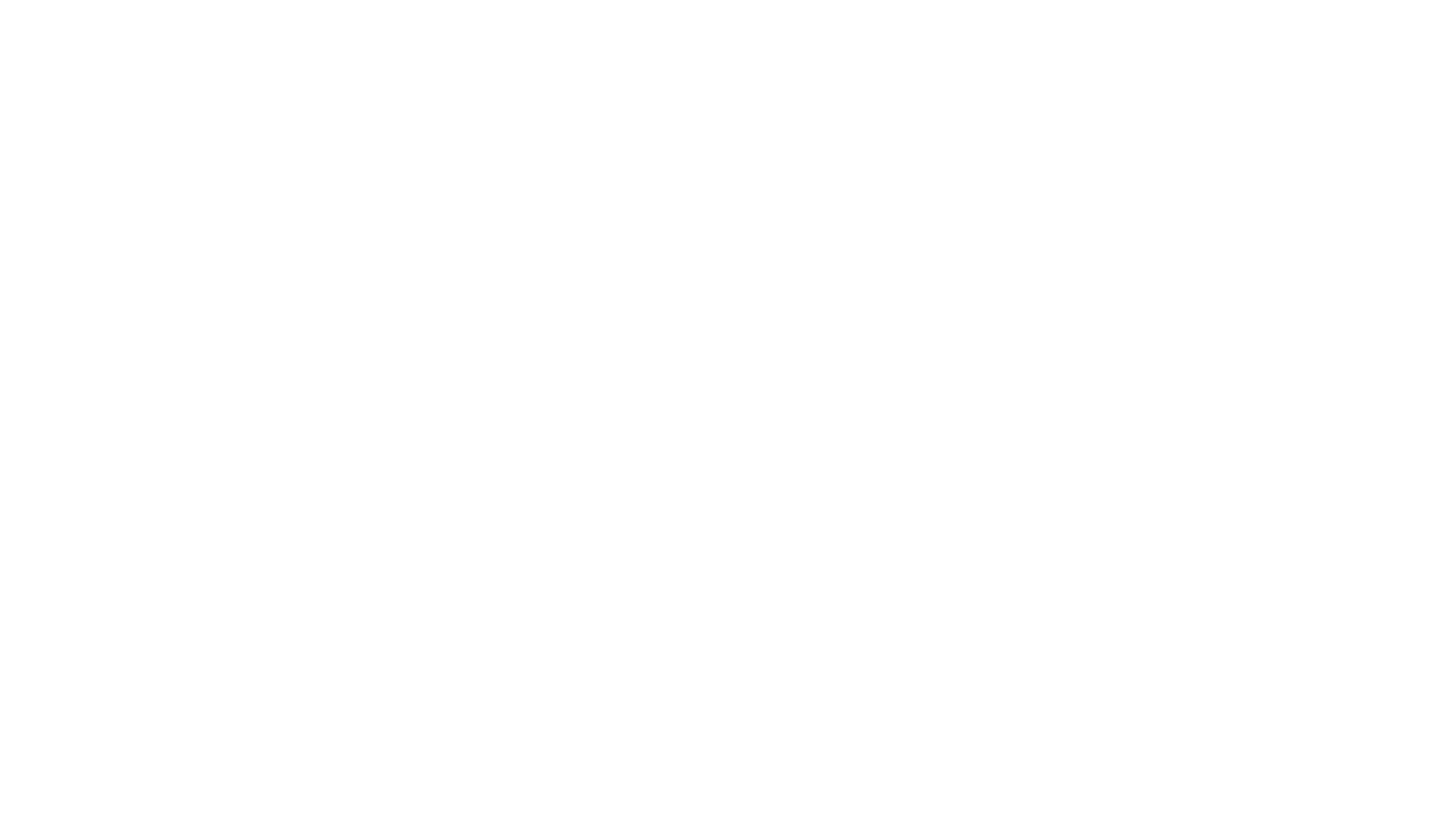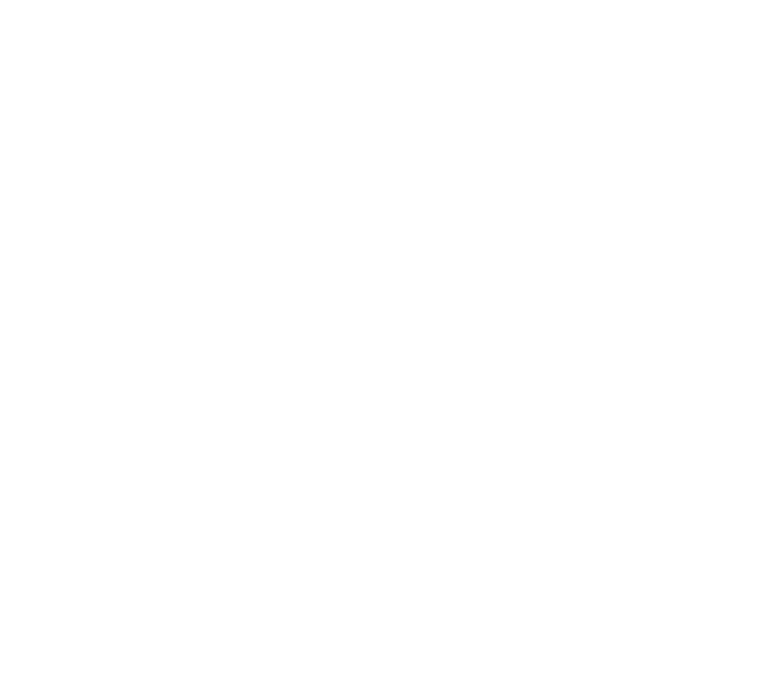- #スタートアップ
- #ソリッドベンチャー
- #成長戦略
ソリッドベンチャーがスタートアップのように急成長を避けるべき理由
公開日:2024.11.19
更新日:2025.4.15
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠

ソリッドベンチャーは、スタートアップのような急成長を追わずに“ジワ新規”と呼ばれる着実な拡大を目指します。外部資金に頼らない安定収益の確保や、組織づくりを大切にすることで、長期視点でリスクを回避しながら企業価値を積み上げる――本記事では、そんなソリッドベンチャーが急拡大を避ける背景と、実際に堅実な拡大を実践している事例をもとに、そのメリットや戦略を解説していきます。
ハイライト
- リスクと資金圧迫を回避するため、急成長よりも安定した「ジワ新規」を選択
- 段階的な組織強化と文化浸透が、拡大期の混乱や内部崩壊を抑えるカギ
- 自己資金や安定収益を基盤にした成長により、投資家圧力に左右されない“ブレない経営”を実現
急成長を目指すか、安定成長を優先するか
近年、「スタートアップ」が市民権を得たことで、市場を短期間で席巻する急成長モデルが大きく注目されています。急激にユーザー数や売上を伸ばしてメディアでも取り上げられれば、VCなどから大量の資金調達が期待できます。一方で、それに伴うリスクが非常に大きいのも現実です。
反面、ソリッドベンチャーと呼ばれる企業は「派手な急成長」を追わず、“コア事業での安定収益”や“長期的な組織づくり”を重視するアプローチを選択します。たとえ地味に見えても、結果として長期間にわたって安定成長を続けることができるため、持続的に企業価値を高められるのです。
本記事では、ソリッドベンチャーの戦略とその背景を改めて掘り下げつつ、なぜ彼らが急成長を避けるのかを説明します。さらに、実際に段階的成長で成果を出している「Union社」「Wiz社」「One Net社」などの事例も紹介しながら、安定成長の魅力に迫ります。
急成長モデルの落とし穴――スタートアップのリスク
資金繰りに追われる短期決戦
スタートアップの代表的な戦略は、大量資金を投入して最短ルートで市場を取ろうとする“攻めの姿勢”です。大きなリターンを狙う投資家がつきやすい反面、以下のような問題が起きやすくなります。
- 多額の資金調達による株式希薄化:創業メンバーの持ち株比率が減り、経営の主導権が失われるリスク
- 短期KPI優先の経営:投資家からのリターン要求が厳しく、長期的な視野を失いがち
- キャッシュバーンの加速:思うように売上が伸びないと資金不足に陥り、追加調達も困難に
つまり、急成長の裏には常に「資金がショートするかもしれない」というプレッシャーがつきまとい、それが経営判断を制約する要因にもなります。
組織崩壊と内部混乱のリスク
急拡大はまた、組織面の混乱を引き起こしやすいです。
- 大量採用→文化のブレ
新規メンバーが爆発的に増えると、創業期の価値観やマインドが浸透しにくく、チーム内で方向性のズレが生じやすい - 未成熟なマネジメント体制
組織が大きくなる速度に、管理手法や報連相フローの整備が追いつかない - 短期目標主導での不協和音
数字に追われるがあまり、従業員のモチベーションや会社のビジョンをないがしろにしてしまう
こうした問題は、急成長の“華やかさ”の陰に隠れがちですが、社内で燻る不満や無理な働き方が長続きすれば、離職率の上昇やプロジェクトの失敗を招きかねません。
ソリッドベンチャーの選択──“ジワ新規”で堅実に拡大
安定収益を柱にするメリット
ソリッドベンチャーが急成長を避ける最大の理由は、まずは堅実に黒字化し、安定収益を確保してから次の手を打つことにあります。スタートアップのように「資金調達がショートしたら終了」というリスクを極力低くするため、最初に受託や代理店ビジネスなど、キャッシュフローが安定しやすいサービスを持ち、そこから生まれる利益を使って新規事業に段階的に投資していくわけです。
Union社の成長手順
- 利益率の高い広告代理事業で安定した利益を作る
- 得たキャッシュを少しずつ新プロダクトの開発に回し、小規模テスト→本格導入のプロセスを踏む
- 大失敗にならないうちに軌道修正することで、会社全体が傾くリスクを回避
この方法なら、失敗してもキャッシュが尽きる前に撤退や改善が可能なため、事業継続の安全度が高まります。
組織文化を守りながらの拡大
ソリッドベンチャーが急成長を好まないもう一つの理由は、組織文化やチームの一体感を重視しているためです。短期で大幅採用を行うより、段階的に人材を増やしながらノウハウや企業理念を丁寧に浸透させることが、長期的には強い組織を築く近道と考えられているのです。
Wiz社の“組織強化”手法
- 大量採用する時期でも、新入社員向けの研修と定期的なフォローを欠かさない
- 小さなチーム単位で、頻繁に情報共有を行い“横の連携”を強化
- 新規サービスはまず少人数の“パイロットチーム”で検証し、成功モデルを拡散
このように、拡大スピードに見合った組織づくりを行うことで、“大きくなるほど内部が崩壊する”リスクを抑えています。
資金リスクと自己資金活用――投資家に振り回されない強み
外部投資を最小限にする柔軟性
スタートアップでは、VCなどの出資を得る代わりに経営権の一部を譲渡し、投資家の意向に左右されることも多いです。短期的な株主価値を優先した無理な成長を求められる可能性があるため、経営判断が“短期KPI”寄りになりがち。
一方、ソリッドベンチャーは“自己資金”や“既存事業の安定収益”を元手に、新しい取り組みを少しずつ行うため、投資家の過度な干渉を受けずに済みます。これにより、長期的な視野で経営戦略を描くことが可能になるのです。
One Net社の少額調達スタイル
- まずメイン事業(営業代行・SES)で月額ベースの安定収益を作る
- 必要に応じて銀行融資などのデットファイナンスを活用し、大型のエクイティ調達は避ける
- 新サービス立ち上げ時は、ある程度顧客ニーズを確信した段階で人員追加
こうして、投資家の“EXITゴール”に振り回されることなく、経営方針を自社主導で決められるのが利点です。
選択肢を増やすM&Aや提携
ソリッドベンチャーであっても、成長局面でどうしても資金が必要になる場合はあります。その際に大規模な資金調達をするのではなく、以下のような選択肢を取れることも強みの一つです。
- 銀行融資(デットファイナンス):黒字実績があるため、比較的低い金利で融資を受けやすい
- 戦略的M&A:不足するノウハウや顧客基盤を持つ企業を買収し、短期間で事業領域を拡張
- 業務提携:他社との協業で開発リスクやマーケ費用を分散し、無理のないスピードでスケール
スタートアップが「ハイリスク・ハイリターンの出資一本」で突き進むのに対し、ソリッドベンチャーにはこうした柔軟な調達手段や成長パターンが備わっています。
“ジワ新規”がもたらす持続的成長の構図
小さな失敗で学べる環境
ソリッドベンチャーは、新規事業であっても「少しずつ試してから広げる」プロセスを踏むため、仮に失敗があってもダメージが限定的です。大失敗が生まれにくいので、失敗から学んだ改善策をそのまま次の事業やサービスに活かすことができ、企業全体の学習効果が高まります。
顧客満足度の維持
急拡大の裏で顧客対応が疎かになると、クレーム対応にリソースが割かれ、結果的に社員の疲弊や離職を招いてしまいます。一方、ジワ新規だと、
- 現在の顧客との関係性を丁寧に維持しながら、新規事業にも力を注げる
- サービス品質を落とさないペースで拡張できる
- 顧客ニーズの細部まで拾い、改善サイクルを回しやすい
このように、ソリッドベンチャーの“焦らない”姿勢は、顧客満足度にもプラスに働きます。
社員育成と組織学習
ジワ新規の成長は、社員一人ひとりがプロジェクトや新サービスを少人数で体験しながら学べる土壌を作ります。急拡大の大規模プロジェクトでは属人的に仕事を進めがちですが、少数精鋭体制で新事業を立ち上げる場合、組織全体がナレッジ共有をしやすくなるのです。
C-mind社が選んだ「ハード×ソフト」の展開
C-mind社は、通信代理店事業などの“儲かるところ”を先におさえ、その“ハード”部分で稼いだキャッシュをもとに、アイデアやユーザーインサイトといった“ソフト”部分をかけ合わせて新サービスを生み出すモデルで成長してきました。
- 創業期:通信の代理店ビジネスで黒字を確立
- 次のステップ:社内に溜まったノウハウを活用し、新規サービス(スリホなど)をローンチ
- 着実な拡大:成功した事業で得た利益をさらに新しいジワ新規事業に再投資
「ハードな収益源」と「ソフトな企画力」の2軸を組み合わせることで、急拡大するスタートアップとは異なる、地道ながらも失敗確率の低い成長を実践できています。
長期的視点がもたらす競争優位性
急成長するスタートアップは、うまくハマれば爆発的なリターンがある一方、そのスピードに組織体制や資金計画が追いつかない場合、大きく躓くリスクも大きいです。
ソリッドベンチャーのアプローチは、短期的なブレを許容しながらも「会社が立ち上がりから数年後、さらに数十年後にも残るかどうか」を最重視しています。
- 焦らないからこそ外部の経済状況に翻弄されにくい
- 堅実な基盤があるため、突発的な資金ショートの恐れが低い
- 従業員が会社の理念を理解して働きやすく、離職率も低めに保てる
こうした特徴は、特に景気の波が激しい時代において、大きなアドバンテージとなるでしょう。
急成長だけが正解ではない
ソリッドベンチャーがスタートアップのような急成長を避ける理由を、あらためて3つにまとめると以下のとおりです。
- 長期的に安定した収益を確保することで、リスクを最小化しながらビジネスを展開するため
- 段階的な採用やチーム作りで、企業文化とマネジメント体制を整え、組織崩壊を防ぐため
- 外部資金に過度に依存せず、自己資金や安定収益で“ブレない経営”を貫くため
もちろん、ネットワーク効果を狙うビジネスモデルなど、スピードが鍵を握る業態も存在します。しかし、あらゆる企業が同じように急成長を目指す必要はありません。むしろ、地道なアプローチを選択できることが、現代では新たな武器になり得るのです。
地道だからこそ生まれる、揺るぎない強さ
「急がば回れ」とは昔から言われてきた言葉ですが、ビジネスの世界にも十分当てはまります。派手なニュースになる急拡大だけが選択肢ではなく、むしろソリッドベンチャーのように少しずつ着実にステップを踏むほうが、“失敗しにくい”かつ“長く勝負できる”モデルになりやすいといえます。
ソリッドベンチャーの教訓は、「慎重な足取りで企業体力と組織文化を育むことが、最終的に揺るぎない強さにつながる」という点にあります。世間の注目が急成長に集まりがちな今こそ、ジワジワと基盤を固めつつ成果を積み上げる経営スタイルに、改めて光を当てる価値があるのではないでしょうか。
長期視点こそが生む、企業の真の持続力
スタートアップの急成長か、ソリッドベンチャーの安定成長か――いずれの道も、ビジネスにおいては正解になり得ます。ただし、あなた自身のリスク許容度や経営観、組織の将来像を踏まえたうえで、どちらのスタイルがより望ましいかを見極めることが大切です。
- スピード重視で一気にシェアを獲得したいなら、スタートアップ型が合うかもしれません。
- リスクを最小限に抑え、安定的に社内基盤を育てながらじわじわ拡大したいなら、ソリッドベンチャー的思考が有効でしょう。
ソリッドベンチャーが示しているのは、急成長がすべてではないという事実です。地道な積み上げによってマネジメント体制や組織文化を整え、安定収益をベースに“ジワ新規”を重ねる経営のほうが、結果的に“長く生き残る”ための確率が高くなることもある――その現実は、これから起業や事業拡大を考える人にとって、大きな示唆となるのではないでしょうか。