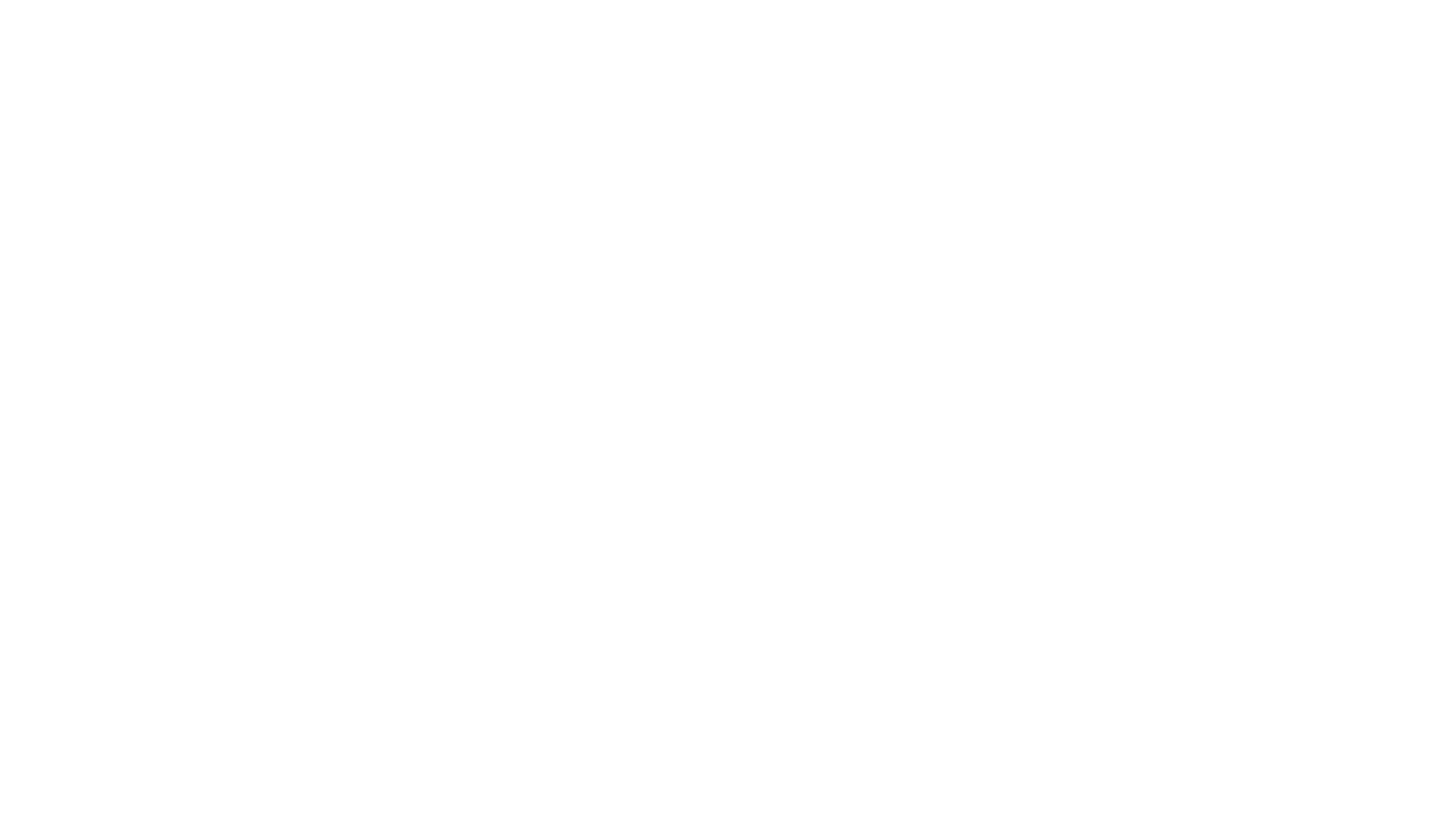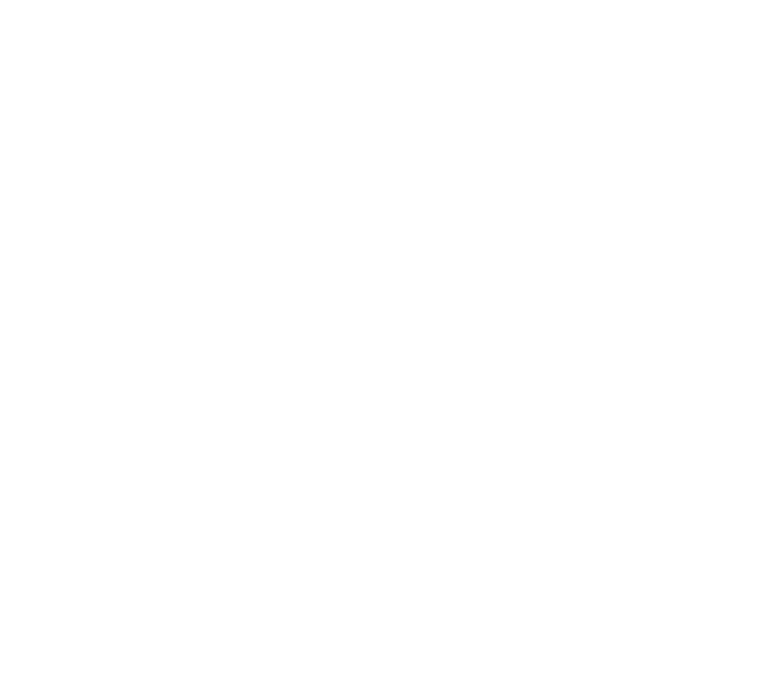- #ジワ新規
- #ソリッドベンチャー
- #事例
ソリッドベンチャーのメリット・デメリットを解説
公開日:2025.01.22
更新日:2025.5.14
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠

スタートアップのような短期間での爆発的成長も魅力的ですが、必ずしもすべての企業がハイリスク・ハイリターンを好むわけではありません。そこで注目されているのが「ソリッドベンチャー」です。外部資金や赤字経営に過度に依存することなく、受託やコンサルなどで早期から黒字を確保し、段階的に新事業へ拡大していく――この堅実スタイルにこそ、大きな強みが秘められています。本記事では、ソリッドベンチャーの定義やメリット・デメリット、そして実際の企業事例をもとに「なぜいま注目を集めるのか?」を詳しく解説します。短期勝負か、堅実路線か? 自社のビジョンや市場環境に合った選択肢を見極めるうえで、ぜひ参考にしてみてください。
ハイライト
- 早期黒字化と“ジワ新規”が特徴: 受託ビジネスなどで安定収益を生み出しながら、新規事業を段階的に開発し、リスクを最小化する。
- 外部資本への依存度が低い: 投資家の意向に左右されずに経営戦略を進められるため、スピードよりも安定重視の拡大が可能。
- 大規模投資には不向きな面も: 爆発的な成長や大量ユーザー獲得が必要な領域では、スタートアップや外資系企業に後れを取るリスクがある。
ソリッドベンチャーのメリット・デメリットを解説
ソリッドベンチャーとは?
近年、「スタートアップ」という言葉がビジネスシーンをにぎわせています。大規模な資金調達をもとに、短期間でユーザーや売上を爆発的に伸ばしていく“Jカーブ型”の成長モデルが華やかに語られ、メディアでも大きく取り上げられることが多い。
しかし、そうした急拡大路線がすべての起業家や企業に合うわけではありません。むしろ、初期から安定した収益を出しながら、段階的に事業を育てていく経営スタイルのほうが、自社にとって無理がなく魅力的に映るケースもあるはずです。
ソリッドベンチャーとは、まさに「初期からの安定収益」にこだわり、外部資本や赤字経営に依存しすぎることなく、着実かつ長期的に事業を成長させていく企業スタイルを指します。本記事では、そんなソリッドベンチャーのメリットとデメリットを整理しながら、どんなタイプの起業家・企業に向いているのかを解説していきます。
ソリッドベンチャーとは?スタートアップとの違い
そもそも「ソリッドベンチャー」って何?
ソリッドベンチャーは一言でいうと、「黒字経営の継続を重視し、リスクを抑えながら新規事業へ徐々に拡大するビジネスモデル」です。
- 短期的に莫大なユーザーや売上を伸ばすより、まずは目の前の顧客に対して受託開発やコンサルティング、あるいはBPO(事務処理代行)などを行ってキャッシュフローを安定化させます。
- その上で、余裕資金を使って新しいサービスやプロダクトの開発に取り組む、という流れです。
スタートアップとの対比:リスクとスピードの違い
スタートアップが「短期間で急成長して株式価値を一気に高める」ことを目標にするのに対し、ソリッドベンチャーは「早い段階での黒字化」と「ジワ新規(小刻みな多角化)」を重視する点で異なります。
スタートアップ:
- 大規模調達を繰り返し、赤字覚悟で市場を席巻
- IPOや大型M&Aを5年以内など短期間で目指す
- ハイリスク・ハイリターン
ソリッドベンチャー:
- 自己資本や小規模資金調達+受託などでキャッシュを稼ぐ
- ゆるやかに利益を積み重ねながら、新規事業を立ち上げ
- ミドルリスク・ミドルリターンまたはローリスク・ミドルリターン
このように、スタートアップが投資家主導のスピード勝負なのに対し、ソリッドベンチャーは経営者主体でリスクを管理しながら会社を大きくしていくイメージと言えるでしょう。
ソリッドベンチャーのメリット
ソリッドベンチャーが「スタートアップほどの爆発力はない」といわれる一方で、次のような大きなメリットがあります。
初期から安定キャッシュフローを得られる
ソリッドベンチャーの大半は、受託開発・コンサル・BPOなどで創業期から売上が立ちやすいビジネスを軸に進めます。結果的に、資金が尽きて事業撤退…というリスクを抑えられるため、持続的に新たな取り組みへ投資する余力を生み出せます。
M&A総研ホールディングス社
(具体的な実績:2024年9月期で売上高約165億円、上場ユニコーンと呼ばれるまで成長)
- 企業のM&A仲介やコンサルティングといった「受託型サービス」をコアに、創業初期から着実に収益を生み出してきました。
- 小規模案件を積み上げることでキャッシュを手堅く確保し、いまでは各種DX支援コンサルにも乗り出すなど、事業領域を拡大中。
メリットポイント: 一つひとつの案件が成立すれば報酬が安定して入り、投資家のEXIT圧力を気にせず成長戦略を描ける。
外部資金依存を最小限にできる
大規模投資に頼らずとも、受託やコンサルからの売上で運転資金を回せるため、株式の希薄化を抑えられるのが大きいポイントです。ベンチャーキャピタルの意向やEXIT期限などに縛られず、経営者が自分の思うペースで事業を組み立てられます。
レバレジーズ社
- ITエンジニア派遣・人材紹介といった「人材系ビジネス」で創業初期からストック型の売上を積み重ね、投資家に大きく依存しない経営を実現。
- 外部からの大きな出資を避けることで、創業者のリーダーシップを維持しながら事業多角化を進めてきました。介護や海外就労支援などにも広く展開し、結果として大規模企業へと成長。
隣接領域への「ジワ新規」がしやすい
地道に稼ぐ本業を持つ企業は、顧客との関係やノウハウがしっかり蓄積されるため、少しずつ新サービスを追加していく“アンゾフの成長マトリックス”の「既存顧客×新商品」がやりやすいです。
ビジョン・コンサルティング社
- ITコンサル・システム構築支援で得た顧客基盤を活かし、人材教育やSES(システムエンジニアリングサービス)、さらに新興技術導入の上流コンサルへと“ジワジワ”領域を広げている。
- 安定黒字を背景に、必要に応じて新しい専門人材を採用し、顧客ニーズに沿ったサービスを増強。投資家の短期リターン要求に左右されることなく、柔軟にポートフォリオを拡張している。
さらに、Speee社のようにB2BとB2Cを行き来しながら成長を続ける事例もあります。創業はモバイルSEOのコンサルから始まり、その専門知識を活かして不動産メディアやレガシー産業DXコンサルへと拡張。爆発的な広告投下には慎重ですが、着実な顧客理解を軸に新事業を積み上げる戦略が功を奏しています。
ソリッドベンチャーのデメリット
メリットの裏側には当然デメリットもあります。ソリッドベンチャーは、急激なスケールアップやハイリスク投資を行わないぶん、以下のような弱点が生じる場合が多いです。
爆発的ユーザー獲得が難しい
大規模資金を広告費やマーケティングに投入しづらいため、市場を一瞬で席巻するような戦略は取りにくいです。SNSやBtoCアプリなど「スピードが勝負」のマーケットで後れを取るリスクが高いと言えます。
成長が緩やかで、大きな投資に慎重
受託やコンサルというキャッシュ源があるとはいえ、そこから生み出される利益には上限があります。大きな投資案件(例えば自社で巨大なプラットフォームを構築するなど)に踏み切るのが遅れ、スタートアップ勢に先行される可能性があるのです。
競合の資金力に勝てない場合がある
外部資金を大量に調達する企業と真っ向勝負になった場合、資金力の差で差し切られることがあります。特に海外勢が豊富な投資をバックに参入してくる市場では、ソリッドベンチャーがシェアを奪い返せなくなるケースも。
事例からみるメリットとデメリット
ここからは、上記で一部ふれた会社とは別に、具体的な企業の事例をいくつか挙げてメリット・デメリットがどのように表れているかをもう少し深掘りしてみましょう。
M&A総研ホールディングス社
- メリット面:
- 受託コンサル型のM&A仲介で安定収益を確保
- 小規模案件でも着実に手数料を得られる仕組みを作り、徐々に知名度を上げながら顧客を拡大
- キャッシュが安定するため過度に投資家に頼らず、独自路線を堅持
- デメリット面:
- 大型案件を一気に取るための資金やネットワーク構築では、大手証券や大規模仲介会社に劣る
- 市場全体が盛り上がった際に一瞬で拡大しきれず、ライバルに先行されるリスク
レバレジーズ社
- メリット面:
- ITエンジニア派遣・人材紹介で創業初期からストック型の売上を積み重ね、資金繰りを安定化
- その後、介護・海外人材など隣接領域へ展開し、ソリッドに規模を拡大
- 投資家へのリターン要求に左右されにくく、経営者主導の長期方針を実践
- デメリット面:
- 大きなIT投資やアプリ開発に踏み出す際は、受託や派遣ビジネスの利益のみではスピードが限られがち
- 大手企業が積極投資してくると資本力の差が顕著に現れる可能性
ビジョン・コンサルティング社
- メリット面:
- ITコンサル・システム支援で堅実に稼ぎ、得意領域を広げていく“ジワ新規”戦略がしやすい
- 内部留保が増えるほど、新規投資や採用に振り向けられるお金が増え、長期安定経営が可能
- デメリット面:
- コンサル業界は競合他社も多く、ブランド力を急激に高めるには限界がある
- スタートアップ型の爆発成長に比べると、企業評価額が一気に跳ね上がるシナリオは限定的
堅実経営を選ぶ理由
ソリッドベンチャーは、スタートアップのように短期的な時価総額アップや大型EXITを狙う路線ではありません。もっと地に足をつけて、赤字リスクを最小限に抑えながら堅実に稼ぐ──その上で徐々に新規事業へ広げていくのが特徴です。
こうした堅実経営は、特に以下のような背景を持つ企業・起業家にとって魅力的と言えるでしょう。
- 自己資金や受託ビジネスでまずキャッシュフローを作りたい
- 数年でのIPOを急がず、長期的な収益安定を目指したい
- 株式の希薄化を避け、経営者の裁量を確保したい
- スモールM&Aでの売却や、地方のニッチ領域での安定成長を選択肢に入れている
もちろん、ソリッドベンチャーには「大掛かりな広告投下が難しい」「競合が急激に資金を投入してきたら不利になりやすい」といった側面もあります。しかし、そのリスクを補って余りあるほど、“自社ペースでの成長”や“経営の安定性”を得られる魅力が大きいと言えるでしょう。
結局のところ、企業の規模や目標、参入市場によって、スタートアップ向きかソリッドベンチャー向きかは大きく異なります。大きなリターンを狙いたいなら前者、堅調な経営を重視したいなら後者──どちらが正解とは限りません。
「早期収益化でリスクを減らしながら成長する」という考え方は、今後さらに多くの起業家や経営者にとって検討に値するでしょう。大きなトレンドの裏で地道に収益を積み上げる企業こそ、長期的に見れば安定的な社会的存在感を確立していくかもしれません。
もしあなたが、スタートアップ路線にやや抵抗を感じる、あるいはまず黒字を確保してから新事業に挑戦したいと思うのなら、ソリッドベンチャーという選択肢は大きな可能性を秘めています。自社の強みを活かした受託・コンサルから始め、そこで得た資金とノウハウを隣接領域へ“ジワ新規”していく──。
その積み重ねが意外なほど大きな企業へと成長させる土台になるのではないでしょうか。
さらなる飛躍のために
ソリッドベンチャーの存在意義は、派手な資金調達や短期勝負に偏らずとも企業が大きくなり得るという事実を示す点にあります。確かに、一足飛びの成長やグローバルなネットワークを構築するには、スタートアップ的な爆速戦略が必要な場合もあるでしょう。
しかし、国内のBtoBサービスやニッチ市場など、地道に顧客基盤を拡大していくほうが実は向いている領域も多いのが実情です。
- 受託開発やコンサル事業で培った信頼関係から、独自のプロダクトをローンチする
- 自社の強みを活かしてM&Aや業務提携を進める
- 社員や顧客とともに「明日の事業」を少しずつ育てる
こうしたステップを踏みながら、ソリッドベンチャーはローリスクで安定的な拡大を目指せます。急成長路線の煽りを受けにくいぶん、経営者のビジョンをじっくりと形にできる自由度も高いと言えるでしょう。
たとえばINTLOOP社がフリーランスのコンサル人材を自社に取り込む独自のハイブリッドモデルを確立し、安定収益と柔軟な拡張を両立しているように、ソリッドベンチャーにはまだまだ新しい可能性が広がっています。
自社の資源や顧客ニーズを丁寧に拾いながら一歩一歩拡大していく“ジワ新規”の発想は、経営環境が不透明な時代にも強いレジリエンスを発揮するはずです。
規模の大小だけにとらわれず、まずは「手が届くところから」稼ぎ、そこで生まれた利益を次のジャンプにつなげる――ソリッドベンチャーの志向は、今後も多くの企業にとって有力な選択肢となるでしょう。