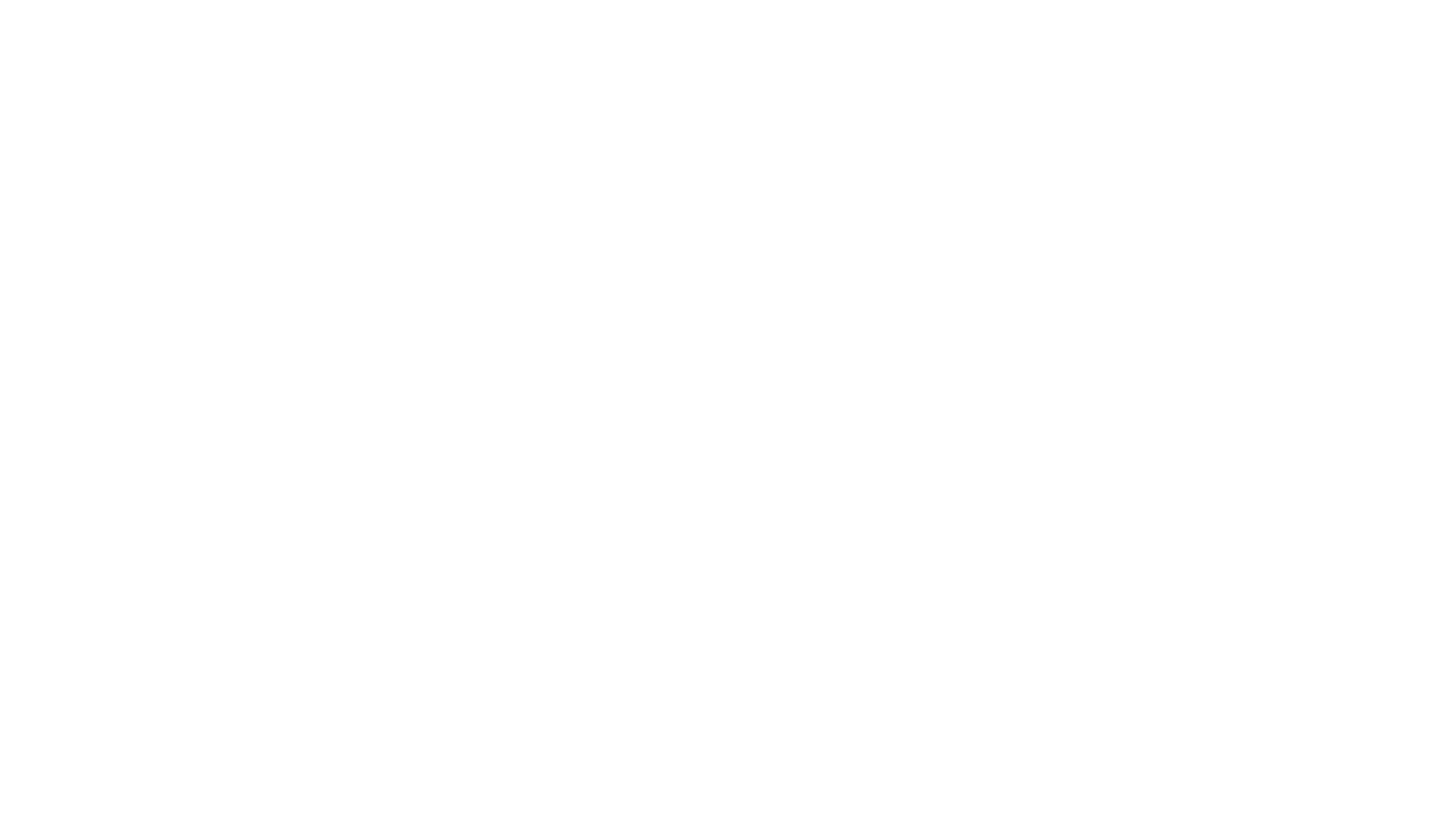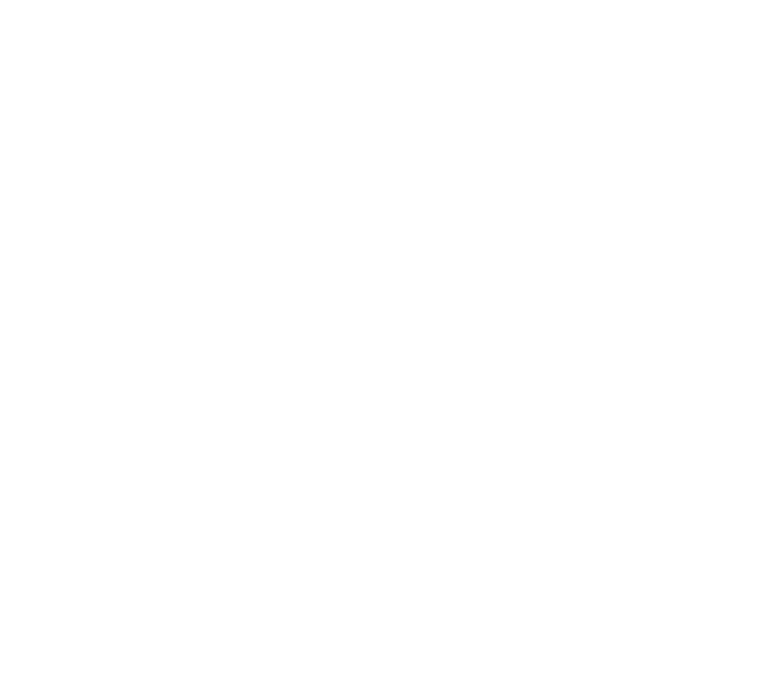- #ソリッドベンチャー
- #成長戦略
- #採用
ソリッドベンチャーで事業をスケールさせるための組織づくり:安定と挑戦を両立するには
公開日:2024.11.19
更新日:2025.3.26
筆者:
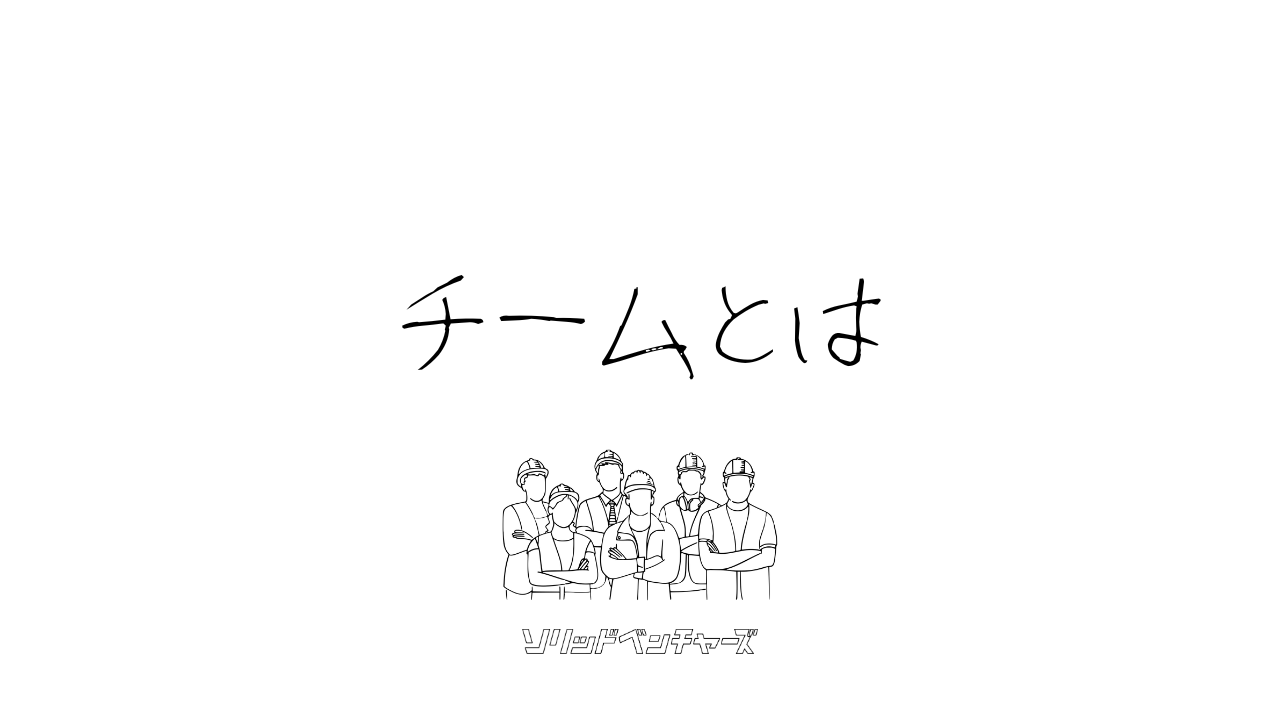
ソリッドベンチャーとして堅実に収益を確保しながら、新規事業を少しずつ拡げていく──。この「安定収益×ジワ新規」のモデルには、一定以上の規模に達したときに乗り越えなければならない組織的課題が待ち受けています。どれほど優れた製品やサービスを提供していても、組織基盤が脆弱だと人材の力を活かしきれず、ビジネスがスケールしづらくなってしまうのです。本記事では、明確な組織設計、柔軟なチーム体制、そしてリーダー育成と人材開発がどのようにソリッドベンチャーの長期成長を支えるかを、具体的事例(Speee社・INTLOOP社など)とともに解説します。
ハイライト
- 役割分担と権限設計を明確化し、成長による混乱を最小化する
- ジワ新規を後押しする“小規模実験×段階的拡大”で、組織に柔軟性を持たせる
- リーダーシップと人材育成への投資が、安定と挑戦を両立する強い組織を生む
堅実な収益基盤を活かす“組織設計”のポイント
スケール時に不可欠な役割分担と権限設計
ソリッドベンチャーは創業初期からキャッシュを生み出す“核となる事業”を持ち、そこから徐々に新規ビジネスを拡張していくため、少人数体制でも回る場合が多々あります。しかし事業が増えて複数のプロジェクトやサービスを抱えるようになると、「誰が何を担当しているのかが不明確」という状態に陥りがちです。
- Speee社を例に取ると、SEOコンサルで安定収益を得ながら、新規サービスとしてレガシー産業向けのDX支援や不動産メディア運営を段階的に拡張してきました。このとき、既存部門と新規部門それぞれの役割やKPIを明確にし、組織上の権限を整理することで、成長に伴う混乱を最小限に抑えています。
組織図をレイヤー化して情報共有を最適化
事業が拡張し始めた段階では、「一人何役もこなす」多機能メンバーが重宝されます。しかし、ある程度の規模に達すると部門ごとの専門化が必要になり、全員が“なんでも屋”だと連携コストが高くなるのです。
部門を作るだけでなく、各部門間の情報共有ルールや連絡経路を仕組み化しなければ、部署ごとの“縦割り”が進んでしまいます。プロジェクト横断の定例会やオンラインツールの導入など、コミュニケーションが円滑になる仕掛けが不可欠です。
ジワ新規を加速する「柔軟なチーム編成」
少人数のプロジェクトチームで“小さく始める”
ソリッドベンチャーの特徴である「ジワ新規」は、既存事業から得られる安定収益を背景に、低リスクで新たな取り組みを試せる点にあります。一方で、社内リソースを大きく割いてしまうと既存事業の安定性を損なう恐れがあるため、まずは少人数でスタートし、顧客や市場の反応を見極めながら拡大していくアプローチが有効です。
- ペンシル社の例では、デジタルマーケティング分野における小規模な新規プロジェクトを複数動かし、成功しそうな芽が見えた段階で人員と資金を追加投入して事業化を進めています。こうした「段階的拡大」はジワ新規の王道パターンといえます。
既存事業とのシナジーを最大化する組織連携
ジワ新規が成功しやすい要因として、既存事業のアセットを活かせることが挙げられます。営業先リスト、顧客基盤、技術基盤、あるいはブランド力など、ゼロから始めるのと比較して大幅にスピードアップできるのが強みです。
そのためにも、新規事業チームと既存事業チームの間で頻繁な情報共有が行われる仕組みが大切。たとえば毎週のクロスチームミーティングを設けたり、部門を横断してKPIを追う共通ダッシュボードを導入したりと、組織全体でシナジーを意識する体制を築くことで、新たなビジネスを“無理なく”拡大できます。
リーダーシップ強化と人材育成で組織の自律性を高める
経営トップの役割から各部門リーダーへの権限移譲
事業規模が拡大すると、経営者だけで全てを管理するのは不可能になります。ここで求められるのは「部門ごとにリーダーを育成し、そのリーダーに意思決定の裁量を与える」ことです。
- INTLOOP社では、コンサルティング事業をマルチに展開する中で、各領域を率いるリーダーを配置し、顧客との折衝やサービス開発を迅速に行えるようにしています。結果として本社の経営陣は“全体最適”の意思決定に注力でき、組織全体の動きがスピーディーになるのです。
社員のキャリア設計と学習環境の整備
ソリッドベンチャーでは、安定収益がある分、学習投資や社員研修にリソースを割きやすいというメリットがあります。社員個々が新しいスキルや知識を獲得できる環境があると、組織はより自律的に動き出し、新規事業の立ち上げにも対応しやすくなります。
部門横断的なジョブローテーションや社内勉強会などを仕組み化し、社員が「次はここで活躍したい」「このスキルを身につけたい」と思えるキャリアパスを描けるようにすることが、長期的な成長を支えるカギです。
組織変革を支える“安定と挑戦”のバランス
安定収益から生まれる“余力”がイノベーションを促す
スタートアップのように資金繰りを常に意識しなければならない状態だと、大胆なアイデアを試す余裕がありません。その点、ソリッドベンチャーは安定収益により、多少の失敗があっても倒れにくい“クッション”を持っています。
- ただし「挑戦を許容する組織文化」が伴わないと、“安定収益”は慎重すぎる姿勢を生み、イノベーションの芽を潰してしまうリスクも。適度にリスクを取るカルチャーを醸成し、社員がトライ&エラーを楽しめる環境が必要です。
組織連携が新規事業の成功確率を高める
成長フェーズに入ると、部署同士の連携や知見の共有が成否を分ける場面が増えていきます。既存事業と新規事業が同じ顧客基盤を共有するのであれば、セールス情報やマーケティングデータの連携が極めて重要になります。
プロダクト開発チームだけでなく、営業、マーケ、カスタマーサクセスなど多様な部門を一体化する仕組みを作り、“どの顧客層にどんな新サービスが響くのか”を常にチーム全体で考えられるようにすることが、組織の連動性を高めるうえで欠かせません。
ソリッドベンチャーの組織構築がもたらす長期的メリット
組織階層ごとに意思決定の権限を委譲することで、事業規模が拡大しても迅速な対応が可能となる。
- 安定収益をベースにした堅実経営と新規挑戦の両立
- 既存事業が稼ぎ頭となるため、チャレンジングな新事業でもリスクを大きく抑えられる。
- 社員も「失敗しても会社が揺らがない」という安心感の下で創造的に行動できる。
- 部門間連携によるシナジーで新規プロジェクトが滑り出しやすい
- 既存顧客との関係やノウハウを新事業側に展開することで、早期に結果が出やすい。
- コミュニケーション設計を整えることで、重複作業や情報漏れを減らし、効率的にプロジェクトを進行可能。
- リーダー育成とキャリアパスの明確化による組織の自立
- 安定利益を背景に学習や研修に投資しやすいため、中長期的に専門性の高い人材が育つ。
安定収益を土台に、新事業を少しずつ拡げていくソリッドベンチャーならではの強みは、「余力」を活かした組織的イノベーションにあります。
失敗を許容できる仕組みと明確な役割分担、そして社員がキャリアを通じて成長できる環境を整備することで、安定と挑戦の両輪をバランスよく回すことが可能となるのです。これは、変化の激しい時代において持続的な競争力を保つための、有力な経営アプローチと言えるでしょう。