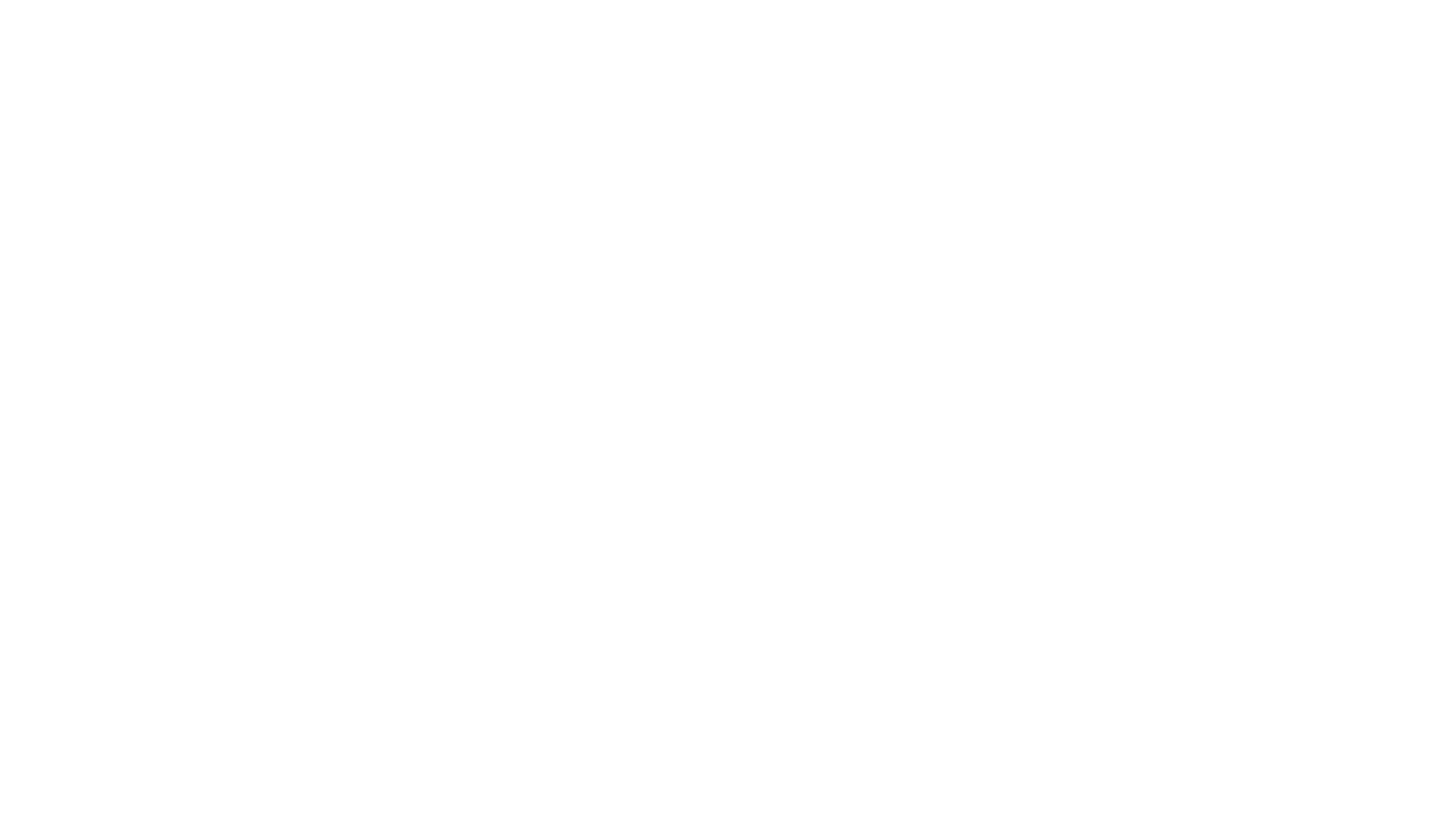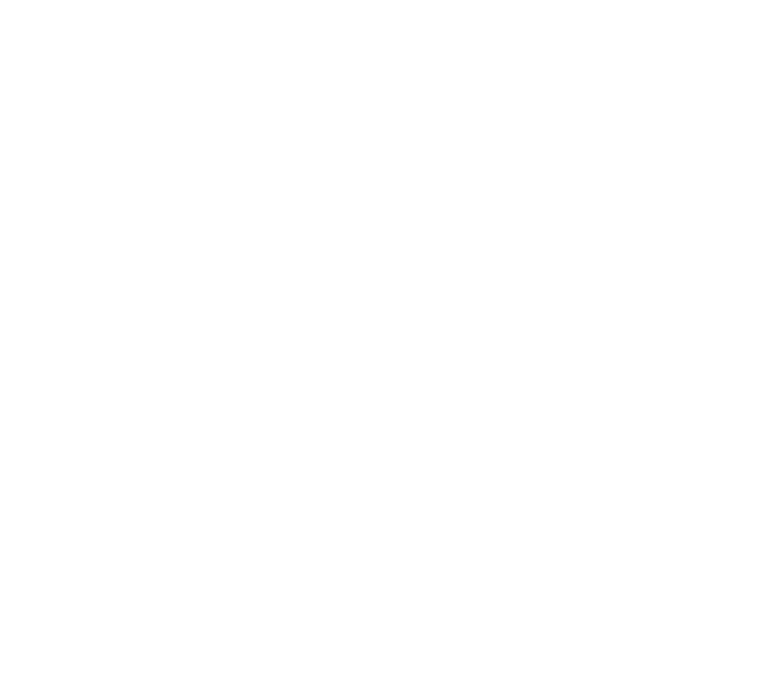- #ソリッドベンチャー
- #収益モデル
ソリッドベンチャー式「安定収益モデル」構築の要諦
公開日:2024.11.15
更新日:2025.4.15
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠

資金調達による一発逆転を狙うスタートアップが注目される一方で、初期から安定収益を確保しつつ、堅実に成長を遂げる“ソリッドベンチャー”が注目されています。本記事では、早期キャッシュフローの大切さ、顧客ニーズを徹底的に拾う姿勢のメリット、そして周辺領域へジワ新規で事業を広げる戦略に焦点を当て、「安定収益モデル」をいかに構築すればよいかを解説します。
ハイライト
- 初期段階での収益確保が、長期的成長と精神的な安定を生む土台になる
- 顧客ニーズを丁寧に拾い、既存事業を基盤に周辺領域へ拡張することでリスクを最小化
- ジワ新規による多角化を進めることで、継続的に収益を積み上げながら柔軟な拡張が可能
初期安定収益こそ長期成長のカギ
“まずは稼ぐ”ことで得られる精神的余裕
ソリッドベンチャーでは、大型投資やVCからの大量出資に頼る前に、
- 受託
- コンサル
- 広告代理
などの比較的「稼ぎやすい」領域でキャッシュフローを素早く生み出すことを重視します。
早期に売上が立つと、外部投資家からのプレッシャーに振り回されずに済むうえ、黒字をキープしながらサービスを改善できるため、経営者のマインドにも大きな安定が生まれます。
投資を自己資金から回せるメリット
初期収益が安定すれば、無理な調達をせずとも新規サービスへの投資がしやすくなります。すでに黒字基調なら「試作品を顧客と一緒に作り込む」ような小さな実験を続けられるのも魅力です。スタートアップのように「大きく当たるか大きく外れるか」に賭けなくても、ジワジワ成長する路線が可能になります。
顧客ニーズを軸にしたサービス設計
初期顧客との“生の対話”が宝
ソリッドベンチャーが重視するのは、まず目の前の顧客と徹底的に対話すること。派手な広告戦略やテクノロジー一辺倒に走るのではなく、「どこに課題があるのか」「何が面倒に感じられているか」を自社の受託や代理業務を通じて把握します。こうした“現場主義”こそが、強固なリピート顧客を生む秘訣になるのです。
顧客負担を丸ごと解消するアプローチ
たとえば、ウェブ制作会社が「制作のみ」ではなく、運用支援や集客施策まで含めてコンサルするといった取り組みは、顧客の不安を大幅に減らします。類似のITコンサル企業も、システム導入から運用研修まで一括で受け負うことで差別化を狙えるわけです。こうした「ワンストップ対応」が、ソリッドベンチャーを顧客にとって頼りがいのあるパートナーに育て上げます。
“ジワ新規”で進めるビジネス多角化
リスクの少ない横展開が可能
ソリッドベンチャーは、既存の営業基盤や技術、人材を無理なく横展開する“ジワ新規”を得意とします。全く別の業界へ飛び込むよりも、現行事業と隣接する領域に少しずつ踏み込むことで、確実に収益アップと顧客基盤の拡大を狙います。
事例:ナハト社
SNS広告事業で安定売上を確保しながら、顧客の要望に応じてインフルエンサーマーケティングや自社メディア展開を追加する形でジワジワと事業領域を拡大。大きな投資リスクを避けつつ、拡張性を高めた。
多事業ポートフォリオでリスク分散
既存の主力事業が多少ダメージを受けても、周辺領域でカバーできる――こうしたビジネスの“ポートフォリオ化”が、ソリッドベンチャーの安定を支える大きなポイントです。結果として、
- 業績のブレが少なくなる
- 従業員が安心して新しい挑戦に取り組める
- 社内リソースの適切な振り分けがしやすい
といった恩恵が得られます。
伸びるソリッドベンチャーの特徴
チームが「まず黒字」の思想を共有
会社全体で「急成長のための赤字覚悟」より「堅実に利益を積む」文化を作っている組織では、ソリッドベンチャー的な成長が生まれやすいです。投資家の顔色を伺うのではなく、顧客との接点を最重視したKPIを追う姿勢が鍵となります。
地道な現場主義と健全な役割分担
マーケットの声をキャッチアップする現場担当と、経営・財務をしっかり管理するバックオフィスがバランスよく機能している企業は強いです。経営者が一人で「アイデア→売上→改善」を回すより、最適なポジションで専門性を活かすメンバーが揃うと、失敗リスクも低下し、長く安定した経営が可能になります。
ソリッドベンチャーが描く未来
多様なEXITと長期的経営
急成長・短期EXITだけがゴールではありません。
- スモールM&Aによる創業者利益の確保
- 上場を視野に入れた長期拡大路線
- 未上場でも数十~数百億規模の企業体質づくり
など、柔軟な選択肢を持ちやすいのがソリッドベンチャーの特長です。必要に応じて資金調達をすることもでき、また無理に調達をせずオーナー経営を続ける道もあります。
企業の新しい選択肢としての位置づけ
スタートアップが一部で過熱する一方、“地味に黒字”の企業の価値も再評価されてきています。地域経済を支える中堅・中小企業の中には、実はソリッドベンチャー型のモデルで着実に売上を伸ばしているケースが珍しくありません。大きなリスクを背負わずとも、ジワジワ確実に成長していく“第三の道”として、ソリッドベンチャーはこれからさらに認知が高まるでしょう。
ソリッドベンチャー式安定収益モデルの全体像
ソリッドベンチャーの安定収益モデルは、以下のような流れで整理できます。
- 初期に確実な売上基盤を作る
- 受託開発、広告代理などで早期にキャッシュフローを得る
- 受託開発、広告代理などで早期にキャッシュフローを得る
- 顧客要望に合わせて漸進的にサービスを拡張
- 現場の声を聞きながら、追加機能や周辺支援を整えていく
- 現場の声を聞きながら、追加機能や周辺支援を整えていく
- 複数事業を展開しリスク分散
- 隣接領域にジワ新規で乗り出し、事業ポートフォリオを構築
これらを重ねることで、企業体質そのものが強固になり、長期視点でも競合との差別化を図りつつ柔軟に市場変化に対応できます。
安定と成長を両立させるソリッドベンチャーの可能性
スタートアップの“爆速チャレンジ”に比べると、ソリッドベンチャーの道はどうしても地味に見えがちです。しかし、リスクを抑えて安定収益を生みながら着実に事業を拡大できるのは、大きな強みといえます。むやみに借り入れやエクイティを集めて“燃えるように走る”のではなく、一歩ずつ堅実な売上をつくることで経営リスクを軽減し、結果的に多様な可能性を手にする――これがソリッドベンチャーの魅力です。
もしあなたが「派手な投資ラウンドは気が進まないが、将来的には大きくなりたい」と考えているなら、ぜひソリッドベンチャーのアプローチを検討してみてください。初期収益モデルの設計からジワ新規の拡張戦略まで、現場レベルでしっかりと“お金を生み出すサイクル”を回すことで、想像以上に大きな成長曲線が描けるかもしれません。