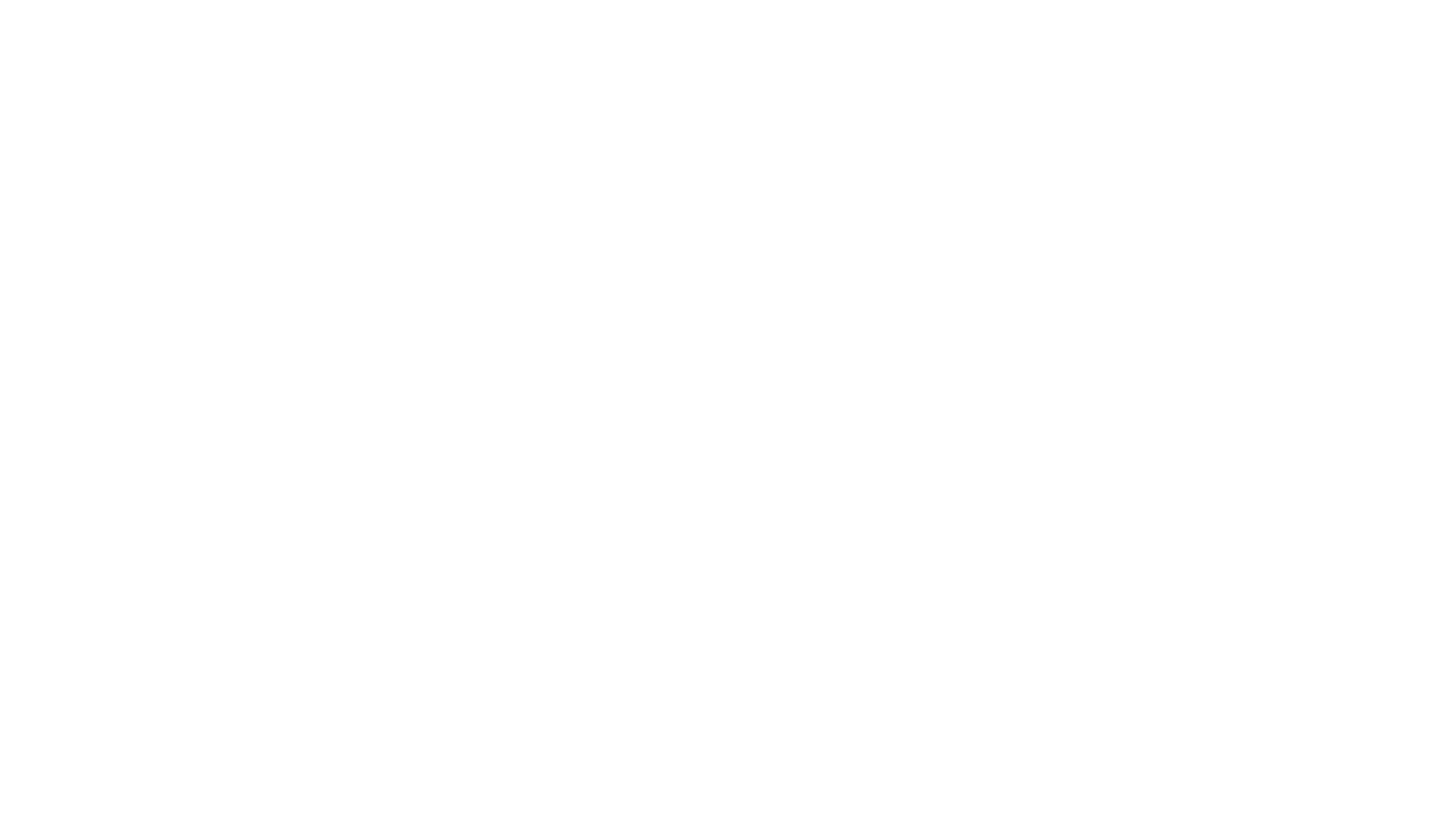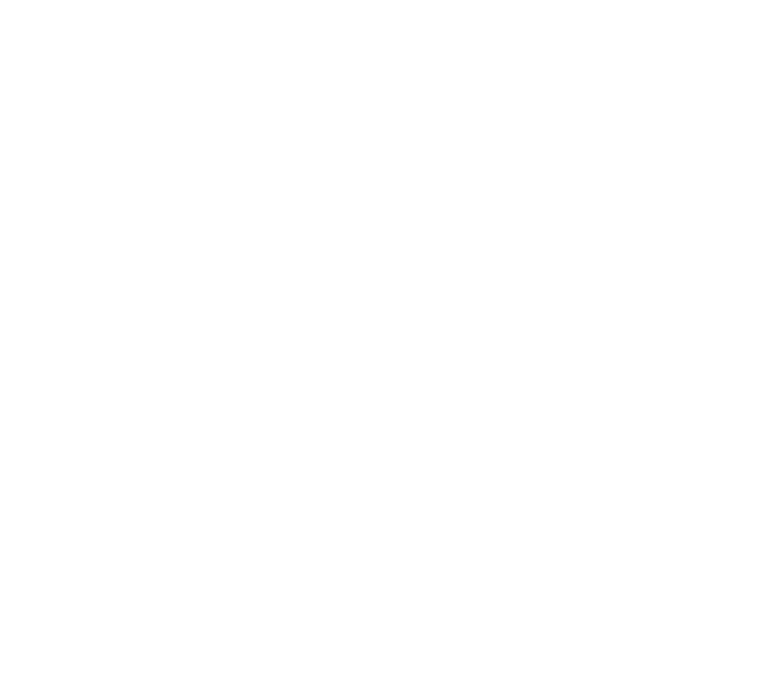- #ソリッドベンチャー
- #事例
ソリッドベンチャーの定義とは?【上場・未上場の事例を踏まえて】
公開日:2024.08.14
更新日:2025.8.26
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠
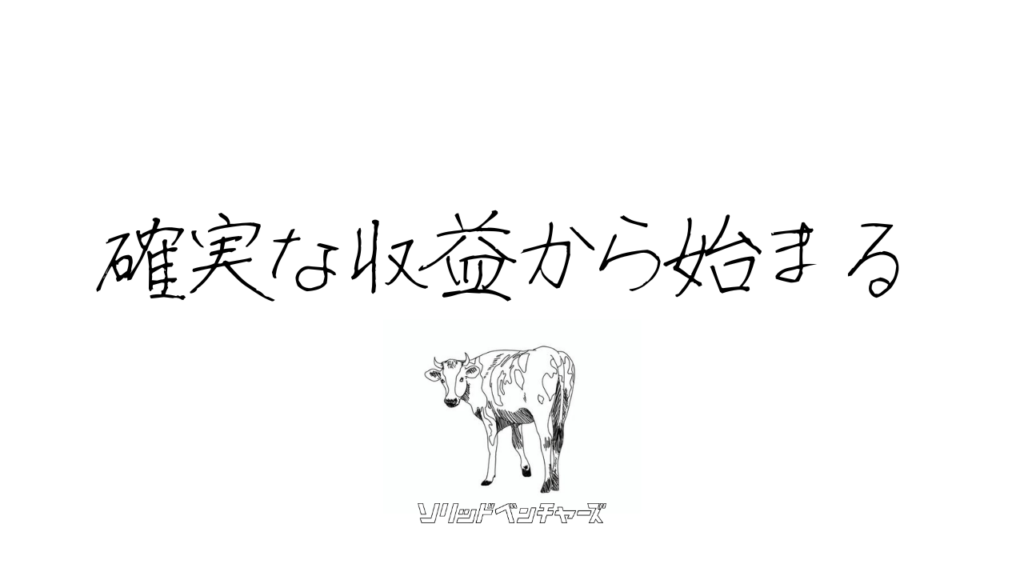
ソリッドベンチャーとは、創業初期段階から収益を実現する事業を構築しそれをキャッシュエンジンとして新事業を持続的に模索する企業のことです。本記事では、ソリッドベンチャーの基本概念からスタートアップとの違い、具体的な事例、メリット、そしてソリッドベンチャーの展望までをまとめました。
記事の要約
【TL;DR】
- ソリッドベンチャー=まず「稼げる柱(キャッシュ・カウ)」を作り、その利益で新規事業に挑戦する会社の型。
- 早めに黒字化しやすく、倒れにくい。挑戦の回数を増やせるのが強み。
- スタートアップとの違い:外部資金で一気に伸ばす前提ではなく、黒字を土台に着実に横展開。
- 事例:SHIFT/TWOSTONE&Sons/ナイル/うるる(上場)や、Union/ナハト 等(未上場)。
【用語の定義】
- ソリッドベンチャー:創業初期から収益を作り、その利益を再投資して事業を広げ続ける会社の型。
- キャッシュ・カウ:安定して利益が出る事業(例:受託開発、コンサル、人材、代理店 など)。
- 再投資:キャッシュ・カウの利益を使って、新しいサービス・プロダクト・M&Aに挑戦すること。
【重要な数字と日付】
- 公開日:2024-08-14 更新日:2025-06-30
- 例)うるる:2024年3月期 ARR 45億超(本文の紹介より)
【登場する主なもの】
- 会社(上場):SHIFT/TWOSTONE&Sons/ナイル/うるる
- 会社(未上場):Union/ナハト/インフィニティエージェント/ルナドクター/CBTソリューションズ/ギークリー/Wiz
- 概念:早期黒字化/再投資/横展開/M&A
【参考リンク】
ソリッドベンチャーを簡単に説明すると? — https://solid-ventures.media/knowledge/a-simple-explanation-of-solid-venture/
ハイライト
- ソリッドベンチャーは、受託やコンサルなどの安定収益源を軸に、新規サービスへ投資するモデル。
- 初期から黒字化しやすく、倒産リスクを下げつつ長期目線の成長を見込める。
- 一方で、市場変化の速い分野ではスピード競争で不利になる場合もあり、安定と挑戦の両立が課題。
ソリッドベンチャーの基本概念
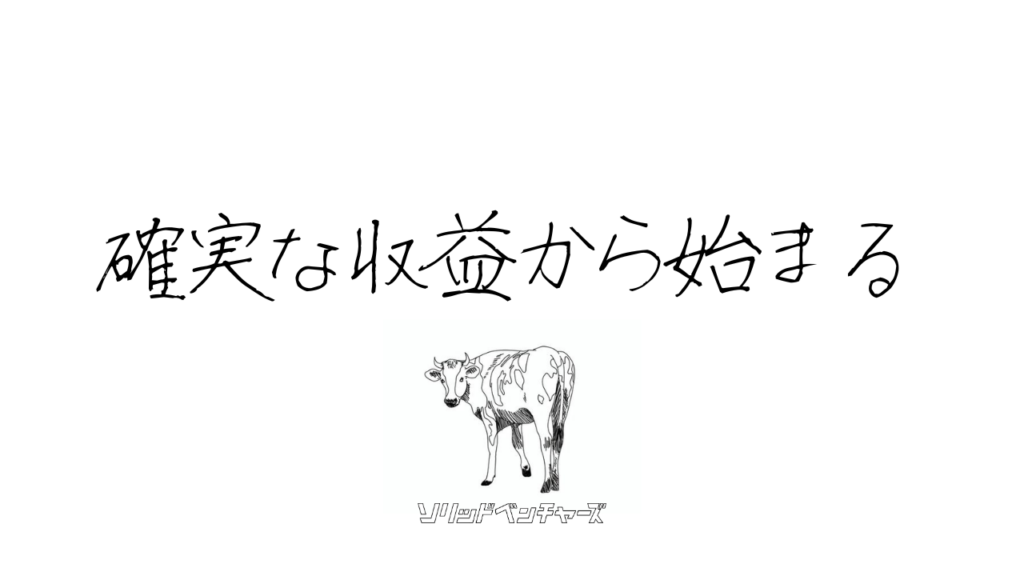
キャッシュ・カウ事業を軸に、長期的に事業拡大を狙う
ソリッドベンチャーの根幹を成すのが「キャッシュ・カウ事業」です。これは、安定収益を生むビジネスの総称であり、具体的には受託開発、コンサル、代理店、人材関連サービスなどがよく挙げられます。
こうした事業に共通するポイントは、“比較的早期に売上が立つ”ということ。
スタートアップのように新技術や新コンセプトをゼロから広めるには時間と資金を要しますが、BtoBの受託案件や既存の大きな市場に向けたコンサル業務であれば、契約を取れさえすればすぐに黒字が期待できます。これがソリッドベンチャーの安定性を生む秘密です。
新規事業が失敗しても倒産リスクを下げられる
キャッシュ・カウ事業の存在により、万一新たなサービスやプロダクトが失敗してしまっても、会社そのものが立ち行かなくなるリスクを大幅に低減できます。
“黒字を生む柱”が残っているため、そこから再度別のアプローチを試したり、開発を一時中断してやり直す余力が確保できます。
長期目線の経営
また、会社清算のリスクが低いため、スタートアップよりも長期的視点で成長を描きやすいのも特長です。
すぐに規模を大きくしてIPOを目指すのではなく、時機を見ながら新サービスをローンチしたり、徐々に人材を増やしたりと、無理のない拡張が可能になります。
資金調達も「どうしても必要なとき」だけエクイティを検討すればよいため、経営者の株式比率を薄めずに済む利点も大きいでしょう。
スタートアップとの明確な違い
急成長・ハイリスク/ハイリターンを受容するスタートアップに対し、ソリッドベンチャーは比較的“ローリスク~ミドルリターン”を狙うビジネスモデルと位置づけられます。
ただし、「リスクを取らない」わけではありません。新事業にはやはり不確定要素がありますが、その土台として安定キャッシュがあるかどうかが決定的な違いと言えます。
スタートアップとの違いを明確にする
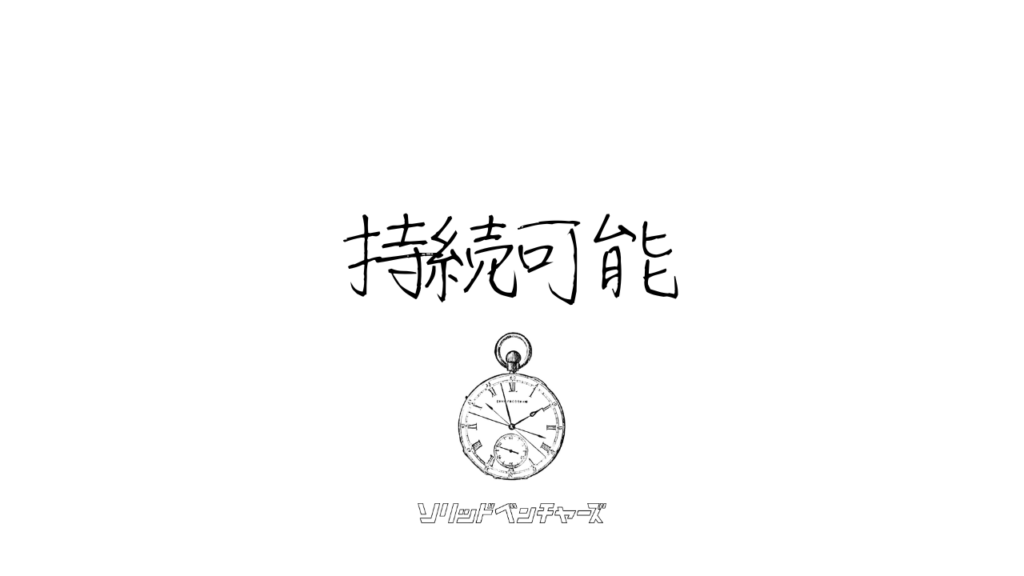
ソリッドベンチャーとスタートアップは、どちらも新しいビジネスを立ち上げる企業ですが、そのアプローチや目的には明確な違いがあります。
スタートアップは一般的に、革新的なアイデアや技術をもとに短期的に急成長を目指す企業であり、リスクを取ってチャレンジすることが特徴です。短期間での成長を重視しているため、リスクマネーとして投資を行うベンチャーキャピタルなどから資金調達を行いながらスケールアップを図ります。
一方、ソリッドベンチャーは、初期段階から収益を生み出すことを重視し、持続可能なビジネスモデルを構築することに焦点を当てています。
ソリッドベンチャーは市場のニーズに応じた製品やサービスを提供し、安定した収益を確保することで、長期的な成長を目指します。安定収益の事業をもっていることで、成長のプロセスで新規事業への挑戦や急拡大に踏み切ることもできます。ソリッドベンチャーは時間軸は長くなりますが、スタートアップに比べてリスクを抑えたアプローチを取ることができます。
このように、ソリッドベンチャーとスタートアップは、ビジネスの成長戦略やリスク管理の観点から異なるアプローチを持っていることがわかります。
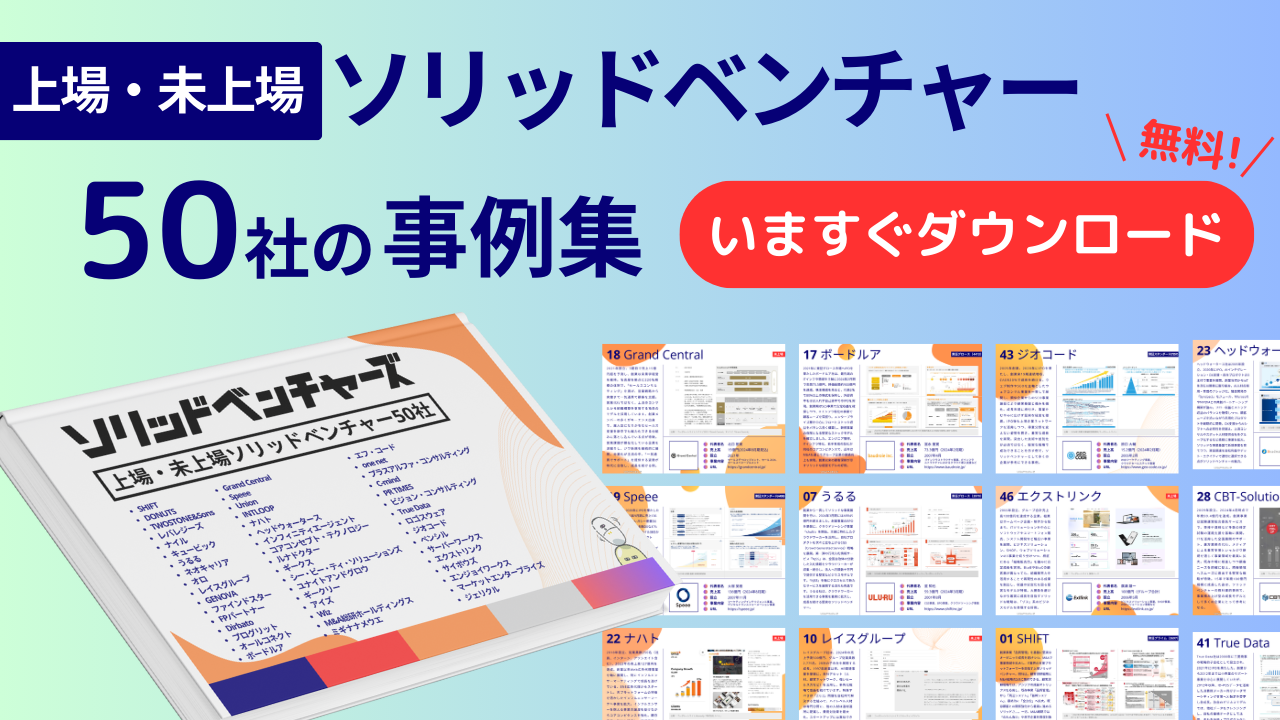
ソリッドベンチャーの具体的な事例紹介
ソリッドベンチャーは、初期段階から収益を上げることを目指す企業形態であり、実際に成功を収めている事例がいくつか存在します。ここでは、勝手にソリッドベンチャーにカテゴライズして事例をいくつか紹介します。
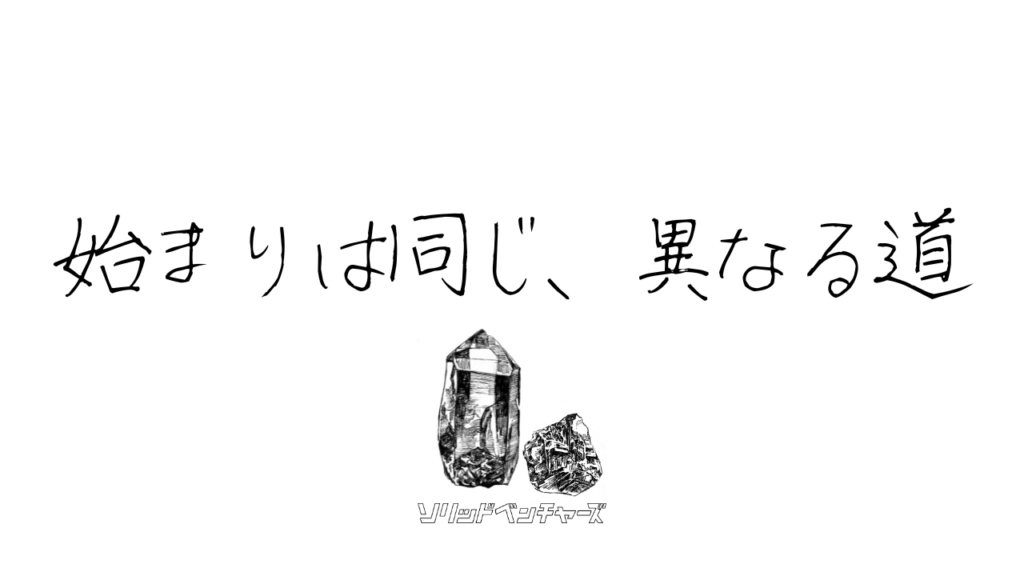
上場ソリッドベンチャーの事例:SHIFT社
創業事業である「品質管理」を軸にソリッド(堅実)にオーガニック成長をさせていきながら、M&Aで“できること”を増やし、将来的きIT業界の支援プラットフォーマーを目指す。既存事業が基盤を固めているからこそ、新しいチャレンジ(M&Aやプラットフォーム構想)ができている、めちゃくちゃ参考になる事例。そして後述してるけど、上場ソリッドベンチャー×未上場ソリッドベンチャーの可能性が垣間見える‥‥。決算資料を眺めていて、SHIFT社の①顧客深耕、②買収しない会社を決めるM&A戦略、は面白いので整理すると、
①顧客深耕:アンゾフの成長マトリックスになぞるような広げ方で着実に
- 顧客を参画レベルマップという四象限で整理
- アンゾフの成長マトリックスと同じような考え方
- まずは創業事業の「品質管理」から入る
- そこから「周辺システム」と「基幹システム」に広げる
- 最終的に「全方位」に変化する
- ポイントは広げていくということ
- いきなり「周辺システム」「基幹システム」「全方位」から入るのではなく、創業事業で強みになっている「品質管理」から入っていること
- アンゾフの成長マトリックスでも、既存事業×既存顧客から始まって、隣接する横または縦に広げて、最終的に全く新しい新規事業×新規顧客にズレていく
- 広げ方もソリッドでカッコいい‥‥
②M&A戦略:のれん負けする会社は「買収しない」と言い切るソリッドさ
- M&Aの戦略として「のれん償却後赤字となる企業は対象外」「高成長企業はハイバリューであり、投資回収リスクが高い」「連結利に即座に貢献しない案件は、原則、検討から排除」と明言
- SHIFT社がこれまで歩んできた、着実で堅実な成長のアナロジーをM&A戦略に組み込んでいる分かりやすさ
- 上場ソリッドベンチャーが未上場ソリッドベンチャーをM&Aしていく未来がここにある気がする‥‥
キャプチャ引用元
SHIFT社の「2024年8月期 第3四半期 決算説明会資料」とGrowth Capital『SHIFTは今後もM&Aを拡大へ「SHIFTに入ると従業員がハッピーになる」秘訣とは』より
上場ソリッドベンチャーの事例:TWOSTONE&Sons社
創業事業は受託開発で着実に売上を上げ、新規事業でエンジニアマッチングプラットフォームやメディアを展開。IPO後にはM&Aを戦略実装。SHIFT社同様に、ハイバリュースタートアップのM&Aは“しない”と明言。
上場ソリッドベンチャーによる未上場ソリッドベンチャーM&Aの可能性が広がる‥‥。人材ビジネスやメディアビジネスは、PERがつきにくいなどでVCから嫌われがちだけど、事業モデルに組み込んでそれぞれが成長トリガーでシナジーがあると強い事業になる。コアコンピとも言い換えられるかも。沿革スライドの「創業期」「拡大期」「飛躍期」のステップはいろんな示唆があって参考になる。
キャプチャ引用元
TWOSTONE&Sons社の「2024年8月期 第3四半期決算説明資料」と 「成長可能性に関する説明資料」より
上場ソリッドベンチャーの事例:ナイル社
創業からソリッド(堅実)な事業を展開しながら、既存事業のアセットやノウハウを活用して新規事業でJカーブを描いて急成長。そしてIPO。創業期はSEOコンサルのクライアントワークから始まり、Appliveというメディアや広告ソリューションでキャッシュ・カウ事業をつくり、それまでのアセットで「おトクにマイカー 定額カルモくん」にチャレンジ。流れが素敵すぎる。
キャプチャ引用元
ナイル社の「事業計画及び成長可能性に関する事項」と沿革より
上場ソリッドベンチャーの事例:うるる社
上場ソリッドベンチャーの事例。うるる社。2024年3月期のARRは45億超。SaaS・BPaaSがメインですが創業からの事業展開がソリッドで面白い。ベースにあるコアコンピをズラさずに“ジワ新規“で着実に広げている。
【NJSSの場合】
- 創業事業はBPO。労働集約型事業をヒントにクラウドソーシング事業へ
- 主婦に特化したクラウドソーシング「shufti」開始
- クラウドワーカーを自社プロダクト立ち上げに活用(CGS:Crowd generated Serviceと名付けられている)
- 第一弾は行政の入札情報サービス「NJSS」
- 全国約1,800ある自治体の入札情報を法人が調べるのはめちゃくちゃ大変(いつか開示されるのかもわからない/どこに開示されるか自治体によって違うなど)
- shuftiのクラウドワーカーが入札情報を調べ、その情報を統合したものが「NJSS」
- 法人には月額数十万で提供
- さらに、「NJSS」も多くの導入顧客の潜在ニーズに合う新しいサービスや事業を拡張・展開してクロスセル
「NJSS」だけでもソリッドな流れでキレイ‥‥。その他の事業も、創業事業のBPOやうるる社が抱えているクラウドワーカーを活用できる事業を着実に増やしていて堅い。
※ジワ新規:造語なのでXの検索で「from:TakumiOokoshi ジワ新規」してみてください
キャプチャ引用元
うるる社の「2024年3月期 決算説明資料」「2023年版価値創造ストーリー」「コーポレートサイト」より
上場ソリッドベンチャーの事例:オロ社
上場ソリッドベンチャーの事例。オロ社。
創業事業はウェブやシステムの受託。着実なクライアントワークで創業から売上を積み上げる。そこからが面白くて、社内用の業務管理ツールが他社でもニーズがあることが分かりERPとして提供、導入が急拡大して2017年にIPO。
創業からある制作受託(IR資料ではマーケティングソリューション事業に組み込まれてる)でソリッド(堅実)に売上のゲタを作りながら、自社課題を解決するプロダクトをつくって新規事業のような形で他社に提供。
ERP ZACの最初は、自社と類似しているような業務が見えにくい会社をターゲットにしていたのも面白い。
「受注金額を振り返るとこのプロジェクト赤字じゃない?」となりがちなウェブ制作やシステム受託、コンサルなどが初期ターゲット。
なぜなら自社がその課題を持っていたので高い解像度でプロダクトを作れるし提供ができる。そこからクラウドERPに滲みでていまに至る。
自社で使っていたツールを外出しして大きくなった事例。Slackも確かそうだったような‥‥。
キャプチャ引用元
オロ社の「2024年12月期 決算説明資料」を2022-2024中期経営計画」「成長可能性に関する説明資料」と沿革より。
上場ソリッドベンチャーの事例:GENOVA社
上場ソリッドベンチャーの事例。GENOVA社。
2022年にIPO。医療機関に特化したバーティカルメディアとDX支援で2024年度の年商86.8億、営利23.0億。
設立2005年。創業事業は医療を中心とした領域の手堅いウェブ制作から。平瀬代表の前職テレウェイブ社がまさにその領域のパイオニア的企業だったので、そのまま領域特化として開始。
祖業はガラケー→スマホでも時代に沿ったアップデートしながら右肩上がりで伸び続け、クライアント社数も比例して伸長。
クライアントネットワークをアセットに2016〜2017年のオウンドメディア全盛期に自社メディア参入。メディア関連の流れにのって大きくなったところは先日ポストしたナイル社も(ナイル社は支援サイドでしたが)。
同時に同じアセットを活用してスマート簡易自動精算機再来受付機などのDX支援もはじめ第二創業的にグロース。(後者は代表の平瀬さんの前職と同じ流れ)
創業のウェブ制作でソリッド(堅実)な事業で売上と顧客を獲得しながら、自社のアセット(セールス力と顧客ネットワーク)を時代のトレンドにのせ事業をズラした展開。一定数の顧客を抱えることができれば、新しい事業でも堅い事業が作れる事例で、領域選定の重要性がめちゃくちゃ分かる‥‥。
アンゾフのマトリックスの「既存顧客×新商品」の新製品開発戦略をやり切っている流れで素敵すぎる。
キャプチャ引用元
GENOVA社の「2025年3月期 第一四半期 決算説明資料」「事業計画及び成長可能性に関する事項の開示」と沿革より。
上場ソリッドベンチャーの事例:FPパートナー社
上場ソリッドベンチャーの事例。FPパートナー社。
2022年にIPO。ファイナンシャル・プランニングを軸に2023年11月期で年商305億円、営利55億円。 「マネードクター」ブランドで全国展開。
設立2009年。FP相談を切り口に安定ストックモデルの生保・損保の提案をしつつ、お金周りの周辺も提案ができる強さ。
一時期、爆発的に増えた“保険に関わる店舗“よりも幅が広い提案ができる。保険の店舗型は「保険の提案のみ」なので。
収益モデルも堅く、生保・損保は契約数が積み上がれば上がるほど安定収入に。さらに、「お金にまつわるいろんな相談」を受けることで生保・損保以外のビジネスチャンスを上乗せできる余白。事実、通信会社KDDIのauブランドと合弁も。
FPの資格者かつ個人で活動されている人は全国に一定数存在していて、それらの方々を組織にし、仕組みにしたのが「ならでは」の価値。
個人でもできる仕事を、組織で効率化して戦う事業。さらに収益構造が堅いストックモデルをベースにしているというのがソリッドすぎる‥‥!
顧客数が増えれば増えるほど、お金に関わるアレコレのクロス提案もできる可能性もあって面白すぎる‥‥。
キャプチャ引用元
FPパートナー社の「2024年11月期 第2四半期 決算説明資料」「2023年11月期 決算説明資料「2022年 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示」と沿革、日本FP協会「データで見るFP資格より。
上場ソリッドベンチャーの事例:プログリット社
2022年に創業6年で東証グロース市場にIPO。英語コーチングサービスを主軸に2024年8月期の年商は約42.5億円予測。
英語コーチングのプログリットから派生する形で、シャドーイングの「シャドテン」、ビジネス特化の発話トレーニングの「SUPIFUL」、AI会話サービスの「DiaTalk」をぞくぞく展開。英語コーチングの軸をずらさないジワ新規※をし続けているのがめちゃくちゃソリッド。
余談ですが、創業からのストーリーが面白くて、事業展開も資本政策も理想のソリッドベンチャー的だったり。創業前は家事代行サービスを発案したものの資金調達で誰も出資してくれる人がおらず、すぐに撤退。
創業メンバーの経験やケイパを無視した「儲かりそうだ」というだけでは全く意味ないと理解して、本当に自分たちが欲しかった/世の中のユーザー候補の人たちが欲しがるものをやろうと決意。
(TAMが大きいから〜で始めるスタートアップはあるけど、往々にして頓挫したり壁にぶつかったりしてるのはこの辺りを理解してないからだと思ってます。市場規模は大切だけどまずは顧客ですよね、当たり前に)
創業メンバーが持っていた課題/国内の英会話教室領域の問題点を照らし合わせ、3ヶ月の英語コーチングのアイディア発案。ビジネス的に小さきながらもすぐに売上が立ち上がる領域で、すでに個人の英会話教室で一定の市場形成されているところにITを掛け合わせたアイディアはソリッド思考で参考になる‥‥!
英会話コーチングは属人型事業になるので人×売上の構造。ここでプログリット社はエンジェル投資家さんなどのアドバイスから、事業の肝は「研修プログラムのマニュアル化」 と設定。
研修をマニュアル化することが出来れば研修に再現性が生まれて、属人型ビジネス自体が参入障壁になる仮説を検証し続けた。
toCサービスでボラリティもあるため投資家は入れずに全部自己資金でやろうと決めたとのことですが、ぶっちゃけ内心では、資金調達をすると投資家の方を向いてしまって、やりたいことができないと思ったのでは?と。先日配信したポッドキャストで同じようなことを話していた起業家がいたので。
結果的にエンジェル投資家を中心に10%ほど株式放出したもののエクイティ調達をほぼせずに上場。
事業の作り方や資本政策がソリッドベンチャーの教科書になりそう‥‥。
※ 「ジワ新規」というのはアンゾフマトリックスの右か下にジワッとずれて作る事業のこと。ジワ新規はすでにあるプロダクトや接点のある顧客にレバレッジをかけられるため、自社でつくる方が上手く立ち上がる。
上場ソリッドベンチャーの事例:ボードルア社
2021年に東証グロース市場にIPO。最先端のITインフラ領域を主軸に2024年2月期の年商は約73.3億円。時価総額、約900億円。
上場時の株主の状況をみると、ほぼ外部資本を入れておらず代表お二人で80%+の株を保有。 限りなく自己資本だけでのIPO。外部資本を入れないソリッドベンチャーの事例にしたい‥‥。
創業はSES事業で足元のキッシュを着実に稼ぎながら、新しい顧客ニーズを獲得する事業展開を進める。ITインフラが年々複雑化しているところを領域特化を武器に顧客層の約67%になるエンプラからフローとストックの売上をバランスよく積み上げている。
特に安定経営をするためのストックビジネスを着実に作れているのは強い。新しいチャレンジをする上でいろんな意味で保険になるので。
①創業からエンジニアを獲得していたこと、②ITインフラ特化を事業のコアにしたこと、③早期から若手育成の型化を進めていたことがいまのボードルア社のコアコンピになっている。
商売で当たり前の「顧客深耕」を創業から続けているのがめちゃくちゃソリッド。
直近では同業のM&Aも進めており、グループインした企業が軒並み業績向上しているのはボードルア社のコアコンピがM&Aでも活用できることの証明なのかも。
キャプチャ引用元
2025年2月期第1四半期 決算補足説明資料、2023年1月 事業計画および成長可能性に関する事項、有価証券報告書(新規公開時)より。
上場ソリッドベンチャーの事例:Speee社
2007年に創業。2020年IPO。2023年9月期の通期136億。いまはレガシー産業DX、DXコンサルを主軸に新規の金融DXも展開。
沿革を調べると、B2B事業とB2C事業を行ったりきたりしながら成長を続けているのがソリッドで面白い。既存事業→ジワ新規プロダクト→さらに別切り口でのジワ新規・・・・のサイクルは参考になる。
創業事業は手堅いBtoB領域のモバイルSEO。クライアントワークから着実に業績を積み上げながら、自社プロダクトのモバイル外部リンク検証ツール「MOLAS bird eye」を開発。そのあとも「SpeeePlatfom」というモバイルSEOに特化した情報統合システムをローンチ。PC SEO開始と同時に不動産メディアをローンチ。
スマホブームにのってBtoC領域のスマホゲームへ参入。その後、再びBtoB領域回帰の新規事業のアドテクを事業ポートフォリオに実装。現在のレガシー産業DXの柱になっているBtoC領域「イエウール」ローンチ。そこからは立て続けにオウンドメディア全盛期に自社メディアをローンチ。
いろいろと展開しながらも、創業事業で培ったメディア運営に必要なノウハウやナレッジを貯めながら活用すること、時流をとらえた新領域選定、顧客ニーズをもとにしたジワ新規、の3つの掛け合わせがうますぎる。
常に新しいことができるのは、事業を支えるしっかりした売上を作るセグメントがあることと、自社のコアコンピとアセットを正確に理解しているから?
Speee出身の起業家が多いのは、組織としての強さの証でもある気がする。
上場ソリッドベンチャーの事例:INTLOOP社
2022年にIPO。社員&フリーランスの混成チームでのコンサル支援。コンサルフリーランスに特化したプラットフォームも保有。2024年7月期の年商270億、営利15億。
設立2005年。創業事業は製造業向けの上流工程の戦略コンサル。いまのフリーランスのハイブリッドチームで価値提供する取り組みはクライアントニーズに沿う形で開始。時期的にクラウドソーシングが注目され始めたタイミング。
祖業のナレッジと既存顧客にレバレッジをかけられるコンサルに特化する形で展開してしたのがソリッド思考。
人材マッチングプラットフォームという新規事業にチャレンジできたのは、クライアントワークで着実に収益を立てられる事業をベースにしているから。
ソリッドベンチャーのいいところは「時代の波(トレンド)を気にしなくていい」ということかも。
トレンドを気にしながら事業展開するのではなく、結果的にトレンドがきたところですでにやっていた、ということができたりする。
INTLOOP社は、DX人材不足が世の中の課題として認識されたときには、その領域ですでに展開していた。
クライアントニーズをキャッチしているから、仮にトレンドに乗らなくても事業として失敗しにくいというのもいい。
創業の労働集約×ナレッジワークというソリッド(堅実)な事業で売上と顧客を獲得しながら、社員とフリーランスのハイブリッドコンサルという顧客ニーズに沿った新規事業の流れがキレイすぎる・・・・!
新しい事業でも顧客を理解していれば堅い事業が作れる事例。
キャプチャ引用元
INTLOOP社の「2024年7月期 通期決算説明資料」「INTLOOP “VISION2030“」より。
上場ソリッドベンチャーの事例:ヘッドウォータース社
設立2005年、2020年にIPO。創業期からAI関連の開発を行っており、AIインテグレーション・DX支援・自社プロダクトの3本柱。フロー売上とストック売上のバランスをそれぞれでとっている。
LLMが市場で盛り上がってきているところに、ぽっと出で参入したAI開発支援ではなく2005年の創業からIoTを含めたAIの開発を行っていたことで、
①AI人材の採用〜育成を社内ナレッジ化
②「SyncLect」という開発モジュールを独自に開発し続けている
③MicrosoftやNVIDIAとの共創パートナーアライアンスができる大人ムーブ、が強い。
事業体の特性としても、顧客に対して開発支援をするモデルなので派手ではないが堅実に事業を展開できるところがソリッド。
今後、DX支援をしてきたところがAIシフトをすることは必然で、その中で「SyncLect」という開発モジュールを開発し続けているのはめちゃくちゃ強くなりそう。R&D組織も戦略的に作ってはいるけど創業から続く開発ニーズを拾いながら汎用化できるプロダクトを作り続けているの、当たり前かもしれないが、クレバー。
また、開発を中心としてきたところから上流のコンサルニーズを拾うためにコンサルに特化した会社や、スポット的な人材ニーズを提供できる会社をグループとして新しく作っている。リニアに顧客ニーズを聞けているからこその動き‥‥。
ソリッドベンチャーは、しっかりと事業で稼ぎながら、コケにくい新しい事業を作り続けることができるのがいいし、
「アイディア先行で残キャッシュを気にしながら顧客ニーズを模索して事業を作らなければならない」というヒリヒリしたことになりにくいので‘’死ぬリスク‘’も低い。
資金調達もデットなのかエクイティなのか、そもそも自社利益だけでいくのか、など是々非々で判断できるのも特徴な気がする。
キャプチャ引用元
ヘッドウォータース社の「2024年12月期第2四半期 決算説明資料」「2023年12月期 通期決算説明資料」「事業計画及び成長可能性に関する事項」より。
上場ソリッドベンチャーの事例:コアコンセプト・テクノロジー社
2009年設立、2021年IPO。創業事業は製造業向けのITコンサルティング。SIerの多重下請け構造をビジネスの軸に1次請け・2次請けをエリアや業界によって変えながら価値提供をしている。
創業メンバーがインクス(現・SOLIZE)出身で、創業期は創業メンバーが経験していたITコンサルをベースにソリッドな事業を展開。SESやコンサルといった堅実な事業から始まり、商流の川上に登って1次請けに。
祖業に近い2次請けの場合は、SESとして人材調達支援と提携先のプロダクト提案による支援。1次請けの場合は、独自プロダクト「Orizuru」を活用したDX支援を行っている。
顧客のエンジニア人材不足のニーズを着実にキャッチしてジワ新規的な広がり方をして成長、いまに至る。新しく広げた1次請け向けの事業は、プロダクトに落とし込んでいるところがソリッドベンチャーっぽい。
コンサルから成長企業へ、そしてIPOをするというケースでソリッドベンチャーの参考になるビジネス展開。
堅実な事業を続けていくことで大きくなった事例。
キャプチャ引用元
コアコンセプト・テクノロジー社「2024年12月期 第2四半期 決算説明資料」「事業計画及び成長可能性に関する事項」、経営ノート『株式会社コアコンセプト・テクノロジー 代表取締役社長CEO 金子武史氏インタビュー』より。
上場ソリッドベンチャーの事例:ギークス社
2019年にIPO。国内はフリーランスエンジニアのマッチングプラットフォーム、海外はオーストラリアをメインとしたSESやMPS事業。2024年3月期の年商237億。
設立2007年。代表の曽根原氏は現・クルーズ創業者で、ギークスはクルーズ社の一事業として始まる。2009年にMBO。当初はフリーランスエンジニアのマッチング以外に動画事業、メディアなども広げていた。
IPO前(2014年)からしっかりとトップラインを作りながら、利益は戦略的に投資しているように見える。
稼げる事業を主軸にジワ新規・ド新規の事業をチャレンジできるのがソリッドベンチャーで、ギークス社もそんな流れ。
IT人材事業は新興の成長企業にフォーカスすることで差別化と効率化をしている。沿革を見ると、創業期のクライアント層がまさにいまのクライアントに紐づいているような気がする。
ほぼ外部資本を入れずにIPOしていたり、社内事業からMBOという流れもソリッドでいい。
AIやITが進めば進むほど労働集約型のビジネスがなくなるかも、と言われていたりするけど、実際はそんなことはなく、むしろ参入障壁になったりする。生産性向上のトレンドも相まって「持たざる経営」「変動費化」ニーズが増えていっているので面白い。
今後の展開はベイカレント社やSHIFT社のように上流から下流までを押さえるような中期計画をされていて楽しみ。
キャプチャ引用元
ギークス社の「2024年3月期 通期決算説明資料」「strainer: 国内フリーランス市場は20兆円!クルーズの共同創業者が設立した「ギークス」新規上場」より。
上場ソリッドベンチャーの事例:ユナイトアンドグロウ社
2019年にIPO。創業から着実に売上を立て続けるソリッドな事業を展開。主には中堅・中小企業に特化したITリテラシーの高い人材のシェアリング事業で、SESに頼むほどではないが社内では重要な情シス周り特化の支援。
派生する形でコーポレートIT(情シス)の内製化支援やITコンサルもジワ新規的に展開。
中堅・中小企業においてこれらのニーズは高いものの予算観点で収益化が難しいため組織単位での競合は少ない。ニーズはあるがマネタイズが難しいというのを「会員制でシェアする」という仕組みでビジネスモデルにしているのがめちゃくちゃ面白い。
そこから顧客ニーズに沿った内製化やコンサルに広げていて、フロントをライトに後からしっかり稼ぐというので理にかなっている。
社内の情シス部門に直結するので今後は情報システムに関わる事業拡大もできそう。
SESでもなければITインフラ構築するところでもないニッチだけどニーズがあるところを事業にしているのがソリッドで素敵。
強いニーズはあるがマネタイズが難しいという領域はたくさんあるはずで、その時にユナイトアントグロウ社の「会員型シェアビジネス」は参考になるかも‥‥!
キャプチャ引用元
ユナイトアントグロウ社の「2019年度(第15期)の業績報告」「2023年12月期 決算説明資料」「2024年12月期第2四半期 決算説明資料」より。
上場ソリッドベンチャーの事例:アイズ社
メディア事業というローコストでソリッド(堅実)な事業を展開しながら、既存事業のシナジーを出せるジワ新規領域のメディアレーダーをM&AしIPO。いまではそれぞれの事業がバランスよく売上比率に。
創業期は口コミマーケプラットフォームから始まり、既存顧客からメディアレーダーを事業譲渡。それぞれがメディアや広告ソリューションを提供できるため初期から顧客開拓ができれば垂直にキャッシュ・カウ事業にすることができる。
福島代表のキャリアをみてもアイズ社の立ち上げに紐づくところも多く、Founder Market Fitの教科書的な立ち上がりな気がする。
キャプチャ引用元
アイズ社の「2024年12月期 第2四半期 決算説明資料」より。
上場ソリッドベンチャーの事例:M&A総研ホールディングス社
2024年9月期で売上高約165億、2024年11月3日時点で時価総額約1,300憶円超の上場ユニコーン。
M&A仲介が創業からの柱で売り手企業は着手金など無料の完全成功報酬制。M&A仲介の上場企業が数社あるが、その中でも後発として「完全成功報酬制」で切り込んだランチェスター戦略的。
労働集約型ビジネスの典型で、人数×1名当たりの売上が収益構造になるモデル。そのためM&A業界としては新興企業(創業2018年)ということもあり、組織全体でデジタル化・AIを積極的に取り込むことでビジネスフローの効率化でき、生産性を上げているとのこと。
DX・AI化をすんなり進められたことは後発だからできること。先発は”人材の数で殴る”戦い方をしているため、一気にデジタルで効率化をしようとしても、これまで当たり前だった”日常の圧力”の負けてうまく進まなくなったりする。
そして、M&A仲介を主軸にしながら資産運用支援や企業のDX支援コンサルなど顧客(買い手&売り手)のクロスセルができる新規事業を立て続けに作っているのがジワ新規でソリッド‥‥!
キャプチャ引用元
M&A総研ホールディングス社の「2024年9月期 通期 決算説明資料」より。
上場ソリッドベンチャーの事例:エフ・コード社
2006年創業、2021年IPO。創業以来、キレイな右肩上がりの業績。
祖業はウェブコンサルでいまでもDX支援としてコアコンピに。IPO後は2年で10社超という積極的なM&Aで顧客提供価値を広げ続けている。
個人的に上場からの決算説明資料を読んで興味深かったのは、①IPO承認直後の「事業計画及び成長可能性に関する事項」ではM&Aについて触れられていない点、②成長企業や顧客基盤を持つ企業とは業務提携をすることで顧客開拓や価値提供の幅を広げている点。
IPO後でも「得意を伸ばしながら他にできることを模索し続ける」でアップデートしているのがかっこいい‥‥。
事業展開はソリッドベンチャーの教科書っぽくて、ジワ新規とド新規で整理されていそうなところがめちゃくちゃ参考になる。
顧客を主語にしてビジネスプロセスを分解し、自社ができることを新規事業などで増やしてジワ新規、自社だけでできないことはド新規としてM&Aや業務提携。
このやり方は考え方次第でどこでもできることもあったりするので、上場有無関係なく検討してもいいはず。
キャプチャ引用元
エフ・コード社の「2024年12月期 第2四半期 決算説明資料」「2022年12月期 通期決算説明資料」「2021年12月 事業計画及び成長可能性に関する事項」より。
上場ソリッドベンチャーの事例:プラスアルファ・コンサルティング社
2006年創業、2021年IPO。創業以来、キレイな右肩上がりの業績。HR SaaSの「タレントパレット」の会社。
創業事業はデータマイニングのシステム開発&コンサルティング。
そこから自社プロダクトのテキストマイニング「見える化エンジン」、顧客の声を見える化ツール「カスタマーリング」、タレントマネジメントツール「タレントパレット」と広げてきている。
それぞれのプロダクトの顧客層はバラバラだけど“データを整理して使いやすくする“というコアコンピを軸にジワ新規で着実に積み上げていて、めちゃくちゃソリッド‥‥!
注力事業の「タレントパレット」からの周辺領域を模索しつつも、新規事業創出のアプローチのスライドが面白く、データ活用度が低い(感と経験)×データ量が増えているという象限にフォーカスしていると。
自社で作りながら、M&Aを組み合わせているのは上場ソリッドベンチャーならでは。
改めて、”データを整理して使いやすくする”という思想を創業からブレずにやり抜いていて素敵。
キャプチャ引用元
プラスアルファ・コンサルティング社の「2024年9月期 第4四半期 決算説明資料」、「2021年9月期 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示」、コーポレートサイトより。
上場ソリッドベンチャーの事例:PR TIMES社
2007年創業、2016年IPO。創業来、右肩上がり。直近は売上・利益ともに非線形の成長。主軸はみんな使ってるプレスリリース「PR TIMES」の会社。
創業事業はいまでも主力のプレスリリースメディア「PRTIMES」。
月額や従量課金でマネタイズしながら、主力のPRTIMES事業を補強するようにプロダクト(Jooto,Tayori)やメディア(THE BRIDGE,isuta,U-NOTEなど)、コンサルを装備的に設置しているのがめちゃくちゃソリッド。
M&Aは自社で持っていないものを機動的に実施。「祖業を補強する」から絶対にブレない。
ネットが普及しても、自社情報を配信してもらいたい会社と自社メディアを持っている会社がFAXやDMでやり取りしていた完全にクローズだったプレスリリースという市場。アナログであるが故にPR担当者は掲載されるか/否かしか見ることができず「数値として現れにくい」ので疲弊する構造。
そんなクローズでアナログな情報のやり取りをアップデートしたのがプレスリリースを掲載するメディア「PRTIMES」。情報をオープンに、リニアに配信することでプレスリリースがコンテンツになるという新しい領域をつくった。
時代の流れにマッチしていたはずで、創業は2007年で、2010年以降のSNS全盛期で追い風になったはず。
そしてプレスリリースをネット完結させることでPR担当者が追うべき数値が可視化されたのも強かった。
「これまでの習慣を変えるには?」「ネットやITを使えばいいのでは?」を真正面から突破した事例。
ポイントは、そもそも市場が存在していたこと、PR担当者が業務としてやっていたこと、この2つを少しアップデートしたことだと思う。
事業は、大掛かりなDX!とかではなくマイナーアップデートでいい。
キャプチャ引用元
PRTIMES社の「2023年度 通期決算説明資料」、「2016年度 成長可能性に関する事項」、「2024年2月期 有価証券報告書」、コーポレートサイトより。
上場ソリッドベンチャーの事例:True Data社
2000年に三菱商事株式会社の戦略的子会社で設立。2021年にIPO。ビジネスモデルがめちゃくちゃ面白い。
2012年を節目に前後でビジネスモデルを変えている。創業から2012年までは小売業のサポート事業をメインに。縮小均衡だったところから2012年以後は「ID-POSデータを活用した消費財メーカー向けデータマーケティング支援」に軸足を変更からの急拡大。
ビジネスモデルが面白くて、ID-POSデータのクレンジングを入口に自社のデータとして蓄積。蓄積したデータを独自分析・マーケ活用につなげていること。いってしまえば他社のデータをまとめて、きれいにして、見やすくして、それを別のプロダクトにして販売している‥‥。めっちゃソリッド‥‥。
中期戦略では「データ」を拡張して、別の大きい予算が流れる領域(広告・ビジネスアナリティクス)に行こうとしている。
散っているものをまとめるだけでも価値があるのは、データだけでなく情報などいろんな可能性はあるはず。
キャプチャ引用元
True Data社の「2024年3月期 決算説明資料 (事業計画及び成長可能性に関する事項)」、「有価証券届出書(新規公開時)」、コーポレートサイトより。
上場ソリッドベンチャーの事例:ジオコード社
2005年創業、2020年IPO。創業来19期連続増収、CAGR20%で右肩上がり。主軸はいい意味で何ら変哲もないウェブコンサル。
ウェブ制作・SEOで創業し、IPO時も変わらず同じドメイン。類似企業からSEO事業を譲受しながら自社の顧客と強みを強化。
成長市場に根付くこと、その領域でむやみに広げずに堅実に経営をすることを徹底して今に至る。
IPO後は、上場企業ネットワークを駆使して様々な企業と提携・連携を行いながら、足元はソリッドに「自社の得意分野は変えない」を地でいっている。
めちゃくちゃ素晴らしい技術がなければいけない、大きな差別化をもたないといけない、というのは、本質的ではないと言い切れるような事例‥‥。
キャプチャ引用元
ジオコード社の「2024年2月期 決算補足説明資料」、コーポレートサイトより。
上場ソリッドベンチャーの事例:サーバーワークス社
創業2000年、IPOは2019年。AWS特化したクラウドインテグレーションと保守運用。2024年2月期の約275億円。
創業時はリセールとしてECパッケージ販売から。創業者の大石代表が元丸紅ということもあり、商社的な立ち上がり。
その後、2009年からAWSに完全特化したサービスを展開。スポット収益のクラウドインテグレーションから入り、運用保守で着実なストック収益を上げ続けている。現在は全体の10%がスポット、90%がストックというめちゃくちゃ堅い事業をされている‥‥。
ストックビジネスを着実に作れているのは強い。新しいチャレンジに日和らなくなるので。
①AWS初期から参入していたこと、②エンジニアを着実に自社内に囲い込んでいたこと、③ビジネス特性上ストックが積みあがりやすいこと、がいまのサーバーワークス社の強さになっているし、ソリッド。
直近ではGoogle Cloud事業へも積極参入をし、これまでのAWS事業のナレッジや顧客アセットを活用してさらに安定収益を増やしていくのかも
キャプチャ引用元
2024年2月期 決算説明資料、有価証券報告書(新規公開時)より。
上場ソリッドベンチャーの事例:サイボウズ社
1997年創業、2000年IPO。創業来、波はあるものの売上は拡大路線、営業利益は2015年だけ赤字になったものの他の年は黒字(!)。スタートアップ界隈だと「kintone」が有名だけど創業から展開しているのは「サイボウズOffice」。
「中小企業でも使いやすいグループウェアを世に広めたい、という想いから独立。価格帯も含め中小規模の組織が導入しにくい状況だったため、サイボウズは「簡単」「低価格」「即導入」をコンセプトに、小規模事業者が気軽に使えるグループウェア製品を提供することから始まった。
創業メンバーの自己資金を元手にスタートいて、これは経営陣が、資金調達に時間や労力を掛けるよりも、迅速なプロダクト開発と販売開始によってキャッシュフローを回す戦略にしたとのことで、めちゃくちゃソリッド思考でかっこいい‥‥。で、創業から約3年後の2000年にマザーズ市場にIPO。
示唆があるものとして、
①オフィス環境や設備投資を最小限にして開発環境も比較的簡素なものでスタート。小規模&ローコスト経営の徹底していたこと
②市場トレンドに乗せたことで初期顧客から得た売上を即座に開発やサービス強化へ再投資でき、事業の成長サイクルを回せる体制を確立できたこと
の2点。
堅実な費用コントロールと、短期的な開発~販売サイクルによる迅速な収益化を可能にしたことが短期的に上場ソリッドベンチャーになれたのかもしれない。
キャプチャ引用元
サイボウズ社の「2023年12月期 決算・事業説明会」、青野慶久著「チームのことだけ、考えた。」、採用サイト、コーポレートサイトより。
上場ソリッドベンチャーの事例:マーケットエンタープライズ社
2006年設立、2015年IPO。創業以来、黒字経営を続け、堅実(ソリッド)に事業拡大。現在は数百名規模の体制を持ち、全国に拠点を展開しながら、オンライン特化のリユースビジネスを推進。
同社が提供するのは「リユースコンシェルジュ」とも言える一気通貫サービス。単なる中古品の売買に留まらず、顧客の商品査定、買取、再流通、さらには独自メディアによる情報発信まで、リユース領域の上流から下流までを包括的にサポートするエコシステムを構築。
中古品は消費財だけでなく農機具まで広く扱っており、リユースコンシェルジュ的に商流を一気通貫するという事業コアコンピの根底にあるからできるのかも。
比較対象となり得る上場企業としては、例えばアイドマ・ホールディングス社が営業支援分野で上流から入る手法を取るように、マーケットエンタープライズはリユース領域で上流(顧客の売却ニーズ顕在化・情報提供)から参画し、顧客接点を深堀りしている点が特徴的。
以前ポストしたIT特化型コンサルのDirbate社が、IT分野で上流〜下流の一気通貫サポートを提供しているように、マーケットエンタープライズ社はリユースマーケットでそれを体現している。顧客ニーズへの密着度、在庫・査定プロセスの構造化、オンラインへの強みなど、ビジネスモデル面での類似性。
創業期、使い捨てカメラ内部の電池再販というめちゃくちゃソリッドな事業からスタートした同社は、属人的になりがちな「中古品売買」という領域で、誰でも一定品質のサービスを提供できるシステム化を確立。これにより、新卒メンバーであっても再利用マーケットの戦力となりうる環境を生み出しているのがすごい‥‥。
改めて、膨大な市場規模と潜在ニーズを抱えるリユース領域は「いまさら入る?」と思われがちなレガシー市場に見えながらも、すでに上場済みのマーケットエンタープライズ社の事例から読み取れるように、
①巨大な市場規模にあえて後発参入する
②上流工程(商品売却ニーズの顕在化・情報発信)を抑えて顧客関係を構築
③採用やシステム構築での徹底した地固め
といった戦略で、後発組であっても着実な成長と利益確保を実現できる事例。
キャプチャ引用元
参考:マーケットエンタープライズ社コーポレートサイト、IR資料、採用ページより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:DONUTS社
公開ベースで売上高200億+の未上場ソリッドベンチャーDONUTS社の事例。創業はソリッド(堅実)なSI事業。創業3期目の新規事業「ハウコレ」のリリースを皮切りに、立て続けにクラウドサービス「ジョブカン勤怠管理」、ゲーム「暴走列伝 単車の虎」、動画・ライブ配信「ミクチャ」、医療「CLIUS」をリリースしながら着実にトップラインを伸ばして、未上場でありながら200億+の売上高に。
キャッシュ・カウになる事業を新規で作り続けながら、既存リソースやシナジーを使って異なる領域のプロダクトを生み出して(そして伸ばし続けて)いるのがすごい。意思決定の関係者が少ないことも着実な成長は、圧倒的なスピードと柔軟性の高い判断・高い自己資本比率が要因になっている。
まさにソリッドベンチャーの雄。
キャプチャ引用元
DONUTS社の「DONUTS Co. Ltd._About us」とDONUTS RECRUITより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:レバレジーズ社
未上場ソリッドベンチャーの事例。レバレジーズ社。2023年に売上約1,150億円。未上場‥‥!創業事業はSES。そこからIT、医療・介護、若手キャリアに展開。
新規事業ではHR Saas、業務DX、オンライン診療、M&A、海外就労支援。設立から18年で売上1,000億超に。“ジワ新規“で着実に業態を広げている。インタビューで中長期で1兆円を目指すとも。創業事業から全く新しい事業にチャレンジするのではなく、既存事業にジワっと隣接している事業にソリッドに進めているのはめちゃくちゃ教科書的で学び深い。
キャプチャ引用元
レバレジーズ社のコーポレートサイト より
未上場ソリッドベンチャーの事例:キュービック社
未上場ソリッドベンチャーの事例。キュービック社。2023年に売上約134億円。創業から自社運営の総合メディアやバーティカルメディアを事業基盤に。派生する形でメディア集客支援の顧客支援のコンサル事業を展開。
新規事業は、新規事業開発を目的とした子会社をつくり、億単位の事業開発予算をつけていることと、M&Aによる事業拡張をしている。M&Aは2025年までに15億の予算で投資される予定とのこと。
創業から一貫した自社メディア運営で会社基盤を固めながら、そのナレッジや考え方を新しい自社メディアや事業や顧客支援に渡しながら広げているのがソリッド的でかっこいい。改めて領域選定は大切だと思った。自社の強みは?で領域を決めるべき‥‥。
キャプチャ引用元
キュービック社のコーポレートサイト、新卒採用ページより
未上場ソリッドベンチャーの事例:ネオキャリア社
未上場ソリッドベンチャーの事例。ネオキャリア社。2024年2月期の売上508億円。グループ会社は19社(!)創業から一貫して人材事業を主軸に周辺領域を展開。周辺領域は幅広く、BPO・営業代行・研修・システム受託など。一見、バラバラに見える周辺領域も、既存顧客を主語にして考えるとめちゃくちゃ合理的。
記憶が確かであれば、最初は自社媒体などではなく採用媒体の代理店(マイナビ?)から始まっているはず‥‥。
そこから強い営業組織をレバーに各事業を広げていっていまのネオキャリア社に。
西澤代表の各メディアのインタビューから注力領域はヘルスケア(介護&保育)。ここの領域だけでも3桁億の売上になっているとこのと。新領域へのチャレンジは基本的にナンバー1の取れるマーケットにフォーカスをして運営する方針。
強い既存事業を作った上で、シナジーのあるジワ新規とド新規を掛け合わせているのが新規事業の教科書的‥‥!
キャプチャ引用元
ネオキャリア社のコーポレートサイト、新卒ページ、logmiBiz『「企業の歴史の長さと価値は比例しない」10年で社員を20倍にしたネオキャリアに学ぶ、ベンチャー企業の採用戦略』より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:レイスグループ社
未上場ソリッドベンチャーの事例。レイスグループ社。2024年着地予想で売上500億円。グループ従業員数は2,775名。28社の子会社を展開。
さらに、創業1997年から2008年のリーマンショックまで12年間増収増益を続けていたとのこと。
HR関連を祖業に、自社アセット(人材や顧客など)を活用しながら着実に、広げて成長し続けている。
事業多角化は戦略的で、ハイレベル人材と‘’それ以外人材‘’を適材適所で配属させ、グループ全体で「2:6:2」問題を自社内完結。これだけでもすごい‥‥(商材単価と人件費などの費用を賄えるスキームにしていること)。
「ワンプロダクトフルスイング」のスタートアップにはできないムーブである、優秀人材は〇〇、そうでない人材は〇〇に配属へ、という事業ポートフォリオを作りながら業績を伸ばし続ける強さたるや‥‥。
自社が持っているアセット(顧客ネットワーク、人材、強いセールス、デリバリーの仕組みなど)を活かすことができれば、年商500億、28社の戸外を展開するグループ企業が創れるという事実を証明している事例。
素直にすごい‥‥🫨
キャプチャ引用元
レイスグループ社のコーポレートサイト、レイスリクルーティングサイトより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ファインドスター社
未上場ソリッドベンチャーの事例。ファインドスターグループ社。
グループ会社15社。グループ全体売上高376億円で従業員数は800名を超える(グループ連結2022年6月時点)。
1996年設立、創業時はウェブ受託開発・運営からはじまる。そして、顧客ニーズからニッチメディアの広告代理店事業を開始し、現在はECおよびBtoB企業をメインのクライアントにするダイレクトマーケティング支援に。ダイレクトマーケティング支援を主軸に隣接業界に広げて、2008年からグループ経営に。
顧客ニーズに沿ったマーケ支援事業をソリッドにジワ新規で広がっていった形。主語が顧客ニーズなので、新しい事業自体もコケることが少ない構造になっている。
前回ポストしたレイス社の展開と似ていて、顧客ネットワーク、人材、強いセールス、デリバリーの仕組みなどが社内ナレッジとして蓄積されていてグループ会社の1/3が営業利益1億を超えているとのこと‥‥!
共通アセットを使って再現性担保できてるのすごい‥‥。
キャプチャ引用元
ファインドスターグループ社のコーポレートサイト、ファインドスターグループ採用ページ、ちば起業家応援事業(イノベーティブハイブ)サイトより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:Dirbato社
2018年設立、6期目で売上高282億円(2024年3月時点)。グループ会社4社。創業からIT領域に特化したコンサルティング事業。グループ会社は本業の領域シナジーがある、IT特化のVC・SES・ITフリーランス紹介・エンジニア育成をそれぞれ展開。
コンサルという事業特性上、顧客が抱えているニーズや課題を知ることがしやすいので新規事業の立ち上がりがスムーズ(顧客ニーズありきで始められるため)。
ソリッドな考え方で、自社アセット(顧客や社内人材)を活用したジワ新規※でスベらないかたちで広げている。
類似になる国内コンサル大手のベイカレント・コンサルティング社のIR資料のKPIからもわかる通り、コンサルティング業界においては、人×売上の構造の積み上げが基本。
コンサルは完全な業務の型化は難しいので突き詰めるところ、
①人を増やし続ける
②いい顧客を獲得し続ける
③その他の収益源を作る、ことで拡大している。
人を増やすといっても利益率を高めるためには業務委託ではなく、正社員をいかに増やすかがポイントなのでどこもかしこも採用は積極的だし、もっというと新卒戦略に走っていたりする。
それにしても、コンサルというクライアントワークでしっかりした商いをしていれば当たり前の広げ方だけど、コンサル以外の案件をしっかりと取りこぼさないようにするためのグループ会社の布陣は合理的‥‥。
類似ソリッドベンチャーに、リブ・コンサルティング社やビジョン・コンサルティング社などもあるのでおいおい調べたい。
キャプチャ引用元
Dirbato社のコーポレートサイト、Forbes『コンサル業界におけるIT人材価値「再興」Dirbatoの最前線パートナーが切り開くテクノロジーの変革』、マイナビ2025「(株)Dirbato」ページ、ベイカレント・コンサルティング社「FY2024 決算補足説明・中期経営計画」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:オールコネクト社
2005年設立。グループ連結売上高434億円(2024年2月)。観測範囲でグループ企業20社。
創業はインターネット回線の訪問販売からスタート。そこからネット経由での回線販売へシフト。ビジネスモデルはシンプルで、営業用のWebサイトを立ち上げ、Web広告で集客し、顧客の対応までをワンストップで行い、成約や成果に応じた手数料を請求するというものアドアフィ領域が対応できない“ラストワンマイル”を組織力でカバーをしている。
固定通信サービスを自社ブランドで取り扱いから販売から運営まで一気通貫で提供するMVMO事業と、通信事業者やウォーターサーバーなどの販売代理店として、Web広告の展開・サイト運営・コンタクトセンター運営。集客〜販売までをワンストップで提供する事業の2つがメイン。
集客と販売をネットを通じて提供というのは顧客に対する表向きであり、実際は顧客対応をする500名を超える人的リソース投下型のアウトバウンドコールセンターで勝負。量で戦うスタイル。
いまでは割とオーソドックスなビジネスモデルになりつつあるが、2005年前後だとまだまだ黎明期で「ネット集客のキモ」「アウトバウンド組織の作り方」がこれから参入するところからしたらハードルになっている。
顧客ニーズをキャッチした上で「人材の量」を一気に投下することをし続けられるのは未上場ならではの動きでさすが‥‥。
労働集約型モデルは人材採用をし続けられるのか?がポイントになるが、オールコネクト社はグループ企業を常に作り続けることで人材の確保を。また、既存事業で培ったノウハウやアセットを活用した新規事業の展開も積極的で常に新しいノウハウを貯めるような仕組みになっている。
初年度こそ赤字だったものの、事業体のならではのソリッドな積み上げができるので成長し続けている。
インサイドセールスで効率化!が主流ですが、オールコネクト社はtoC向けのインサイドセールス兼フィールドセールスの役割りをになっていたりする。
結果論かもですが、2005年からこの取り組みを始めている岩井代表の先見の明がすごい。
キャプチャ引用元
オールコネクト社のコーポレートサイト、オールコネクト社のWantedly、福井の転職サイトで福をつかむなら『福てん』 : 社員平均20代! Web活用を突き詰め世界最高の直販ソリューションを提供する先進企業、社員平均20代! Web活用を突き詰め世界最高の直販ソリューションを提供する先進企業、DevelopersIO:【レポート】オールコネクトDX挑戦とAmazon Connect 導入〜国産レガシーCTIからピュアなクラウド型CTIへ〜より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:Grand Central社
2021年設立。3期目進捗中で15億円+予測。創業以来、黒字経営でソリッドに事業展開。名古屋がヘッドオフィスで業務委託を入れて220名規模。
「セールスコンサルティング」というコンセプトで営業戦略〜実働までを一気通貫で顧客支援。類似の上場企業だとアイドマ・ホールディングス。営業代行ではなく上流のコンサルから入って組織構築の支援をするというもの。
先日ポストしたDirbate社はIT特化の上流〜下流コンサルで、Grand Central社はセールスに特化した上流〜下流までのコンサル。売上の積み上がり方、顧客アプローチ方法、人員数、採用、それぞれにおいて似ている点が多い。
創業メンバーの多くがキーエンス出身。属人型になりがちなセールス支援を、新卒でも戦力化できるような仕組みができている。
セールスに関して一気痛感でサポートできるということは「営業の課題が顕在化しているところから入る」ことができれば勝ちゲーになりやすい。営業に課題を持っていないところの方が少ないのでなおさらで。
“できること“を徹底的に深掘ることでソリッドなジワ新規をし続けることができるのがソリッドベンチャーっぽくていい。
THE MODELでセールスの分業化が当たり前になったものの、ちゃんと運用することの難しさが課題になっているところで「一気通貫で全部やります!」は時代の流れ的にもハマっている気がする‥‥!
改めて、巨大な市場規模の労働集約型ビジネスって「今更参入する?」感はあるものの、上場した企業や伸びてるソリッドベンチャーをみていると
①市場規模が膨大なところに後発参入
②上流工程を抑えるクライアント獲得
③採用ベタ踏み
だったりするんだよなあ。
キャプチャ引用元
Grand Central社のコーポレートサイト、リクナビ2025「Grand Central」、マイナビ「Grand Central」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:Union社
2012年設立。従業員数30名、売上高49億円(2023年10月期)、2024年10月期見込で65億円。
創業はSEM関連広告を中心としたデジタルマーケティングの企画・運用・制作を行う広告代理店からスタート。オウンドメディア運用、アフィリエイト広告運用、SNS広告運用と地続きの「ジワ新規」でソリッドな事業展開をし続けている。
「でも、差別化が難しいデジマ広告代理店でしょ?」と言われがちですが、それは商売を理解してないだけなのでスルーでよくて。
GAFAMがそれぞれ提供しているサービスやプロダクトのデジタル広告を日常的に見ているし、時価総額15兆円のリクルートもバンバンデジマに予算投下している。対極にあるような年商数千万円の会社だってデジマ広告予算を確保していたり。
すでに市場として認知されていてお金が動いているところは確実に儲ける方法が存在するので、ソリッド的な事業を探したいなら参考にしても。
ソリッドベンチャーは、世の中の会社が既に支払っている市場から参入して、独自の色やプロダクトを作って成長を目指すもの。見た目は地味だけど「会社を潰すリスク」を低くできる。
デジマ広告代理店は運用支援になるため人材採用、生産性がポイントになる。既存事業が軌道に乗ると「安定した稼ぎ」があるため積極的に新しい事業や取り組みに投資できるのが強い。
キャプチャ引用元
Union社のコーポレートサイト、AUBA「株式会社Unionの共創プロフィール 」、ベストベンチャー100「Union」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ナハト社
2018年設立。250名(社員、インターン、アソシエイト含む)、売上高127億円(2022年)。
創業から一貫してWeb広告代理店で展開。特にインフルエンサーを軸にしたサービスで拡大。
SNS広告代理から始め、その後各プラットフォームごとの特徴を活かしたインフルエンサーマーケに滲み出る。インフルエンサーを抱える事業の譲渡を受けながら自社のコアコンピを鍛えながら今に至る。
今後は新規事業やM&Aも積極的に行い、グループ会社を乱立させる戦略を検討中。
実際、既存事業の利益からジワ新規・ド新規のチャレンジをし続けている。
いまこの瞬間、伸びている市場に参入することがまず最初の一歩という事例。「他社や多くの企業が参入しているから敬遠する」は時と場合によっては悪手で、誰でも参入できて、誰でも一定稼ぐことができる市場は顧客からのニーズが高いため目の前のマネタイズが楽で速度も速い。
トレンドに乗って、「誰でもできること」をすることはソリッドベンチャーの初期事業をにはいい選択かも‥‥!(確かに広告やSESを軸に大きくなっているところは“当時のトレンド“だったりしたし)
キャプチャ引用元
ナハト社のコーポレートサイト、Wantedly「株式会社ナハト」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:インフィニティエージェント社
2015年設立。72名(2024年8月時点)、売上高33.2億円(2024年3月期)。本格的な事業開始は2017年。そこから3つの軸で事業を展開。①デジタルマーケ、②フィンテック、③リフォームテック。
経営陣や創業メンバーの過去キャリアに紐作く①デジタルマーケ事業から始まり、業界特性を理解した上で不動産DXの②フィンテック、③リフォームテックに拡大。
売上は①デジタルマーケが多くを占めていて、そこから培ったナレッジやインサイトをもとに②③に事業投資をしているのはジワ新規的な広がりでめちゃくちゃソリッド。
事業は「その領域で稼げますか?」がどこかでないと詰んでしまうもので、逆にその領域が群雄割拠でいろんなプレイヤーがごった煮になっているところは「稼げるから多数のプレイヤーがいる」となる。
なので、すでにニーズが顕在化している領域から最初の一歩をすすめ顧客深耕をしていく中で新しいニーズをキャッチしてジワ新規的に広げる流れが“転ばない“事業の作り方だと思う。インフィニティエージェント社はまさにそれを地で行っている気がする。
キャプチャ引用元
インフィニティエージェント社のコーポレートサイト、マイナビ2025・リクナビ2025「株式会社インフィニティエージェント」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ルナドクター社
未上場ソリッドベンチャーの事例。ルナドクター社。2020年設立。 売上高推移は、
1期目:3億円
2期目:124億円
3期目:154億円
女性特化のヘルステック事業のフェムチェック領域、オンライン診療、医療DX支援を展開。近都代表が産婦人科医であり産業医という「中の人」。
医療DX支援をキャッシュカウにしながらフェムチェック領域にチャレンジ。フェムチェックで問題の顕在化をしたユーザーをオンライン診療へ送客。事業全体のストーリーがキレイすぎる‥‥。
さらにM&Aや事業提携も積極的に行っており、ジワ新規だけでなくド新規領域も積極的。
「中の人」起業家は業界課題インサイトや解決策センターピンの解像度がめちゃくちゃ高いので事業がスベりにくい。
キャプチャ引用元
ルナドクター社のコーポレートサイトより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:シー・ビー・ティ・ソリューションズ社
年商99.4億(2024年4月)。未上場‥‥!
創業事業は試験運営総合委託サービス。英検や漢検を筆頭に数多ある「〇〇検定」の運用支援から始まり、ITを活用した全国展開のサポート、裏方業務の代行、メディアによる集客支援まで基軸になる事業からソリッドなジワ新規で着実に領域を拡大。
設立2009年から事業を積み上げて15年で年商約100億規模に。
これまで存在していた市場を創業事業に据えながら顧客ニーズを常にキャッチして、既存事業にジワっと隣接している事業にソリッドに進めているのはめちゃくちゃ教科書的で学び深い。
キャプチャ引用元
シー・ビー・ティ・ソリューションズ社のコーポレートサイト より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ギークリー社
2011年設立。 2026年に売上高100億を目指す。
IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介。奥山代表の過去のキャリア経験とナレッジをレバーに現事業を拡大。スマホやアプリ、ゲーム全盛期の2011年に業界特化で事業を開始。
トレンドにのって小さくまとまらずに組織拡大路線に乗せる、という展開で現在に。参入のタイミングと市場選択は本当大切‥‥!
本業から隣接するジワ新規の事業(メディアと口コミサイト)もしっかり作っているのもソリッド。
労働集約型ビジネスが「弱い」「魅力的ではない」としている人もいるが、個人的にはめちゃくちゃ可能性があると思っていて、2025年の投資テーマもそこに置く予定。
一見、弱いと思われることも、見方やアプローチを変えると実は追随するのが難しくなるくらい強くなるというのがあるはずで。
ギークリー社のアプローチはすごい参考になる。
キャプチャ引用元
ギークリー社のコーポレートサイト、採用サイトより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:Wiz社
2012年設立。2023年11月期の売上高194億。従業員数1,100名超。グループ会社16社。
セールスナレッジ(営業手法)をビジネスの根幹にして、自社だけではなく同業の支援も行っている。
具体的には、個人パートナー事業(個人向けの営業をしている会社の支援)、法人パートナーDX事業(法人向けの営業をしている会社の支援)、マンションDX事業はセールスナレッジのビジネス。そのほかHR事業
やM&A事業を行っているが、これらも実は「セールス人材」や「同業パートナーマッチング」だったり。
山崎代表の過去のキャリア経験をベースにしながら、川上に登る形で上流コンサル+ベンダー的なポジションを確立したのが強い‥‥!
グループ会社は16社まで広げながら、各社がそれぞれ綿密なつながっていてソリッドな事業展開をしている。顧客ニーズを着実に拾って事業にしているのがわかる。
自社が代理店になるという選択もあったはずだけど、コアコンピを理解した上でさらに上流にのぼるというやり方はめちゃくちゃ勉強になる‥‥!同じ構造で別の領域でも全然あるはず。
キャプチャ引用元
Wiz社のコーポレートサイト、マイナビ2025「Wiz」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ミギナナメウエ社
2018年設立。2024年8月期の売上高20億円見込み。
採用コンサル、転職エージェント、SESの3事業。沿革を見るとわかるソリッドな展開で、コンサルからのSES事業、そしていまのHR関連事業に。
安定収益モデルを作りながら周辺顧客へニーズありきのジワ新規で広げているのがソリッドベンチャーっぽい‥‥!
現在の3つの事業の共通項は労働集約型の事業モデルであること。AIやITが進めば進むほど「労働集約型のビジネスがなくなる!」と言われてますが、実際はそんなことはなくて、むしろ参入障壁になったりするので個人的に注目してる。
世の中の生産性向上のトレンドも相まってアウトソーシングニーズが増えていっているのでこれからどんどんいろんな切り口での面白い企業がでてくるはず。
キャプチャ引用元
ミギナナメウエ社のコーポレートサイト、Wantedlyより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:one net社
2016年設立。売上高20億円超。北海道発ソリッドベンチャー(現在の本社は東京都)。
主軸事業は3つでテレマによるアライアンス事業、SES事業、インサイドセールス事業。祖業は星代表のキャリアに紐づくアウトバウンドテレマ。その後、SES事業・インサイドセールス事業という流れで、顧客が求める「外部パートナーからの支援」をベースに事業展開しているところが堅くてソリッド。
Salesforceの導入してインテグレーションも始められていたり、ジワ新規的な顧客ニーズありきのマーケットインで事業自体がコケにくい。
労働集約な人×売上の事業モデルは参入しやすいのでプレイヤー多数になりやすいけど、特定領域でニッチトップになって領域を独占するとめちゃくちゃ参入障壁になるのはあって。
さらにCSを拡充することで顧客の「剥がれにくさ」もつくようになるとリカーリングモデルになっていったり。
組織化が得意な起業家はこの辺りの領域で強い会社が作れそう‥‥。
キャプチャ引用元
one net社のコーポレートサイト、星代表のnote、ベストベンチャー100「one net」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:C-mind社
2011年設立。2023年2月期の売上高35億。従業員数グループ全体で300名超。15期連続で増収。
創業期から通信の代理店事業。ジワ新規の広げ方で、強い収益基盤をつくりそこで創出した利益を新しい事業へ投資していくスタイルで拡大。
定額制レンタルプリンター「スリホ」やリクルートスーツの無料レンタルサービス「カリクル」などが新規事業として生み出されたもの。(それぞれのサービスだけでもめちゃくちゃ面白いし興味深いけど文字数・・)
C-mind社の事業の作り方は、同社が持っているアセットを「ハード」「ソフト」に分けると理解しやすい。
・ハード:セールス組織、顧客基盤、デリバリーの仕組み
・ソフト:顧客やユーザーのインサイトをもとにした企画、アイディア
収益を生むキャッシュカウ事業は主に「ハード」を活用して作り出し、そこで得たインサイトを「ソフト」で掛け合わせて新サービスをつくる。「ハード」がベースにあるので立ち上がりがめちゃくちゃ早い。さらに、それぞれの新規事業はキャッシュカウ事業に紐付くように設計されているのもイケてる。(黄色ラインがキャッシュカウ、赤ラインがソフトアセットを活用した新規事業)
参入するキャッシュカウ事業は明確に「儲かるところ」にフォーカスしているのもソリッド。儲かるところとは、巨大産業かつ社会のインフラとなる領域に事業集中と明言。いま時点でITインフラ・人材・不動産が基盤に。
「ハード」「ソフト」を掛け合わせてジワ新規で拡大していて、まさにソリッドベンチャー‥‥!
キャプチャ引用元
C-mind社のコーポレートサイト、マイナビ2026「C-mind」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ビジョン・コンサルティング社
2014年設立、10期目で1,000名超、売上高106億円(2024年1月期実績)。グループ会社1社。
創業からIT領域に特化したコンサルティング事業。グループ会社は領域シナジーがある、IT特化の人材紹介事業。コンサルティング業界においては、人×売上の構造の積み上げが基本。類似する国内コンサル大手のベイカレント社の事業KPIからもわかる。
コンサルは完全な業務の型化は難しい。なので、
①人を増やし続ける、
②いい顧客を獲得し続ける、
③その他の収益源を作る、ことで拡大している。アクセンチュア社も引いてみるとそんな展開をしているはず。
人を増やすといっても効率化と利益率を高めるためには正社員をいかに増やすかがポイントで同社と同業の採用は積極的で、特に新卒採用に注力。サービスの型化が先行するけど、それができれば会社のDNAを早期に浸透させるための新卒採用はマッチしているから。そのためのワンプール制でデリバリーの水準を落とさない体制にしているのかも。
キャプチャ引用元
ビジョン・コンサルティング社のコーポレートサイト&採用サイト、ビジョン・キャリア社のコーポレートサイト、リクナビ2025「(株)ビジョン・コンサルティング」ページより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ロゴスウェア社
2001年設立。eラーニングや研修ライブ配信のプロダクトがメイン。2022年チェンジ社の子会社化に。
創業はソフトウェアの受託開発。資金力がなく、自社製品を出せなかったため、受託で作った製品を有効活用し製品に転換。創業3期目にようやく自社製品をローンチ。
そこからは受託開発を行いながら自社製品のアップデートをし続け、いまでは受託開発はほとんどゼロに。eラーニングの先駆者的存在でパッケージからクラウド化の流れもしっかりキャッチ。
受託開発にリソースを割きすぎて本来目指すべき方向からずれてしまいがちだけど、その受託開発を事業のタネにするため腰を据えて考えるというもの選択肢としてあり。
キャプチャ引用元
ロゴスウェア社のコーポレートサイト&採用サイトより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ペンシル社
2024年2月実績で売上24.8億円。創業は1995年。
創業から一貫してインターネット関連ビジネスの裏方で展開。初期はドメインレンタルから始まり、検索エンジン最適化のSEOを主軸に着実に成長。
創業10年がたった2006年にはじめて自社サービスをリリース。そのサービスも既存事業の効率化ツールであり、すでにもっているアセットをしっかりと使ったソリッドな事業展開。
クライアントワークを深化させて顧客提供価値を横に広げて着実な収益をつくりながらコケないサービスをつくって「ウェブ総合コンサル」的な支援をしていてソリッドベンチャーの理想‥‥。
リリースページを見てわかる通り、常に新しいチャレンジや研究開発ができるのは盤石な収益があるからできること。
キャプチャ引用元
ペンシル社のコーポレートサイトより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:エクストリンク社
2006年設立。 売上高はグループ合計で100億円。
祖業はコンテンツ/ホームページの企画・立案・制作。ITソリューション領域を中心にソフトウェアやスマートフォンの販売、そしてシステム開発など、幅広い事業を展開。
事業はビジネスソリューション事業、SHOP事業、ウェブソリューション事業と切り分けてはいるが、根底にある強みの「組織販売力」で力強い成長をしている。
顧客がBtoB/BtoCで変わったとしても組織販売力をうまく活用できれば再現性のある成果が出やすいので。
組織販売力を強みにできることで収益も安定化しやすい。いわゆる”ゾス”系に通ずる考え方で、大勝負をしないという点でソリッド‥‥。
キャプチャ引用元
エクストリンク社のコーポレートサイト、採用ページより。
未上場ソリッドベンチャーの事例:エンジョイワークス社
2017年設立。売上高は右肩上がりで9期目で12億円+予測。創業以来、9期連続黒字経営でソリッドに事業展開。
ホームページ制作×大阪本社のシブイ掛け合わせ。事業はホームページ制作やシステム/アプリ開発、記事制作などで派手ではないが、エリアと顧客を絞って着実に積みあがっていてめちゃくちゃソリッド。公開されている事業もほとんどが隣接する事業でジワ新規アプローチでこけにくい‥‥。
普遍的にニーズのあるものは探すといくらでも見つかる。ただ、キラキラしたようなものでは全くないのも事実。ただ、普遍的にニーズがある=単客が楽&マネタイズが楽ということだったりするのでソリッドベンチャーへの一歩目でこのような事業選択はめちゃくちゃアリ。
祖業で培ったアセット(顧客や社内ノウハウやインサイト)をもとに既存事業を毀損しないさじ加減で新しい事業チャレンジをすることで急拡大路線にはいっていくことも。
キャプチャ引用元
エンジョイワークス社のコーポレート/採用サイト、リクナビ2026「エンジョイワークス」より。
未上場ソリッドベンチャーの事例:ジェリクル社
2018年設立。数億円規模の黒字を継続しながら堅実(ソリッド)に事業拡大。
「ゲルで医療に革新をもたらす」というコンセプトで、テトラゲル(Tetra-gel)の研究開発から薬事承認のための実証実験、さらには工業・農業領域への展開までも一気通貫で推進。
日本国内のバイオ系スタートアップとしては珍しく、上流(基盤技術の開発)から下流(製品化・社会実装)まで自社で連携しながら、パートナー企業と共同開発・ライセンスアウトの両面戦略を取っているのが特徴。しかもすでに黒字化‥‥。
医療・バイオ版の“フルカバレッジ型”ビジネスモデルを確立しつつあって、売上の積み上がり方や顧客(製薬企業・医療機器メーカー・工業材料メーカー)へのアプローチ方法、研究者の採用やアカデミアとの連携など、多くの点で「典型的なハイリスク型バイオベンチャー」とは一線を画している。
自社のコアコンピを小さく多くジワ新規的に広げており、めちゃくちゃバイオソリッドベンチャー。
「ゲルの技術課題が顕在化しているところ(アンメットメディカルニーズ)から入る」というのは、医療・産業現場の顕在ニーズがありこけにくい。事実、ゲルの物性制御に課題を抱えている領域は多く、そこへジェリクル社が一気通貫で課題解決を提案できることで安定的に新規案件を獲得できている気がする。
“自社のコア技術を徹底的に深掘りし、最適なソリューションを提供する”というスタイルで、堅実に契約数を積み重ねることができるのが、いわゆる「ソリッドベンチャー」ならでは。
THE MODELのように研究・製品化・営業を分業するのではなく、「プラットフォーム技術」として全部やります、という動きがバイオ領域でも使えるんだという当たり前だけど新鮮な驚き。
ゲルやバイオの巨大な市場規模は「いまから参入しても遅いのでは?」と思われがちな半面、上場したバイオ企業や着実に伸びているソリッドベンチャーの実例を見ていると、
・需要拡大が見込まれる巨大マーケットへ後発参入
・基幹技術(上流工程)でクライアントとのリレーションを確保
・採用・研究拠点の強化で事業を加速
という定番の勝ちパターンがある。
国内のみならず海外(米国SkyDeckやJLABSなど)へも積極的に進出しているあたり、グローバルでの成長余地を見越した動きも印象的で、さらにディープな研究室 × シリアルアントレプレナーという組み合わせは、これから増えてくるかも?と個人的に。
キャプチャ引用元
ジェリクル社コーポレートサイト,社長名鑑『独自のハイドロゲル技術を開発!高難度治療分野の克服を目指す社長の経営戦略と展望とは』,SELECK『バイオベンチャーこそ資金調達を踏み止まれ。3期目で億単位の利益をあげるジェリクルの軌跡』より
これらの事例からもわかるように、ソリッドベンチャーは収益性と持続可能性を両立させることが可能であり、今後も多くの企業がこのモデルを採用することが期待されます。
ソリッドベンチャーのメリットと問題
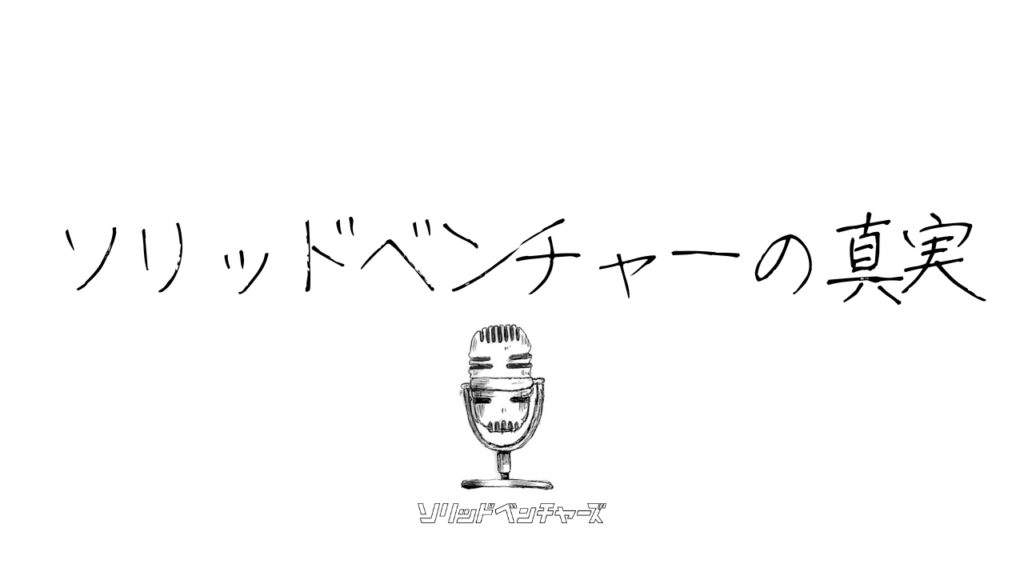
メリット1:初期の資金安定と長期的成長
ソリッドベンチャーの最大のメリットは、何といっても「創業期から安定収益が期待できる」点です。現金収入が定期的に得られることで、銀行融資も受けやすくなりますし、投資家から見ても“すでに黒字”という安心感が生まれます。結果的に、追加の資金調達でも好条件を引き出せる可能性が高まります。
また、スタートアップが「数年で大きなEXIT」を求められるケースが多いのに対し、ソリッドベンチャーは長期的な成長を重視できます。数年で2~3倍の売上を目指すよりも、10年かけて10倍の売上を狙うといった腰の据わった経営が可能なのです。
メリット2:投資家のプレッシャーを受けにくい
スタートアップにありがちな大型ファイナンスでは、VCのEXIT期待や株式上場のタイムリミットなど、外部プレッシャーが強く働きます。その結果、経営者は強いリスクテイクを迫られたり、希望しないスケール戦略を取らざるを得なくなることもあります。
一方、ソリッドベンチャーはキャッシュフローを自社で回していけるため、「すべてを外部資金に頼らない」体制が構築しやすい。必要があれば銀行借入れで賄うなど、より自由度の高い選択肢が生まれるのです。
メリット3:新規事業失敗時のダメージを最小化
先ほど述べたとおり、ソリッドベンチャーは万が一の新サービス失敗時にも倒産の危機を迎えにくい構造を持っています。
少なくともキャッシュ・カウ事業が回っていれば固定費を補えるため、事業修正やピボットを検討する時間が確保しやすく、企業としての寿命が長くなるわけです。
課題:市場の変化への柔軟対応・イノベーションの速度
ただし、ソリッドベンチャーに課題がないわけではありません。初期収益を重視した結果、どうしても堅実な領域にフォーカスしがちとなり、新技術や新アイデアを大胆に展開するタイミングを逃す可能性があります。
あるいは、安定収益に甘えてしまい、組織として新規プロジェクトへの取り組みが後回しになるケースもあるでしょう。
また、市場の動きが速い分野では、スタートアップが一気に資金調達してマーケットを制圧することもあります。ソリッドベンチャーはそのスピード感に追いつきにくく、時として先行者利益を奪われるリスクに直面しがちです。地道に伸ばすメリットと変化への俊敏さの両立をどう図るかが大きな課題と言えます。
ソリッドベンチャーの展望
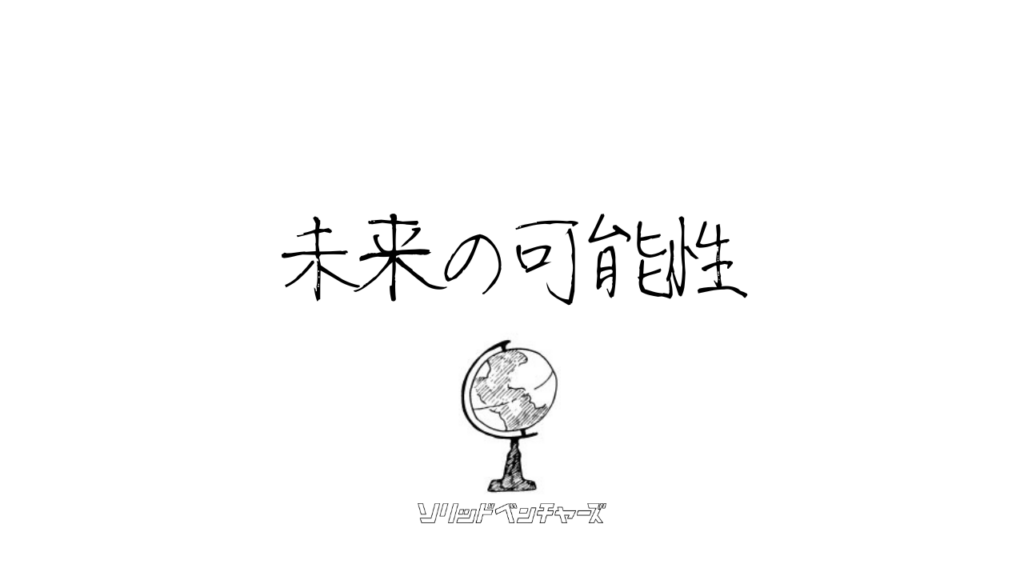
今後の社会ニーズとソリッドベンチャーの可能性
近年、環境問題や社会課題への意識の高まり、あるいはDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速によって、新たな事業チャンスが次々と生まれています。
ソリッドベンチャーは、こうした領域においても「まずは確実に稼ぐ仕組みを作り、得た利益で社会的インパクトのある事業へ乗り出す」という柔軟なアプローチが取りやすいでしょう。
一方で、グローバル展開や大規模マーケットを狙う際には、やはり資金力を持った競合が出現する可能性は高いです。スタートアップと同じ土俵で戦うにはスピードが物を言うため、安定と挑戦のバランスをどのように取るかが、今後のソリッドベンチャーにおけるカギとなってきます。
地に足つけた成長戦略を選ぶなら
ソリッドベンチャーは、スタートアップほど派手な資金調達や急拡大のシナリオこそ描きにくいかもしれません。しかし、まずは堅実に黒字を確保し、そのうえで新規事業に投資し続ける姿勢は、マーケットが成熟しつつある日本のビジネスシーンにおいて、むしろフィットする側面も多々あります。
- 受託やコンサル等のキャッシュ・カウを先に整えることで、開発や実験に必要な資金と時間を捻出。
- 外部資金のプレッシャーを受けすぎず、経営の方向性を自社がコントロールできる。
- 長期的な視点で製品やサービスのブラッシュアップを実行しやすい。
各社の事例のように、地味な領域(受託・コンサル)から出発しつつ、社内発のサービスを磨き上げて上場を果たす企業もあります。短期勝負とされるスタートアップのエコシステムに一石を投じる意味でも、ソリッドベンチャーという選択肢はこれからますます注目されるかもしれません。
もしあなたが「新技術に挑戦したいけど、まずは早期黒字化を実現したい」と考えているなら、ぜひソリッドベンチャー的な手法を検討してみてはいかがでしょうか。
小さな受託ビジネスを軸にして、そこから得られる収益で開発に投資し、“ジワジワ”とイノベーションを形にする――そんな堅実かつしなやかな成長モデルが、次代の企業形態として広がる可能性は十分にあると言えます。
“倒れにくい挑戦”のすすめ
ソリッドベンチャーは 「黒字基盤で倒れにくく、挑戦で伸びる」 という2枚腰の戦略を取れる。
- 早期黒字の安心感は、社員・顧客・金融機関の信頼を高める強力な盾になる。
- 一方で、安定に甘えず再投資ループを明文化し、挑戦事業を“常に並走”させる攻めの仕組みがなければ、スピード勝負の世界で置き去りにされる。
安定と挑戦の黄金比をどう設計するか――そこに、次世代ソリッドベンチャーの真価が宿るのでは?
FAQ(よくある質問)
Q1. ソリッドベンチャーって一言でいうと?
まず“稼げる柱”を作り、その利益で新しい事業に挑戦し続ける会社の型です。だから倒れにくく、挑戦の回数を増やせます。