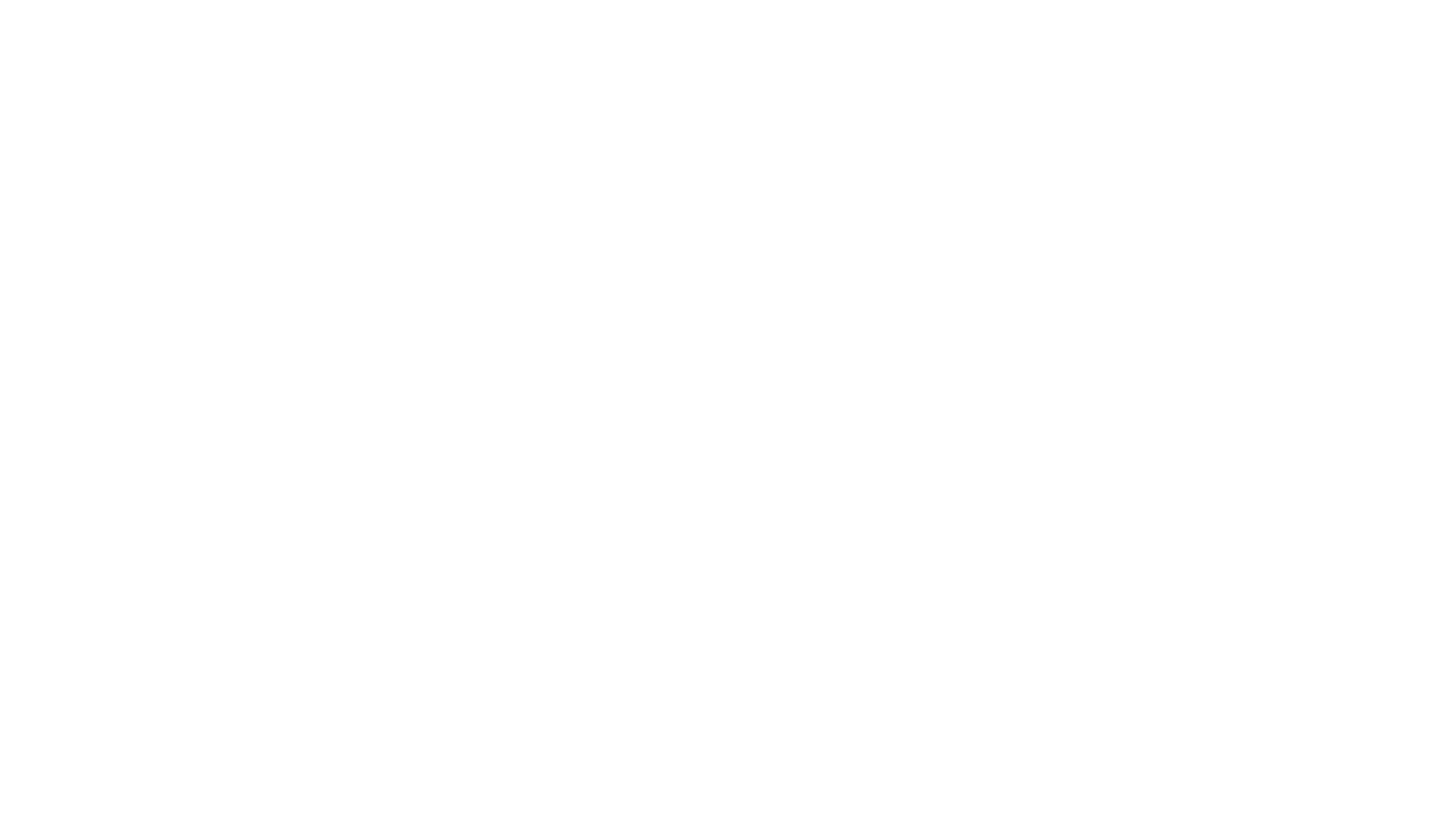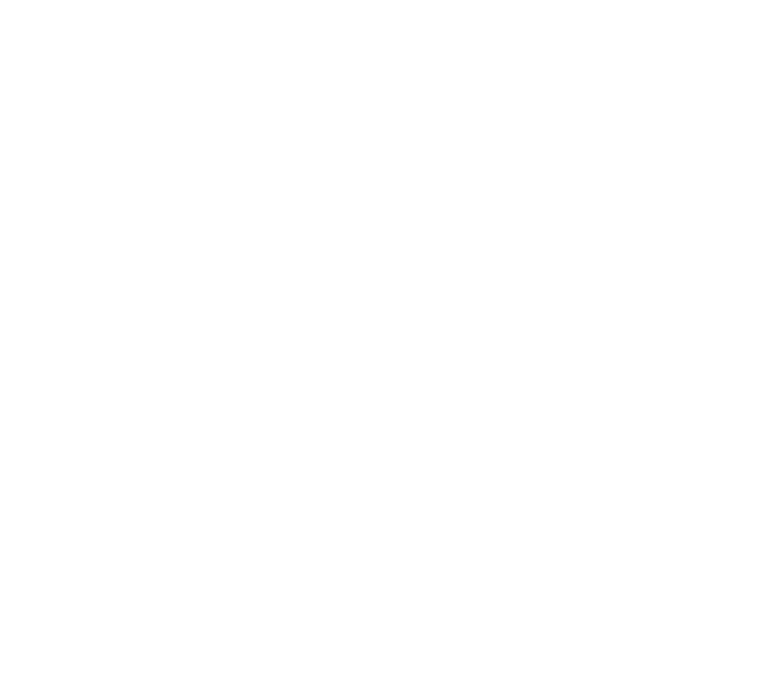- #ソリッドベンチャー
- #起業
ソリッドベンチャーを起業するための10個のチェックリスト
公開日:2025.01.22
更新日:2025.4.25
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠

ソリッドベンチャーとは、「まずは安定収益を得られる事業を創業初期に作り、その利益を活用して段階的に新領域へ拡張していく」ビジネスモデルです。スタートアップのような大きな資金調達や赤字拡大路線とは異なり、堅実かつ着実に会社を伸ばす姿勢が特長。VC投資が多様化する今、資金ショートのリスクを抑えながら息の長い成長を狙う選択肢として注目が集まっています。ここでは、ソリッドベンチャーを起業するための10個のチェックリストを見ながら、早期黒字化への具体的アプローチを深堀りしていきましょう。
ハイライト
- 受託やコンサルなど、まずは着実にキャッシュを確保できる事業で黒字を目指す。
- “ジワ新規”により隣接領域へ少しずつ踏み込めば、大きな赤字を抱えず多角化が可能。
- 過度に外部資金に依存しないため、爆発的拡大は難しくとも長期視点で堅実に成長できる。
ソリッドベンチャーを起業するための10個のチェックリスト
いま、なぜ「早期黒字化のソリッドベンチャー」が注目されるのか
近年、「スタートアップ」という言葉が社会に広く定着し、短期集中型の爆発的成長を目指す企業が数多く誕生してきました。華々しい成功事例も増えていますが、一方では資金調達やマーケットの変化に振り回され、急激な赤字拡大から撤退を余儀なくされるケースも目立ちます。
そのような中、「まずは黒字をしっかり作る」「リスクを極力抑えながら伸ばす」というスタイルが改めて評価され始めました。受託開発やコンサルティングで確実に利益を得ながら、新規プロダクトに投資するソリッドベンチャー型は、短期的な“ドカン”こそないものの、息の長い成長を可能にします。
- VC任せの成長からの脱却
外部資金が集まる時期は良いですが、調達が厳しくなると経営が一気に悪化するリスクが高い。 - 経営基盤の安定
受託やコンサルで早々に黒字化できれば、倒産の危険性を大幅に下げられる。 - 市場への着実なアプローチ
エンドユーザーの課題を受託時点で把握しやすく、新規事業にもつなぎやすい。
こうした理由から、よりリスクを抑え、堅実に利益を積み上げていくソリッドベンチャー型の起業が注目されているのです。
ソリッドベンチャー型の10チェックリスト──“まずは黒字”を目指す仕組みづくり
ソリッドベンチャーの核となるのは、“いかに早期に黒字化し、その後のチャレンジ費用を稼ぎ出すか”です。ここからは、創業期に押さえておきたい10のチェックリストをひとつずつ見ていきましょう。
【Checklist 1】 最初の受託・コンサルで確実にキャッシュを生む
なぜ必要?
創業直後は、まだ開発資源も人的リソースも十分ではありません。自社オリジナルのプロダクトを大きく育てる前に、すぐに売上を立てられる“受託”や“コンサル”でキャッシュフローを生むことが、ソリッドベンチャーの肝です。大きく赤字を掘るのではなく、まずは地に足をつけて利益を作り、そこからの再投資を検討します。
ポイント
- 小規模案件でも即金性重視の分野を選ぶ
- 専門領域に特化して競合と差別化を図る
- 顧客の課題に素早く対応できる体制を最初に整備する
ここで利益を出せるかどうかが、創業期の生存確率を大きく左右するのです。
【Checklist 2】 顧客との長期契約を狙う
なぜ必要?
単発の案件だけだと安定感に欠け、毎月の売上を読みにくくなります。月額サブスクや年間契約など、継続的にお金が入るモデルを組み合わせることで、キャッシュフローが安定し、さらなる開発投資に集中できるのが強み。
ポイント
- 運用・保守フェーズの契約をセットにし、ストック収益を確保
- 複数年の長期契約により、営業コストを抑えつつ売上を安定化
- 定期的なアップセルの機会を見込み、既存顧客の深耕を図る
安定契約があるだけでも、銀行借入などの際に信用が増すというメリットもあります。
【Checklist 3】 社内の業務フローを“標準化”する
なぜ必要?
受託やコンサルは、人材スキルに依存しがち。属人化したタスクが多いと、プロジェクトごとに品質がブレたり、新人を育てる負担が膨れ上がったりします。そこでプロセスをマニュアル化・共有化しておけば、人が増えてもスムーズに作業を回せるようになります。
ポイント
- 作業ステップとチェック項目をテンプレート化
- プロジェクト管理ツールの導入で情報を一元管理
- ノウハウを蓄積し、誰でも対応できる体制を構築
これにより、受託業務の生産性・利益率がアップし、中長期の経営基盤が安定します。
【Checklist 4】 早い段階で顧客の“別の課題”をヒアリング
なぜ必要?
ソリッドベンチャーの強みは、「顧客の信頼を得た上で横展開(ジワ新規)しやすい」こと。受託やコンサルをしていると、別部署や隣接領域の課題が自然と見えてきます。それらを押さえておくことで、次に作る新規サービスのヒントを得られ、拡販もスムーズになるのです。
ポイント
- 受託案件の合間や定期ミーティングで顧客の悩みをリスト化
- 社内で「次の提案先」としてデータを共有
- 小さな課題にも着目し、追加契約や新サービス立ち上げを検討
“まだ顕在化していない需要”を拾えるかどうかが、後々の大きな差につながります。
【Checklist 5】 投資ペースを自己資金ベースで管理する
なぜ必要?
VCからドカンと資金を入れるスタートアップ型とは異なり、ソリッドベンチャーは手元キャッシュを生むことを先に優先します。そのキャッシュを元手に新サービス開発や人材採用に投資するので、外部投資家から厳しいリターン要求を受ける心配が減り、経営主導権を確保しやすい点が魅力です。
ポイント
- 月次や四半期の利益を見極めながら少しずつ開発投資
- 必要な場合はデットファイナンスも選択し、株式希薄化を抑制
- 急拡大ではなく、堅実な拡張計画でリスクマネジメントを徹底
創業者が持株比率を大きく維持しつつ、段階的にサービスを成長させられます。
【Checklist 6】 小規模なM&Aや事業提携の選択肢を常にチェック
なぜ必要?
自社に足りない機能やノウハウを「スモールM&A」で補えば、時間とコストを大幅に節約可能。ソリッドベンチャーは大規模M&Aより、数千万〜数億円レベルでシナジーの高い事業を取り込む手法をとりやすいのが特長です。
ポイント
- 補完サービスを提供している小規模企業をリサーチ
- 自社の営業力と連携すれば売上拡大が見込めるかシミュレーション
- 単純な買収だけでなく、アライアンスや業務提携でもOK
例として、コンサル事業に人材紹介やBPO企業を掛け合わせるなどが典型的パターンです。
【Checklist 7】 組織拡大の前に“コア人材”を確保
なぜ必要?
ソリッドベンチャーは、いきなり大量に人を採用してリスクを負わないのが基本。まずは品質管理と顧客対応ができるリーダークラスを確保し、少人数でも受託・コンサルをしっかり回せる体制を築きます。その後、案件拡大に合わせて組織を段階的に大きくするやり方が安全です。
ポイント
- プロジェクト管理能力をもつリーダーを優先採用
- 新規事業の種を一緒に考えられるメンバーの育成も視野に
- 組織が大きくなる前に、業務フロー・カルチャーを定義
急激に人数が増えすぎると、コストと教育負担が跳ね上がるので要注意です。
【Checklist 8】 利益率を意識して価格設定を見直す
なぜ必要?
受託やコンサルは“低価格の競争”に巻き込まれると利益が出にくくなります。安易に値引きに応じるのではなく、“自社の強みや付加価値”を明確にアピールし、正当な価格を設定することが必要です。
ポイント
- 作業範囲と追加オプションを最初に明文化し、見積もりを明確に
- アップセルや連続契約での値引き条件を用意して単価を保つ
- 顧客満足度を高める仕組み(定期報告や追加提案)で価格を納得してもらう
安すぎる案件ばかり増やすと、労働力ばかり取られて成長が止まる可能性があります。
【Checklist 9】 顧客ロイヤルティ向上にテック導入を図る
なぜ必要?
コンサルや受託のみだと“人の頑張り”が中心になりがち。しかし、自社ツールやSaaSを組み合わせて効率化しつつ、他社にはない付加価値を作れれば、顧客ロイヤルティが上がり、サービス継続率も高まります。
ポイント
- 自社内で実際に使うミニツールを開発し、改善しながら外販も検討
- BPO+自社クラウドツールなどのハイブリッドモデルで差別化
- 顧客満足度が高まれば、他部門への横展開も発生しやすい
ツールを使った顧客対応が定着すれば、ストック型モデルへの移行も視野に入ります。
【Checklist 10】 “ジワ新規”への進出時期を決めておく
なぜ必要?
受託案件が好調だと、ついそちらにフル稼働して新規事業の開発が後回しになります。あらかじめ“いつから開発リソースを割くか”“どの程度の投資をするか”を決めておかないと、一向に新規ビジネスが形にならず、気づけば「受託専業」になってしまうかもしれません。
ポイント
- 1年目は黒字達成、2年目〜3年目で新サービスβ版リリースなどロードマップを作成
- プロダクト開発専任チームを早期に確保し、並行して動かす
- 新規事業の進捗を定期的にチェックし、受託人員との兼ね合いを最適化
ジワ新規を成功させるには、戦略的に“いつ動くか”を社内で合意しておくのが重要です。
INTLOOP社が実践するソリッドベンチャー戦略
ソリッドベンチャー的な経営で堅実に売上を伸ばしながら、新規事業への拡張も見事に成功させている企業として挙げられるのがINTLOOP社です。彼らの取り組みは、まさに上記10のチェックリストを活用しながら段階的に組織を拡大してきた好例といえます。
INTLOOP社の概要
- 設立:2010年代(正確な年はここでは省略)
- 主軸ビジネス:ITコンサルティング、人材マッチングサービスなど
- 展開:受託コンサル⇒フリーランス活用支援⇒SaaS的なDX支援と段階的に拡大
INTLOOP社は、まずIT分野のコンサルおよび開発支援事業をスタート。特に大企業からのプロジェクト単位の受託に強みを持ち、それによって早期の黒字化を達成しました。さらに、その安定的な受託収益を背景に、人材領域やSaaS型サービスといった“隣接領域”へ進出しているのが特徴です。
受託+人材ビジネスで安定売上を確保
まずはITコンサルティングと開発支援で複数の大手企業と契約し、定期的かつプロジェクトごとの報酬を得られるようにしたことが大きかったと言われます。
そこに加えて、フリーランスエンジニアを企業に紹介し、契約が続く限り手数料収入が生じるという人材マッチングサービスを組み合わせることで、より強固なキャッシュフローの基盤を築き上げました。
- Checklist 1〜3の実行
- 初期から受託コンサルで確実に黒字を出す
- 営業・作業フローを標準化し、同時に複数プロジェクトを回せる体制を整備
- 月額モデルや長期契約形態を取り入れ、安定収益源を確保
階的に新規サービスを投入
INTLOOP社は受託コンサルで得た顧客との信頼関係を活かし、顧客のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を支援する小規模ツールを内製で作り上げました。プロジェクト管理やタレント管理を自動化するための独自システムを構築し、それをクライアント向けに拡張・提供し始めたのです。
こうした“SaaSビジネス”への転換こそ、ソリッドベンチャーの真髄といえます。最初の受託収益があるからこそ、一定期間は赤字を許容しながらツールを開発し、ある程度完成度が上がったところで外部の顧客に向けて提供をスタートすることが可能となりました。
- Checklist 4〜5の応用
- 受託の過程で顧客の課題を吸い上げ、「こういうツールがあれば解決できそう」といったアイデアを試作
- 外部からの大型出資ではなく、自社のコンサル利益を再投資する形でツール開発を進行
シナジー重視の成長モデル
INTLOOP社はまた、スモールM&Aや事業提携にも積極的に目を向けているとされています。ITコンサルと人材マッチングで培った営業基盤を生かし、関連領域の小規模プレイヤーを取り込むことでサービスラインを一挙に増やす。こうした手法は、Checklist 6で挙げた「小規模M&A」の典型的な成功パターンです。
組織拡大に関しては、まず「コア人材」を優先的に採用し、プロジェクト全体の品質を管理できる仕組みを構築。それがある程度整った段階で、ようやくスタッフを増やしていくという段階的アプローチを取っています。
これはChecklist 7の内容とも合致し、リスクを抑えながら人員を増やしていくソリッドベンチャーの特徴そのものと言えます。
INTLOOP社が示すポイント
- “大きな外部資金に振り回されることなく”サービスラインを拡張
- コンサル・受託の安定収益を基盤に、新規開発の予算を自己資金ベースで管理
- 顧客との長期契約やフリーランス契約のストックビジネス化で、キャッシュフローを強化
- 小規模なDXツールを自社開発→SaaS展開という流れで継続収益モデルを構築
結果的に、INTLOOP社は“安定収益+SaaS的ストック収益”を両立させる組織として成長を遂げています。早期黒字化に成功したからこそ、あとから新しいサービスやM&Aに取り組む余力が生まれたとも言えるでしょう。
ソリッドベンチャーが広がる背景
ソリッドベンチャーという経営スタイルは、一見「華やかさに欠ける」「成長スピードが遅い」とみられがちですが、近年はむしろ安定性と長期的視点の重要性が評価され、注目が高まっています。その背景には、いくつかの社会的・経済的要因があります。
- VC投資の多様化
かつては「10倍〜100倍」のリターンを求める投資家が主流でしたが、最近では緩やかでも堅実に利益を出す企業に魅力を感じる中小規模の投資家やファンドも増えてきました。スモールM&Aが活性化し、億単位の“小ぶりな買収”でも十分利益を得られると考える投資家が現れています。 - 市場環境の変化
コロナ禍以降、景気変動が激しく、短期的な大勝負を避けて足元を固める戦略を選ぶ企業が増えました。IT人材不足や後継者問題といった構造的課題に対して、地道にBPOや受託サービスを提供し、そこからSaaSや新規事業に発展させるモデルは、多くの企業ニーズと合致します。 - 地方創生やニッチ市場への関心
地方に根ざす中小企業がソリッドベンチャーの要素を取り入れ、ローカル受託ビジネスで黒字を確保しつつ、その後に独自のサービスを立ち上げるケースも増えています。急成長が難しい市場だからこそ、初期から黒字を大事にする経営スタイルが適しているのです。
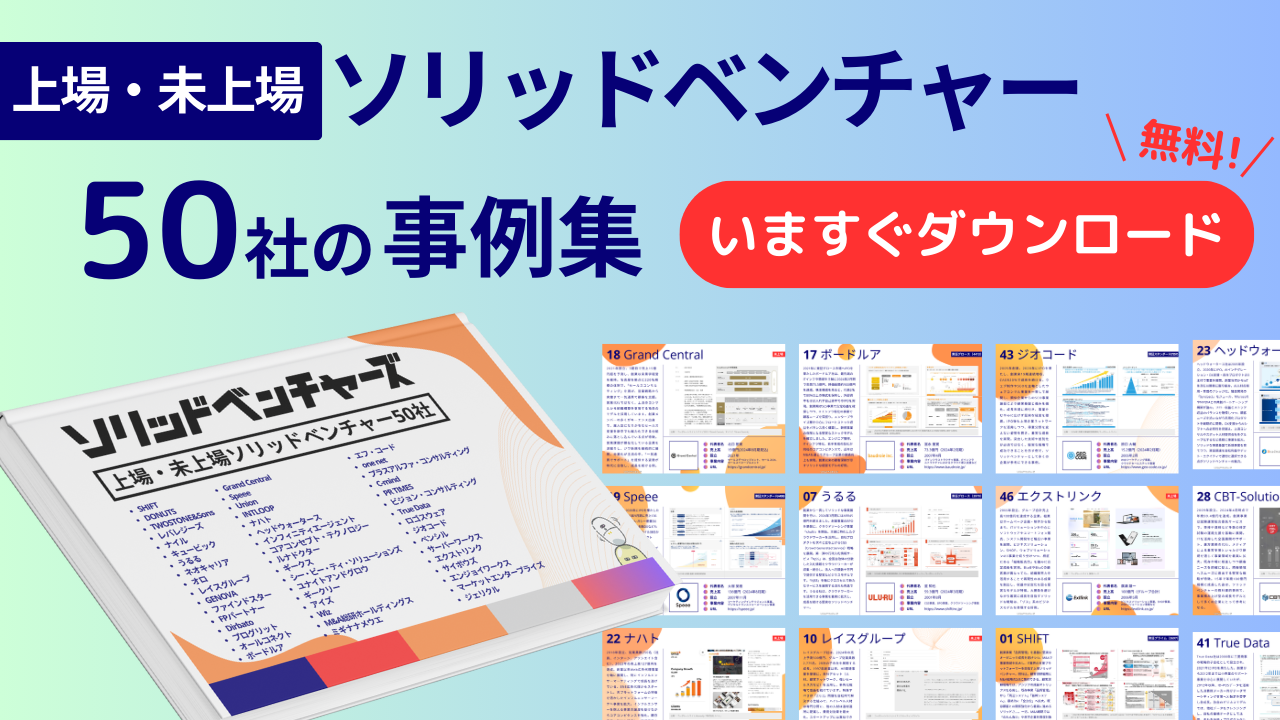
10のチェックリストを軸に“最速黒字”へ
最後に、ソリッドベンチャーの要点と今回の10のチェックリストをふまえて、早期黒字化を目指すうえでの重要ポイントを整理します。
地に足のついた“ソリッドベンチャー”で息の長い成長を
「創業から黒字化まで」というと、スタートアップの世界観ではどうしても**「短期勝負」「赤字上等で大量投資」というイメージが先行しがちです。しかし、ソリッドベンチャーの視点では「まずはしっかりとした受託・コンサルで利益を出し、その利益を次の投資に回す」という手堅いサイクルこそ最速黒字化への近道と捉えられます。
今回紹介した10のチェックリストは、実際にソリッドベンチャーとして成功を収める企業が少なからず実践しているポイントをまとめたものです。
とりわけ1〜5では「早期の受託獲得とキャッシュ確保」に重点を置き、6〜10では「M&Aや新規事業への展開方法、組織拡大の手順」といった中期的な要素をカバーしています。
INTLOOP社の例でも明らかなとおり、安定収益をまず確立したからこそ、新しいプロダクトの開発やSaaSへの転換、さらには小規模M&Aなどの次の一手を柔軟に打てています。
スタートアップ型の加速路線とは異なりますが、ソリッドベンチャーには“堅実に黒字を続けながら段階的に拡大できる”という大きな強みがあります。市場環境が激変しやすい時代だからこそ、この“安定志向×段階的成長”のモデルはますます価値を増していくでしょう。
ソリッドベンチャー型アプローチは、たしかに即座に爆発的な売上を生むわけではありません。
しかし、受託やコンサルで培ったキャッシュフローと顧客基盤を活かしながら、徐々に自社サービスを拡充していく手法には、多くのメリットがあります。
ソリッドベンチャーで未来を切り開く
大きな投資を呼び込み、一気にスケールさせるスタートアップの魅力も確かに存在します。一方で、長期にわたり安定的に成長し続ける企業が評価されはじめているのも事実。ソリッドベンチャー型なら、まずは倒産リスクを最小化しながら、早期黒字化を実現し、そこから余裕をもって新たなチャレンジへ踏み出せます。
- 「地味だけど倒れにくい」——この強みが、いまビジネスシーンで見直されている理由
- 受託やコンサルの安定収益をベースに、SaaSやスモールM&Aへ拡張可能
- 外部の投資家都合に流されにくく、創業者のビジョンを貫きやすい
もちろん急成長を狙う道も否定はできませんが、「まずは黒字」という基盤を持っているだけで未来の選択肢が広がります。10のチェックリストを踏まえ、堅実路線と新しい発想を組み合わせた“ソリッドベンチャー”のアプローチで、あなたのビジネスも大きな可能性を切り開いてみてください。