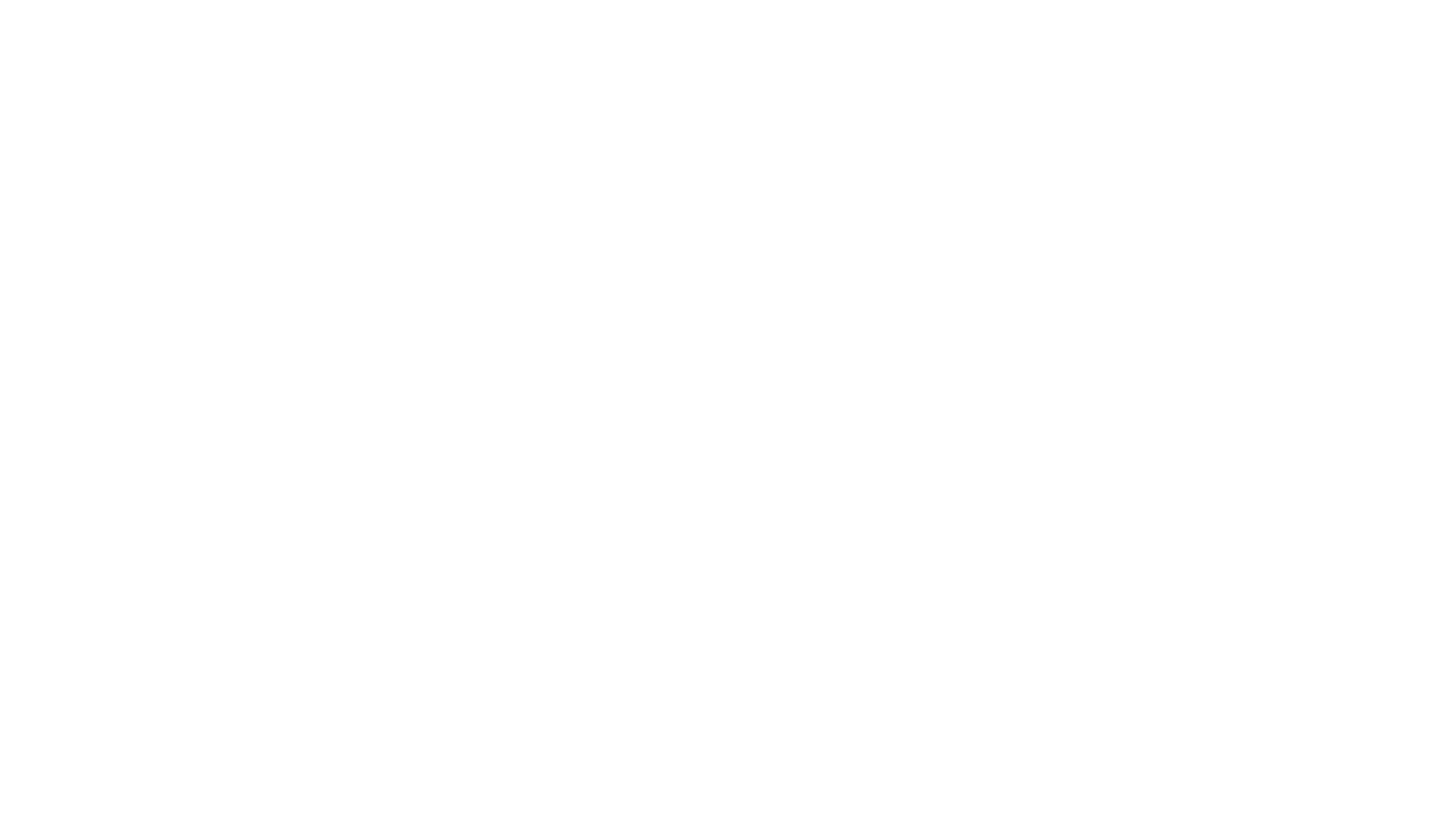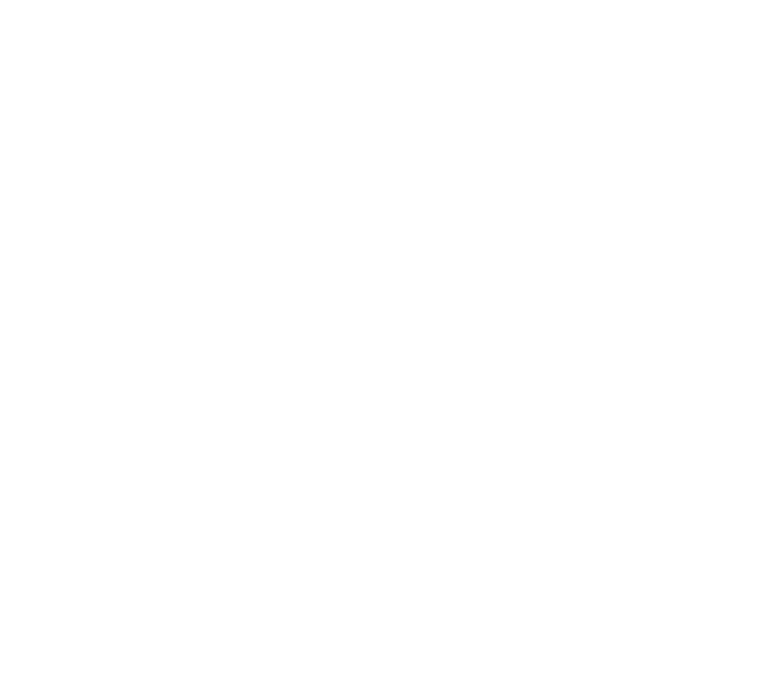- #ソリッドベンチャー
- #成長戦略
後発参入でも勝てるのか?ソリッドベンチャー式“追い風”のつかみ方
公開日:2024.12.25
更新日:2025.6.30
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠

競合がひしめく既存市場に後から参入するのは一見ハードルが高そうですが、安定した収益と顧客密着を武器に地道にシェアを伸ばす“ソリッドベンチャー”ならば、後発でも十分に勝機をつかめます。大手が拾いきれない細分化されたニーズを見極め、ジワ新規でサービスを拡大する戦略こそが、着実かつ堅牢な成長を実現するカギ。本記事では後発参入での成功パターンや、実践ステップまでを詳しく解説します。
ハイライト
- 隙間セグメント×個別対応──大手が捨てた低採算・高要望ゾーンに特化しリピーターを囲い込む
- ジワ新規投資でリスク最小化──受託/BPOなど黒字源泉を盾に隣接サービスを検証・横展開
- 顧客ロイヤルティが参入障壁化──密着サポートでコミュニティを育て、広告ゼロでも紹介が雪だるま式に増加
後発参入が注目される理由――ソリッドベンチャーの視点
後発のメリットとデメリット
市場に後から参入する場合、いくつかのメリットがあります。とくに、先行企業が市場啓蒙をある程度完了しているため、新規で「この製品の価値は何か」を一から伝える負担が軽減されやすい点は大きいです。
また、大手が幅広く顧客をカバーしているように見えても、現実には“あまり収益性が高くない小口顧客”や“複雑な要望を持つ一部セグメント”を切り捨てているケースがあります。ここに「すき間市場」や「取りこぼし顧客」の存在が後発にとってチャンスになります。
一方で、すでに強固なブランド力や広告力を持つ先行企業と真っ向勝負になるのは事実。潤沢な資金で価格競争を仕掛けられる恐れもあるでしょう。ここで勝ち抜くために重要となるのが“ニッチ領域への特化”や“個別要望の柔軟対応”です。ソリッドベンチャーは、後発でもこの差別化ポイントを武器に市場で認知を広げることが可能です。
ソリッドベンチャーが強みを発揮する背景
ソリッドベンチャーとは、VCなどから大きな資金を調達して急拡大を狙うスタートアップとは異なり、手堅い黒字基盤を築きながら少しずつ新事業を増やす経営スタイルを指します。
大手が主導する市場では、時間とともに複雑化したニーズや“個別サポート不足”といった不満が顧客に蓄積しがち。そこで、細かい要望に応えながら着実にユーザーを増やす戦略が“後発でも勝ち残る一手”になりえます。
まとめると‥‥
後発優位の3条件
- 需要は確立済みだがサービス満足度が低い
- 小規模/複雑案件を大手が切り捨てている
- 法規制・商習慣で柔軟対応が求められる
事例に見る後発参入パターン
TWO STONE & SONS社の堅実な多角化
TWO STONE & SONS社は、まず受託開発でキャッシュフローを安定させながら、その利益をもとにエンジニアマッチングプラットフォームやメディア運営など新事業へジワジワと展開しました。プラットフォーム事業は大手も参入している激戦区でしたが、以下の要素で差別化に成功しています。
- 受託開発で培った既存顧客との信頼をそのまま新事業の初期ユーザーに移行
- 大手が提供しづらい手厚いサポートとニッチ機能で競合とは異なる切り口を確保
このように、“堅実さ”と“周辺領域への拡張”を両立できたのは、ソリッドベンチャーらしい着実な黒字経営と少人数から始めるジワ新規が功を奏したからです。
GENOVA社のバーティカル領域深耕
医療機関向けサービスで後発参入しながらも、徐々にバーティカルメディアや精算機など周辺事業に拡大しているのがGENOVA社です。大手代理店がすでに医療市場に入っている中、
- 医療特化のノウハウを構築し、他業界に流用しづらい独自強みを確立
- コンサルや対面サポートを重視し、顧客要望を素早く反映する改善体制
- メディア×機器導入といった“クロス展開”で顧客接点を拡大
といった施策で“後発”のハンデを上回る成長を実現しました。大手では対応しきれない「細かな医療業界の習慣や規制」に合わせ込むことで、リピートや紹介が増えているのです。
ソリッドベンチャーが追い風をつかむ3つのポイント
隣接領域への“ジワ新規”
ソリッドベンチャーの特徴は、急拡大に走らず既存事業で得たキャッシュを使って、隣接領域へ段階的にサービスを増やす「ジワ新規」スタイル。リスクを最小限に抑えながら、
- 本業で黒字を確保
- 既存顧客の関連ニーズを狙った追加サービスを小スケールで立ち上げ
- 口コミ・追加発注により少しずつシェア拡大
という流れを繰り返すことで、後発でも大手に負けない安定顧客基盤を築けます。
大手が落とす細分化ニーズを拾う
成熟市場では、大手が一見“市場を総取り”しているようでいて、実は「単価が低い」「要望が特殊」「地域密着が必要」といった理由で、対応を敬遠されている顧客が少なくありません。
ソリッドベンチャーは効率性よりも「顧客ロイヤルティ」を重視するため、こうした細分化されたニーズに積極的に応える余地があります。大手に依頼して断られたユーザーほど、細かいサポートが嬉しいもの。リピーターや口コミが発生しやすくなるポイントです。
長期的な顧客関係の確立
ソリッドベンチャーは短期的な拡大よりも、顧客との信頼を着実に育てることに注力します。新機能の要望や問題点を素早く吸い上げ、可能な限り改善する姿勢が「後発だけど頼りになる」という評価につながりやすいのです。結果として、顧客が大手を離れてソリッドベンチャーのサービスを長期間利用するケースも増えます。
後発参入を成功させるための実践ステップ
- 競合分析で“狙いどころ”を把握
先行企業がどんな顧客をメインターゲットにしているのか、どんなサービス内容でどこに弱みがあるのか、リサーチを徹底。そこから、自社がカバーできる“隙間”を抽出します。 - 少人数でも利益を回せる収益モデルを用意
ソリッドベンチャーの強みは大規模投資に頼らないこと。小規模チームで利益を上げられるモデルを組み立て、キャッシュフローを早期に安定させましょう。 - 継続的な顧客コミュニケーションと改善
リリース後は細かいフィードバックを積極的に収集・反映するサイクルが重要。機動力の高さこそ後発の武器なので、顧客の声に合わせた素早いアップデートを繰り返します。 - 必要に応じたM&Aや業務提携での拡大
ある程度地盤が固まったら、専門領域を補完し合える企業との提携や買収を検討。既存顧客との関係を維持したまま横展開を進めるのが、ソリッドベンチャー流の“負担の少ない成長”です。
安定収益×後発参入で活路を開いた「Grand Central社」
名古屋拠点のGrand Central社は、設立わずか3期目で15億円超を目指す一方、無理な採用や大規模投資をせず安定黒字を続けています。
- 2024年売上11.2億円・営業利益率12%
- 営業BPO → インサイドセールスSaaS → ChatGPT活用スクリプト自動生成と拡張
- 採用は年間15人ペースを死守し、教育コストをPL5%以内に抑制
「営業コンサル」という確実に需要がある領域でまずは利益を確保し、そこから少しずつ周辺サービス(インサイドセールス支援など)に広げることで、一足飛びの拡大ではなく着実な顧客満足を積み上げてきました。
- 細分化された営業課題にフォーカスし、大手の一括対応が難しい小規模案件を積極サポート
- 機動的なチーム編成でフィードバックを吸い上げ、改善サイクルを高速化
- “採用ベタ踏み”ではなく、必要人員を的確に揃えてキャッシュフローを崩さない
後発参入でも堅実な売上増を実現できたのは、まさにソリッドベンチャー特有の「無理せず堅実に拡張する」戦略によるものです。
後発のほうが優位に働く市場とは?
市場が成熟し、大手が存在感を放っていると「後から入っても勝てないのでは?」と思いがちです。しかし実際は、以下のような条件がある市場では後発参入がむしろ有利に働きます。
- ユーザー要望が多様化・複雑化している
大手は標準的なサービス提供に集中するため、個別対応を必要とする顧客が不満を抱えがち。 - 競合企業が効率重視で小規模顧客を切り捨てる
少額案件やニッチ案件にこそ、“ソリッドベンチャーならではのきめ細かさ”が価値を発揮。 - ブランド力より実質的サポートが重視される
ネームバリューよりも“困ったときすぐに助けてくれるパートナー”を選ぶ顧客が多い領域。
こうした特徴を持つ市場であれば、後発でも十分にシェアを伸ばす余地があると考えられます。
後発ソリッドベンチャーが生む“地道な拡張”の強さ
派手な広告投下や大規模なキャンペーンを行わずとも、ソリッドベンチャーは安定収益と地道なサービス拡張によって少しずつ市場での存在感を高めていきます。これは短期的には目立ちにくいですが、一度基盤ができると崩れにくい強みがあります。なぜなら、以下の効果が働くからです。
- 長期顧客による安定収益
個別サポートを評価した顧客は離反しにくく、安定的に売上が積み上がる。 - 顧客コミュニティの形成
丁寧な対応で得られた信頼は、口コミや紹介につながり、新規ユーザー獲得コストを抑えられる。 - 追加機能・新規事業の再投資がしやすい
黒字を維持しながら新規領域に投資できるため、経営リスクを最小限に抑えられる。
大手が築いた市場フレームを活用しつつ、後発ソリッドベンチャーはこのような“じわじわ拡張”で大手にはまねしづらい顧客親和性を構築するのです。
後発参入を“追い風”に変えるために
結論として、後発で市場に入ることにはもちろんハードルがあるものの、“大手が拾えない細分化されたニーズを埋める”という強力なチャンスが存在します。ソリッドベンチャーならではの地道なキャッシュフロー運営やきめ細やかな対応力があれば、短期的な競争力不足を補うことが可能です。
- 市場分析で大手の弱点(低単価案件や特殊要望など)を特定
- 小規模から黒字を出す収益モデルを設計し、無理なく拡大
- 顧客フィードバック重視で対応スピードを武器にし、継続利用を促す
こうしたアプローチができれば、後発参入であっても長期的に大手と並ぶ—or 上回る—ポジションに進むケースは十分にあり得ます。成熟市場であればあるほど、その“隠れた余白”を見つけ出しやすいからです。ソリッドベンチャーはまさに、この“追い風”を上手に活かして長く堅実に伸びていくモデルと言えるでしょう。
“地道な拡張”が描く未来
今後も多くの業界で大手による市場形成が進む中、細分化された要求に応える“ソリッドベンチャー型”企業の台頭がさらに加速していくと考えられます。後発という立場を逆手に取った着実な成長と、顧客に寄り添ったサービス改善こそが、大型競合には実現しにくい“持続的な差別化”となり、市場の多様化を支えていくことになるでしょう。