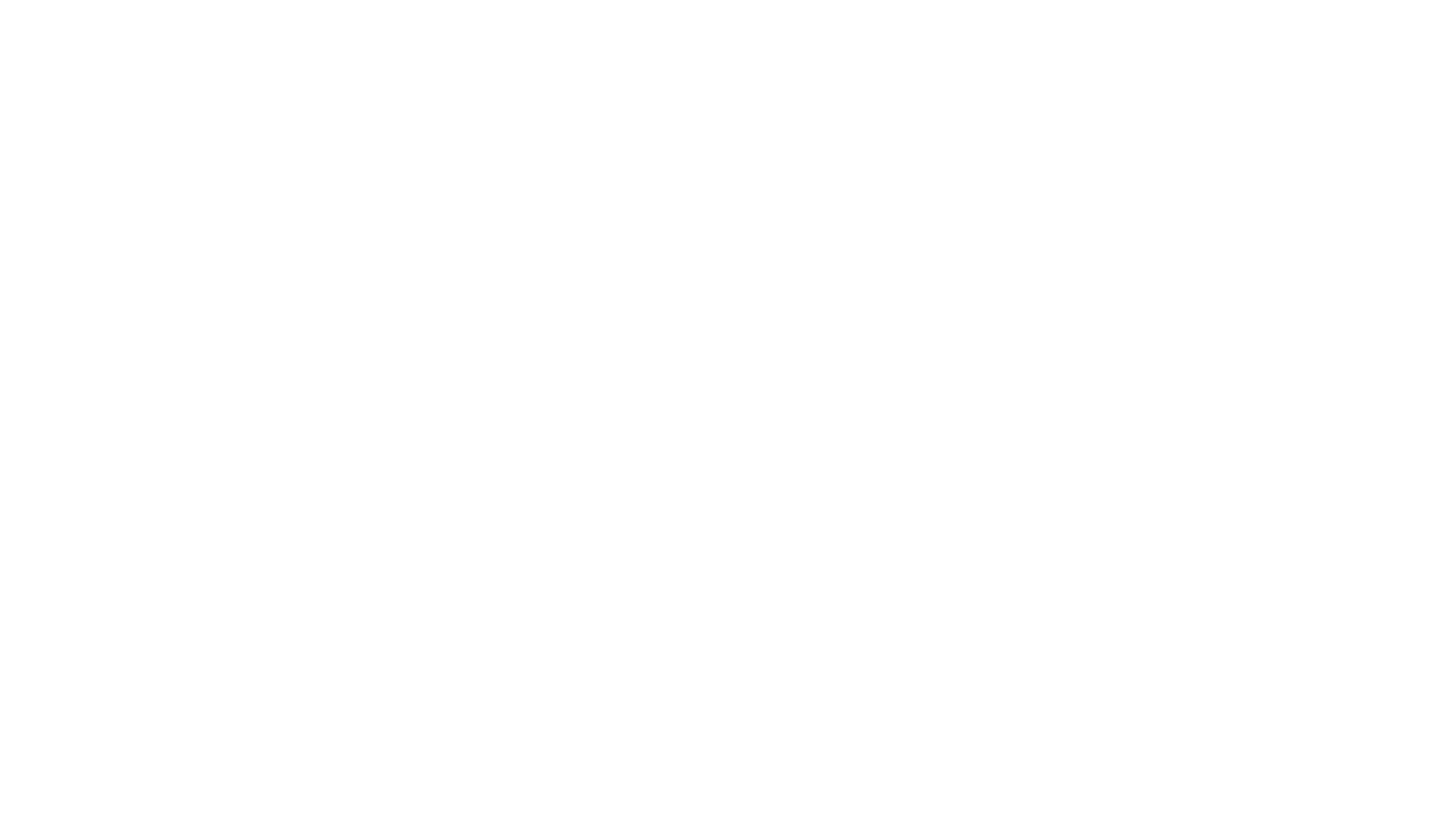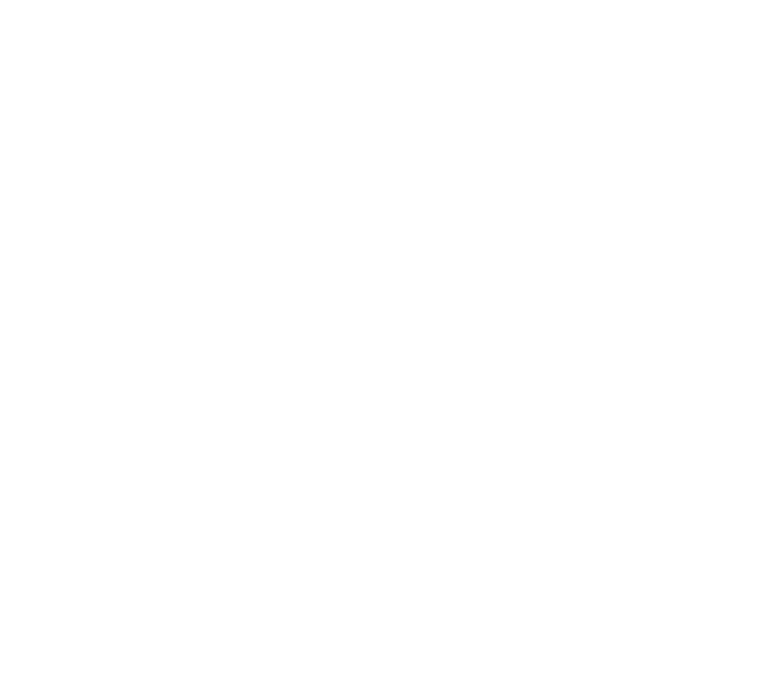- #ソリッドベンチャー
- #成長戦略
- #新規事業
ソリッドベンチャーが選ぶ垂直統合の魅力と可能性
公開日:2024.11.19
更新日:2025.3.26
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠
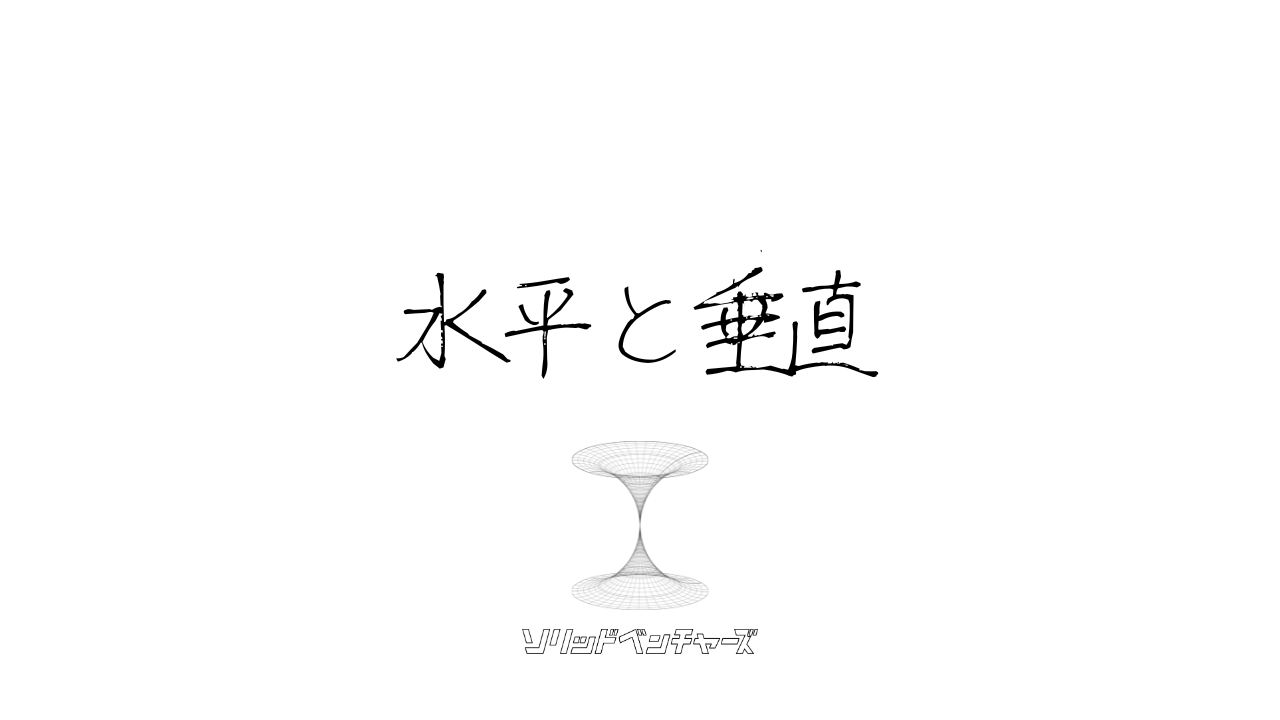
ソリッドベンチャーとは、創業初期から地道に安定収益を築き、その安定基盤を足がかりに段階的に成長していく企業形態です。競争が激しいマーケットを勝ち抜き、さらなるシェア拡大を目指すために多くの企業が模索する戦略のひとつが「垂直統合」。サプライチェーンの上流から下流にかけて、自社の管理体制を敷くことで品質維持やコスト削減、顧客体験の向上を同時に狙えると言われています。本稿では、“ジワ新規”という段階的な成長アプローチと垂直統合の組み合わせが、なぜソリッドベンチャーのビジネスモデルを強固にしうるのかを、事例をまじえながら探っていきます。
ハイライト
- 安定収益をもつソリッドベンチャーだからこそ、垂直統合の大きな投資リスクを段階的に回避できる
- “ジワ新規”で部分的に内製化を進めながら市場の反応を検証し、スケールアップを図る手法が有効
- サプライチェーン全体を自社で掌握することで、コスト最適化と顧客満足度の向上を同時に実現
ソリッドベンチャー × 垂直統合が注目される理由
安定収益のある企業だからこそ踏み込める統合戦略
スタートアップのなかには、大規模な投資を伴う垂直統合に挑んだものの、資金難やオペレーション負荷で頓挫してしまう例が少なくありません。そこで光るのがソリッドベンチャーの存在。彼らは創業初期から安定したキャッシュを生み出す事業を持ち、それを元手に段階的に垂直統合を進められる強みを備えています。
- ネオキャリア社は国内人材関連ビジネスで確固たる売上を築き、東南アジアの企業買収や新サービス統合を徐々に実施してきました。これも安定収益があったからこそ成し得た戦略と言えます。
“ジワ新規”がリスクを抑えるカギ
ソリッドベンチャー独特の「ジワ新規」とは、既存資産(顧客基盤・ノウハウ・キャッシュ)を活かし、大幅なリスクをとらずに新規事業へ浸透していく手法。その考え方を垂直統合にも応用すれば、一気にフルスタックを掌握するのではなく、「まずは一部工程だけを内製化し、様子を見ながら統合領域を拡張していく」という段階的アプローチが実現します。
これにより、もし計画通りにいかなかったとしても、既存事業からのキャッシュフローでダメージを吸収しやすく、失敗のリスクを最小限に抑えられるというわけです。
垂直統合がもたらすメリットと成長へのインパクト
サプライチェーンの可視化とコスト最適化
垂直統合を進める最大のメリットのひとつが、自社内でサプライチェーンの可視化が行いやすくなること。たとえば、レバレジーズ社はITとヘルスケアなど複数の人材サービスを手がけていますが、分業が進みがちな人材紹介の工程をなるべく内製化することでコスト管理を徹底。既存事業を安定基盤としながら、関連領域のサービス拡大と効率化を同時に実現しています。
- 外部委託や仲介を減らすことでコスト削減が期待できる
- 工程が把握しやすくなるため、クオリティ管理や納期対応が迅速化
結果として、顧客からの信用力がアップし、長期的な収益増に結びつく可能性が高まります。
マーケットニーズへの迅速な対応
垂直統合のもうひとつの利点は、顧客ニーズや市場変化への対応が早くなること。工程が分断されていると、市場からのフィードバックがダイレクトに届きにくかったり、改善施策を打ちづらかったりします。しかし、サプライチェーン全体を自社でコントロールしていると、
- 需要の変化をいち早く察知して製造・販売計画を修正
- 新たなサービスや製品開発を素早く判断・実装
が可能となります。
特に、創業初期から安定事業を育ててきたソリッドベンチャーの場合、このフットワークの軽さがビジネス成長の「第二のエンジン」となるでしょう。
“ジワ新規”で進める垂直統合のプロセス
まずは一部分を内製化する
ソリッドベンチャーが垂直統合を始める際に多いパターンとして、「まずは部分的に工程を内製化する」という段階があります。たとえば、従来外部に委託していた顧客サポートや物流管理の一部だけを自社に取り込み、効果測定を実施。そこで得たデータやノウハウをもとに徐々に拡大することで、大きな投資リスクを回避しながらステップアップが可能になります。
- オールコネクト社は回線販売から運用、カスタマーサポートまで段階的に取り込むことで、コールセンターなどの人材育成手法も確立。初期投資を抑えつつノウハウを蓄積しています。
既存事業のキャッシュフローを駆使する
安定収益を持つソリッドベンチャーだからこそ、大胆な統合にもチャレンジできるという点も見逃せません。キャッシュカウとしての既存事業から得られる利益を、次の工程内製化や設備投資に振り向けることで、外部からの多額な資金調達をせずとも成長サイクルを回せます。
- 一気に複数工程を買収・内製化しようとすると資金繰りに苦労するケースが多いですが、“ジワ新規”で進めることで毎期のキャッシュフローに合わせた投資が可能。
垂直統合を支える組織文化とマネジメント
コラボレーションを促進する社内体制
垂直統合によって部門間の連携度が格段に高まるため、社内文化も変革を迫られる場合があります。特に技術部門、営業部門、サポート部門など、それぞれが一気通貫で動けるような組織設計が求められます。
- 定期的な部門横断ミーティング
- 社員が全工程の大枠を理解できる教育システム
- 部門同士が相互評価し合う制度
こうした仕掛けを準備しておくことで、垂直統合がスムーズに進み、摩擦を最小限に抑えられるでしょう。
“顧客起点”で価値を再定義する意識
垂直統合の目的は、コスト削減だけでなく、顧客満足度の向上にもあります。製造・開発工程を内製化すると、顧客の声をダイレクトに反映できる一方で、「作ること」がゴールになりがちなリスクも。
ソリッドベンチャーとしては、既存事業で築いた顧客基盤をフル活用し、「顧客は何を本当に望んでいるのか?」を常に見極めながら、内製化やサプライチェーン管理の範囲を広げていくことが肝心です。事業の原点である“顧客価値”を失わないための定期的な振り返りが重要となります。
ソリッドベンチャーが描く垂直統合の未来
ソリッドベンチャーの最大の武器は、安定的なキャッシュフローを背景とした地に足の着いた成長戦略です。そこに垂直統合を掛け合わせることで、コスト構造の最適化と差別化された顧客体験の両面を手にしやすくなります。
- ネオキャリア社やレバレジーズ社のように、部分的に工程を自社内に取り込んでは実績を作り、段階的に全体を統合していく流れ
- 社内の連携強化で新サービスや派生事業が生まれ、さらなる収益源を育成
こうした動きは、経済環境や市場ニーズが刻一刻と変化する中でも柔軟に舵を切れる“しなやかな経営”を実現してくれるはずです。
最終的には、垂直統合を押し進めることでサプライチェーン全体が自社で可視化・制御できる状態を作り上げれば、リスク分散とビジネス拡張の両方を手堅く進められるという大きな利点があります。
ジワ新規で失敗の可能性を低減しながら、長期的ビジョンに沿って壮大なビジネスエコシステムを築く。これこそがソリッドベンチャーの強みを最大限に活かす垂直統合の醍醐味と言えるでしょう。