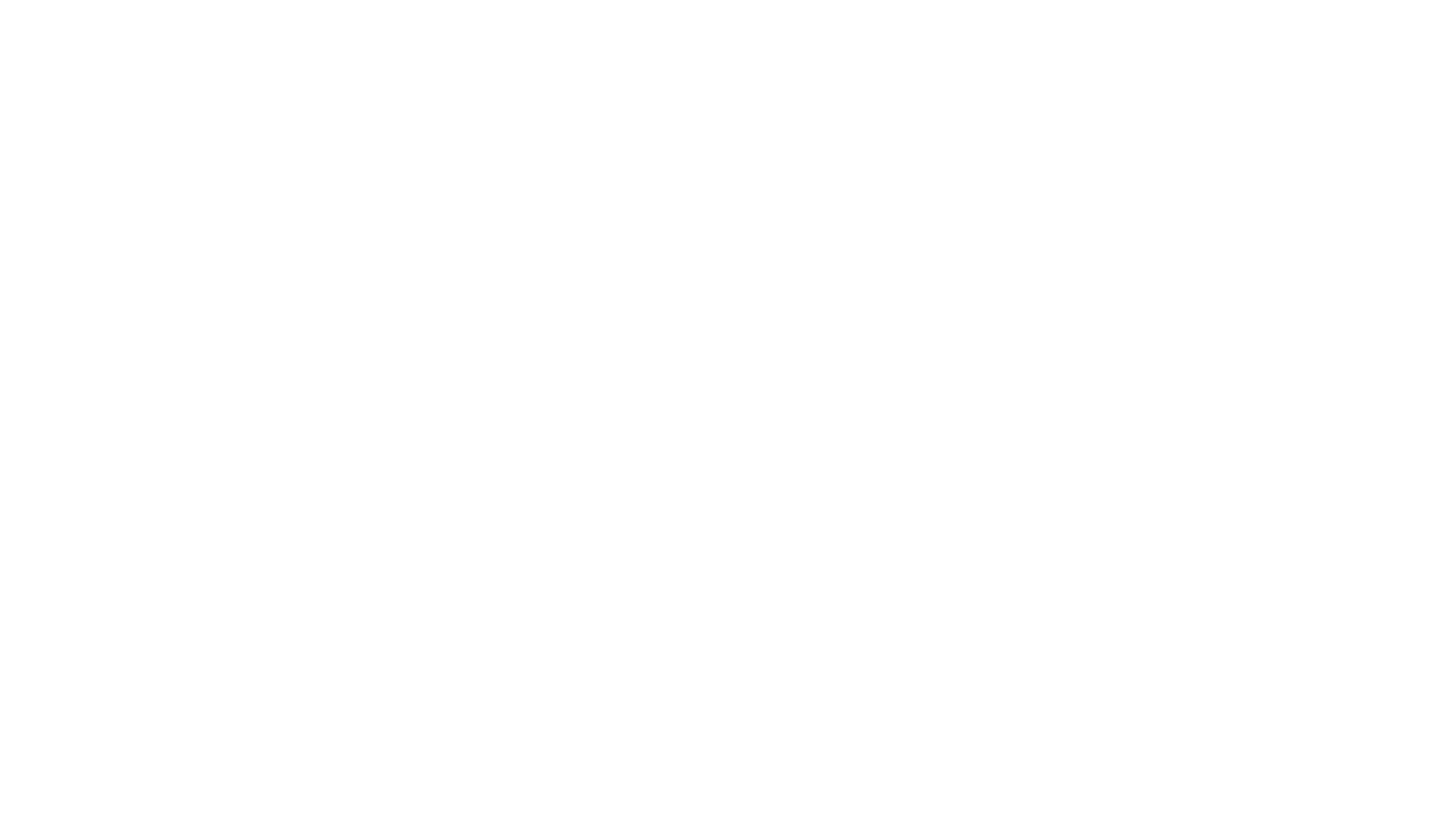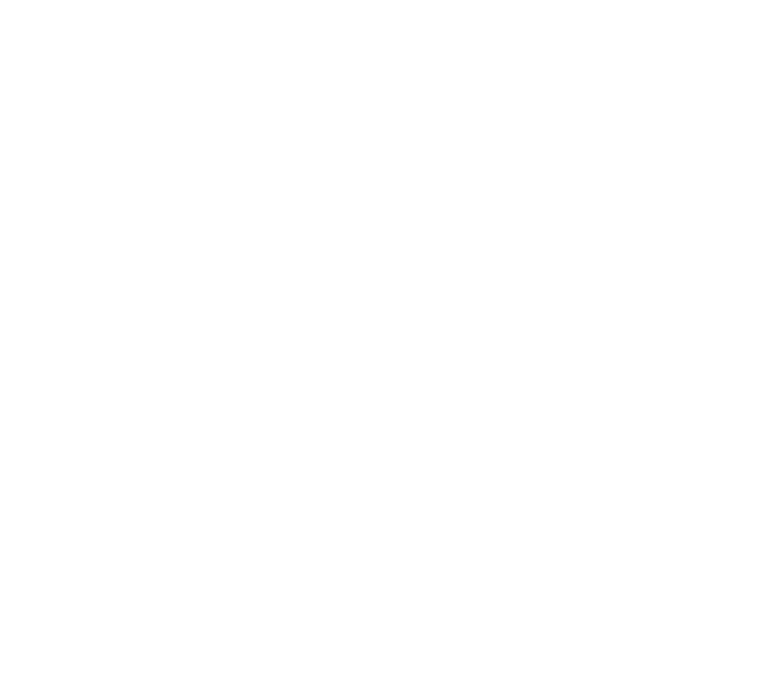- #ジワ新規
- #ソリッドベンチャー
- #収益モデル
ソリッドベンチャーの成長モデルは“じわじわ”דキャッシュカウ”で大きくなる?
公開日:2025.02.27
更新日:2025.11.12
筆者:

スタートアップ=「短期に巨額資金を調達して急拡大」というイメージが定着しがちですが、最近は“地味×安定”に黒字を重視し、じわじわ成長を遂げる「ソリッドベンチャー」にも注目が集まっています。受託開発やBtoB保守など、いわゆる“堅実ビジネス”を起点にキャッシュカウ(安定収益源)を育て、得た利益を新規事業やM&Aに回しながら数年単位で大きくなるモデルです。派手な広告投資をして一気にシェアを奪うわけではないため、倒産リスクは低く、創業者が株式を希薄化せずに長期視点の経営を貫ける利点があります。日本ではSHIFT社やナイル社などがこのスタイルで上場・ユニコーン級へと躍進し、多くの経営者に「VC依存ではない成長パターンもある」ことを示しています。本記事では、代表的なソリッドベンチャー5社の事例を通じて、“じわじわ成長”を可能にする仕組みやメリット・デメリットを詳しくひも解いていきます。スタートアップ一択だと思っていた方こそ、ぜひご一読ください。
結論(TL;DR):倒れない黒字源で学び続け、勝機だけを強く張る。
- ソリッドベンチャーという“状態”=黒字の安定源×学習ループ×再投資余力(資本政策の一貫性)
- キャッシュカウ→小規模検証→顧客横展開→選択的M&Aで、負けにくく勝ち切る
- 希薄化を抑えながらEPSを伸ばす運転(内部留保+デット)で創業者主導を貫徹
“じわじわ成長”דキャッシュカウ”とは?
ソリッドベンチャーが注目される理由
スタートアップと聞くと、多くの人は「VC(ベンチャーキャピタル)から大型の出資を受けて、赤字を垂れ流しながらでも急拡大する」イメージを抱くのではないでしょうか。
確かにこうしたモデルは、短期間で市場を席巻し、爆発的な成長を実現する可能性を秘めています。しかしその反面、投資家からのリターン要求が激しく、短期的なKPIを追い続けるプレッシャーが大きくなりがちです。
もし想定どおりに成長曲線が描けなければ、資金ショートから撤退せざるを得ないリスクも高まります。
一方で、近年注目されているのが、“地味×安定”をモットーに創業初期から黒字経営を重視するソリッドベンチャー型。大きな調達こそ行わないものの、受託やBtoB保守、人材派遣など地道にキャッシュを生むビジネスを柱に置き、そこから得た利益を再投資しながらじわじわ成長。
結果的に5〜10年スパンで時価総額1,000億円を超えるユニコーン級へ到達する例が、国内外で増えてきています。
“じわじわ成長”דキャッシュカウ”のキーワード
ソリッドベンチャー型が堅実に成長していくうえで欠かせないのは、以下の2つのキーワードです。
- じわじわ成長(ジワ新規)
短期的に巨額の赤字を掘ってシェアを奪うのではなく、段階的な拡大を重視します。既存事業で安定した収益を作りながら、新規サービスやM&Aに少しずつ投資するので、大きく倒れるリスクが比較的低い。 - キャッシュカウ(安定収益源)
ソリッドベンチャーが“急には儲からなそうだけど確実に黒字を生む”事業をまず手がけるのは、このキャッシュカウを育てるため。BtoB向けの受託や保守サービス、人材ビジネス、仲介業など、地味でも継続的に利益が見込める事業を軸に据えることで、無理なく事業ポートフォリオを拡張できます。
本稿では、いくつかのソリッドベンチャー事例を取り上げつつ、“じわじわ成長(ジワ新規)”דキャッシュカウ”のモデルがなぜ成功するのか、その背景と仕組みを整理してみます。
まとめると‥‥
ジワ新規=検証→拡張→横展開
① 黒字源泉で資金余力を確保
② 小規模プロダクトをPoCし、KPI達成次第スケール
③ 既存顧客へクロスセルしてCACを極小化
この3段ロケットが、ハイリスクな赤字投資を避けながら企業規模を何倍にも押し上げる基本構造だ。
ソリッドベンチャー5社の事例 ― ジワ新規のリアル
ここでは、上場済みのソリッドベンチャー企業の中から5社をピックアップし、どのようにキャッシュカウを活かして着実に成長しているのかを見ていきましょう。
SHIFT社 ― 品質管理の地道なオーガニック成長+M&A
創業事業:ソフトウェア品質管理(テスト事業)
SHIFT社は、ソフトウェアの品質保証・テストというニッチ領域を軸にスタートし、堅実に売上と利益を伸ばしてきたソリッドベンチャーです。ポイントは「品質管理」のサービスを“キャッシュカウ”として、M&Aを積極的に進めている点にあります。
- 既存顧客との信頼関係を深化
まずは品質管理の分野で顧客と長期的な取引関係を築き、安定収益を得られる状態を作った。 - “のれん負け”しそうなM&Aは絶対しない
SHIFT社は、高成長スタートアップを無理に買わず、買収後にすぐ黒字化できる小粒な企業を狙う方針を徹底。これにより財務リスクを最小化に。 - 新領域への拡大
テスト工程の周辺システムから基幹システムに広げるなど、段階を踏んで顧客深耕を進め、最終的にはIT業界全般を支援するプラットフォームを構築中。
SHIFT社の好例は、ニッチでも堅い領域でキャッシュを生み出し、それをM&Aや新事業に振り向けることで、じわじわと勢力を拡大している点にあります。
ナイル社 ― 受託(SEOコンサル)を起点に定額カーリースでブレイク
創業事業:SEOコンサルや広告メディア(Applive)
ナイル社は、創業当初からSEOコンサルやメディア運営で安定収益を確保し、そこから「定額カルモくん」というカーリース事業を立ち上げ、一気に成長カーブを描いた企業。
- SEOコンサルで黒字を確保
早い段階からSEOコンサル・広告メディアによる収益が安定し、自社で投資可能なキャッシュを生み出していた。 - 新規事業への再投資
自社メディアや広告ノウハウを活かし、カーリースの「定額カルモくん」を展開。広告費を抑えながら効率的にユーザーを獲得し、大きなJカーブを実現。 - “じわじわ”からの“バネ”
一見無関係そうなカーリース業界に乗り出しましたが、着実なキャッシュがあったからこそ、初期投資と事業拡大を焦らず行えた。
ナイル社の事例は、受託やメディアがキャッシュカウとして機能し、その余力をもって新規領域のチャレンジで成功を掴んだパターンを象徴しています。
うるる社 ― BPOを武器にSaaS「NJSS」でARR45億円超
創業事業:BPO(主婦向けクラウドソーシング)
うるる社は、労働集約型のBPOビジネスを起点に、クラウドワーカーによるデータ収集・入力などを行い、そこからSaaS「NJSS(行政入札情報サービス)」を開発してARR(年間経常収益)45億円を突破した企業。
- BPO=地味だが堅実な売上
主婦層を中心としたクラウドワーカー組織を構築し、継続的に受託業務をこなすことで安定利益を確保。 - クラウドワーカー活用でSaaS開発
入札情報など、自治体ごとにバラバラに管理されている公的情報を一括取得。月額課金モデルの「NJSS」をローンチし、高いARRを実現。 - “じわじわ”拡張し、他サービスにも波及
BPOで培った人的リソースを新しいSaaSや周辺事業に転用できるため、同社は次々とクラウドワーカー活用型プロダクトを増やしている。
受託のBPOがキャッシュカウとなり、その労働力を自社SaaSにレバレッジさせる発想が、“地味×安定”からのスケールアップを体現しています。
オロ社 ― 受託から始めてERP「ZAC」を外販、大ヒットでIPO
創業事業:ウェブ&システム受託開発
オロ社は、創業当初はウェブ制作・システム開発などの受託をメインに堅実に売上を積み上げてきました。その後、自社内で使っていた業務管理ツールを外販化してクラウドERP「ZAC」として急拡大し、2017年にIPOを果たした。
- 受託がキャッシュカウ
受託開発の安定収益により、投資余力を維持。赤字を大きく掘ることなく新プロダクトの企画・試作を続けられた。 - 自社課題→製品化
自分たちの受託プロジェクト管理に使っていたツールが他社でもニーズがあると気づき、クラウドERPとして商品化。 - 既存顧客からの信頼で導入加速
自社ツールという実績・ノウハウが評価され、中小から大企業まで導入が進んだ結果、ライセンス収入も大幅に拡大。
地味に見える受託こそがキャッシュカウとなり、その上にイノベーションを積み上げて“ERP企業”として大きく飛躍した典型例。
M&A総研ホールディングス社 ― M&A仲介を軸にユーザー資産をクロスセル
創業事業:M&A仲介(完全成功報酬制)
M&A総研HDは、M&A仲介を完全成功報酬型で提供し、短期間で売上高165億円・時価総額1,300億円超を達成した上場ユニコーン。
- 仲介手数料をキャッシュカウ化
仲介ビジネスは一件一件の手数料が大きく、しかも完全成功報酬制で新興企業として後発参入しやすかった。 - 組織全体をデジタル・AIで効率化
伝統的に“属人的”とされるM&A仲介業務をデジタルツール導入で最適化し、無駄な赤字を出さない。 - 顧客(売り手・買い手)へのクロスセル
一度仲介で接点を持った企業に対し、資産運用支援やDXコンサルなどを追加提供し、多角化と収益アップを実現。
赤字を掘らずとも、M&A仲介だけで安定キャッシュを生み、それをもとに新たなサービスを展開しながら着実に拡大した点が非常にソリッドベンチャー的。
ソリッドベンチャーが“じわ”דキャッシュカウ”で伸びる仕組み
キャッシュカウで投資余力を確保
ここまでの事例を見ても分かるように、ソリッドベンチャー型の最大の特徴は赤字拡大を許容せず、まずは地味でも利益を確保できるビジネスモデルを構築すること。これにより、
- 銀行融資(デットファイナンス)が受けやすい
- ベンチャーキャピタルからの出資に頼らずとも、新規事業やM&Aに充てる資金を捻出できる
- 投資家のExit圧力が小さく、経営コントロールをしっかり保てる
たとえばSHIFT社なら品質管理事業が、うるる社ならBPOが、オロ社なら受託開発が最初のキャッシュカウとなっています。“最初の地味なビジネスこそが会社を大きくする原動力”というのが、ソリッドベンチャーの共通した戦略なのです。
積み重ねた利益を“ジワ新規”に投入
スタートアップであれば数十億円の調達を一気に行い、一年のうちに大規模マーケティングをしかけることもあります。しかしソリッドベンチャーは、キャッシュカウで稼いだ利益を再投資しながら、段階的に新事業を拡大していくのがポイント。
- ナイル社:SEOコンサル→メディア事業→定額カルモくん
- うるる社:BPO→クラウドワーカー活用SaaS(NJSS)→周辺サービス連発
- SHIFT社:品質管理→周辺システム→M&Aで周辺領域拡充
この流れを指して“ジワ新規”と呼んでいます。既存顧客やアセットを活用して開発・販売できるため、大規模な赤字投下を最小限に抑えつつ、“じわじわ”と新市場を獲得していきます。
M&A・クロスセルで安定拡大
さらに、多くのソリッドベンチャーが小さめのM&Aや周辺領域へのクロスセルを繰り返しています。SHIFT社やM&A総研HDのように、
- 高額バリューでのれん負けリスクが大きい企業は対象外
- すぐに連結黒字化できる案件のみ買収
- 既存顧客に横展開できるシナジーを狙う
という鉄則を貫くことで、倒産リスクを最小化しながらサービスラインを拡張し、じわじわ経営規模を大きくしていきます。
メリットとデメリット ― 爆発力はやや薄いが、失敗が少ない
メリット
- 倒産リスクが低い
創業初期から黒字を重視するため、キャッシュが枯渇してすぐ撤退、というシナリオが起こりにくい。 - 経営コントロールを保持しやすい
VCによる大株主化を避ける傾向が強く、創業者や経営陣が大株主として、長期視点の戦略を貫きやすい。 - 希薄化リスクが低く、EPS成長に寄与
上場後も公募増資を頻繁に行わず、1株あたり利益(EPS)が自然に高まりやすい。株価の安定成長が見込める。 - 事業ポートフォリオを着実に広げられる
キャッシュフローが堅いため、新規事業やM&Aがコケても会社全体へのダメージが少ない。長期的な多角化が可能。
デメリット
- 爆発的なシェア獲得は難しい
スタートアップのように「とにかく短期集中投下で市場を一気に奪う」という作戦を採りにくい。 - 大手競合に蹂躙される可能性
資金力に物を言わせた広告攻勢が必要な局面では不利になりがち。 - 地味なビジネスゆえの人材確保課題
成長企業といえど、華やかな投資を繰り返すスタートアップと比べると魅力が伝わりにくく、優秀人材の採用に苦戦するリスク。
地味×安定こそが“じわじわ成長”を生む
“キャッシュカウ”モデルがもたらす安定性
事例で見たとおり、ソリッドベンチャーは地味でも安定収益をもたらす事業を起点に、長期的な拡大を実現するモデル。SHIFT社やナイル社、うるる社、オロ社など、いまや時価総額数百億〜1,000億円超の企業が少なくありません。受託やBPO、保険、仲介など、派手さはないビジネスこそが“会社を支える土台”となり、新規事業やM&Aに挑戦する資金・時間的余裕を生み出しています。
スタートアップ型が正解とは限らない
一気に世界市場を狙うなら、大型調達によるハイリスク・ハイリターンのスタートアップ型も有効でしょう。しかし、
- 倒産リスクを極力抑えたい
- 創業者としての経営コントロールを維持しながら成長したい
- 長期的にEPSを上げて株主価値を高めたい
こうした考えを持つ起業家には、ソリッドベンチャーの選択肢がマッチしやすいのです。市場特性や事業の性質にもよりますが、安定経営×中長期視点を望むなら、ソリッド型も十分に“成功ルート”となり得ます。
今後の潮流は?
近年、世界的にスタートアップ投資が落ち着きを見せる一方で、“安定した黒字ビジネスを育てる”動きが再評価されています。特に日本国内では、老舗の受託・保守・仲介などで確実に儲けながら、じわじわ拡大してIPOする企業が増えています。
ベイカレント・SHIFTのように時価総額1兆円級へ成長する例も登場し、ソリッドベンチャー型の魅力はますます注目されるでしょう。
- ソリッドベンチャーは資本効率こそ激的ではないかもしれませんが、株式希薄化を最小化でき、創業者・経営陣が長期視点を失わずにいられるのが強み。
- IPO後も大きな舵を切りやすく、M&Aで事業領域を広げる余地が大きい。
結論として、「地味×安定」にみえる事業こそが、企業を大きく飛躍させる基盤になるのです。華やかなスタートアップモデルが唯一の成功ルートとは限らない――多くのソリッドベンチャーが実証してきたように、キャッシュカウで黒字を守りながら、時代やニーズを捉えてじわじわ成長する戦略は、今後も有力な選択肢になるはずです。SHIFT社やうるる社のように、最終的にユニコーン級に到達する事例が増えれば、さらにこの流れは加速するのではないでしょうか。
「短期的に稼いで早期売却」というゴールに囚われず、中長期で着実に積み上げる“ジワ新規”モデルこそが、自社の強み・社内カルチャー・創業者のビジョンを最大限に活かせるかもしれません。あなたの事業にフィットするのはどちらか? 改めて考えてみる価値は十分にあるはずです。
今こそ“じわじわ×キャッシュカウ”を再評価する時
短期勝負の資金市場が揺らぐいま、倒れず・希薄化せず・EPSを積み上げるソリッドベンチャー型は再び存在感を強めている。
- 地味でも確かな黒字ビジネスを磨き
- 顧客の未充足ニーズに小さく挑戦し
- 好機には内部留保とデットを梃子に一気に拡張する
この“三段活用”こそ、SHIFTやKeePer技研、Mailchimpが証明した普遍モデルだ。華やかなVCモデルと比べて派手さはない。だが、負けにくい道を選びながら最後に大きな果実を得るという選択肢があることを、いまこそ経営者・起業家は思い出していい。