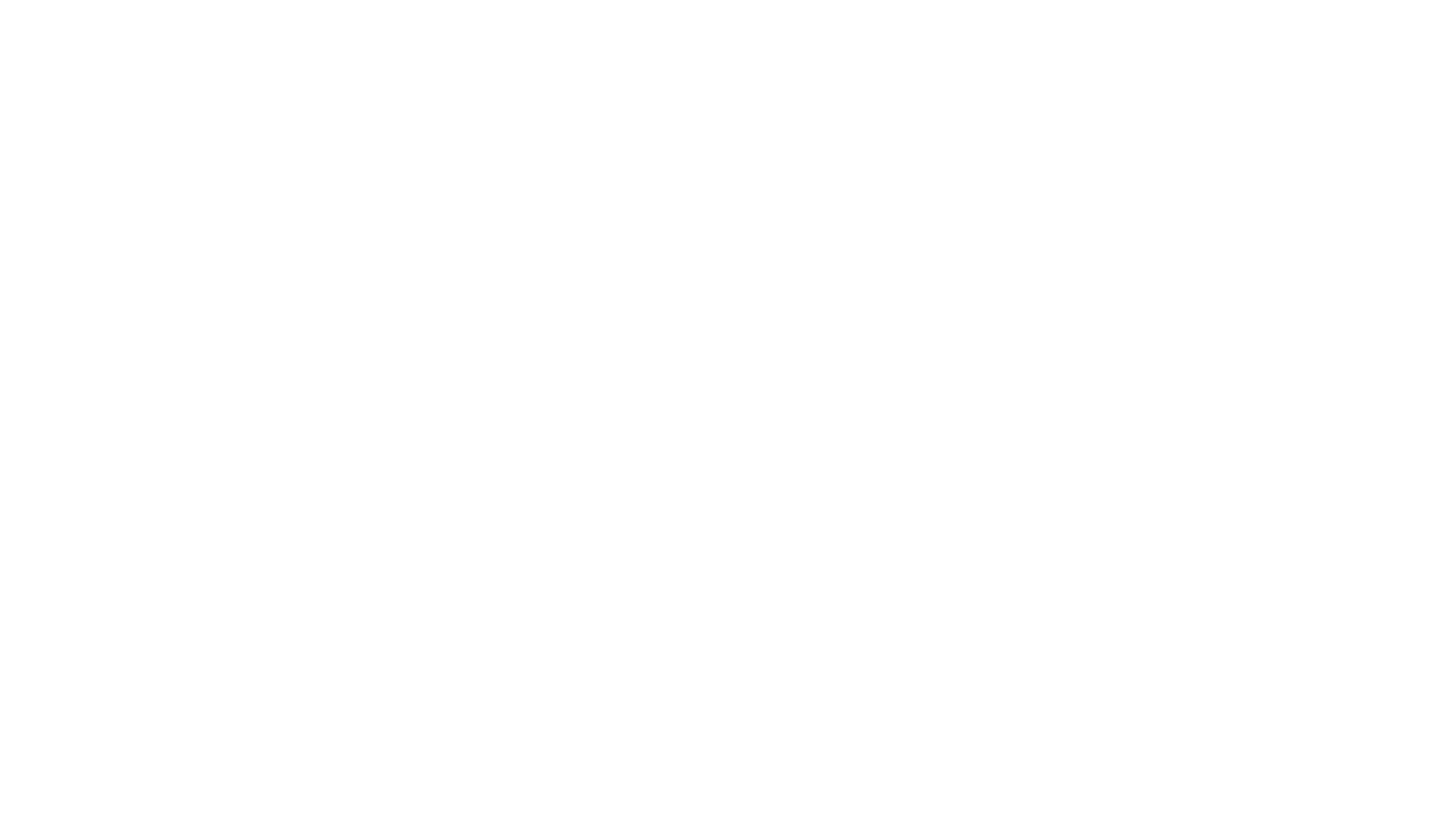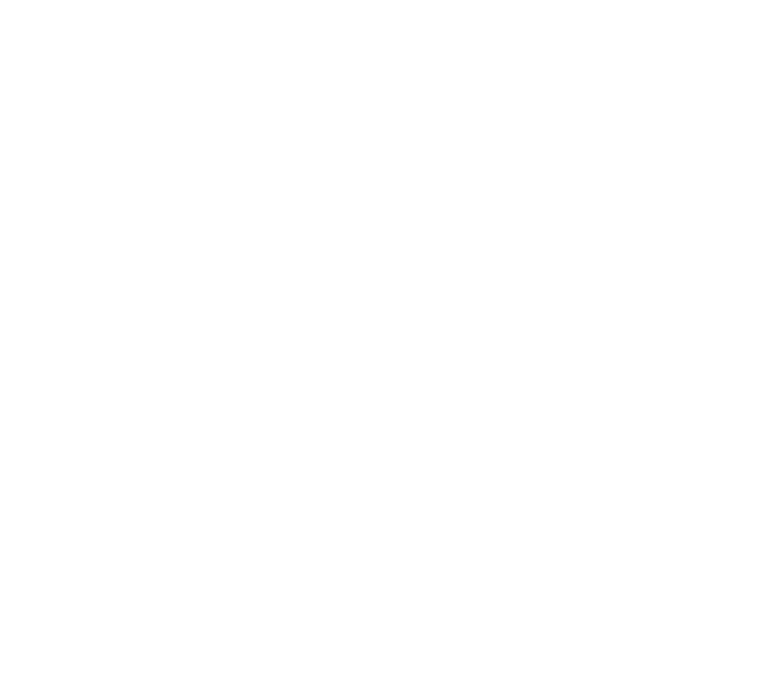- #ソリッドベンチャー
- #成長戦略
ソリッドベンチャーがターゲット市場を拡大する方法
公開日:2024.11.19
更新日:2025.3.26
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠
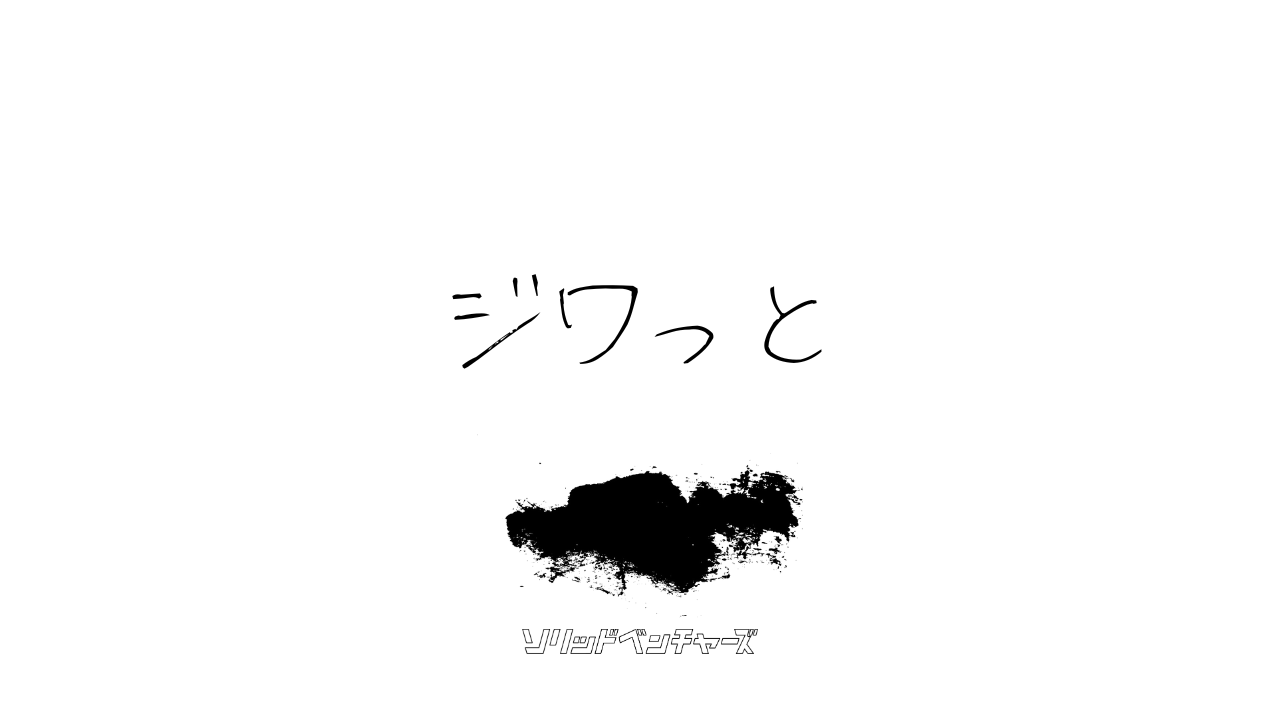
大きな資金調達に頼らず、安定した黒字経営をベースに徐々に成長を遂げていく――これが「ソリッドベンチャー」の特徴です。とはいえ、堅実路線だからといって成長を止めていいわけではありません。どのようにして既存事業から新たな市場へ足を踏み出すのか?本記事では、隣接領域へのジワジワ拡大やターゲット顧客の再定義など、ソリッドベンチャーならではの市場拡大アプローチを紹介します。
ハイライト
- 黒字基盤を強化しながら、隣接領域に“少しずつ”進出してマーケットを拡張
- 既存顧客との信頼関係やアセットを活用し、セグメント拡張・ターゲティングを再定義
- 新市場ニーズに柔軟に対応する“ジワ新規”戦略で、リスクを抑えた持続的成長を実現
まずは“黒字基盤”で安定収益を固める
コア事業の強化が拡大の起点
ソリッドベンチャーが新市場に挑戦する前に欠かせないのは、既存事業の黒字安定化です。たとえば労働集約型の受託開発やコンサル事業は大きな爆発力こそないものの、需要が底堅く、比較的早期から黒字化しやすいのが特長。
- オロ社の事例
- 創業期はウェブ受託開発で着実に売上を積み上げ。
- その安定収益をベースに、受託開発で得た業務ノウハウを自社ERP「ZAC」に落とし込み、大幅成長へ繋げました。
要するに、「まず稼ぐ土台をしっかり築いてから、次の成長路線を描く」ことがソリッドベンチャーにとっての鉄則になります。
キャッシュフローが“ジワ新規”の原資
既存事業の収益が黒字基盤として確立されると、そこから生まれるキャッシュを使って段階的な新規投資が可能となります。リスクの高い大勝負を避けながらも、安定基盤があることで周辺領域への進出を検討しやすくなるのです。
隣接市場への“ジワ新規”アプローチ
アンゾフ的視点で少しずつずらす
ソリッドベンチャーは、スタートアップのように一気に新事業へ飛び込むのではなく、既存顧客×新商品や新顧客×既存商品など「隣接」した方向へ徐々に動きます。
- ミギナナメウエ社のHR拡大
- 採用コンサルから始まり、SES事業や転職支援など“人材関連”の隣接マーケットへ段階的に進出。
- 無理なく事業を横に広げつつ、組織体制を強化しています。
新規投資の“スモールスタート”でリスク回避
ジワ新規の場合、追加投資も小規模から試して市場の反応を見ることができるため、大きな失敗を回避しやすい利点があります。これが、キャッシュをいきなり数十億単位で投下するような“ド新規”とは違う、ソリッドベンチャー独特の成長スタイルです。
ターゲティングの再定義で市場拡張
既存顧客の“上位セグメント”や“周辺顧客”へ進出
ターゲット顧客を微調整することで、新しいセグメントを獲得できます。たとえば、はじめは小規模企業向けだったサービスを大企業向けにアップデートする、あるいは業界特化型から別の業界へノウハウを転用するなど、多様なやり方があります。
- GENOVA社の医療領域展開
- 中小のクリニック向けウェブ制作から、バーティカルメディアや自動精算機導入支援などを追加。
- 大手病院グループや他の関連サービスへも応用し、営業範囲を広げています。
サービス拡充×顧客層拡大の相乗効果
既存顧客への上位サービスや、まったく新しい顧客層への提供など、サービスとターゲットの両面でアップデートしていくのがソリッドベンチャーの常套手段。
- レバレジーズ社
- 当初はITエンジニア向けSESが中核→そこから看護師や介護職、海外就労支援まで横展開。
- 同じ「人材」というコアコンピに基づき、強みを他セグメントへ転用している形です。
顧客ニーズ起点の柔軟なサービスアップデート
直接的なヒアリングで現場の課題を把握
ソリッドベンチャーは派手なマーケ投下よりも、既存顧客との密なコミュニケーションを重視します。これにより、「◯◯が足りていない」「△△を自社で導入したいがノウハウがない」といった課題を早期にキャッチし、新規サービスへ落とし込めます。
- INTLOOP社のDX支援拡大
- 製造業向けITコンサルで蓄積した知見を基に、顧客の「エンジニア不足」や「システム刷新」などを補う形で事業を拡充し、フリーランス人材マッチングやDX推進に対応。
“ジワ新規”だけでなく“ド新規”も可能にする安定基盤
通常は隣接領域へのジワ新規がメインですが、黒字基盤が十分に確立されれば、思い切った“ド新規”にも挑戦しやすくなります。
- オロ社のERP化
- 受託開発で安定売上を確保したうえで、まったく新しいビジネスモデルとも言える自社ERPの開発にリソースを投下。
- リスクをかけた挑戦でも、失敗時のダメージを抑えやすいのがソリッドベンチャーの利点です。
市場拡大を支える組織と人材採用の工夫
安定経営がもたらす“採用メリット”
ソリッドベンチャーは、未上場であっても比較的早期から黒字を実現しているため、「倒産リスクが低い」「腰を据えて新規プロジェクトに取り組める」といった魅力を人材採用で打ち出せます。
- Grand Central社の例
- 営業コンサルを軸に着実に黒字を積み上げることで、新卒や中途採用でも“安定×チャレンジ”のバランスをアピール。
- 結果的に優秀な人材が集まり、営業領域をさらに横展開できる体制を整えています。
組織全体での“学習能力”向上
新たな顧客領域へ入る場合、未知のノウハウを吸収できる仕組みが必要です。プロジェクトごとのナレッジ共有や新規事業チームの自主性など、社内で学習サイクルを回す工夫が欠かせません。ここでも、黒字基盤による資金余力が大きく役立ちます。
ソリッドベンチャー流ターゲット市場拡大のキーポイント
- 既存事業を安定化させる
- 受託開発・コンサル・代理店など、早期からキャッシュを生むビジネスを強化し、黒字基盤を固める。
- 受託開発・コンサル・代理店など、早期からキャッシュを生むビジネスを強化し、黒字基盤を固める。
- 隣接領域や顧客層を“ジワ新規”で広げる
- アンゾフ的に少しずつずらしながら新市場を探り、成功の確度を高める。
- アンゾフ的に少しずつずらしながら新市場を探り、成功の確度を高める。
- 顧客ニーズを拾い柔軟にサービスをアップデート
- 安定収益の恩恵で大きな投資リスクを避けつつ、開発方針を迅速に修正できる環境を整える。
- 安定収益の恩恵で大きな投資リスクを避けつつ、開発方針を迅速に修正できる環境を整える。
こうしたアプローチにより、オロ社が受託開発からERPビジネスを成功させたり、GENOVA社が医療機関向けウェブ制作から周辺領域へ拡張しているように、ソリッドベンチャーは大規模な調達をせずともターゲット市場を拡大できるのです。
安定路線というと地味な印象を持たれがちですが、着実な黒字を土台にすれば、次々と新市場へ挑戦するための“攻めの投資”を行えます。リスクを抑えながら成長を積み重ねる“ジワ新規”こそ、ソリッドベンチャーの持続的成長を可能にする一番の強みといえるでしょう。