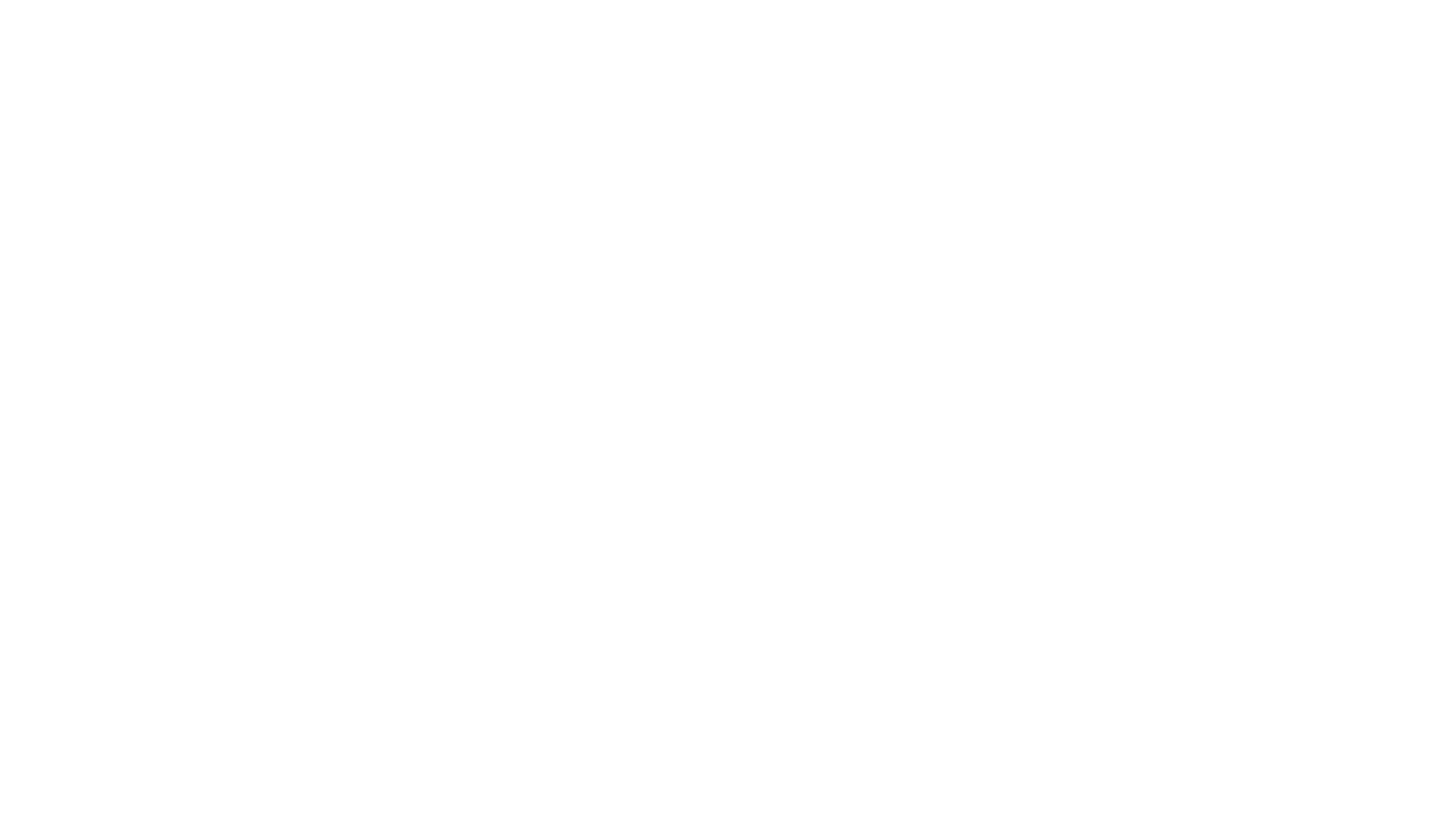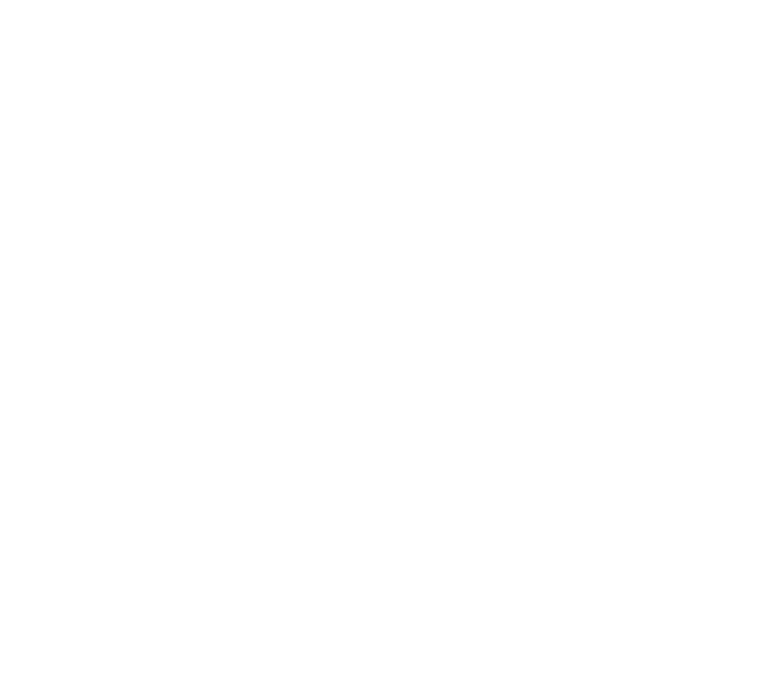- #ソリッドベンチャー
- #成長戦略
ソリッドベンチャーで成功するためのパートナー選定:成長を支える協力体制の秘密
公開日:2024.11.19
更新日:2025.3.26
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠
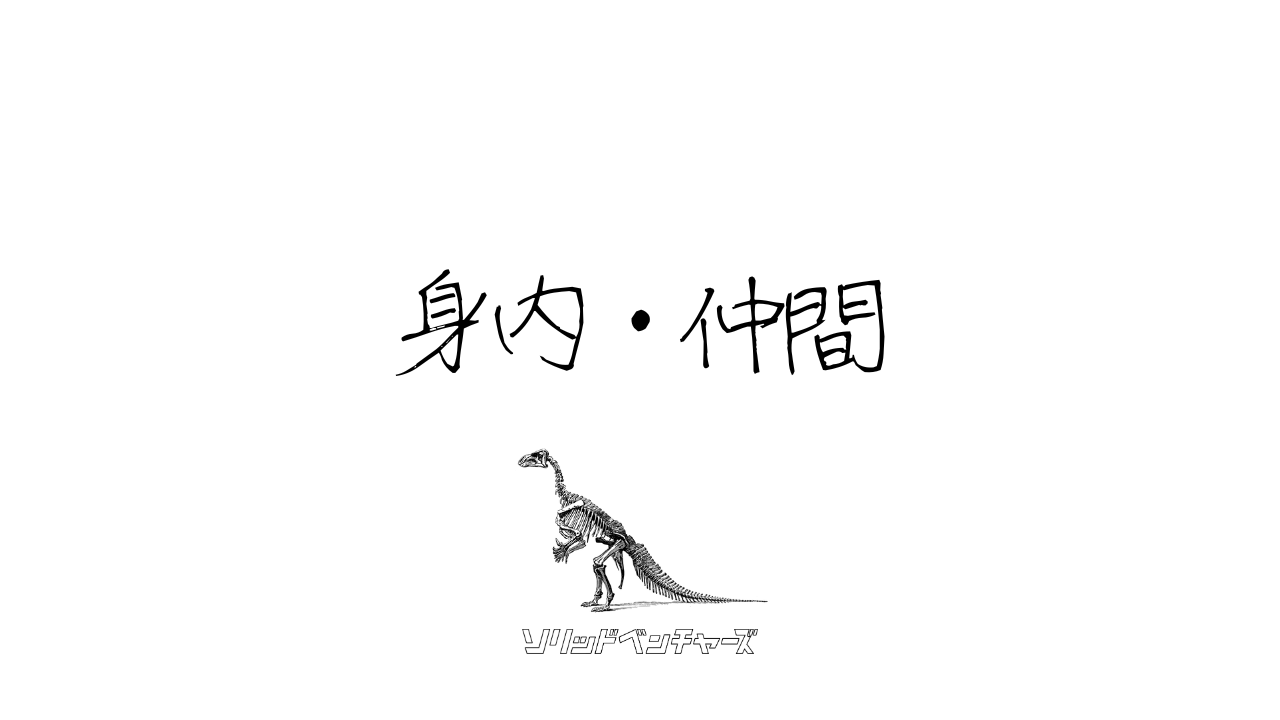
ソリッドベンチャーが成果を出す上で欠かせないのは、地道なキャッシュカウの確保と“ジワ新規”アプローチ。けれども、それを支える外部パートナーの存在も見逃せません。開発提携、営業支援、共同企画など、相手をどう選ぶかで事業スピードや広がりは大きく変わります。対スタートアップほどの爆速拡大こそ目指さないまでも、安定収益と段階的成長を両立させるソリッドベンチャーにとって、パートナーはまさに“成長エンジン”の重要ファクター。本記事では、パートナーシップを成功に導くための視点や事例を具体的に紹介し、地に足の着いた拡大を目指す企業に向けたヒントを提供します。
ハイライト
- ビジョン共有と専門性の組み合わせが、“1+1>2”のシナジーを生む
- 長期的な信頼関係&柔軟なコミュニケーションが、段階的な新事業推進を後押し
- “ジワ新規”のフェーズごとに必要なリソースを見極め、最適なパートナーと組む
なぜ“パートナー選び”がソリッドベンチャーのキーポイントなのか
単なる外注先ではない“協働モデル”が成長を加速
ソリッドベンチャーにとってのパートナーシップは、ただの外部委託やコスト削減ではありません。 むしろ、本業の強みをさらに強化したり、新規事業の可能性を広げたりする“協働モデル”として機能します。
例えば、ナイル社は自社のSEOコンサル・広告メディア事業で安定した収益を作ってきましたが、その先の「定額カルモくん」展開にあたり、広告・マーケ領域で伴走してくれる外部パートナーをうまく巻き込みました。こうした“専門性を掛け算”する形で、自社単独では難しかったスピード感を生むわけです。
“安定収益”をベースにじっくり選べる強み
スタートアップの場合、急激な赤字投資のリスクをとるため、短期で大きな成果を求めるVCなどの投資家を意識せざるを得ません。その結果、パートナー選びも投資家の意向が色濃く反映され、本来の事業ビジョンとズレるケースが見受けられます。
一方、ソリッドベンチャーは着実な黒字化を基本とし、投資家に振り回されにくい構造が強み。つまり、自社ビジョンを理解してくれるパートナーを時間をかけて探し、じっくり育む余地があるのです。
長期視点の協力関係が生む“リスク分散”と“柔軟性”
お互いのビジョン整合が前提条件
パートナーと手を組む際に重要なのは、お互いのビジョンをどれだけ深く共有できるか。短期的なKPIを追いかけるだけでなく、長期的に“どういう世界観を創りたいか”を擦り合わせると、多少の方針転換や市場変化があってもブレにくい関係に。
- 事例:FPパートナー社
- 保険・マネーコンサルを軸に成長しながら、KDDIなど大手企業との合弁を通して新しい金融サービスを展開。
- “顧客本位のFPサービス”というビジョンをパートナーとも共有していたからこそ、部分的な戦略転換にも柔軟に対応しつつ、強固な信頼関係を築けた。
トラブルや環境変化への迅速な共同対応
ビジネスにトラブルはつきものですが、ソリッドベンチャーは一発逆転より段階的成長を狙うモデルなので、途中の小さな障害でも致命傷にはなりにくい。一方で、パートナーともオープンかつ頻繁に情報交換する姿勢がないと、小さなミスマッチが積み重なって後々の大きなリスク要因になり得ます。
例えば、Grand Central社の営業コンサルチームでは、クライアントニーズの変化を常にパートナー企業とも共有し、必要ならサービス内容をピボット。早い段階での連携修正が、大きな混乱を防いできたそうです。これは、長期的な視点で一緒に走る“同士”のような関係性があってこそ機能する仕組みと言えます。
“ジワ新規”を成功させるパートナーシップのカギ
周辺領域への拡張=パートナーの力を借りる絶好の機会
ソリッドベンチャーの代表的成長スタイルである「ジワ新規」は、既存事業の顧客基盤やノウハウを活かし、新サービスを少しずつ追加していく戦略。ここでは、新規領域で必要な専門知識やリソースを持つパートナーと組むのが理にかないます。
- 例:ボードルア社
- SESやITインフラを軸にしつつ、コンサル領域へ拡大する段階で、外部パートナーから新市場の知見とコンサル人材を得てスムーズに“ジワ新規”を実現。
- これにより既存インフラ事業とのクロスセル効果も得られ、売上の安定と新収益の両立を実現。
リスクを最小限に抑えた実験⇒迅速なフィードバック
ソリッドベンチャーの魅力は“倒産リスクを下げながらの緩やかな成長”。パートナーとの共同実験(PoC)や一部顧客への限定リリースなど、小規模テストを繰り返しつつ学びを積むことで、大掛かりな失敗を防ぐことができます。
- M&A総研ホールディングス社
- 本来のM&A仲介に加え、資産運用やDXコンサルなど周辺サービスを展開。
- これらのサービス開始時に、外部の専門チームと連携しながら小規模実装→顧客の反応を見て最適化。
- “ジワジワ拡大”路線でもパートナーの協力があると市場投入がスピーディーになり、なおかつ安全に検証できる。
具体的なパートナー候補の選定ポイント
お互いの強みが重なる“シナジー領域”をまず明確化
ソリッドベンチャーはキャッシュカウ事業を持つため、“自社がすでにできること”と“今後やりたいこと”がハッキリしているケースが多い。そこに対してパートナーが提供できるリソースや技術、チャネルを整理し、「ここを組み合わせたらどんな新規ビジネスが生まれるか?」をイメージするのがスタートです。
- ポイント
- 専門性:技術領域、販売チャネル、法務・財務など
- リソース力:人材数、顧客基盤、海外展開ノウハウ
- 社風・ビジョン:長期志向か、短期成果重視か、など
信頼構築のためのコミュニケーション設計
良いパートナーを見つけても、日常的な連絡が不十分だと“ちぐはぐな関係”に陥りがちです。ソリッドベンチャーは通常のスタートアップよりも投資サイクルが長く、コツコツと改善するプロセスが重要。
そこで、定例ミーティングやオンラインコラボツールなど、双方が気軽に発言&相談できる場を設けることが成功を後押しします。
- 例:TWOSTONE&Sons社
- 創業事業(受託開発)の延長でメディアやマッチングプラットフォームを立ち上げ。
- それら新規事業のサポートを担う外部パートナーとは、月次で事業進捗を細かく擦り合わせる仕組みを構築。
- おかげで要望や不安を早期に共有し、大掛かりなトラブルを避けながら成長できた。
パートナー選定が“成長エンジン”になる理由
安定収益+新領域挑戦=パートナーがいるから回る“両輪”
ソリッドベンチャーの大きな強みは、既存事業で安定した利益を確保しつつ、新しい商機に投資できる点。ただし、新たな領域に踏み込む際のリスクや人的リソース不足は否めません。そこを埋めてくれるのが、自分にない武器を持ったパートナーです。
たとえばオロ社は、ERP製品をさらに普及させるため、導入コンサルを得意とする外部企業と戦略提携。結果として、単独で売り込むより短期間で導入実績を積み、知名度・実績ともに加速度的にアップしました。
長期的関係が生む“ブランド強化”と“高リピート”
ソリッドベンチャーは顧客ロイヤルティを重視しながら長期で成長するため、パートナーとの関係も“一時的な利益”ではなく“ブランド価値向上”を見据えたものが望ましい。
そのため、両社が協業によって得られる評判や顧客満足度を高め合うことが、結果的にリピートや紹介につながり、ブランド力を補強してくれます。既存顧客が「この会社ならではのネットワークとパートナーシップがある」と思ってくれれば、新たなサービスを提案しても信頼度が高まります。
着実に成長するソリッドベンチャーほど“強いパートナー”を持つ
ソリッドベンチャーは、一気呵成の資金調達で市場を取りに行くモデルではなく、既存事業を堅実に回しつつ、徐々に新規領域を開拓するスタイル。その過程で「どのパートナーと組み、どんなシナジーを生むか」が成長速度と安定性を左右します。
- ビジョンを共有できるかどうか―短期的KPIではなく、長期的なビジョンを融合
- 専門性やリソースを補完し合えるか―単なる外注先ではなく、ともに事業を作る協力体制
- “ジワ新規”フェーズへの柔軟なアプローチ―段階的検証とフィードバックでリスクを抑える
「ソリッドベンチャー=ゆっくり成長」ではありません。確かに爆速拡大はしないかもしれませんが、その分、盤石な基盤と低リスクでの事業拡張が実現しやすいのが強み。その鍵を握るのがパートナー選定です。
- M&A総研ホールディングス社が複数の専門家や企業と連携しながらサービスを拡充したように、
- ボードルア社がITインフラからコンサルへと領域を広げる際にパートナーを活用したように、
適切なパートナーとタッグを組めば、リスクを抑えつつ確実に飛躍する道筋を描けます。あなたの企業も、パートナー選びの視点を改めて点検してみませんか?
“地味だけど確実に利益を出す”という土台の上に、外部リソースを巧みに取り入れれば、思わぬシナジーが生まれるかもしれません。