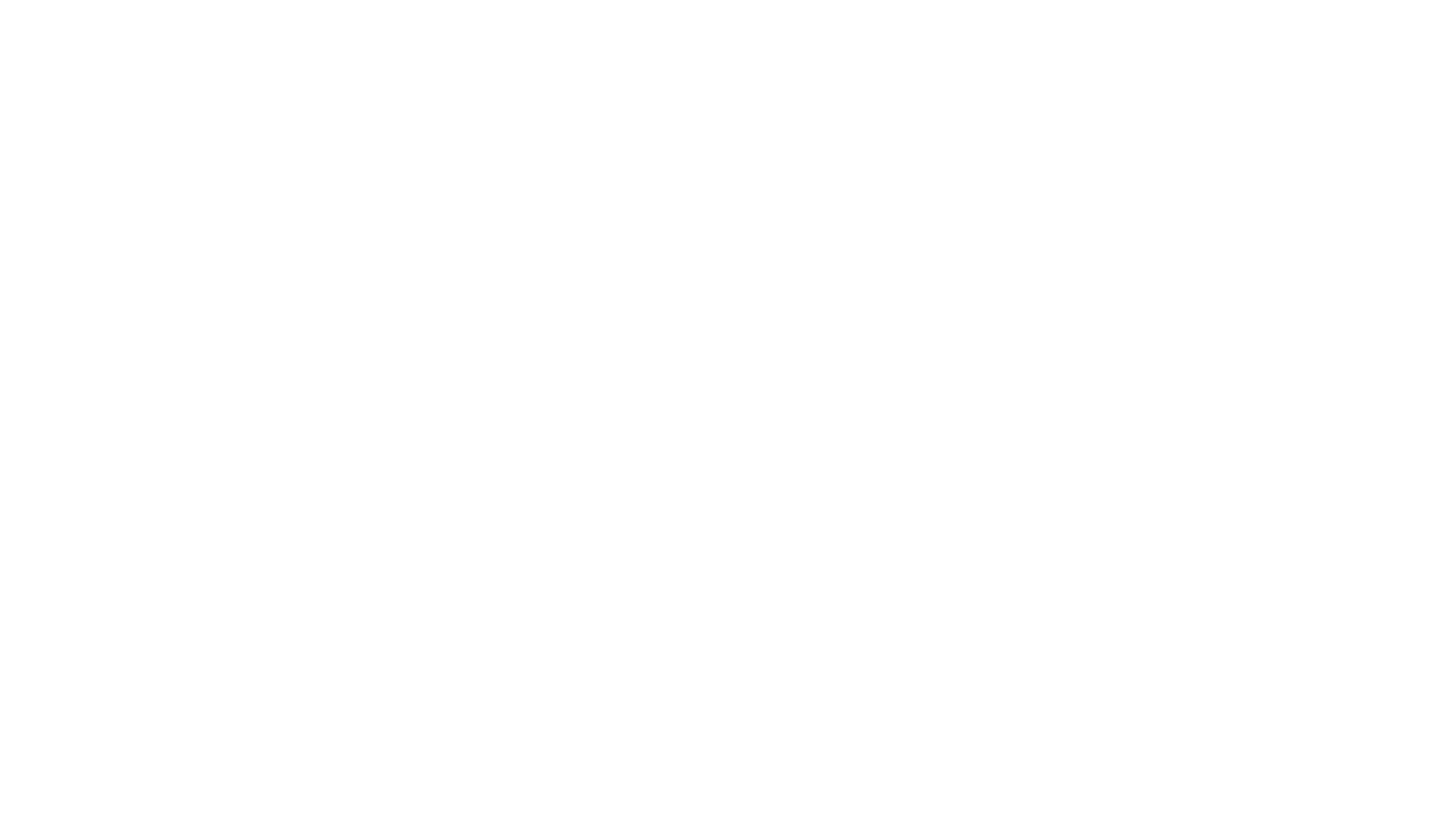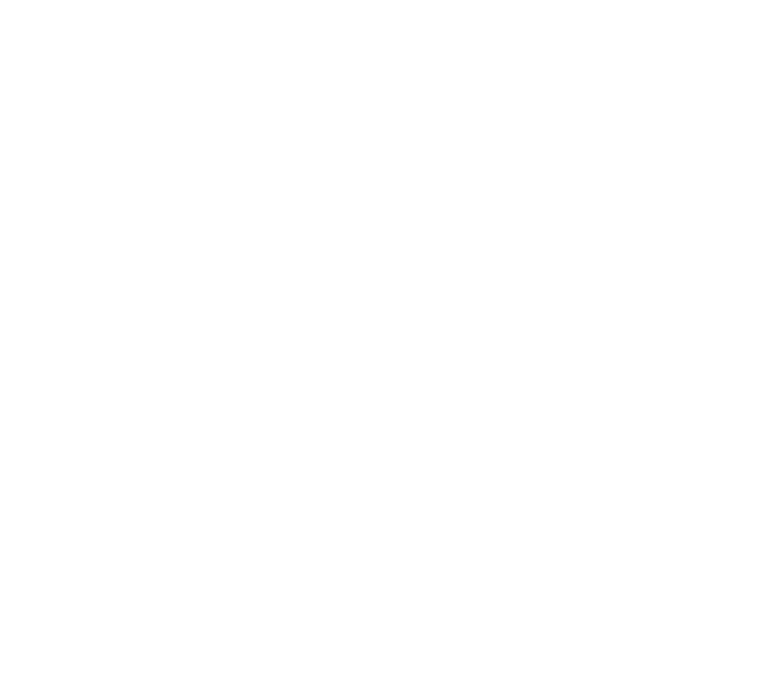- #スタートアップ
- #ソリッドベンチャー
- #ビジネスモデル
- #事例
なぜソリッドベンチャーがスタートアップよりも安定して成長するのか?
公開日:2024.09.19
更新日:2025.4.17
筆者:エンジェルラウンド株式会社 大越匠
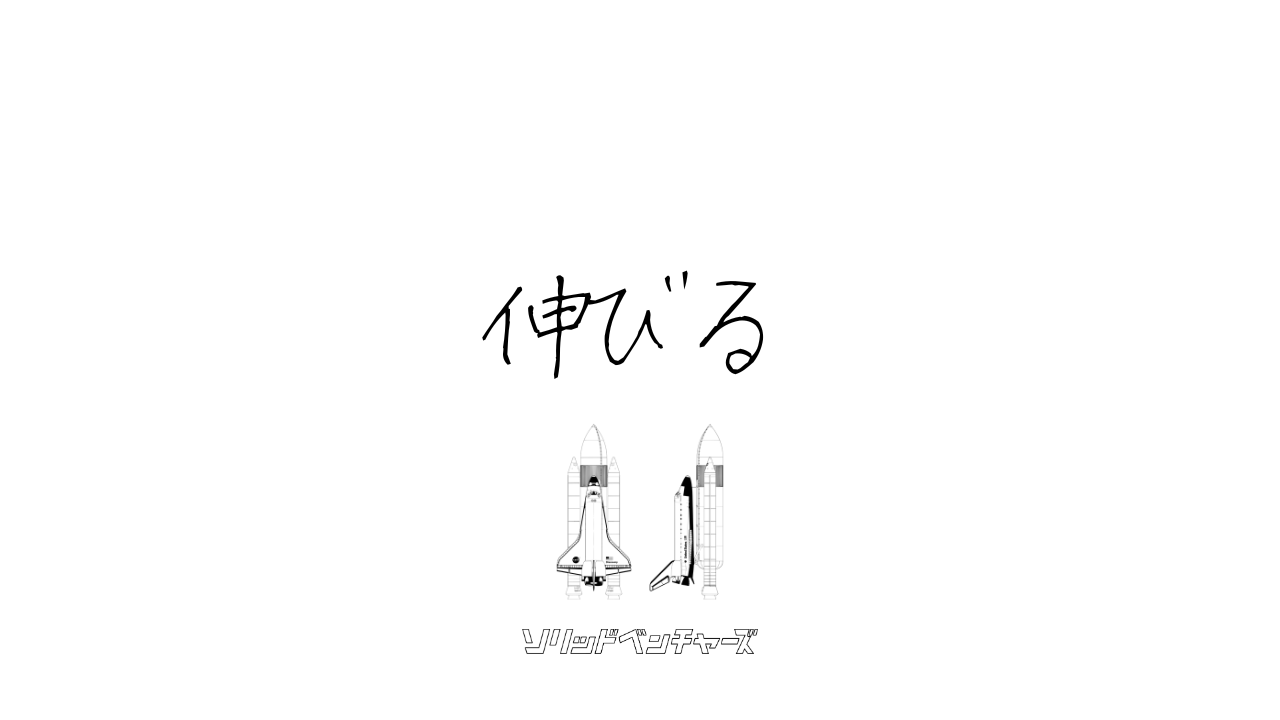
ハイライト
- 安定黒字を先行して確保し、リスクを小さくする
- 投資家依存が小さいため、経営の柔軟性を保てる
- 既存顧客ニーズをもとに、スモールステップで新規事業を追加
企業が成長を目指す際、スタートアップとソリッドベンチャーという2つの異なるモデルがあります。スタートアップは、早期の急成長を目指してリスクを取る一方、ソリッドベンチャーは安定した収益源を確保しながら新しい挑戦に備える戦略を取ります。この違いが、両者の成長パターンに大きな影響を与えます。ソリッドベンチャーは、なぜスタートアップと異なり、安定して成長し続けることができるのでしょうか?この問いに答えるため、まずはソリッドベンチャーとスタートアップの基本的な違いを探り、さらにその成長戦略やリスク管理の手法を具体的な事例とともに考察してみます。SHIFT社やTWOSTONE&Sons社といったソリッドベンチャーの実例を通じて、安定した収益基盤を持つことが、どのように新規事業への挑戦を支えるのかを明らかにしていきます。
本記事では、ソリッドベンチャーがどのようにしてリスクを分散しつつ、持続可能な成長を実現するのか、そのプロセスを解説し、ソリッドベンチャーならではの強みについて深掘りしていきます。
スタートアップ一辺倒ではない選択肢
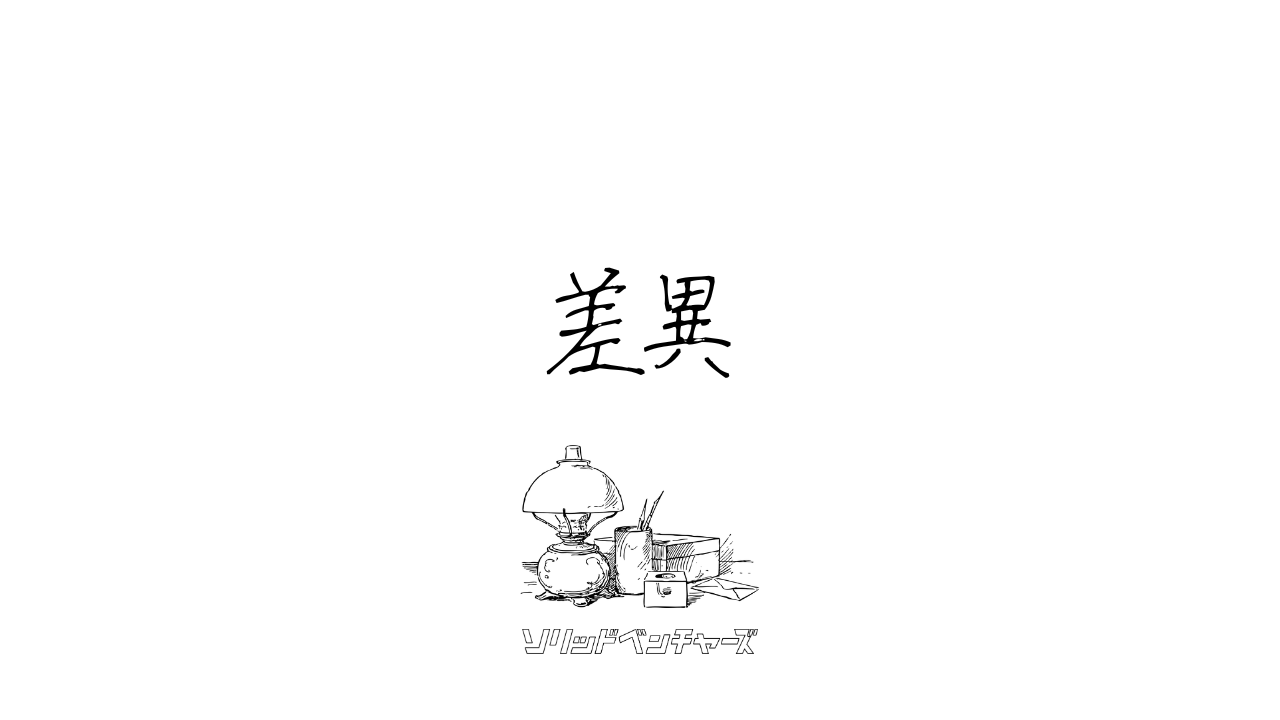
“スタートアップ=急成長” だけじゃない?
日本におけるベンチャー企業像といえば、しばしば「シリコンバレー式」のスタートアップが連想されます。大規模資金調達や短期間でのIPO、あるいはM&Aによる巨額リターンなど、華々しい成功物語がメディアの注目を集めがちです。
しかし、実際のところ、すべての新規事業がハイリスク・ハイリターン型の急成長を必要としているわけではありません。
特に日本市場の場合、人口減少や需要の成熟化などの構造的背景から、「大きなリスクを取りにくい」「顧客も急変動より着実な提供を望む」といった要素が重なり、アメリカで想定されるようなスタートアップモデルが合致しないケースも増えています。
さらに地方やニッチ市場では、華やかなテック企業のような急成長よりも、自社の黒字をしっかり確保しながら長く安定して稼働することが評価される環境があるのです。
ソリッドベンチャーというもう一つの道
そこで近年注目されるのが、ソリッドベンチャー(Solid Venture)という概念です。これは、初期の安定収益(キャッシュフロー)を獲得しつつ、段階的にリスクをとりながら新規事業を拡大していくビジネスモデル。
スタートアップでは「赤字を許容してでもユーザー数やシェアを先に取りに行く」戦略が定石ですが、ソリッドベンチャーは「まずは着実に黒字を出し、将来の投資に備える」アプローチを採用します。
ここで想定されるのは、例えば受託開発・コンサルティング・人材紹介・BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)などの、比較的早期に売上を確保できる事業が主軸になりやすいモデルです。
こうした事業で黒字化した後、その利益を自己資金として新規サービスやプロダクトに投下していくわけです。
なぜ「安定路線」が注目されるのか
ソリッドベンチャーとスタートアップの根本的な違いから、ソリッドベンチャーがいかにリスクを管理しながら成長を続けるのかを中心に解説します。
また、いくつかの事例も挙げながら、「地味かもしれないが、確実に収益を生む土台」がどのように新たなチャンスを生むのかを見ていきましょう。
後編では、さらなる詳細事例や具体的な戦略論、組織づくりのポイント、そして今後の展望などを掘り下げ、ソリッドベンチャーが日本のベンチャーシーンにもたらす影響を考察します
ソリッドベンチャーの基礎理解:定義と特徴
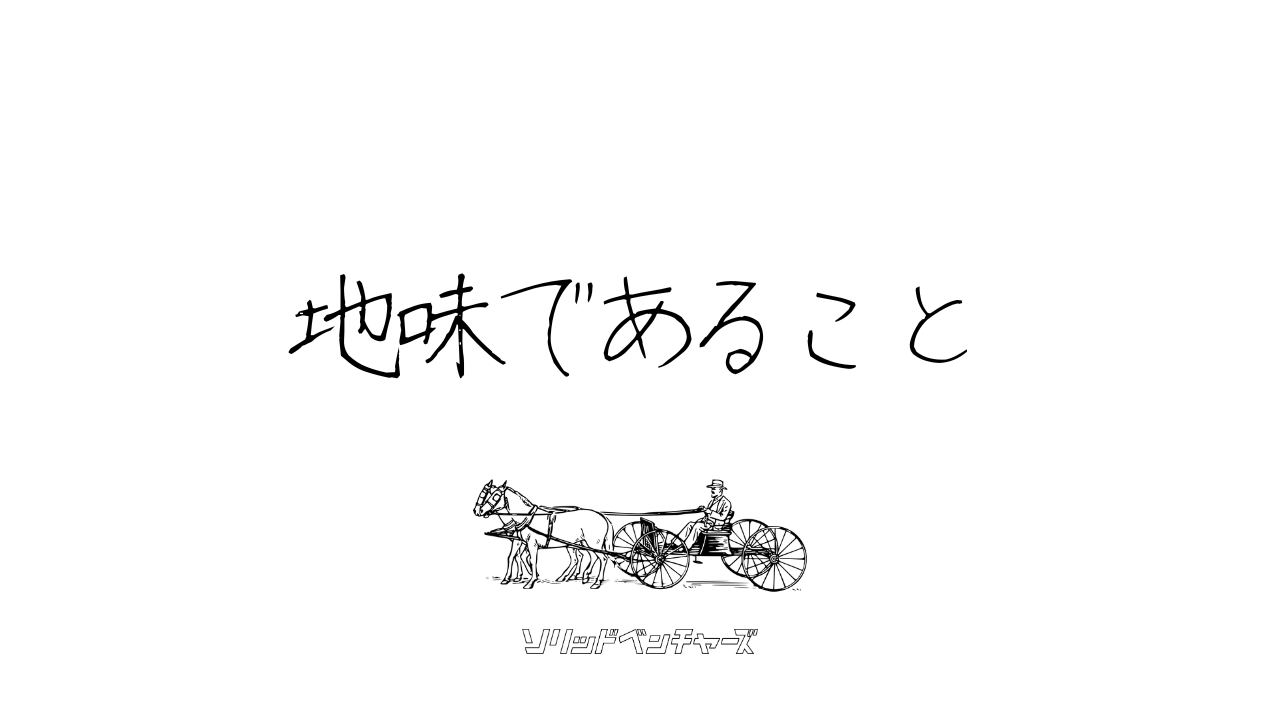
ソリッドベンチャーの定義
改めて、ソリッドベンチャーの定義を整理すると、
「創業初期から安定的に収益を獲得する事業を立ち上げ、
その利益をキャッシュエンジンとして新規事業を持続的に模索する企業」
と言えます。既存の言葉でいえば、「スモールビジネス+成長企業」のハイブリッドモデルにも近いかもしれません。
なぜ「ソリッド(Solid)」なのか?
「ソリッド」は「堅実」「安定」という意味合いを持ち、ここでは「リスクを無闇に拡大しない堅実な経営スタイル」を指しています。
スタートアップがしばしば「急成長や投資家のリターンを最優先」とするのに対し、ソリッドベンチャーは「自社が安定して稼ぐ能力」を土台に、必要に応じて投資を行う、という発想です。
スタートアップとの違いを再確認
ソリッドベンチャーが注目される背景には、スタートアップ路線のメリット・デメリットがあらためて認識されるようになったことがあります。
スタートアップの特徴と課題
- メリット:短期的な爆発成長が期待でき、大規模な市場を一気に制覇できる可能性がある
- デメリット:赤字が続く期間が長く、資金繰りが常に不安定。VCの投資判断次第で方向転換を余儀なくされる
ソリッドベンチャーの特色
- メリット:初期から黒字化するため、資金ショートリスクが低い。投資家の圧力が小さく、経営者がコントロールしやすい
- デメリット:大規模広告やユーザー爆発的拡大などを狙いにくい。市場によっては先行者利益を逃す
したがって、「急成長が最優先ではない」「ローカルやニッチで強みを発揮したい」と考える起業家や企業にとって、ソリッドベンチャーは魅力的な選択肢となるわけです。
なぜソリッドベンチャー的な企業が増えているのか
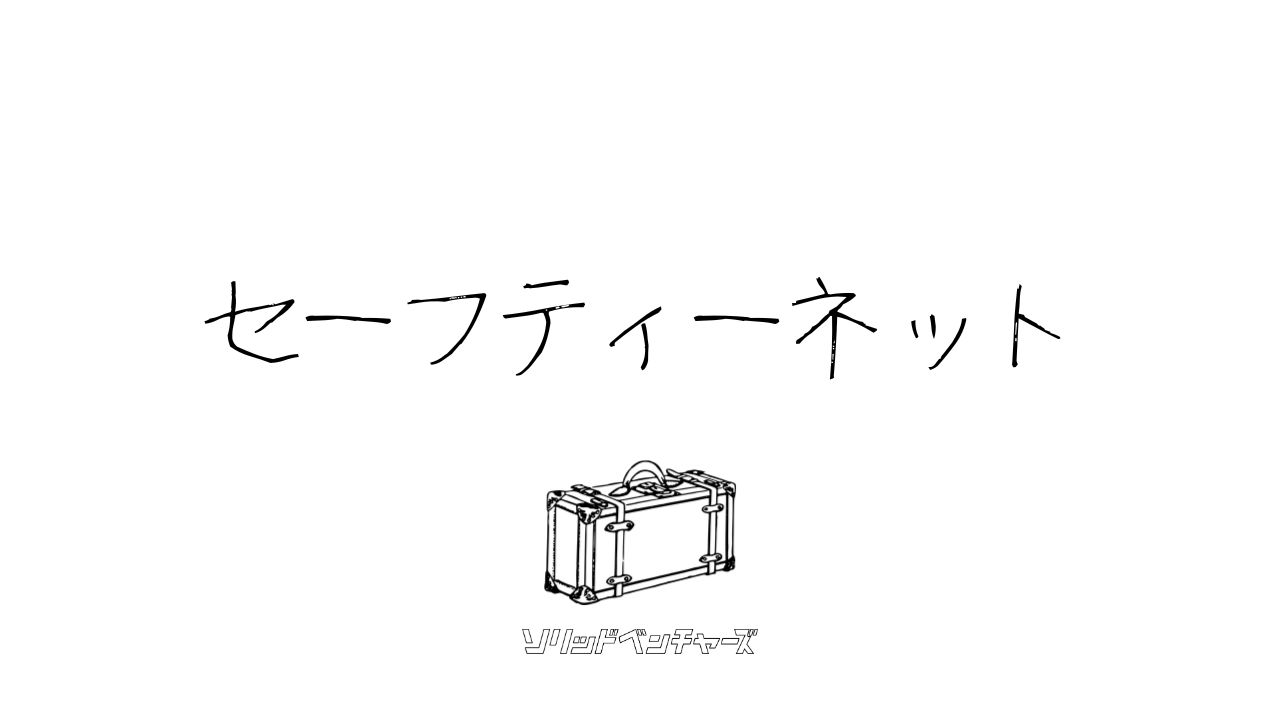
地方創生や中小企業のDX需要
地方では、地場産業や中小規模の企業が多く、急激な膨張を狙うよりも「まずは地元需要を獲得し、じわじわ成長したい」という層が多い。ここに対し、ソリッドベンチャー的アプローチはフィットします。
投資家の視点の変化
ベンチャーキャピタルの中でも、「リターンは大きくなくても、着実に利益を出す企業なら投資対象になる」という動きが出てきています。特にSaaSやBtoBビジネスは、堅実な売上×サブスク収益の組み合わせが評価されやすくなりました。
スモールM&A市場の拡大
IPOを目指さなくても、他社への売却(M&A)で小規模のEXITを実現できる機会が増えています。黒字が続く企業なら、買収される側としてもバリュエーションが安定しやすいメリットがあります。
ソリッドベンチャーのメリット:安定収益とリスク分散
メリット①:早期黒字化で“倒産リスク”を抑える
ソリッドベンチャーの最大の強みは、何といっても「創業間もなくから売上を確保する」点にあります。ITツール開発や受託ビジネス、あるいはコンサルティング・人材派遣など、比較的すぐに契約とキャッシュインが期待できるモデルなら、資金繰りによる倒産リスクは大幅に低減します。
スタートアップの定番リスク:
- 「サービスは評価されているが、まだマネタイズできていない」
- 「調達ラウンドが途切れて資金ショート」
ソリッドベンチャーの典型:
- 「小さいながらも確実に売上がある」
- 「黒字経営を守りながら、新規事業に投資を再配分」
メリット②:経営主導権を保ちやすい
大きな資金調達をするスタートアップでは、経営者がVCに対して株式の希薄化を受け入れ、経営判断にも一定の制約がかかることがあります。対してソリッドベンチャーは、初期の受託・コンサルで得たキャッシュフローを上手に回すことで、外部資本への依存度を下げられます。
- VCの投資比率が高くなると、経営方針の柔軟性が損なわれるケースも
- 自己資金+銀行借入(デットファイナンス)+一部エンジェル投資程度なら、創業者が経営をリードし続けやすい
メリット③:リスクの分散と再挑戦の余地
一度安定収益がある事業を確立すると、新規事業で多少失敗しても“会社全体”が即座に危うくなるわけではありません。
- スタートアップの場合、メイン事業のコケ=即アウトな状況に陥りがち
- ソリッドベンチャーなら、既存事業の安定収益がセーフティーネットとして機能し、再挑戦の機会を得やすい
ソリッドベンチャーのデメリット:成長スピードと大勝負の制限
もちろん、ソリッドベンチャーにも弱点があります。着実に進める代償として、“派手な勝負”をしにくいとも言えます。
デメリット①:急拡大が難しい
初期から黒字を狙うと、どうしても利益重視の姿勢になり、大きなマーケティング投資やユーザー獲得施策が打てない場合があります。大企業やスタートアップが短期間に巨額投資をしてシェアを奪う市場では、ソリッドベンチャーが後手に回りやすい。
デメリット②:地味なイメージの事業が多い
受託やBPOなどを主軸にしていると、どうしても「華やかさ」に欠けるというイメージがあるかもしれません。大手IT企業やスタートアップからの転職を検討する優秀な人材にとって、「自社プロダクトがない」「地味なテスト工程や裏方業務に特化」という状況は魅力に欠ける場合もあります。
- SHIFT社などは当初、「テスト工程だけをやる会社?」と扱われ、人材確保に苦労したという話もあります。
- しかし長期的にはIPOやM&A戦略の展開などで成果を出し、現在では優秀なエンジニアも集まる企業になりました。
デメリット③:競合が先行してしまう可能性
市場によってはスピード勝負が重要となり、他社が大型調達をして一気にシェアを取ってしまうことも。例えばBtoCのSNSやAI・ビッグデータ領域など、一瞬の勢いが明暗を分ける場面ではソリッドベンチャー的アプローチは不向きかもしれません。
ソリッドベンチャーのリスク管理:安定と挑戦の二重構造
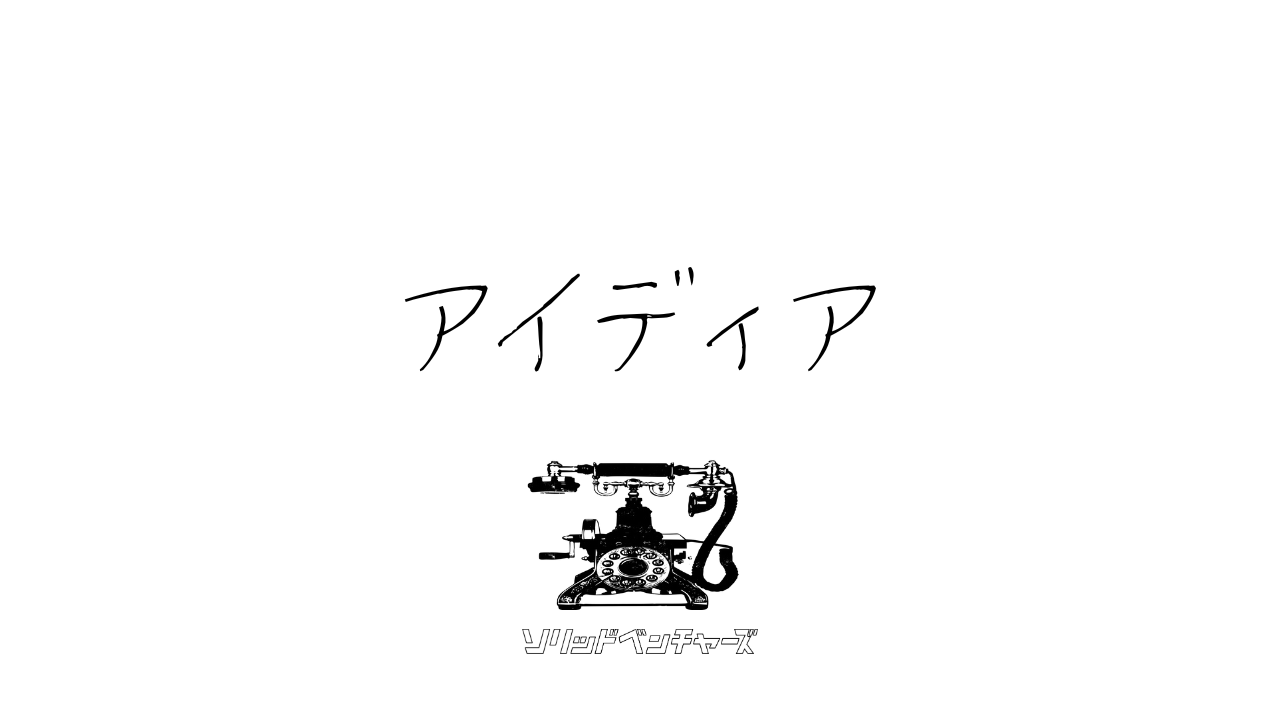
ソリッドベンチャーが安定成長を実現する要因の一つに、「既存事業と新規事業を分けて考え、投資ペースをコントロールする」という戦略があります。
SHIFT社: デバッグ事業を基盤とした安定成長
既存事業=キャッシュフローエンジン
創業当初から受託・コンサルで稼ぐモデルを確立しておけば、この既存事業が“エンジン”となって会社全体の収益を支えます。たとえ新規プロダクトがうまくいかなくても、黒字基盤があるため即座に会社が倒れることはありません。
新規事業=攻めと実験
一方で、新規事業への投資は“黒字基盤が生む利益”を原資に進めます。必要に応じて追加借入をすることもあるでしょうが、ある程度経営者が主体的に投資タイミングや規模を決められるのが特長です。
- 調達ラウンドのスケジュールに追われるスタートアップとは異なり、じっくりと開発や市場テストを行える
- 新規事業が失敗しても、既存事業は存続するため、経営資源の再配分が可能
経営指標:EBITDAやキャッシュフローマネジメント
ソリッドベンチャーではキャッシュフローが特に重視されるため、EBITDA(利払い・税引前利益)などの経営指標が注目されることがあります。スタートアップは、時価総額やユーザー数などの成長指標をアピールしがちですが、ソリッドベンチャーの場合は現金収支や営業利益など、“堅実さ”を示す指標が投資家や金融機関にも評価されます。
“地味でも強い”――もう一つの成功曲線
スタートアップとソリッドベンチャーの対比を整理しました。ここからは「地味だが抜群にしぶとい成長曲線」を描いた企業を取り上げてみます。
PR TIMES──BtoB SaaS×メディアの二段ロケット
- 祖業はプレスリリース配信プラットフォーム。月額課金と従量課金がバランスよく積み上がり、創業期からキャッシュフローが潤沢。
- 既存顧客(広報担当)が抱える「PRの成果を可視化したい」という課題を起点に、タスク管理SaaS「Jooto」やCSツール「Tayori」を順列拡張。
- メディア買収を通じて流通チャネルを自前化し、ユーザー獲得コストを逓減している点は、“自社アセット再循環”の好例。
GENOVA──医療DXの縦堀りで売上80億超
- ウェブ制作からスタートし、クリニック向けにSEO・広告運用を提供。ここで得た医療機関ネットワークをテコに、
- 自社メディア
- 自動精算機・再来受付機
- クラウド型予約システム
を順に投入。
- 医療現場はITリプレイス頻度が低く失注リスクも低いため、ストック収益が厚く、M&Aを絡めたサービス拡張も進行中。
M&A総研ホールディングス──“後発×完全成功報酬”で業界地図を書き換え
- 参入障壁が高いとみられていたM&A仲介市場に、「着手金ゼロ×AI活用の業務効率化」で切り込み。
- 初期投資はコンサルティング受託で賄い、短期間で黒字化→利益の大半を営業人員とプロダクト開発に再投資。
- 本業のストック収益を梃に、資産運用支援やDXコンサルへ水平展開。――“ソリッド化→Jカーブ化”の王道ストーリーを体現している。
安定成長を支える“4つの鉄則”
本文で示したメリット・デメリットに加え、浮かび上がった共通パターンを整理しました。
- キャッシュエンジンは「顧客の必需品」に張る
- テスト(SHIFT)、PR配信(PR TIMES)、医療機関の集患(GENOVA)など「なくならない作業」にフォーカス。
- テスト(SHIFT)、PR配信(PR TIMES)、医療機関の集患(GENOVA)など「なくならない作業」にフォーカス。
- 利益率より再現性を優先
- 受託や代理店は粗利が薄くても、案件を回すごとに顧客課題の“データベース”が構築される。のちのSaaS化や内製化で利益率を跳ね上げる布石。
- 受託や代理店は粗利が薄くても、案件を回すごとに顧客課題の“データベース”が構築される。のちのSaaS化や内製化で利益率を跳ね上げる布石。
- M&Aは“のれん負けNG”を徹底
- SHIFTやTWOSTONE&Sons同様、「償却後赤字化する案件は買わない」という明確なガイドラインで統合コストを最小化。
- SHIFTやTWOSTONE&Sons同様、「償却後赤字化する案件は買わない」という明確なガイドラインで統合コストを最小化。
- KPIはEBITDA×営業CF/人月
- ユーザー数やMAUよりも、“稼ぐ力”を示す指標でガバナンスを効かせる。現場も財務も同じ物差しで動くため、迷いが少ない。
SHIFT社の事例――ニッチなテスト工程からの拡大
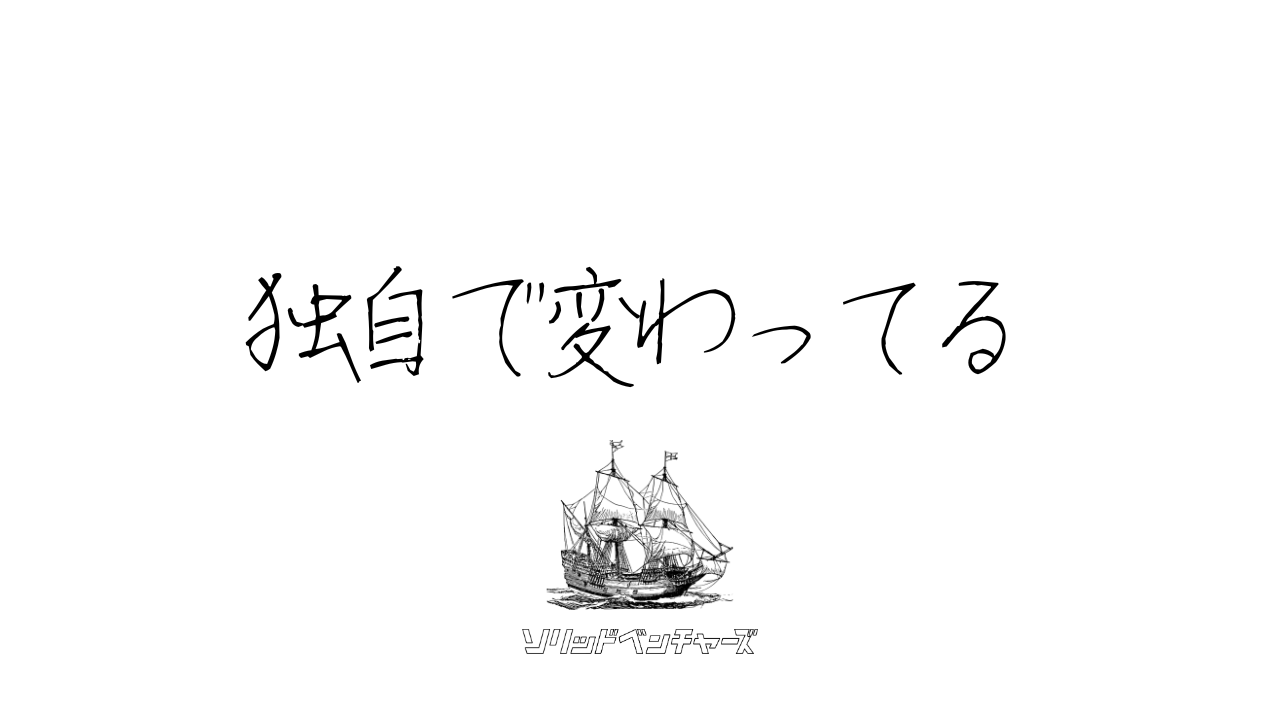
SHIFT社の概要
SHIFT社は、ソフトウェア開発の中で地味な領域とされてきた「テスト工程」を専門に請け負う事業モデルで成長した企業です。元々はスタートアップのように派手な資金調達をしていたわけではなく、「ニッチかつ確実な需要があるテスト領域」を攻略することで早期収益化に成功しました。
テスト工程への特化がもたらした安定
SHIFT社が狙ったのは、企業がソフトウェアを開発するときに必ず必要となる“検証・テスト”の部分です。多くの開発会社は、テストに割くリソースや専門ノウハウが不足しがちだったため、SHIFT社の「テスト請負」というサービスは非常に受け入れられやすかったといえます。
- 大手SIerやゲーム開発会社の下請けではなく、あくまでテスト専門の外部パートナーとして位置付け
- プロジェクトごとの受託契約が繰り返されやすく、安定キャッシュフローを確保
M&Aを活用した周辺拡大
SHIFT社はテスト工程で稼いだ資金をもとに、ソフトウェア品質管理や上流工程のコンサルなどへ段階的に進出。さらに関連企業をM&Aすることでサービスの幅を広げ、既存顧客のニーズに対してワンストップで対応できる体制を構築しました。
- 最初に確実な収益を得るコア領域を持ち、そこから少しずつ上流下流に広げる
- M&A戦略もソリッドベンチャー的アプローチが核にあり、買収先企業の赤字を自社黒字で吸収しながら成長
SHIFT社の成長モデルは、まさに「小さく堅実に始め、徐々に大きくしていく」ソリッドベンチャーの成功例と言えるでしょう。
レバレジーズ社の事例――人材ビジネスを軸に多角化
レバレジーズ社の概要
レバレジーズ社は、主に人材紹介・派遣領域から出発し、そこから新卒支援、医療・介護人材、さらには海外展開にまで事業を拡大してきたソリッドベンチャーです。
- 人材ビジネスは成功報酬型が多く、契約が成立すると確実な売上を得られる
- 需要が途切れにくい分野(ITエンジニアや看護師など)に特化し、早期黒字を実現
複数の専門領域を堅実に攻略
レバレジーズ社の特徴は、一つの人材領域に固執せず、複数セクターに分散投資している点です。例えばITエンジニアの派遣・紹介が好調なら、そこから得た利益を医療系人材の紹介ビジネスに再投下し、また別のセクターを開拓します。
- 人材業界の情報・知見を横連携できる
- 各セクターで競争が激化しても、別セクターで補える
自社メディアや海外展開へのチャレンジ
レバレジーズ社は人材紹介だけでなく、自社メディア運営なども手がけており、求人プラットフォームを自前で育てることで広告収益を得るビジネスモデルも構築しています。さらに海外にも進出し、現地のIT人材・日本企業とのマッチングなど、ニーズのある領域を多角的に攻めています。
- 「収益源をいくつも持つ」ことで市場リスクを分散
- どれかが不調でも全体としては黒字を維持
レバレジーズ社は、スタートアップのような派手な資金調達の話題は少ないものの、確実に売上高と利益を伸ばし続ける代表的なソリッドベンチャーといえます。
TWOSTONE & Sons社の事例――受託開発からのM&A多角化
TWOSTONE & Sons社の概要
TWOSTONE & Sons社は受託開発を中核としながら、新規事業や関連企業のM&Aに積極的に取り組むことで事業範囲を拡大してきた企業です。案件単位での受託開発による安定的なキャッシュフローをベースに、ITスタートアップや専門領域の技術企業を買収してサービスラインを増やしていく戦略を取っています。
受託開発+M&Aのメリット
受託開発:
- 大手顧客を獲得すれば、継続的に案件を受注できる
- 安定利益を生み出し、自社プロダクト開発資金にも回せる
M&A:
- 自社にない技術・プロダクトを一気に獲得
- 既存顧客に対してクロスセル・アップセルがしやすい
TWOSTONE & Sons社は、この2軸を組み合わせることで、早期黒字化+新サービス導入+リスク分散を同時に実現しています。
新規事業における失敗許容度
またTWOSTONE & Sons社は、受託開発で黒字を守りながら、新規事業にトライしては軌道に乗ったものをスピンオフしたり、別子会社化したりして発展させる手法を採っています。万が一、新規事業が大きく外れても、受託が安定収益源として残るため、会社全体の損失を最小限に抑えられるのです。
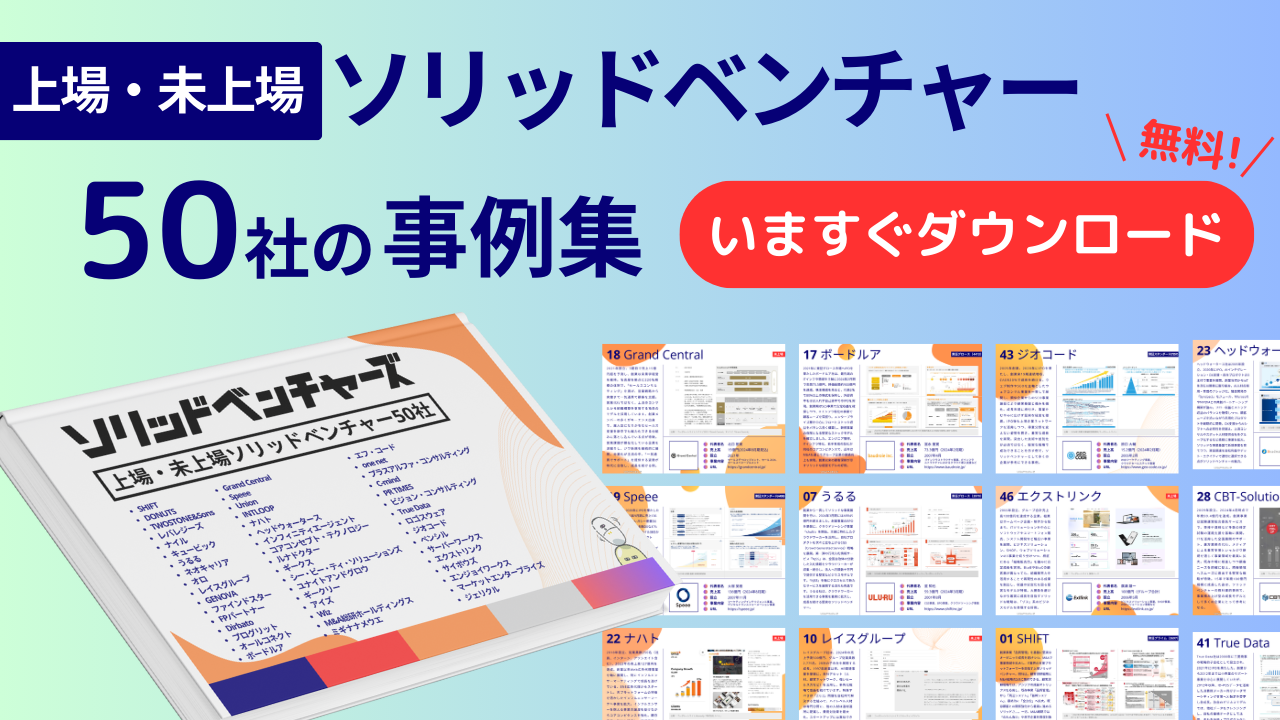
ソリッドベンチャーの今後:小ぶりM&Aと地方創生へのインパクト

ここまでの事例から、ソリッドベンチャーは地に足の着いた経営を続けながら、複数の新規サービスを模索するという姿が見えてきました。では、今後このモデルはどのように発展していくのでしょうか。
スモールM&Aの活性化
日本では数億円~数十億円程度の「小ぶりなM&A」が増えています。地方の老舗企業や中小企業の後継者不足などが背景にあり、“買える会社が増えている”のが実情です。
- ソリッドベンチャーは自社が黒字ならば、M&Aの際に銀行融資を引きやすく、買収で得た会社をリスク小さく立て直すことが可能。
- 単発プロダクトを持つ小さなITベンチャーも、ソリッドベンチャーにとって“機能追加”の一手段として買収対象になりうる。
地方やニッチ産業での存在感
地方創生の流れや、ニッチ市場での課題解決型ビジネスが脚光を浴びる中、急成長よりも「地元密着」「着実なサービス提供」を重んじる風潮は高まる可能性があります。
- ローカル企業がIT化やDXを進める際、ソリッドベンチャー型のITパートナーが頼られる
- 一発屋的な展開よりも、継続的に地元雇用と税収に貢献してくれるソリッドベンチャーが支持されやすい
ソリッドベンチャーから大企業へ
安定収益と複数事業の成功を積み上げることで、結果的に大企業並みの規模に成長するソリッドベンチャーも現れるでしょう。
近年、SHIFT社が上場を果たして大企業の仲間入りをしているように、必ずしも「ソリッド=小さいまま」というわけではありません。
むしろ、時間をかけて堅実に拡大すれば、スタートアップ型とは違う形で社会的影響を持つ企業になりうるのです。
ソリッドベンチャーの戦略設計:安定基盤×挑戦の二刀流
戦略的多角化の重要性
ソリッドベンチャーは“最初の黒字事業”がある程度軌道に乗ると、隣接領域への拡大を模索し始めます。これはアンゾフの成長マトリックスで言えば「既存市場×新製品」「新市場×既存製品」の段階的アプローチに近い方法です。
- 既存市場×新製品:
例)ITコンサルを行う会社が、顧客企業向けのSaaSツールを自社開発する - 新市場×既存製品:
例)地方企業向けに展開していたBPOサービスを、首都圏大企業向けにもアレンジ
このように、「無理にまったく新しいことを始めない」のがソリッドベンチャーの特徴と言えます。最初に築いた顧客基盤やノウハウ、リソースを最大限再利用して、新規事業のリスクを抑える狙いです。
連鎖的イノベーションと顧客起点
多角化を成功させる鍵は、現場の顧客ニーズを的確につかむことです。受託やコンサルで蓄積した顧客課題の情報を、新規プロダクト開発のアイデアソースとして活用します。これを連鎖的イノベーションと呼び、ソリッドベンチャーならではの着実な進化スタイルが確立されるのです。
組織づくり:少数精鋭×現場力の活用
組織規模のコントロール
急成長するスタートアップは、短期間に採用を増やし、数百~数千人規模の組織になることもあります。しかしソリッドベンチャーでは、利益率や品質を守るために少数精鋭で運営を続ける選択が多く見られます。
- 人材コストが増えると、初期事業の利益が圧迫されがち
- 組織肥大化で意思決定が遅くなるのは、堅実経営と相性が悪い
エンジニア・コンサルの役割
受託開発やコンサルを行う企業では、プロジェクト型で動くことが多い。そこでは優秀なエンジニアやコンサルタントが現場で稼ぎながら顧客を理解する役割を担います。彼らが得る知見こそが、次のサービス開発や業務効率化に直結していきます。
新規事業チームの内製化or分社化
ソリッドベンチャーの中には、新規事業を“社内ベンチャー”として育てるケースもあれば、社内で実験的に始めたプロジェクトを別会社にスピンオフさせるケースもあります。
どちらにせよ、既存事業と新規事業は財務状況やKPIを分けて管理することが多く、どれだけ投資していいかを明確にしている点が特徴的です。
資金調達の選択肢:エクイティ/デット/自己資金のバランス
エクイティファイナンスの意義
ソリッドベンチャーであっても、大きく成長するタイミングでは、*式発行による資金調達(エクイティファイナンス)を活用することがあります。ただし、その際にも「どの程度株式を発行するか」や「VCからの要求」に注意しながら、自己資本比率を極端に下げないよう意識されることが多いです。
デットファイナンス(銀行借入)の活用
受託やコンサルで黒字を出していれば、銀行からの借入がしやすくなります。さらに、M&Aなどを行う場合にも、黒字企業なら融資が受けやすいというメリットがあります。スタートアップほど「バリュエーションを気にする必要」が少ないため、返済計画を立てやすいのです。
自己資金の再投資
ソリッドベンチャーは、既存事業の安定収益を原資に新しいプロジェクトに投資を回す手法を好みます。これにより、外部からのリターン要求に縛られず、経営者の裁量で投資戦略を調整できるわけです。
資金調達の最新トレンド――“ミックス型”が主流へ
デット+少額エクイティ+自己資金のハイブリッド比率が高まっていくと考えられる。GENOVA・PR TIMESなど、上場後も借入余力を確保している企業は、金利上昇局面でもM&Aを滞らせずに済み、“調達せずに伸ばす”こと自体が信用力を高め、低利融資→巨大な資金調達枠へと転換しやすいサイクルができつつあります。
スモールM&A戦略:買収先企業の統合とシナジー創出
前編でも触れたように、ソリッドベンチャーの拡大手段としてM&Aが注目されています。ここでは、より詳細にスモールM&Aのメリットや成功ポイントを探ってみましょう。
スモールM&Aのメリット
- 成長スピードを補う
ソリッドベンチャーは自然成長だとどうしても時間がかかるが、買収によって一気に機能や顧客基盤を拡大できる。 - 既存事業とのシナジー
買収先が自社と近い領域であれば、クロスセルやアップセルが容易になり、収益増に直結しやすい。 - リスク低減
既存事業で黒字を確保できていれば、買収した企業を立て直す期間を確保でき、赤字転落のリスクを分散できる。
M&A後の統合プロセス
M&Aで大切なのは、買収後のPMI(Post-Merger Integration)です。ソリッドベンチャーは組織や財務基盤が比較的シンプルなため、過剰に統合を急ぐのではなく、段階的に文化やシステムの融合を図るケースが一般的です。
- 初期は開発リソースや営業チャネルを共有
- 人事制度や社内ルールは徐々に統合
- 結果的に、買収先の独自性を活かしつつ、本社の経営ノウハウを注入して成長させる
ケーススタディ:受託企業が小規模SaaSを買収
例えば、ある受託開発企業が、特定の業務分野に特化したSaaSスタートアップを買収したケースを考えましょう。
- SaaSスタートアップ:プロダクトは優れているが、単独では資金や営業力が足りない
- 受託開発企業:顧客基盤はあるが、自社サービスが少なく、収益の安定性に課題を抱えている
両社が統合することで、受託顧客にSaaSをクロスセルでき、SaaS側は営業コストが減り、受託企業はストック収益を得られるビジネスモデルに変貌。まさにソリッドベンチャーならではの「1+1=3以上」のシナジーを作り出すのです。
地方・海外展開とソリッドベンチャー:拡張モデルの可能性
地方企業との相性
先に触れたように、地方では急な成長よりも長期安定を求める企業が多く、ソリッドベンチャーと親和性が高いです。実際に、
- 地元の企業がIT化を進めたい→ソリッドベンチャー型のITコンサルが受託で対応
- 地方の製造業が後継者不足→ソリッドベンチャーが買収し、ITによる効率化と新商品開発を進める
というようなシナリオが各地で生まれています。スタートアップほどのスピード感はなくとも、地域に根ざした着実なビジネスが生まれる可能性が高まるわけです。
海外展開:アジア新興国との接点
ソリッドベンチャーが海外進出を果たすケースとしては、アジア圏の新興市場に進出し、日本の企業支援や日本向けサービスの受託を行うパターンなどがあります。
- 初期投資を抑えつつ、現地パートナーと協力しながら小規模で足掛かりを作る
- 自社が培ったノウハウ(人材紹介、ITコンサル)を現地企業に導入することで収益化
海外展開においても、スタートアップのように「全世界へ一気に打って出る」というよりは、まずは狭いターゲット市場で黒字を作り、それを基盤に拡張していくのがソリッドベンチャー流と言えます。
ソリッドベンチャーへの転換:既存中小企業の活用
中小企業の“第二創業”という捉え方
もともと別の事業で安定経営をしてきた中小企業が、新規プロダクトやITサービスに乗り出す際、ソリッドベンチャー的な姿勢を取りやすいです。
- 安定した本業の黒字を使って、新しい商品開発に投資
- 自社内に新規事業部署を作り、段階的に試す
こうした「第二創業」的な取り組みが増えるほど、ソリッドベンチャーに近い企業が次々と誕生していく可能性があります。
事例:製造業がIT子会社を設立
ある地方の製造業が、自社の業務効率化のために内製でシステムを開発し始めたところ、これが外部からも評価され、外販ビジネスへと発展したというケース。
最初は自社の経営を支える黒字事業(製造)を持っているため、IT事業で多少の赤字が出てもカバーでき、時間をかけて成熟させることができる。
- 製造×ITという組み合わせで、最終的にユニークなプロダクトやサービスを世に出せる
- こうした事例は日本各地で増えつつあり、ソリッドベンチャーという括りで語ることもできる
スタートアップとの協業:ハイブリッドモデルの可能性
ソリッドベンチャーがスタートアップを支援する
興味深いのは、ソリッドベンチャーがスタートアップに対して受託やコンサルを行い、売上を得るという構造もあり得る点です。
急成長を目指すスタートアップは、新規アプリやサービスを素早く開発したいが、自社リソースだけでは足りない。その開発を“ソリッドな”受託企業が支えている、というケースは実は少なくありません。
- スタートアップをクライアントに持つことで、トレンド技術やノウハウを吸収
- スタートアップとの協業で、自社の新規プロダクト開発にも刺激が生まれる
提携や共同事業の展開
さらに進んで、ソリッドベンチャーとスタートアップが共同でプロダクト開発を進めることも考えられます。スタートアップはアイデア・スピードがあるが資金や安定性が弱い。
ソリッドベンチャーは資金力や開発リソースがあるが、革新的テーマを追求する人材やカルチャーが不足している――互いに足りない部分を補完し合う形がとれます。
組織文化と長期的ビジョン:ソリッドベンチャーの持続力
経営理念と価値観
ソリッドベンチャーでは、短期間で結果を出すプレッシャーが少ない分、経営理念や企業文化が育ちやすい傾向にあります。いわゆるスタートアップのカオスな環境では、社員が常に膨大なノルマやタスクに追われ、定着率が低い場合も。
でもソリッドベンチャーは、社員一人ひとりが自社ビジョンに共感し、長期的視野で働く風土が根づく可能性が高いのです。
社員に与えられる「失敗の余裕」
新規事業での失敗を許容できる財務体力があることで、社員が安心してチャレンジしやすくなります。これは企業文化にも大きく影響し、「挑戦を奨励するが、焦りすぎず地道に進める」という独特の雰囲気が形成される場合があります。SHIFT社やTWOSTONE & Sons社なども、組織内で“次の種を仕込み続ける”文化を育んでいるとされています。
具体的ロードマップ:ソリッドベンチャーを目指すためには
ここでは、もし今からソリッドベンチャー型の起業を考える人、あるいは既存企業の第二創業を想定する人に向けて、ステップバイステップのロードマップを提案してみます。
ステップ1:市場調査と“即金性”確認
- ニッチ市場かつ、安定需要があるかを確認
- できれば競合が少ない、あるいは大手が参入しにくい領域を探す
- 例えば、特定の業界におけるシステム保守、物流や経理のアウトソーシング、地域特化の人材紹介など
ステップ2:初期契約の獲得→早期黒字化
- 最低限の人材(コアメンバー)で、初期受注をとる
- 費用倒れしない程度に適正価格を設定し、地道に複数案件を回す
- ここでの目標は、月次で赤字にならない体制づくり。多少の利益でも重要
ステップ3:既存顧客の課題をリサーチ
- 受託・コンサルの現場で、顧客の課題を余すところなく聞き取る
- 「何度も繰り返される作業」「他社でも似た問題を抱えている」などの共通ニーズを発見
- 新規プロダクトやサービスのアイデアリストを蓄積
ステップ4:新規事業のスモールスタート
- 既存事業で得た利益の範囲内、またはデットファイナンス(銀行借入など)で予算を確保
- 試作品やパイロット版を、既存顧客にテストしてもらう
- フィードバックを受けつつ、本格リリースのタイミングを計る
ステップ5:複数事業の並行運営
- コア事業は継続して黒字をキープ
- 新規事業がある程度立ち上がったら、別部署または子会社として運営し、KPI管理を分ける
- 必要に応じてM&Aも検討し、シナジーがある企業を買収して成長をブースト
ステップ6:組織の安定と新陳代謝
- 特定の事業に依存しすぎないよう、人材ローテーションやジョブローテを実施
- 現場力と企画力を高める教育制度を整え、社員の定着率アップ
- 新規事業の芽が出たら、積極的に独立させたりリーダーを任せたりする
ステップ7:“黒字継続ライン”の自動監視
- 月次営業CFが3カ月連続で警戒水準を下回ったら即座に投資抑制。
ステップ8:“出口なきIPO”or非上場貫徹の選択
- PR TIMES型(上場しつつ長期保有)か、レバレジーズ型(未上場のまま1,000億円超)か――資本政策を早期に言語化しておく。
ソリッドベンチャーはどこへ向かうのか? 未来への展望
「安定」の再評価と企業観の変化
これまでベンチャー界隈では、「大きく資金を集め、一気に世界を目指す」ストーリーがもてはやされてきました。しかし、コロナ禍や世界的な経済不安などを経て、安定的に利益を上げながら必要十分なリスクをとる――こうした企業の在り方が再評価され始めています。
- VC投資が鈍化する局面では、自力で稼げる体質を持つ企業が生き残りやすい
- 日本特有の中小企業文化とソリッドベンチャーの哲学は相性がよい
エコシステム全体の多様化
スタートアップ、ソリッドベンチャー、大企業、NPO、地方行政など、多様な主体が組み合わさることで、より豊かなビジネスエコシステムが形成されます。
ソリッドベンチャーが安定供給・コンサル・受託などの役割を担いつつ、スタートアップが最先端技術や新しいアイデアで突破口を開き、大企業がその両方を吸収してさらなる拡大を目指す――そんな構図が描けるようになるでしょう。
海外でも評価される可能性
アメリカや中国の巨大スタートアップの影に隠れがちですが、近年は欧州や東南アジアなどでも「大きなリスクより、安定した会社の方が評価される」という動きが見られます。
海外の投資家が日本のソリッドベンチャーに注目するケースも増え、逆に日本のソリッドベンチャーが海外企業を買収するシナリオも考えられます。
ソリッドベンチャーがもたらす価値と可能性
ソリッドベンチャーの戦略的多角化や組織づくり、資金調達の方法、地方や海外展開の可能性、そして未来への展望に至るまでを広くカバーしました。スタートアップのような短期集中の爆発ではなく、長期的視野に立った着実な拡大がソリッドベンチャーの真骨頂であることが改めて見えてきたのではないでしょうか。
ソリッドベンチャーは「地味」に映るかもしれません。しかし、その安定収益と低リスク構造は、一度花開くと複数回の挑戦を可能にし、気づけば業界のキープレイヤーへと成長しているケースも少なくありません。
SHIFT社やレバレジーズ社のように、上場やグローバル展開を視野に入れることも夢ではなく、「まずは受託で資金繰りを凌ぐ企業」から始まるストーリーが、やがて大きな果実を結ぶのです。
ソリッドベンチャーが生み出す新しい“王道”
華々しさやスピードがもてはやされるベンチャー業界において、ソリッドベンチャーのアプローチは「守りから入り、攻めを続ける」異色の存在に見えるかもしれません。
ですが実際には、このスタイルが日本企業の気質や現状の市場構造に合致している面は大きいです。
- 黒字を手堅く積み上げることで、市況の変動があっても急に消えない企業体力を確保
- 社員や顧客との長期的信頼関係を築き、無理なく新規サービスを育てる
- 地方や海外においても、着実に根を下ろしながらビジネスを拡大
こうした堅実な方法論だからこそ、スピードでは及ばない相手と違うフィールドで勝負できるのです。表舞台で大きく脚光を浴びる機会は少なくとも、ソリッドベンチャーは着々とその存在感を増しており、今後も多くの企業がこの路線で成功を目指すことになるでしょう。
もしあなたが、「急成長型スタートアップはリスキーすぎるけど、単なるスモールビジネスに留まりたくはない」と感じているなら、ソリッドベンチャーという選択肢をぜひ検討してみてください。
受託やコンサル、あるいは自社の既存ビジネスの延長線から始めてみる――そこに安定と成長の両立という、新しい経営スタイルの可能性が広がっています。